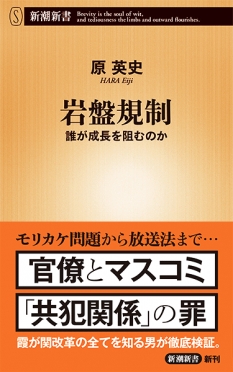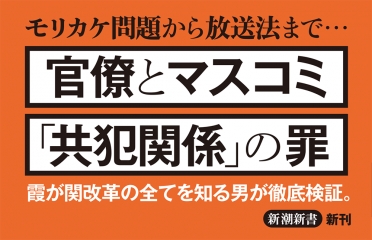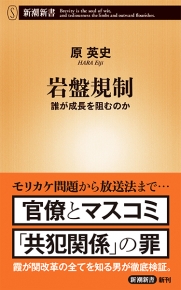
岩盤規制―誰が成長を阻むのか―
814円(税込)
発売日:2019/03/15
- 新書
- 電子書籍あり
モリカケ問題から放送法まで……官僚とマスコミ、「共犯関係」の罪、霞が関改革の全てを知る男が徹底検証。
数十年の長きにわたって、この国をがんじがらめにしてきた岩盤規制。一九八〇年代の土光臨調以来、昨今の獣医学部新設問題まで、それを打ち砕く試みは繰り返されてきたが、道はまだ半ばだ。なぜ岩盤規制は生まれ、どのように維持され、今後の日本経済の浮沈にどうかかわるのか。そして、官僚とマスコミはこの旧弊をどう支えたのか。現場の暗闘を知るトップブレーンが、改革の現状と未来をわかりやすく指し示す。
書誌情報
| 読み仮名 | ガンバンキセイダレガセイチョウヲハバムノカ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-610806-8 |
| C-CODE | 0231 |
| 整理番号 | 806 |
| ジャンル | 政治・社会 |
| 定価 | 814円 |
| 電子書籍 価格 | 814円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/03/22 |
書評
ダークサイドに落ちた日本を救うために
岩盤規制、縦割り行政、面従腹背、忖度、虚偽報道(フェイクニュース)、格差問題……。ここ20年の日本の停滞は、本書に頻繁に登場するこれらの言葉に表される。
規制そのものは別に悪いことではない。社会の、国民の利益のためにルールを作って、過度な自由競争ではなく秩序ある競争を促そうとする、いわば治世の知恵。ところがこの言葉に「岩盤」という文字が付くと意味合いは全く変わってくる。絶対に変えてはいけない過去に作られたルール。変えてはいけない理由はただ一つ。その規制によってラクにビジネスしている人たちが競争を忌避できるからだ。
ラクして儲かる。そんなうまい話があれば誰でも飛びつく。競争によってではなく規制によって秩序がもたらされる世界。当然新規参入は認めない。永年見知った既知のプレイヤーがほどよく競争し、他社に過度な脅威を与えず、自社にも致命的な危機が訪れない世界。素晴らしく平和で、理想郷のように聞こえるが、そのツケを払わされるのは顧客であり、国民である。
誰もが知っている映画「スター・ウォーズ」は「ダークサイド」という概念がシリーズを貫くテーマとなっている。
卓越した能力を、社会正義の実現ではなく、個人利益の実現に使う人たち。長い年月の中で、環境に影響され、状況に流されて、自己利益追求最優先に転向する人たち。
現在の日本にはダークサイドに落ちてしまった人がたくさんいる。競争を回避するために医学部新設を認めない医師会、獣医師会。おかしな対面販売の原則を貫く薬剤師会。机間指導にこだわる日教組。反Uberのロビイングを続けるタクシー協会。民泊に反対するホテル・旅館組合など。
問題は、そこに官僚が癒着することだ。ダークサイドに落ちた官僚は、国民の利益よりも業界保護を優先する。その方が仕事がラクだし、退官後にいいこともあるからだ。これらの人々にとって社会正義や国民の利益は二の次。自分たちの秩序を規制で守り、秩序を乱すものは容赦なく撃滅する。
容赦なく攻撃するにはロジックが必要だ。しかし多くのロジックはITのなかった数十年前に作られている。時代に合っていないことにうすうす感づいてはいるが、目の前の規制を温存すれば、ぬくぬくとラクにビジネスができる、という誘惑はまさにダークサイドの怖さである。
規制産業でこれほどまでにダークサイドがはびこると、その周辺の非規制産業の人たちにもダークサイド的な考え方が広がっていく。自分が長く人事権を保ちたいがために役員任期を変えてしまう経営者。会社よりも家の存続を重視する同族企業。法律的に問題のない範囲で限りなく自己利益を優先する風潮は、日本のあらゆるところにはびこっている。
日本人に大きな影響を与えるメディアの中にも、競争よりも共存、弱肉強食よりも、牧歌的でのんびりした社会が理想だと、まじめに喧伝する人たちが未だに存在する。もちろん私たちはそのような社会が実現できるのではないかと夢見る。が、少なくとも今のところ、それを実現する手法を持っていない。夢見るのは自由だが社会実装できなければ無責任な机上の空論。そういう意味では、具体論なくただ理想論を語る人たちもダークサイドと言える。
考えなしにメディアや他者の言うことをよしと思い、規制改革に反対する一般人もまたダークサイドにいる。競争のない社会が実現すると、誰も努力しなくなり、イノベーションは産まれず、国全体の競争力がなくなって、残るのは粗悪な製品と高価格なサービス。最終的にはすべてが崩壊してしまう、ということを証明したのが旧ソ連をはじめとする社会主義国の実験ではなかったのか。彼らの半世紀にわたる壮大な社会実験は人類に多大なコストを強いた。ここからの学びは大きかったはず、なのに。
本書には、我々が今、考え直さなければいけない主題が詰まっている。「失われた平成」を取り戻すために、我々は歴史から学ばなければいけない。そのために、まずみんなで「ライトサイド」に戻ろうではないか。本当に社会に必要なことを実現しよう。供給者の安定ではなく、対価を支払う需要者にとってよい仕組みを構築しよう。ある一者、あるグループにとっての利益ではなく、社会全体にとっての利益を最大化するために。日本の将来は、そこから再出発することでしか開かれないのだ。
(なつの・たけし 慶応大学特別招聘教授・ドワンゴ社長)
波 2019年4月号より
蘊蓄倉庫
官僚の遵法精神は強いのか?
官僚の遵法精神は強いのか?
答え=弱い。なぜならば、ルールは自分たちで作るものだという意識があるからです。たとえば、加計学園で注目を集めた獣医学部新設問題ですが、法律では、学部新設は「大臣の許可を受ければ」できると書いてあります。ところが文科省は、「法律」の下位規範である「告示」で獣医学部新設は一切できないとしています。もう少しわかりやすく言うと、国会を通さなくても大臣さえ丸め込めば自分たちで決められる「告示」で、上位の法体系である「法律」の内容を書き換えているのです。こういうことをやっている役所からは、法律で禁止された天下りを裏で積極的に進め、自分の座右の銘は「面従腹背」と明言するおかしな幹部が出てくるというわけです。詳しくは本書第3章で。
掲載:2019年3月25日
担当編集者のひとこと
「岩盤規制」はビジネスの邪魔をしています。
「規制緩和」と言えば小泉政権、「脱官僚」と言えば民主党政権時代に流行った古臭いテーマだと考えている方が多いのではないでしょうか。しかし、それは間違いです。いずれも強すぎる霞が関官僚の力を削ごうとした動きだったのですが、その力は今でも厳然として存在し、ビジネスの邪魔をしています。よく言われる我が国の“失われた20年”の大きな原因ともなっています。この本の筆者である原英史さんは、経済産業省に在籍中から霞が関改革に携わり、退官して政策シンクタンクを立ち上げた後も、この問題の最前線で奮闘を続けています。民間ビジネスの邪魔をする「岩盤規制」とは何なのか? その現在・過去・未来をわかりやすく解説します。
2019/03/25
著者プロフィール
原英史
ハラ・エイジ
1966年生まれ。経済産業省などを経て2009年「(株)政策工房」設立。著書に『岩盤規制 誰が成長を阻むのか』(新潮新書)など。