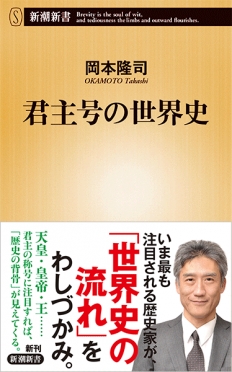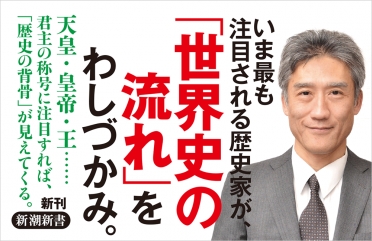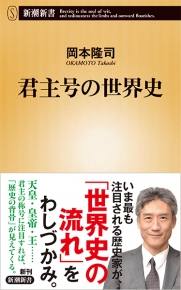
君主号の世界史
902円(税込)
発売日:2019/10/17
- 新書
- 電子書籍あり
いま最も注目される歴史家が、「世界史の流れ」をわしづかみ。天皇・皇帝・王……君主の称号に注目すれば、「歴史の背骨」が見えてくる。
天皇、皇帝、王……。君主の呼称とは、「世界史を貫く背骨」である。その国や地域の人々の世界観の表現であると同時に、国際関係の中での「綱引き」の結果なのだ。古代中国、古代ローマから、東洋と西洋が出会う近代に至るまで、君主号の歴史的変遷を一気に概観し、世界史の流れをわしづかみにする。多言語の史料を駆使してユーラシア全域を見据える、いま最も注目の世界史家が描き切った「統治者」たちの物語。
2 東洋史家の
2 皇帝の確立
3 「天下」の秩序とその破綻
4 並立する皇帝、相剋する胡漢
2 共存と「混一」
3 華夷秩序の天下
4 清朝と西洋――「皇帝」の定着
2 皇帝と中世
3 近代ヨーロッパの形成と「皇帝」の運命
4 離れゆくイギリス
5 「帝国主義」の時代
2 日本国王
3 「公方」と「皇帝」と「国王」
4 「大君」とその変貌
2 維新の波紋
3 東アジアの変貌
2 現代の世界と日本
主要参考文献
書誌情報
| 読み仮名 | クンシュゴウノセカイシ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 272ページ |
| ISBN | 978-4-10-610832-7 |
| C-CODE | 0222 |
| 整理番号 | 832 |
| ジャンル | 歴史・地理 |
| 定価 | 902円 |
| 電子書籍 価格 | 902円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/10/25 |
インタビュー/対談/エッセイ
スター・ウォーズの敵はなぜ「帝国」なのか
スター・ウォーズといえば、ハリウッドで最も成功した映画の一つ、日本人にもおなじみだろう。日本ではじめて上映されたのは1978年、すでに四十年以上を閲しながら、なお人気は根強い。筆者も中学生のころからのつきあいであり、ご多分に漏れず、シリーズ作品をいくつも、再放送でくりかえし見たクチである。
息もつかせぬスペクタクルが大きな魅力なので、それだけに筋立てはごく単純明快。銀河を支配する帝国の圧政に抗して、解放を求めて戦う共和国復興の物語である。美しきヒロインのアミダラとレイアは母娘二代の元老院議員、冷酷非道なライヴァルが独裁権力を握る帝国皇帝という配役で、これまたとてもわかりやすい。
と思ったところで、考えこんでしまうのが、歴史屋の悪い癖だろう。皇帝と元老院はどこかで聞いたことのある名前、英語もemperorとsenateなら、ローマ帝国にほかならない。ひいては、それを受け継いだ欧米の国家・国制の概念である。
戦闘シーンに興奮した幼い観客のころ、帝国・皇帝が悪、共和国・元老院が善というイメージで、何となく納得していた。しかし東アジアの歴史を学び、否応なく世界史を考えなくてはならぬ歴史屋ともなれば、一概にそうと断言はできない。
ローマ史あるいは市民革命を経た欧米的な価値観・偏見ではないのか。とりわけ史上はじめて共和制を布いた人工国家のアメリカ合衆国がしかり。元老院ならぬ上院Senateをおいたのは、実際の機能はどうあれ、はるかローマ共和政への仮託であって、それなら帝国専制へのアンチテーゼにちがいない。だとすれば、それはそのままスター・ウォーズの世界につながる。
これに対し、東アジアでは二千年来、史上の君主は「皇帝」を頂点に、独自の秩序体系を築き上げていた。皇帝=emperorが悪なら、東アジアの歴史は全くの暗黒となってしまう。まさかそんな史実は存在しない。けれども近代の欧米人は、東アジアを専制体制だと蔑視して憚らなかった。
差別ばかりではない。二〇世紀になると、アメリカは最後まで残った「帝国」の日本を悪の権化として、露骨に敵視した。自国と同じ共和制に転じた中国を圧迫しているとあっては、なおさらである。大日本帝国は消滅したけれども、そんなアメリカ人のセンスが今もなお、そこかしこに残滓をとどめている。スター・ウォーズの世界的な人気もまた、その一つに数えてよい。
古今東西、君主号の歴史をたどってみたら、そんな「皇帝」はじめ、いろんな政体と抗争、多様な関係やバイアスが見えてくる。スター・ウォーズはあくまでエンターテイメント、無邪気に楽しむべし。でも歓楽を尽くした後は、少しマジメに考える時間もあっていい。
(おかもと・たかし 京都府立大学教授)
波 2019年11月号より
蘊蓄倉庫
「裸の王様」は王様ではなかった!
「裸の王様」という、誰でも知っている童話があります。原書は、デンマークの童話作家アンデルセン(Hans Christian Andersen)が1837年に発表したもので、原題は “Kejserens nye klæder”。デンマーク語の原題をドイツ語にすれば“Des Kaisers neue Kleider”、英語なら“The Emperor’s New Clothes”となります。日本語で正確に訳せば「皇帝の新しい服」。「裸の王様」は実は「王」さまではなかったのです。
掲載:2019年10月25日
担当編集者のひとこと
ユーラシアの鼓動が聞こえる
天皇、皇帝、王……。君主の呼称は、その国や地域の人々の世界観の表現であると同時に、国際関係の中での「綱引き」の結果でもあります。
例えば、古代中国の周王朝では、君主は「王」と称し、そこには「天子」という含意もありました。いわゆる「諸侯」が「王」を称することはありませんでした。
しかし、蛮族が侵入し、諸侯が割拠するようになった戦国時代になると、彼らも「王」を自称するようになり、「王」号のインフレが起きます。かくして「王」では中国全土に君臨する天子のありようを表現できなくなり、中国を統一した秦は「皇帝」の号を使うようになるのです。
一方、ローマはもともと「王rex」を頂く王政でしたが、それを嫌ったローマ人たちは、世襲の「王rex」を置くのをやめ、元老院に集った貴族たちが執政官(コンスル)を選ぶ仕組みに変えました。
そのリーダーシップの最たるものは軍の指揮権(imperium)ですが、これを行使する人がimperatorです。カエサル以前、imperatorはたくさんいましたが、imperiumの一元化を目指したカエサルが倒れた後、アウグストゥス以降はこの称号を名乗れるのは「元首Princeps」だけになりました。
その「元首」がカエサル家によって世襲されるようになってimperatorとcaesarは事実上一体化。これがいわゆる「皇帝(エンペラー・カイゼル)」の語源となり、「元首(第一人者)Princeps」の方は「prince」の語源となったのです。
imperium(軍の指揮権、事実上の統治権)の届く範囲が「帝国Imperium」になる構造は、ローマも中国も一緒です。
このように、君主の称号を追っていくと、歴史の動的な実像がくっきりと浮かび上がってきます。君主の称号はいわば「世界史を貫く背骨」とも言うべきもので、この背骨を辿っていくと、世界史の流れがざっくりと分かる。『君主号の世界史』では、古代中国、古代ローマから、東洋と西洋が出会う近代に至るまで、君主号の歴史的変遷を一気に概観し、世界史の流れをわしづかみにしています。
著者は、岡本隆司・京都府立大学教授。東洋史を知る日本人の立場から欧米流の「グローバル・ヒストリー」を批判しつつ、ユーラシア世界から見たご自身独自の「世界史」を構想しているスケールの大きな歴史家です。
岡本先生の歴史叙述の魅力は「動的」であること。もともとのご専門は近代の東アジアの国際関係史、近代の中国史ですが、岡本先生は、「中国」という国も、「中原」という地域も、ユーラシア全域の動態の中に位置づけて理解しようとするので、中国歴代王朝の姿を描く場合でも、それは「アメーバ的」なものとして描き出されます。そこでは自然に、ペルシャ系ソグド商人などがシルクロードを行き交う様子が想像され、草原を疾駆するテュルク系民族の蹄の音も響いてくる。歴史の場面が絵として浮かんでくるのです。そんな歴史叙述が岡本先生の持ち味です。
私は岡本先生が中公新書で出された『中国の論理』を読んで以来、すっかり岡本先生の書くものにハマってしまいました。『世界史序説』『腐敗と格差の中国史』『世界史とつなげて学ぶ中国全史』など、近刊は出るたびに読んでいますが、どれも真に面白い。
初めて岡本先生にお目にかかった際には、ご自身が編者となった学術書『宗主権の世界史』で発酵させたテーマである「君主号の変遷」を追いたいとのご意向を伺いました。ただ、「書き下ろしはきつい」とのことでしたので、新潮社のウェブ雑誌「フォーサイト」での連載をご提案し、二週間に一度のペースで執筆頂きました。その連載をようやくまとめたものが、この「君主号の世界史」となります。
多言語の史料を駆使してユーラシア全域を見据える、いま最も注目の世界史家が描ききった「統治者」たちの物語、どうぞご堪能ください。
2019/10/25
著者プロフィール
岡本隆司
オカモト・タカシ
1965年、京都府生まれ。京都大学大学院文学研究科東洋史学博士後期課程満期退学。博士(文学)。宮崎大学助教授、京都府立大学教授を経て、2025年2月現在、早稲田大学教授。専攻は東洋史・近代アジア史。著書に『近代中国と海関』(大平正芳記念賞受賞)、『属国と自主のあいだ』(サントリー学芸賞受賞)、『中国の誕生』(樫山純三賞、アジア・太平洋賞特別賞受賞)、『世界史とつなげて学ぶ 中国全史』、『悪党たちの中華帝国』など多数。