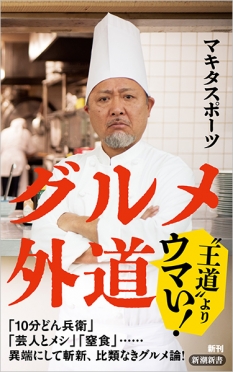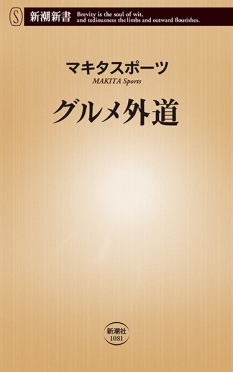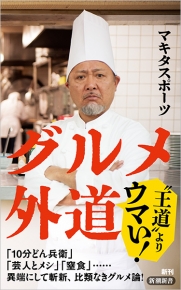
グルメ外道
1,056円(税込)
発売日:2025/03/17
- 新書
- 電子書籍あり
“王道”よりウマい! 「10分どん兵衛」「芸人とメシ」「窒食」……。異端にして斬新、比類なきグルメ論!
大切なのは、テメエが美味いと思うかどうか。世間の流行や他人の評価に背を向け、己の舌に忠実に“食道”を追求する──これ即ち「グルメ外道」なり。自ら提案して大バズりした「10分どん兵衛」から、ラーメンにカレーに焼肉、「窒食」「志村けんの水割り」といった独自すぎる食技法までを、比類なき言語化能力で綴る。庶民的でスケベで斬新──そんな「美味しい能書き」をたっぷり詰め込んだ、最初で最後のグルメ論!
はじめに――胃袋の夜明け
自分が“主役”/「背景食い」という楽しみ/空腹の境目
第一章 私の「ライスハック」
1.「10分どん兵衛」の誕生
哀しい能力/「10分どん兵衛」とは?/誕生の背景/切実な欲望
2.「ライスハック」という極意
五箇条の「ライスハック」/“汁”への偏愛/先発完投型のフライパン/俺は冷蔵庫DJ/窮地を救う名バイプレイヤー/満腹は哀しみ、空腹は娯楽
3.「窒食」という秘かな愉しみ
行きずりの行為/窒食の甘美な記憶/新幹線の茹で卵とコーヒー/窒食アラカルト
4.「納豆チャーハン」の最適解
手強いぞ、納豆は/「納豆チャーハン」は完成しない/納豆にまつわる根深い問題/到達した現在地
5.恥ずかしいバーベキュー
「そこは戦場だ!」/政治的なバーベキュー/バーベキューからの逃避/実践的バーベキュー講座
6.外道寿司
内陸県出身者の複雑な寿司観/寿司歴格差/聖域なき寿司改革
7.素晴らしき哉、メニュー!
あり得たかもしれない「注文」/注文における駆け引き/メニューとは宝探しの地図である/幸福な後悔
第二章 カレー・ラーメン・焼肉――定番をもっと美味しく
1.私のカレー観
カレーと“悪”/「カレー的な何か」/日本とカレー
2.余は如何にしてラーメンを語ってきたか――外道のラーメン論I
ブームの最終地点/「ラーメン評論家」を気取っていた頃/ラーメン界の渋谷陽一
3.「美味しい」だけでは疲れてしまう――外道のラーメン論II
最近のラーメンは疲れる/ラーメンの物語化/55歳の挑戦
4.私のラーメン物語――外道のラーメン論III
一般化の毒/ラーメンの「私化」/極私的ラーメン物語/その店の名は……
5.50代からの焼肉革命
焼肉界の辰吉丈一郎/転ばぬ先のロース――カルビ時代の終わり/「タレ」を知る/「タン塩」をインターバルに/スープで感じる「半島感」/「勝手にビビンパ」――焼肉の脱構築
第三章 芸人とメシ
1.芸人を「食」にたとえる
「ビートたけし=ラーメン」説/「タモリ」という記号/松本人志とお笑いのフランチャイズ化
2.志村けんの水割り――酒とコントは定位にあらず
ただ酔っ払いたいだけ/私のハイボール、その流儀/「混ぜないでくれ」/酒もコントも定位にあらず
3.コロッケとナルシシズム
コロッケが内包する難しさ/コロッケと勝俣州和/親しみやすくない製作工程/コロッケは「おかず」になるのか?
第四章 その思い出に“用”がある――「グルメ外道」の原点
1.歌舞伎町のつくね煮――外道の料理の原点I
我いかにして料理を始めたのか/歌舞伎町の磯辺揚げ/忘れられない味/「つくね煮」を盗む
2.私のモスバーガー物語――外道の料理の原点II
帰郷してすぐに副店長/鬼のバイトリーダーに叱られる/常連さんによる「通過儀礼」
3.食はいつも未知なもの
はじめてのアボカド/習慣と面倒臭さのあいだ/袋麺の政権交代
4.義母が作る奇跡のお雑煮
料理と文脈/「文脈無視」な義母のお雑煮/「奇跡のお雑煮」を継承
第五章 外道のグルメ論
1.人の“食欲”を覗く
「メザシ」の“食欲”/「ピープショー」としての“食欲”/生きる意欲
2.生まれた時からナポリタン
ナポリタンの明後日/「三国同盟的傑作」の末路/ゼネラルとローカル/ナポリタンはナポリタン
3.“実存”としての焼き鳥
たかが焼き鳥……/実体の無い怪しさ/「鳥の肉」という“実存”/「虚鳥実鶏」――焼き鳥のイディオム
4.餃子、その完全なるもの
「包むもの」と「包まれるもの」の神秘/イジられる魅力/「不味い餃子」が美味しい/「マズウマ」の黄金比率
5.現地メシ――その地方の息吹と生活を食べる
スナックの通過儀礼/豊橋で食べる八丈島料理/食べたいのは、地元の「息吹と生活」
6.分けて食べるか、混ぜて食べるか――「丼もの」をめぐる議論
その無分別で非秩序なるもの/メシ汚し問題/“いいかげん”な魅力/「丼もの」におけるステレオとモノラル/山梨の「カツ丼」と冷めた「丼もの」
7.淡さ論――「味巧者」への道
“淡さ”という「センス・オブ・ワンダー」/ふたたびの残り汁/“強い”から“淡い”へ/「味巧者」への道
おわりに――ピュアな外道
書誌情報
| 読み仮名 | グルメゲドウ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 考える人から生まれた本 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 256ページ |
| ISBN | 978-4-10-611081-8 |
| C-CODE | 0270 |
| 整理番号 | 1081 |
| ジャンル | アート・建築・デザイン、クッキング・レシピ |
| 定価 | 1,056円 |
| 電子書籍 価格 | 1,056円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/03/17 |
書評
逸脱から始まるルネッサンス
腹が減ったらメシを食う。そのメシがうまければ、こんなに幸せなことはありません。人類史の大半において、人は常に飢餓と隣り合わせでした。しかし今の日本は決してそうではありません。おおよそ誰もが、うまいもので腹を満たす自由を手に入れています。
うまいものを食う自由が極まったのが、グルメという概念です。生命維持のための栄養補給という目的を遥かに超え、様々な叡智が自由闊達に駆使されます。それなのになぜかグルメの世界においては、皮肉なことに、自由は何かと剥奪されがちです。
マナーが堅苦しい、みたいな話をしているのではありません。そもそもマナーというものは、その食べ物を最もおいしく食べるためのノウハウが蓄積されたものでもあります。よしんばそれが肌に合わずとも、グルメの世界においては、マナーに縛られず豪放磊落にかっ喰らうという振る舞いも、許されるどころかむしろ推奨されています。
では何がいったい不自由なのか。グルメの世界には、暗黙の前提が多すぎるのです。たとえばラーメンを例に挙げてみましょう。麺にはコシがないといけないことになっています。スープはあっさりだろうとこってりだろうと、コクがあって複雑な旨味を湛えたものでなければなりません。チャーシューはジューシーでなければなりません。そうでなければ「うまいラーメン」とは認定してもらえないからです。それがルールです。
ラーメンに限らず、カレーも餃子も焼肉も寿司も、だいたいあらゆる食べ物は、「こういうものがうまいとされているのだ」的な、暗黙の了解の上に成り立っているのがグルメの世界と言えるでしょう。それは本来、おいしいものに効率よく出会うためのヒント集のようなものだったはずです。しかしそれはいつしか、逸脱を許さない経典の如きものになっていきました。
著者マキタスポーツさんは、紛う事無きグルメです。その美食への飽くなき追求ぶりは、どこか求道的ですらあります。だから本書は、誰もが美食にたどり着くための実用的なヒントが満載です。
一世を風靡した「10分どん兵衛」に始まり、試行錯誤の末に辿り着いた納豆チャーハンのレシピ、カルビの脂がキツい年齢になり始めてからの焼肉の楽しみ方、丼物の盛り付けに関するコロンブスの卵的新提案……。それらは読者のグルメライフを、明日からでもすぐに向上せしむるものです。しかもそれらは、単にノウハウのみが示されているわけではありません。そこに至る背景と道程が、実に丹念に記されています。
ところがその道程における著者の態度は、一般的なグルメとは大きく異なります。すっかり経典化しつつある現代のグルメルールから、ひたすら逸脱し続けているのです。著者はそれを、人の話を聞くのが苦手という哀しい能力があるから、と自己分析しています。しかし本書を読み進めていくと、そこにはもうひとつ、重要な要因があることにも気付かされます。それは「恥」の概念です。
作中、著者はやたらと恥ずかしがっています。乙女のようです。普通であれば、人々は、グルメルールから逸脱してしまうことを恐れ、恥じます。だからこそグルメルールは経典化したのです。しかし著者は逆です。意識的にせよ無意識的にせよ、グルメルールに沿ってしまいそうになると、途端に恥ずかしくなってしまう。
それどころか、食べることについて考えること、語ること自体が恥ずかしいとまで言い切ります。グルメがすっかり高尚な趣味の如く扱われるようになった現代において、我々がつい喪失してしまいがちなこの繊細さこそが、本書のしなやかな背骨となっています。
タイトルに「外道」とあるように、本書は終始、既存の経典からの道を外れつつ、それでもおそらく多くの人々の共感を呼ぶでしょう。だからそれはある意味、新しい経典のようにも見えます。しかし同時に著者は、経典となることを決して望みません。その代わり、そこに書かれていることが全て、あくまでパーソナルな「私だけの食べ方」であることが強調されます。だからむしろそれは、硬直化するグルメ経典から、人間中心主義的な主体性を取り戻すルネッサンスなのです。
いったいどういうことなのか。最後に、作中で著者自身も一部引用している寅さんの名言を置いて終わりたいと思います。
「おまえと俺は別の人間なんだぞ。早え話がだ! 俺が芋食って、おまえの尻からプッと屁が出るか!」
――「男はつらいよ」脚本:山田洋次・森崎東(1969年、松竹)
(いなだ・しゅんすけ 料理人)
著者プロフィール
マキタスポーツ
マキタスポーツ
1970(昭和45)年山梨県生まれ。芸人、ミュージシャン、俳優、文筆家など、多彩かつ旺盛に活動中。映画『苦役列車』で第55回ブルーリボン賞新人賞などを受賞。著書に『決定版 一億総ツッコミ時代』『すべてのJ-POPはパクリである』『越境芸人』『雌伏三十年』など。