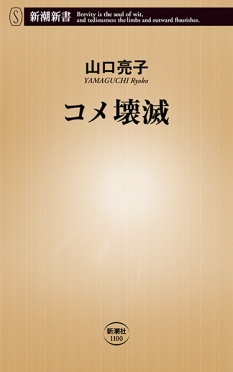コメ壊滅
968円(税込)
発売日:2025/09/18
- 新書
- 電子書籍あり
国民負担3兆円の衝撃! コメ騒動は何度でも繰り返す。
コメ不足は予測できた。農業白書には「需要が供給を上回る」ことを明示したグラフさえ載っていた。それでもコメが消えたのは、需給をマッチングさせ価格を下げすぎないという、市場原理を無視した減反政策が続いてきたからだ。農相がパフォーマンスで価格介入したところで構造はすぐには変わらない。つまり、この人災はこれからも繰り返されるのだ。農業ジャーナリストが抉り出す「日本のコメ」の歪んだ現実。
序章 1年で3兆円が消えた
第1章 農相が吐いた「七つの大嘘」
1 「新米が出回れば、価格は落ち着く」
2 「備蓄米を放出しない決断に誤りはなかった」
3 「流通がスタックしている」
4 「価格の安定なんて書いてありません」
5 「自己批判できる」農林水産省に
6 コメ不足は「風評」
7 「44万トンを新たなプレーヤーが持ってらっしゃる」
第2章 高すぎて消えていく需要
1 中食・外食に打撃
2 日本酒、焼酎、米菓に味噌……日本の食文化がピンチ
3 小売りまで外米が席巻
第3章 減反の罪
1 人災
2 「令和のコメ騒動」へのレール
3 繰り返すコメ不足
第4章 農業ムラが潰したコメ市場
1 戦前の統制経済の亡霊
2 先物市場の廃止
3 遅すぎた再上場
第5章 空転する輸出戦略
1 消費者に負担を強いる内外価格差
2 ワシントンの業界団体が猛攻勢
3 輸出業者は「大打撃」
第6章 コメ不足を招く「三高」
1 「コシヒカリ神話」の終焉
2 「高温」「高騰」「高齢化」
3 「安くなりようがない」
終章 小泉劇場という茶番
主要参考文献
初出一覧
書誌情報
| 読み仮名 | コメカイメツ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-611100-6 |
| C-CODE | 0261 |
| 整理番号 | 1100 |
| ジャンル | 農学 |
| 定価 | 968円 |
| 電子書籍 価格 | 968円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/09/18 |
インタビュー/対談/エッセイ
消費者悩ます米価の二極分化
新米・高知県産コシヒカリ 3980円(税抜)
国産備蓄米 3980円(同)
8月下旬、近所のスーパーのコメ売り場で、同じ価格のコメが並んでいた。同じと言っても、袋の大きさは全く違う。前者は5キロ、後者は倍の10キロである。
あまりの違いに、売り場を訪れた客は、値札としばし睨み合うことになる。30代と思しい男性客が、意を決したように高知県産コシヒカリの袋を摑み、レジへと大股に歩いて行った──。
男性の一大決心(?)は、現状のコメの流通を踏まえると合理的と言える。この時期に買える新米で、高知県産は割安だからだ。
温暖な気候の高知県は、通常より早く収穫する早期米の産地だが、コメ業界では、JAのモチベーションの低さで知られている。あるバイヤー(買い付け担当者)は、当地のJAについてこう話していた。
「やる気がないんだ。高く売る気がないんだよ」
JA高知県が示した2025年産の概算金(農家への仮払金)は、60キロ当たり2万2000円(一等米コシヒカリ)。前年産より5割近く高い。
そうではあるが、早期米の他の産地が示した概算金に比べると、やはり見劣りする。鹿児島は2万7000円程度、宮崎は3万2000円程度だ。
そんな高知県産の新米ですら、備蓄米の倍の値が付いている。いわんや他産地をや。千葉県産ふさこがねは、5キロ4280円(税抜)という、備蓄米より1割近く高い値段で売られていた。
ふさこがねは収量が多く、冷めても味が落ちにくいとされる。どちらかというと、中食、外食といった業務用に好まれる。それがこの高値である。
同じ価格で倍の量を買えるのが、小泉進次郎農相が放出した備蓄米「小泉米」だ。ただ、この小泉米のコメ業界における評判は芳しくない。
古い備蓄米は、貯蔵の過程でカビが生えたり食味が落ちたりしやすく、品質を担保しにくい。コメ卸からすると、江藤拓前農相が放出した比較的新しい「江藤米」と違って、消費者から経年劣化に対するクレームが届きかねないという心配があった。だから、小泉米の販売者は、スーパーなど小売店になっている。
もともと8月に売り切るはずの小泉米は、大量に売れ残っている。安いコメの選択肢を残すとして、引き続き店頭に並ぶことになった。かたや新米は、早期米に限らず東北をはじめとする大産地も、強気の値付けをしている。
新著『コメ壊滅』では、このようなコメを巡る様々な「歪み」の原因を探った。それにしても、店頭価格の二極分化はいつまで続くのだろうか。
(やまぐち・りょうこ ジャーナリスト)
蘊蓄倉庫
暑さに弱いコシヒカリ
日本全体のコメの作付面積のうち、現在「コシヒカリ」が3分の1を占めています。魚沼などの有名な生産地を抱える新潟県について言うと、その割合は62・7%(2023年)と圧倒的な高さです。食感がよくておいしいコメの代表品種であることは間違いないですが、実はこのコシヒカリ、「暑さに弱い」という欠陥があります。
猛暑に見舞われた2023年には、新潟県産コシヒカリで、最高等級にあたる一等米の割合が過去最低の4・7%を記録しています。近年は75%ほどなので、いかに「熱にやられた」かが分かります。ちなみに「あきたこまち」もコシヒカリの近縁種で、同じ2023年には秋田県の一等米比率が過去15年で最低の水準に落ち込みました。コメ不足には、このような「コシヒカリ系統のコメばかり作ってきた」生産現場の偏りも背景にあったのです。
掲載:2025年9月25日
担当編集者のひとこと
令和のコメ騒動は人災だった。
2024年、「令和のコメ騒動」と言われる事態が発生しました。コメが品薄になり、米価が急上昇。それでも農水省は「コメは足りている」と強調するばかりで、事態を沈静化させることはできませんでした。
端的に言えば、農水省はウソをついていたのです。その証拠は、他ならぬ農水省が出している公的文書です。『農村白書』に掲載されたグラフを見れば、コメの需要と供給が2021年にほぼ一致したのを境に、ずっと供給量が需要を下回っているのが確認できます。つまり、コメ不足はここ数年で構造化してしまっているのです。
そうなる理由は、温暖化や異常気象による生産量の減少、インバウンド需要によるコメ消費の増大、生産量予測体制の不備など細々したものもありますが、根本的かつ最大の理由は「減反政策が大失敗したこと」にあります。コメ需要の低下を予測しコメ価格の維持・高騰を狙った農政が、転作を奨励し、主食用米の生産量をずっと減らし続けたそのツケが、「コメ騒動」という形で噴出したのです。
通常の商品であれば、市場による調整機能によって需給は自然とマッチングしていきます。しかし、コメについては国家カルテルによって需給が調整されています。小売価格の指標になるのは、JAが生産農家に提示する不透明な「概算金」だけ。価格の指標となるコメの先物市場を本格的に導入しようとの機運も農業界にはあって、試験的な導入もされていましたが、価格決定権を手放したくないJAからの横やりが入り、本格導入前に潰されてしまいました。
実は、こうした農政の構造の形成には、現在の与野党トップにも大きな責任があります。2009年に麻生内閣の農相を務めた石破茂現総理は当時、省内に改革チームを立ち上げて減反の是非について検討し、「減反は将来性がないから早くやめた方がいい」という結論を得ていました。しかし、そのシミュレーション結果が農水書の公式見解となることはなく、農政の軌道修正はされませんでした。石破総理は少なくとも、「無策だったことの罪」からは免れられません。
また、立憲民主党代表の野田佳彦氏には、2010年、民主党が政権を担っていた当時の財務大臣として、「農業者戸別所得補償制度」を導入し8000億円もの巨額予算をつけた過去があります。これは、主食用米から米粉用米や飼料米へ転作すると大きな補償金が交付される制度ですが、コメの「用途」を決めてしまうことで、特定の用途のコメが足りなくなるという構造問題を生んでしまいました。
実際、米粉用や飼料用のコメが激増し、2012年には今回と同じような主食用米の不足が起きて、備蓄米の放出を余儀なくされています。民主党政権が生み出した「コメをコメで転作する」方法が、現在の主食用米の不足、米価の高騰を招いていることもまた確かなのです。
著者の山口亮子さんは、政策担当者から生産現場、流通関係の当事者まで幅広く取材し、コメ行政の「歪んだ現実」を暴きだしています。これは「過去の話」ではありません。問題の発生には農政の構造問題があり、その構造が変わらない限り、同じ問題は何度でも繰り返す。つまり、これは将来の話でもあるのです。
令和のコメ騒動を受けて、農水省は減反から増産に舵を切りましたが、需給をマッチングさせるという生産調整機能は手放していません。つまり、社会主義的なシステムは残っている。その構造が続く限り、「騒動」は何度でも起こるでしょう。
コメと農政の問題を理解するという点において、最適な著書による最適な本です。自信をもっておすすめします。
2025/09/25
著者プロフィール
山口亮子
ヤマグチ・リョウコ
ジャーナリスト。愛媛県生まれ。京都大学文学部卒。中国・北京大学修士(歴史学)。時事通信記者を経てフリーに。著書に『日本一の農業県はどこか 農業の通信簿』『農業ビジネス』『ウンコノミクス』などがある。企画編集やコンサルティングをてがける(株)ウロ代表取締役。