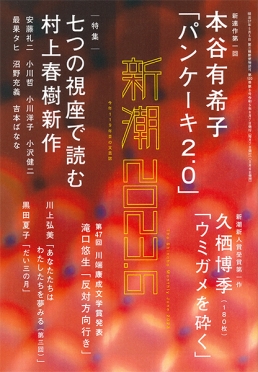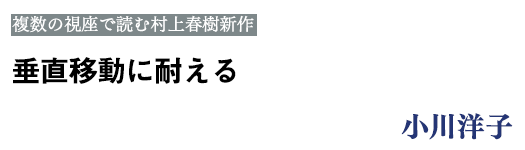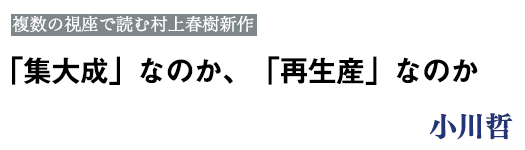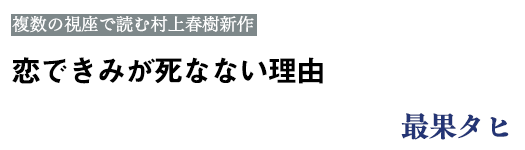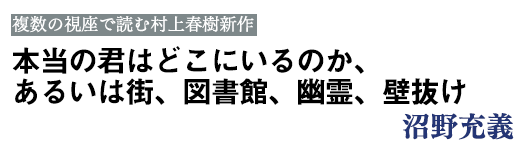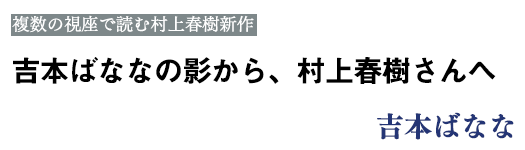作家は自らに固有の表現の場所を定め、それを深く、広く、掘り進めてゆく。いまここに『街とその不確かな壁』を世の中に問うた村上春樹は、そうした作業をこれまで徹底して追究してきた希有な作家である。そのことが、誰の目にも明らかとなった。作者自身が巻末に例外的に付した「あとがき」のなかで、この特異な長編小説が書き上げられるまでの経緯を過不足なく語ってくれているからだ。
なによりも、この物語には原型となった中編小説が存在している。雑誌『文學界』一九八〇年九月号に掲載された「街と、その不確かな壁」である(以下、この中編小説を指す場合には「街」を、ほぼ同じタイトルを付された長編小説を指す場合には『街』を用いる)。しかも、作者が自らにとって表現の原型にして表現の原風景としてある作品を長編小説として書き直すのは、今回がはじめてではないのである。現在から見るならば、その初期の文業を代表する『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(一九八五年)が、それである(以下、『世界の終り』と略する)。
『世界の終り』は、村上春樹がその後に展開していく作品世界全体の基本構造を規定していくことにもなった。時間と空間によって隔てられた二つの世界の並行と対立、そしてその交錯という構造にして形式である。そうした構造と形式をもつ物語世界は、やはり作者自身が『世界の終り』の非連続的な続編と位置づけている『1Q84』において頂点を迎える。私はそう思っている。私が、村上春樹のこれまで刊行されてきた著作群のなかで代表作を選ぶとするならば、この二つの巨大な作品、『世界の終り』と『1Q84』に尽きる。
そうした自身の表現の起源に位置する作品に、いまここで、あらためて立ち還ろうというのである。「街」が書かれたのは作家としてデビューした直後、その翌年のことであった。起源とは、時間的かつ空間的に固定されたものではなく、そこに立ち還る度ごとに新たな表現の時間と空間が生み落とされ、生み直されるものでもあるだろう。そういった意味で、起源の場所とは発生の場所であり、反復こそが差異を生み出す祝祭に似た儀式が執り行われる場所でもあったはずだ。生命の故郷であり、想像力の故郷である。しかし村上春樹には、大江健三郎における四国の谷間の村、中上健次における紀州の「路地」のような、表現の種子を無尽蔵に秘めたような特権的な故郷は存在しなかった。そのような故郷を、ただ想像力のみによって、いまここに創り上げなければならなかった。
特権的な故郷をもたない者は、一体どこに故郷を求めれば良いのか。「心」のなか、その深みにおいて、である。「街」から『街』へ、それが村上春樹の導き出したきわめて一貫した結論である。「心」の深みには、永遠にして無限の世界へと至る通路がひらかれている。しかし、その世界は、そこにおいて時間が消滅し、空間が消滅してしまう、まさに〈世界の終り〉としか形容できない場所でもあった。〈世界の終り〉では、個別の肉体と個別の名前をもった人間は、影から切り離されることによって、個別の肉体と個別の名前を失い、いわば純粋な想念としてのみ生きる存在となってしまう。高い壁に囲まれた、他者からは閉ざされた領域を生きる存在となってしまう。果たしてそのような場所に生の幸福、表現の幸福は存在するのであろうか。〈世界の終り〉を〈世界の始り〉に転換することはできるのであろうか。
さまざまな形で表現の実験を繰り返しながら、村上春樹は、自らが書いてしまった〈世界の終り〉について、責任を負い続ける。『世界の終り』には、すでにこの時点で、後の作家としての悪戦苦闘を予言するかのような一節が刻み込まれていた。「だからこの〈世界の終り〉という君の意識の
村上春樹は、『世界の終り』の結末を引き受けつつ、壁の外側へと脱出した影のその後の物語を紡ぐことを選ぶ。影にあらためて固有の肉体を与え、具体的な時間と具体的な空間を生き直させる。〈世界の終り〉に留まったこの「私」を生き直すための分身としての物語を与えるのだ。そして、現在しか存在せず、「虚空」に宙づりにされてしまったような街から、過去と未来が存在するこの大地に、「私」を落下させる。そうした「私」を受け止めてくれる者として、「私」の分身を育む。高い壁に囲まれた街を、あらためて時間と空間のなかに受肉させるのだ。そのとき、〈世界の終り〉は〈世界の始り〉へと転換するであろう。現実へと落下する「私」の受け手を物語として育む。そこには、自身が日本語へと翻訳した『キャッチャー・イン・ザ・ライ』からの反響を読み取れる。さらに、高い壁に囲まれた街の発生そのものを、『世界の終り』のように「私」にだけ閉じることをさせない。高い壁に囲まれた街は、「きみが語り、ぼくがそれを書き留める」ことによってはじめて目で見ることが可能になったと記す。「ぼく」の前から消え去ってしまった「きみ」に十全な物語を与える。そこには、〈声を聴くもの〉である教祖と青豆、物語を語る教祖の娘「ふかえり」とそれを書き直す天吾という『1Q84』における関係性が創造的に再生されているかのようだ。
つまり、『世界の終り』以降その手にすることができたあらゆる技法を駆使し、あらためて自身の表現の起源の場所に立ち、その起源の場所をゼロから作り直すことが試みられているのだ。一体なぜ、そのような試みが、全世界が感染症によって閉じられてしまった時期になされなければならなかったのか。「そのような状況は何かを意味するかもしれないし、何も意味しないかもしれない」。作者が「あとがき」にそう記している以上のことを批評家が言えるわけもないし、言ってもならないであろう。しかし、最後に一つだけ、特権的な故郷をもたなかった村上春樹が執拗に書き続けた想像の故郷、「心のなかの、いまだ何処にも存在しない場所」(映画監督ジャン=リュック・ゴダールの言葉から借りた)について、その著作をここまで読み続けてきた者が思ったことを記しておきたい。
村上春樹は、ガルシア=マルケスやホルヘ・ルイス・ボルヘスへの偏愛を隠さない。『世界の終り』ではボルヘスが参照され、『街』ではマルケスの著作が直接引用されている。ボルヘスもマルケスもヨーロッパの言語で著述をなしたが、そこには超近代的な世界文学と、前近代的で「土俗的」なラテン・アメリカの文学が相互に矛盾するまま一つに結び合わされていた。生者と死者の境界が曖昧であり、心の内側の世界と外側の世界の境界が曖昧である。近代の日本文学もまた、ボルヘスやマルケスが生きざるを得なかったのと同様な場所に生まれたのではなかったか。普遍を目指した近代的な世界文学と、前近代的な影を引きずった日本あるいはアジアに固有の文学との狭間に……。村上春樹が書き続け、その謎を解き明かそうとし続けている〈世界の終り〉もまた、一方では近代的な心の科学の主題である、意識の「水面下深くにある、無意識の暗い領域」であるとともに、もう一方では、前近代的な心の信仰の主題である、村上春樹もその血族の一員として連なる浄土の教えと重なるものではなかったか。エピグラフに掲げられた『クブラ・カーン』、その源泉となった『東方見聞録』とも響き合うような……。
「街」においても、『街』においても、「私」ははるかな「東」から西の涯にある街を訪れる。その街を維持し、「古い夢」を生み出すのは黄金の身体をもった無数の獣たちである。西方極楽浄土は無限の時間(