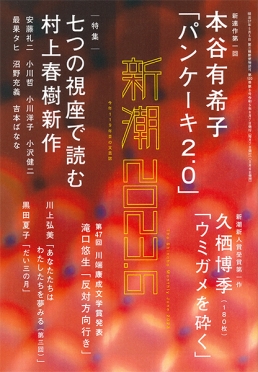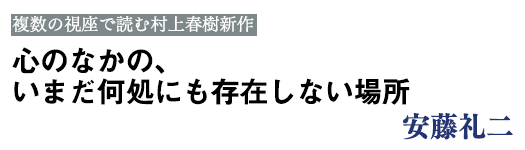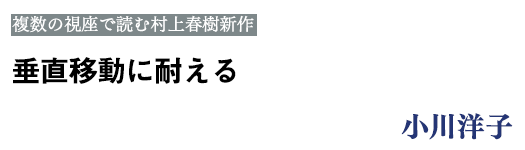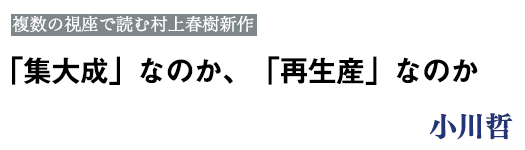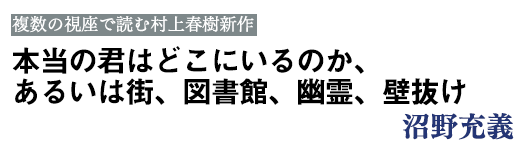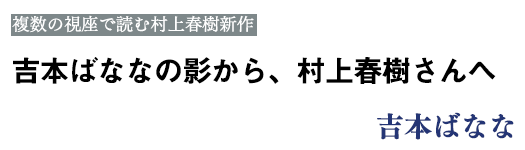昔の恋を忘れられずいつまでもそれに囚われる、というのは、本当のところどういうことなのだろう。それは本当に運命的な一度きりの恋なのだろうか? 突然終わりを迎えてしまったからこそ、そこに運命を読み取らずにはおれず、自分の心に杭を打ち付けてしまっているのではないか。
不完全燃焼だった恋だからこそ、永遠のものに感じることはあるのかもしれない。後悔や未練が生み出したのがこの物語でいう「街」であるとして、「私」はその「街」に永遠に住むことはなかったのだ。それが何より重要なことのように思える。永遠を達成するのはまた別の、「特別な」少年であって、「私」は未練のそのあるじであったのに、自らの意思でそこを出て行くことになる。
愛情の成就は、それを終わらせる引き金ともなる気がする。二人が結ばれたのなら後はほどけていくだけだ。だから、結ばれる手前の関係が一番、「永遠」を感じさせる。まだ来ない最良の時を待ち望むことができるから、そのときだけ「永遠」を信じることができる。
突然、そんな「永遠」の気配を感じている状態で関係が途切れたとき、人は「永遠」の夢を、それこそ永遠に見てしまうんだろう。むしろそれまで遠くで揺れて見えていた「永遠」のきれはしを忘れないために、いつまでもその恋を運命だったように捉えてしまう。他のどんな恋人もその記憶を超えることがない、というのは当たり前で、成就してしまえばいつも「永遠」は消えてしまうものだから。彼女だから、というより、途切れてしまったから、いつまでも忘れられないのではないか。
もちろん、途切れてしまったのは彼女が彼女だから、なのだけれど。それでも「途切れる」ことこそが、「永遠」と「街」に大きな意味をもたらしているように思う。
街にいる彼女は「私」を思い出さない。別の存在なのだから当たり前だ。終わってしまった関係が、未練によって作られた街で、再生することはない。当たり前だ。再生すればきっと何年も未練が続くような恋にはならないようにも思える。「街」が厳格な作りをしていたのは、恋が不完全燃焼だったからだ。もう一度、火をつけることはできない。
美しい記憶や人生に打ち付けられた楔のような恋を、それは途切れてしまったからであって、恋そのものが奇跡的であったからとは言えません、と前述のように言い切ってしまうのは簡単だけれど、そんなことは本当は誰もが知っていることであるはずだ。それより、どうして人はそうやってそんな「途切れた恋」に永遠を見出してしまうのか、そしてそれでもどうして生き延びているのか、そここそが大切なことのように感じる。途切れた恋に「永遠」を見出すなら、人間は恋などしない方が幸福で、もしくは、「永遠」が見えた瞬間に死んでしまうのが唯一の手立てに見えてしまうんだ。
それでも人は、そんな「永遠」の中に閉じ込められて、未練を単なる心のくすぶりではなく、一つの冒険や課題として見つめられたとき(つまり「未練」の中で今を生きることができたとき)、自分が永遠や不変や奇跡に属するようなそんな鮮烈な感情とはまた違うものを、抱きしめられることを知る。自分の心や肉体が、そもそも絶対的にも永遠にもなれないことを知る。自分は、劇的な感情のために生きているわけではないと知るんだ。それは人間の生々しさ、血の色や肉の柔らかさ、体温の生ぬるさそのもので、肉体だけでなく心にもそうしたところがあるのだろう。生ぬるくて、全てを燃やし尽くすような情熱とは真逆の、ある意味で「中途半端」でロマンチックとは共存し得ないものが。
通常なら、未練や後悔をただ頭の中で燻製するしかなく、過去を何度も繰り返し思い出すしかなく、それらを今の冒険として捉え、今の感情として昇華していくことなどなかなかできないはずだけれど、けれど、それでも「課題」として未練を見つめ直すことができれば、人は自分の心のぶよぶよとした生々しい手触りに気づくことができる。苦しみや悲しみの奥にある、語られることはなかなかないぬるくて淡い感情。どんなに苦しんでも悲しんでも、その後も生きてきたのはどうしてなのか。あれが恋の全てだと思っても、その全てが終わっても、死ななかったのはどうしてなのか。ドラマで取り上げられるような、激しい感情が心の全てではなく、悲しい日も苦しい日も人体はお腹が空くように、心にもまた、悲しみきれない部分がある。普通は目の前の痛みに囚われて、それらに目をやることができない。でも、物語はそれを可能にするのだ。「私」という他者の未練を追うことで、私たち読者は人の、ぬるくて淡い感情の中に飛び込むことができるんだ。
「現在」が超えることのできない「過去」。絶対的な恋。奇跡的な関係。それらに人はロマンを感じすぎだ。本当はそんなものは体には合わない、心にも合わない、そしてそんなものを軽々と超えてしまえる肉体と心の身勝手さと中途半端さこそが、決して一つの真実なんかに収束していかないその姿こそが、生命のきらめきなのかもしれない。
16歳の頃の恋の相手を永遠に忘れられなかった男性がたどり着く相手として、コーヒーショップの女性は個人としてはそれほど説得力を持たない。もしも「この人なら」という説得力が少しでもあったら、まるでその人のために昔の恋はあったように(つまり踏み台になったように)見えるだろうし、その人自身には大して説得力がないからこそ、その人が探していた存在だと思い至る「私」の生命がきらめいて見えてもいる。彼女が「待つ」必要のない女性であるなら、「私」は「街」を出る気にはならなかったのではないか。コーヒーショップの女性もまた「永遠」の可能性を携えている人だ。「私」はコーヒーショップの女性そのものに全てを覆されたというより、完全に結ばれる日がまだ遠く、「永遠」になり得る関係を見出したからこそ、ここに落ち着いたのだろう。
コーヒーショップの女性との出会いは偶然そのものであるし、運命や「おさまるところにおさまる」というものでもない。彼女と状況が似た他の女性と他のあり方で出会っていても、もしかしたら同じ結論になるのかもしれない。「待つ必要がある女性」は、この世界に僅かにしかいないわけではない。そしてそれでいいように私は思う。そのほうがいい。人は、物語のために生きているわけではない。運命的な恋に殉職するように一人の人を思い続けて死ぬ人間などいないし、そこに「純粋」や「誠実」を第三者が感じ取って、痺れたり涙を流したりするのはグロテスクだと思っている。そしてそれを本人がなぞろうとしてしまうことも。長く引きずってきた過去の恋への未練が終わる時、そこに「絶対的な恋」を求めるのはそれはあまりにも図々しい期待だ。人の命は未熟で生っぽくて、それから「オチ」のためでも「結末」のためでもない過程を愛することができる存在だ。「私」はまさにそういうあり方を最後に選び、そうして「街」を出ていった。過去より現在が優ったからでも、過去を諦めるのでもなくて、人は生きているから。どうやっても眼前に広がるのは「現在」なのだ。本人が選ぶなんて、そんな話ではなく。そこにあるのは意思ではなく、ただの事実だ。生きているから次に行くのだ。
新たな恋を見つけるというより、新たな「待つ必要」に遭遇して、「私」は「街」を出て行った。
影は、本体を受け止められるだろうか。その答えを物語は描いていない。でも、受け止められないわけがない、と思う。彼は目の前に起きた出来事を、自分の「今」として受け入れている。物語の殉職者としてではなく、命として在ることを選んだなら、命は彼に応えるだろう。人は、過去の自分を納得させようと紡いだ運命や奇跡の物語のために、生きていくわけではないんだ。