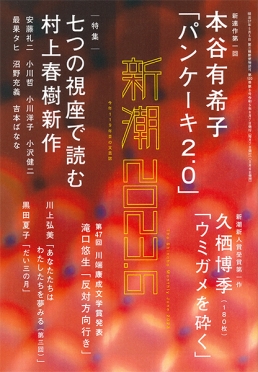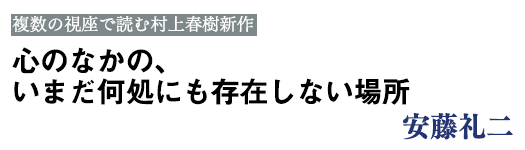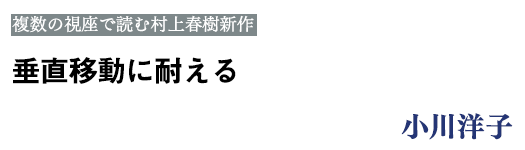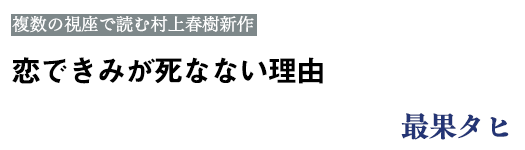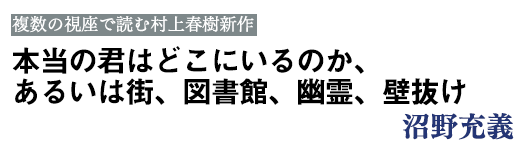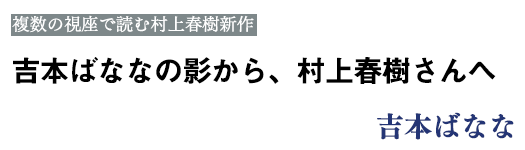海外文学から多大な影響を受け、著作が広く翻訳され、日本だけでなく世界中に読者を獲得している作家――と言われて、誰の名前を思い浮かべるだろうか。
あるいはこう言い換えてもいい。同じモチーフやテーマを複数の作品の中で繰り返し問い続け、自作の参照や再解釈を行う作家。
ある人は大江健三郎の名前を、また別の人は村上春樹の名前を思い浮かべるだろう。
こうして二人の世界的な作家の特徴を恣意的に取りだすと、二人は非常に似通っているのではないかという印象を抱くかもしれない。しかし――おそらくみなさんもご存知のように――この二人の作風や文体に近い点は見当たらない。むしろ、ある意味では対極にあると言ってもいいかもしれない。『1973年のピンボール』が『万延元年のフットボール』をもじったタイトルであるという点以外に、二人を結びつける点はなさそうに思える。
どうして僕がこんな話をしたのかというと、村上春樹の新作『街とその不確かな壁』をプルーフ版で読んだときに大江の「晩年様式」という言葉を思い出し、そしてそれから間もなく大江の訃報を耳にしたからだ。この二つの出来事は偶然でありながら、しかしこの偶然には何か意味があるのではないかと考えたくなった。
村上春樹という作家に対してそれなりの知識を持っている読者であれば、『街とその不確かな壁』というタイトルを耳にして、すぐに二つのことが頭に浮かぶはずだ。一つはかつて文學界に掲載され、本人の意向で書籍に加えられていない幻の中編「街と、その不確かな壁」のこと。そしてもう一つは「街と、その不確かな壁」を書き直す形で発表された長編『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のこと。大江健三郎が『同時代ゲーム』を書き直す形で『M/Tと森のフシギの物語』を発表したことは有名だが、村上春樹は一度ならず二度までも「街と、その不確かな壁」という作品を書き直したのだ。
『街とその不確かな壁』(ややこしいかもしれないが、新作長編の方)は三部構成となっている。
第一部では、十七歳の「ぼく」が十六歳の「きみ」の影と恋をする話と、大人になった「私」が本当の「君」のいる「高い壁」に囲まれた「街」で生活する話が交互に語られる。
第二部は、「街」から「現実」へと戻ってきてしまった「私」が、福島県の山間にある小さな町の図書館で働きはじめる話だ。その町で、前館長の子易さんや司書の添田さん、イエロー・サブマリンのヨットパーカを着た少年、コーヒーショップの店員の女性などと交流しながら、私は「街」と「町」の境界を彷徨う。
第三部は、再び「街」の世界に入りこんだ私が、再び「現実」へ戻ろうとする話だ。
その「街」の外には「金色の獣」がいるし、「街」に入るためには「影」を引き剥がさなければならない。「街」へやってきた「私」は「図書館」で〈古い夢〉を読む仕事をしているし、その図書館では「君」が働いている。「街」の造形や設定がかつての「街と、その不確かな壁」(あるいはその長編化である『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』)と類似しているだけではなく、本作は村上春樹作品によく出てくるモチーフに溢れている。かつて交際していた「心がこわば」った「きみ」と、コーヒーショップで働く「彼女」の二人に、『ノルウェイの森』における直子と緑を重ねることもできるだろう。あるいは、福島の小さな町の図書館からは『海辺のカフカ』の甲村記念図書館を思い出すかもしれない。ある日を境に連絡が取れなくなってしまう「きみ」は、『ねじまき鳥クロニクル』の妻クミコのようでもある。迷いこんでしまった異世界から脱出する話という意味では、『1Q84』とも似ている。もちろん作中ではサラダも作るし、パスタも茹でる。深い穴や井戸も出てくる。
本作について「村上作品の集大成」という言葉が真っ先に浮かぶ。あるいは少し意地悪な言い方をして「再生産」と評したくもなる。
「集大成」なのか。それとも「再生産」なのか。
どちらにせよ、長年村上作品に親しんできた一人の読者として、これまで村上作品において物語を形作ってきた技術的な側面が、ほとんど職人的な域に達していることには触れておきたい。
止まることなく体に染みこんでいく平易でリズムのいい文章に、芸術的なまでに上手な読点の使い方。生と死、光と闇、身体と影、日常と非日常といった概念を対比させつつ、その間を行き来する表現。「高い壁」に囲まれた「街」というフィクションと、「山」に囲まれた「町」という現実。たとえば二つの「街」と「町」に、死者として現れる子易さんは、フィクションと現実の境界を曖昧にし、しばしばその二つを反転させる。そうやって、一見して対比的な二つの概念を反転させたり、止揚したり、あるいは対比が存在するための梯子を外してしまう場面が、本作では繰り返し描かれている。この技術の集積が、平易かつ難解な物語を成立させ、「言語化のできない事象を物語る」という文学の核心に迫っていく。
また、ユーモアや比喩の力も健在だ。僕は一人の小説家として、村上春樹のユーモアや比喩表現そのものよりも、その使い方にいつも着目している(もっと言うならば、「盗みたい」と思っている)。村上春樹は、物語上の難所や、言語化のできない場面を、ユーモアや比喩によって容易く突破してしまう。あまりにもあっさり突破してしまうので、読者はしばしば「わからないことに納得してしまう」という事態に気づかないまま先へ進む。
たとえば、少年が行方不明になってから、コーヒーショップで彼女と会う場面だ。かつて「ぼく」が交際していた「きみ」と、目の前にいる「彼女」がオーバーラップし、過去と現在の境界が曖昧になる描写がある。かつての「きみ」の言葉を思い出して目を閉じた「私」は、「ねえ、何を考えているの?」と聞かれ、「ロシア五人組のこと」と答える。ロシア五人組のうち、あと一人が思い出せない、という話と、「彼女」を一人にしない、という「私」の思いが重なり、すべての描写と会話がシームレスに繋がっていく。なるほど、こういうやり方があるのか。
あるいは、「街」に再びやってきた「私」が、イエロー・サブマリンの少年から酋長の話を聞く場面もそうだ。少年は「誰でも足を使って椰子の木に登るが、椰子の木よりも高く登った者は、まだ一人もいない」という酋長の話を引用する。もともとはヨーロッパ人が高い建物を建設して上を目指す様子を揶揄する言葉だが、この現実離れした「街」に滞在することを「椰子の木よりも高く椰子の木を登って」しまうことだと表現することで、「虚空に浮遊している」という状態をアナロジーによって説明してしまう。ここでは、「椰子の木に登る」というシンプルな挿話から、「テキスト通りの酋長の話」と「酋長の話の解釈」と「酋長の話の超越」という三つの相が取りだされ、それぞれの相を少しずつずらしていくことで「虚空に浮遊している」という「街」の状態の説明へと到達している(「街」とは何か、という問いは、この小説の根幹を成す部分でありながら、しかし明確に説明することが不可能だ)。
はたして本作は「集大成」なのだろうか。あるいは「再生産」なのだろうか。
この作品を読んでどう感じるかは、それぞれの読者が決めることだ。それは間違いない。ただ僕は、「集大成」でも「再生産」でもなく、「収穫」と評してみたい。前述した通り、本作には村上作品において――とりわけ長編作品において――繰り返されてきたモチーフやテーマが数多く登場する。しかし逆の見方をすれば、村上作品において繰り返されてきたモチーフやテーマのすべては、本作の元となった「街と、その不確かな壁」という中編に登場していたと考えることもできるのだ。
デビュー二年目に書かれた中編小説の中に、それから長い時間をかけて描かれてきた長編の種が植えられていた。作家として経験を積んだ村上春樹が、四十年以上の時を経て、自ら蒔いた種を収穫したのではないか――僕はそんなことを考える。
大江健三郎が一度発表した『同時代ゲーム』を『M/Tと森のフシギの物語』という形でリライトした原因に息子の存在があったように、本作がリライトされたきっかけの一つが新型コロナウイルスであることは間違いない。閉鎖された「街」に隔離された「私」の話は、自宅に隔離され他人と会えなくなった僕たちの話でもある。「街」に残るか、「現実」に戻るか、という答えのない問いは、コロナ禍の僕たちにとって「他者と関わること」がどういう意味を持つのかを考えることでようやく結論が見えてくる。
『大江健三郎 作家自身を語る』の中で、大江健三郎は自身を「二十世紀の作家」と評し、村上春樹を「二十一世紀」の作家だと述べていた。二人の偉大な作家から一世代離れた僕は、それを読んでひどく驚いたことを覚えている。二人とも二十世紀にデビューし、二十世紀のうちに作家として完成していたのではと思ったからだ。
しかし今になって考えてみると、この二人の間には年齢差以上の、「一世紀」に値するような「壁」が存在していたのかもしれない。二人の作品にはそれくらい大きな違いがある。一人の読者として、デビュー時の種を収穫し終えた村上春樹がこれからも描くであろう「二十一世紀」を楽しみにしている。