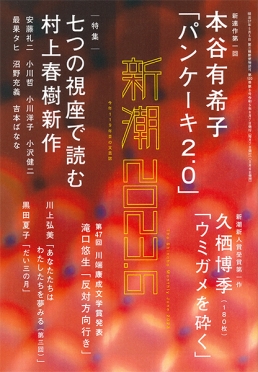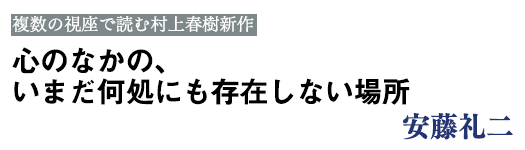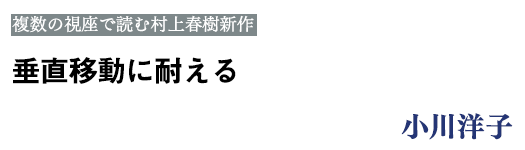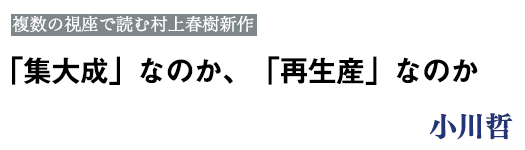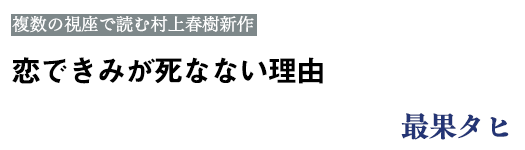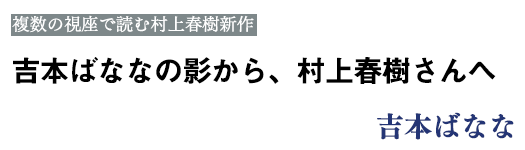村上春樹の新作長編『街とその不確かな壁』は、書下ろし作品だが、著者自身による「あとがき」でも説明されているように、じつは『文學界』一九八〇年九月号に掲載された中編小説『街と、その不確かな壁』を核としている(紛らわしいが、これら二つのタイトルは読点の有無だけが異なっている)。中編のほうはその後、作品集などに再録されることは一度もなく、数多い村上作品の中でも珍しく、書籍化されず言わば封印されたままになっていた。
いや、「封印」というのは言い過ぎだろうか。実際には作品のアイデアは一九八五年に出版された堂々たる長編『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の「世界の終り」の部分にほぼ全面的にとりこまれていたからだ。改めて確認しておけば、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、壁に囲まれた「街」を舞台とした静的でファンタジー的な「世界の終り」のパートと、「計算士」、「記号士」、地下に住むおぞましい正体不明の存在「やみくろ」などが入り乱れたSF風冒険活劇「ハードボイルド・ワンダーランド」のパートの二つが組み合わさり、交互に進行していくという構成になっており、その「世界の終り」パートは『街と、その不確かな壁』と違ったところもあるとはいえ、基本的に同じ設定に基づいている。
『街と、その不確かな壁』が提示していた課題に対して、村上春樹は『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』という解答では満足できず、その四十年近く後にもう一つ、『街とその不確かな壁』という別の解答を与えたということになる。そのどちらがより正しいというものではないだろう。ただ、単純な読後感として一つ言えるのは――あまりにも常識的な言い方になるが――四十年の歳月が作家としての円熟をもたらした、ということだ。それは老成というものではない。『街とその不確かな壁』の村上は、「ハードボイルド・ワンダーランド」にみなぎっていた元気のいいアクション感覚を余計なものとしてそぎ落とし、もっと地に足のついたとでも言えそうな、着実なストーリーテリングによって、いくつもの意匠が絡み合う物語を巧みに縫い合わせている。四十年経ても変わらない「村上印」というものもあるが(たとえば機知にとんだ比喩やジャズへの偏愛)、年月を経てますます鍛えられたきびきびした筋肉を思わせる文体の進化ということもある。『街とその不確かな壁』は村上の集大成というよりは、むしろ作家としての長年の経験を経て醸し出された新境地を示すものとして受け止めるべきだろう。
『街とその不確かな壁』は、「ぼく」が十七歳、「きみ」がひとつ年下の十六歳のときに始まる。とても幸福そうな若い愛だが、「きみ」は独自の「街」を頭の中に持っていて、その様子を詳しく「ぼく」に教えてくれる。そして若い恋人たちは、二人で熱中してその架空の町をより詳しく描き出していく。「街」は高い壁にまわりを囲まれていて、中に入るのはとてもむずかしい。「きみ」はそこの図書館で働き、「ぼく」はそこで「きみ」に出会う。「ぼく」はその図書館で「きみ」に助けられながら〈夢読み〉の仕事をするようになるのだ。奇妙なことだが、「きみ」は「本当のわたし」が生きて暮らしているのはその街の中であって、今ここにいるのはその「身代わり」「ただの移ろう影のようなもの」に過ぎないのだという。街には単角を持つもの静かな獣たち(一角獣)がいたるところにいる……。
こんな風に、若い「きみ」と「ぼく」の初々しい付き合いが続くのと並行して、「街」が具体的に築かれていき、「ぼく」は現実の世界とは別の独立した世界として「街」を経験するようになる。現実の世界では「きみ」と「ぼく」の交際は突然途切れる。「きみ」からの手紙が来なくなり、「きみ」は「ぼく」の前から失踪してしまうのだ。現実の世界で「ぼく」は「きみ」を失ったまま独身を通し、四十五歳になり、そのとき不可解な形で街に入り込んでしまう。
このように作品の基本的な設定というか、あらすじを確認しようとしても、どう説明すべきかわからず、当惑する局面が多い。現実の世界と「街」は一見したところ、現実対夢とか現実対幻想といった比較的単純な二項対立に還元されそうでいて、その関係は流動的で、どちらが「本当」の世界でどちらが「かりそめ」なのか、しばしばよく分からなくなる。そして「きみ」は街の図書館で働く少女こそがほんものの自分だと主張するのだが、他方、「ぼく」は不可解な形で現実の世界と「街」を往復し、現実の世界では中年にさしかかるまでの時が経つ。物語が進行するにつれて、読者は二つの世界がさほど截然と区分されているわけではなく、むしろ、「二つの異なった世界が、その先端部分で微妙に重なり合っている」という感覚を強めていく。そして主人公で語り手の「私」(若い日の「ぼく」は後に成熟してからは「私」という一人称になる)は、「自分が現在おそらくは「あちら側」と「こちら側」の世界の境界線に近いところに位置しているらしい」と自覚するのだ。
「現実の世界」で中年にさしかかり、書籍流通を扱う会社でまずまず順調に勤めていた「私」は、ある日突然辞職し、図書館で働こうと思う。そして公募に応募して、福島県の山間の町の図書館で館長として働き始める(町の名前はZ**としか示されないが、町の様子や場所についてはリアルな説明がある)。ここで物語は、全く新たな要素を付け加え、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』とは完全に違う方向を取る。新たな要素というのは、一つは街の図書館の前任の館長、
子易さんとM**少年はまったく異なったキャラクターだが、どちらも二つの世界の間をつなぐ、あるいは二つの世界の境界で揺曳している、という点で共通していると言えるだろう。ここで図書館は『海辺のカフカ』の場合と同様に、異世界との接点の役割を果たしている。幽霊と言えば、この小説には、死んだ女の亡霊が登場するガルシア=マルケスの小説『コレラの時代の愛』からの引用も盛り込まれ、「現実と非現実とが、生きているものと死んだものとが、ひとつに入り混じっている」、いわゆるマジック・リアリズムの世界観が示されるのだが、ガルシア=マルケスからの引用は、死んでからなお幽体として姿を現す子易さんのケースを言わば下支えするものになっている。
このように読んでくると、『街とその不確かな壁』で村上春樹の頭を悩ませ続けた中心的な問いは、人は本当にはどちらの世界に所属すべきなのか、この「世界」かあの「街」か、現実か異世界か、そして究極的には、本当の私は、そして本当の君はどこにいるのか、というものではなかっただろうか、という気がしてくる。これこそは十代の若い愛に対して村上春樹が四十年かけて出した解答ではないか。そう考えると、表題に「街」と並んで登場する「壁」の重要性もよく分かるだろう。壁は言うまでもなく、二つの世界を隔てるものだが、それが強固なものであればあるほど、それを通り抜け、二つの世界の間を行き来することが、大きなチャレンジとなるだろう。「街」を脱出しようとする「私」とその影の前に立ちはだかる壁を、「私」は力を振り絞って疑念を捨て、通り抜けるのだが、これこそは『ねじまき鳥クロニクル』で岡田亨が行う「壁抜け」以上の積極的な意味を持った意志的な行為である。再度「私」が街を出て、現実の世界に復帰することを示唆する『街とその不確かな壁』の結末はやや曖昧だが、これもまた境界を越え、現実の世界にコミットしようとする主人公の――そして作家の――意志的な選択であろうと、私は受け止めた。