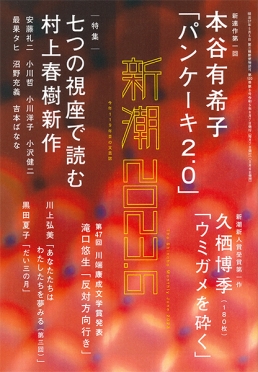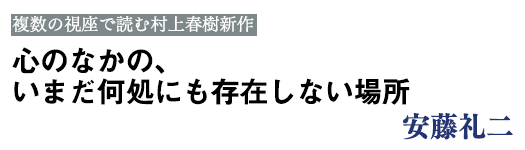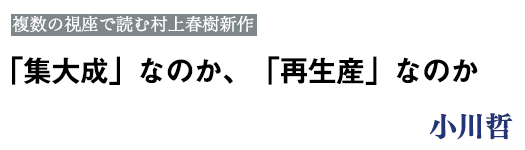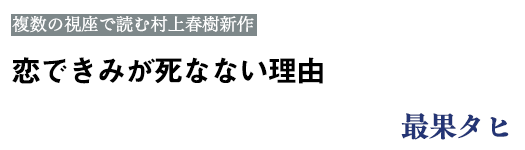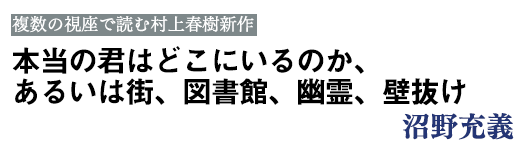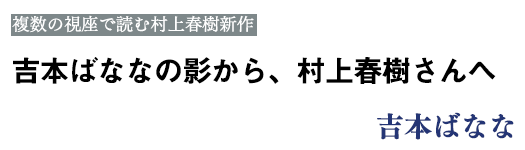一人の男の長い告白を、今、聴き終え、安易にうなずくこともできず、かけるべき言葉も浮かばず、ただ沈黙の中にじっと身を沈めているような気分だ。私たちの間で燃えていたはずの薪ストーブはいつの間にか消え、林檎の香りは半地下の部屋の暗がりに飲み込まれている。
最初から、自分は男に会ったことがあるはずだ、と気づいていた。学生寮の屋上で、飛び去る蛍に手をのばす若者、ただ果てしもなく歩き続けるだけのデートをするカップル、本が一冊もない図書館へ通う目の悪い〈夢読み〉、たまりの水面に映る影。かつて目にしたそのようなもろもろの場面で、彼の姿を認めたのは間違いない、と思うこちらの確信に、彼は無関心を装う。あくまでも礼儀正しく、しかしきっぱりと、いいえ、あなたのことは知りません、という態度を貫く。
それでも男の声は心地よく耳に届いてくる。彼にとっての最も大事な話を、私一人のために打ち明けてくれているような錯覚に陥る。もちろん男は救いなど求めてはいない。最後の言葉が発せられたあと、残るのは暗闇だけだと十分に承知している。半地下に置き去りにされた私は、元へ戻るためには、上昇すればいいのか、下降するべきなのか、分からなくなっている。どちらでも同じじゃないか、と声の名残りがつぶやいている気がして、その真実の重みにたじろいでいる。
“私”は、他者と真正面から向き合い、徹底的に我をぶつけ合い、感情に振り回される経験をほとんど語ろうとしない。十六歳の“ぼく”だった頃に出会った、十五歳の“きみ”との体験が、決定的な楔となって奥深い心の一点に打ち込まれ、そこから逃れられなくなったせいなのか。別に原因を探る必要はないのだろうが、すべてのはじまりが“きみ”にあったのは間違いない。
彼は若者らしい恋に夢中になる。手紙をやり取りし、水辺を散歩しながらあまりにも多くのことについて会話する。健全な性欲を抱きつつ、いっそう強く少女に引き寄せられてゆくなか、彼女は街について言及しはじめる。最初のうち、それは雑談の一部の自然な話題を装っていたかもしれないが、そこは単なる空想の街ではなかった。意識をえぐる痛みを伴う場所だった。地中深くに杭を打たれ、宙に向かってそびえ立つ壁が、痛みの輪郭を強固になぞっていた。
「隅から隅まであなたのものになりたい。あなたとひとつになりたい」
少女は言う。ひとつ、の意味は彼が思うよりずっと複雑で、ある種の残酷さを秘めている。その証拠に彼女は、夢の話を途中止めにしたまま、最後になる長い手紙を一通残して去ってゆく。以降、“私”の孤独な移動がはじまる。
「そのような愛は当人にとって無上の至福であると同時に、ある意味厄介な呪いでもあります」
図書館の前館長、子易さんのこの言葉は、“私”の孤独の本質を、素直すぎるほどに言い表している。彼が呪いを背負わざるを得なかったのは、移動の方向が水平には広がってゆかず、ただひたすら垂直に限られていたからである。
彼は壁に囲まれた街と、壁の外を行き来する。二つの場所は、溜まりの奥に広がる暗闇でつながっている。どれぐらい深いのか、時間で測ることもできない。その果てしもない垂直に耐えられた原点には、“きみ”がいた。どれほど苦悩を伴う呪いであったとしても、それが至上の幸福を突き抜けた先にもたらされたものであるとするなら、耐えるに値する。
移動の途中、“私”はさまざまな人々に出会う。大学の友人や会社の同僚、門衛、福島県の図書館のスタッフ、コーヒーショップを営む女性、図書館の熱心な利用者である少年、前館長子易さん、そして街の図書館で働く“君”。しかしどの関係も、彼を垂直移動から解放してくれる存在にはなり得ない。街とも壁とも無関係な人々はただ、広がりのない風景のように彼の前を通り過ぎてゆくばかりだし、溜まりの底に渦巻く闇を共に凝視してくれる人々は、彼をその中により深く引きずり込もうとする。
唯一、水平に広がる世界を彼に取り戻させるのでは、という希望を抱かせたのは、コーヒーショップの女性だったかもしれない。けれど彼女は自分の肉体を特殊な下着で防御し、拒絶の代わりに待つことを強いた。結局彼は、“きみ”との記憶に舞い戻ってゆくしかなかった。
“私”が最も親しみを感じたのは子易さんだろう。子易さんとの会話には、迷う者に手を差しのべようとする慈しみが感じられた。
「……来たるべき激しい落下も防げるはずです」
子易さんは落下そのものを否定しない。むしろ思慮深く一歩ずつ下降してゆくことを勧める。その結果“私”は、特別な才能を宿命として背負わされた、とある少年の提案を承諾する。離れ離れでありながら、同時に一つの存在を分け合うという矛盾を受け入れる。
何もかもすべてが“きみ”の消失からはじまっている。街にいる“君”は、“ぼく”との記憶を失っている。それでも“私”は本当の“きみ”を求め続け、垂直の移動にこだわり続ける。いくら深く闇を掘っても、“きみ”は戻ってこない。高くそびえる壁をいくら登っても、そこには虚空しかない。
唐突かもしれないが、ここで川端康成を思い浮かべた。川端は、結婚を約束した恋人が、ある不運に襲われたため、別れざるを得なかった過去に生涯こだわり続け、あらゆる形でその傷を作品に残した。例えば、『掌の小説』に「不死」という一編がある。六十も歳の離れた老人と若い娘が、恋人の姿で並んで歩いている。二人は芝生の向こうにある高い金網を、ふうっと通り抜ける。少女は十八の時、海に身投げをした。おかげで十八のまま、永遠にあなたを思いつめていられた、身投げしてよかった、と言う。しかし耳の悪い老人に、もはやその声は届かない。少女に死なれ、落ちぶれた老人は、彼女の死んだ海の上にあるゴルフ場で、ひたすら球を拾い続けてきた。やがて二人は大樹の幹の中に消えてゆく。
身投げは子易さんの言う、激しい落下を思い起こさせる。金網と壁は、こちらとあちら、二つの世界を隔てている。老人にとって少女は不死の存在だったからこそ、最期の時、彼らは再会できた。一緒に大樹の上の虚空に登っていった。
長編『山の音』にも、無上の至福が打ち破られたあと、執拗につきまとってくる厄介な呪いが描かれている。『山の音』は息子の嫁、菊子に老年の父親が心を寄せる話だと、長年思い込んでいたのだが、再読してみると全く違っていた。主人公が生涯にたった一人きり愛したのは、妻の亡くなった姉だった。遠い昔、彼女が盆栽の植木鉢に積もった雪を払う姿や、白い息が少女のやさしさで匂っていたのさえ、主人公はありありと覚えている。六十三になっても、二十代で死んだ彼女は、やはり年上のままであり、縋りつきたいほどに恋しく思っている。息子の嫁は、死者となった姉の身代わりに過ぎない。主人公は、息子と結婚する前の処女の菊子を愛したいという、叶うはずもない欲望に捕らわれる。“きみ”を追い求める“私”と、死者しか愛せない『山の音』の主人公が重なって見える。
取り返しのつかない過去の欠落に縛られ、身動きできなくなった人間は、どれほどの痛みを伴おうと、何度でも過去のその一点に立ち返ろうとしてもがく。意識、記憶、心、魂、とにかく言葉では言い表せない自分自身の内側にしか、そこへ至る通路はない。暗闇に閉ざされた通路は、危険な垂直方向にどこまでものびている。ようやく欠落を取り囲む高い壁にたどり着き、そこをすり抜けたとしても、失われたものが取り戻せるわけではない。両手に残るのは、ぼんやりした夢の感触だけだ。
闇への落下か、上昇した先の虚空か。その垂直移動から逃れる脇道はない。
最後、ロウソクが吹き消されたあとの闇が、なぜ柔らかなのか。それを単なる救いという言葉で誤魔化すのを、“私”は許さないだろう。“私”は、垂直の通路を抱えて生きる決意を固めた。生涯、不死の“きみ”とつながっていられる方法を見つけたのだ。