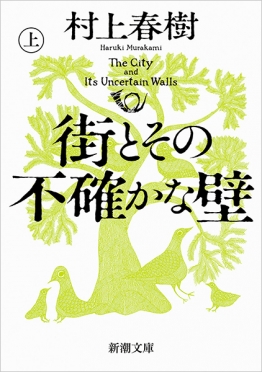美希子と知り合ったのは上京してくる二年前のことだった。当時十七歳の僕は、関西に住んでいた。通っていた予備校で仲良くなったグループの一人に美希子がいた。今から約二十年前、一九九四年のことだ。
予備校でできた仲良しグループでは、僕以外の皆が進学校に通っていた。年明けの一月十五日から二泊三日の勉強合宿に行くことを田中が計画し、僕も乗った。実質は、男子三名に女子三名の気晴らし旅行だ。立案者の田中は、京都大学を志望しているエリート高校の生徒だった。中学からずっと男子校だった彼は、女子とまともに話したことがないらしく、予備校で自分がそんなグループを形成できたことに驚いていた。
先日から、Facebookの「知り合いかも?」の欄の上の方に、その田中の名前が表示されている。プロフィール写真をクリックしてみたところ、今の勤務先は東京のコンサル会社となっている。受験直前に京都大学から一橋大学に志望を変えた田中は、僕と同じタイミングで上京したのだが、東京で遊ぼうぜ、という淡い約束は守られることなく、近況はよく知らなかった。懐かしさもあって、僕は田中に友達申請を送った。二人目の子供が生まれたという最新の投稿にいいね!をして、「久しぶり、今度飲みに行こうぜ」とメッセージも送った。すぐに親指を立てた拳を模した「Thumbs up」マークが返ってきた。
まあ、元気に生きている田中のことはどうでもいい。美希子のことだ。美希子が亡くなったのは阪神・淡路大震災のせいだった。僕たちの合宿中にそれは起こった。僕たちは高校をずる休みし、一日目は、早朝から神戸三宮駅付近の神社にお参りに行った。帰り道の喫茶店でだべるのも午前中で切り上げ、午後からは予備校の自習室に入った。神戸市内のビジネスホテルに寝泊まりして、二日目は皆で一日中勉強した。楽しかったのは、連泊した日の夜だ。男子が泊まる部屋に集まり、コンビニで買った酒も少し飲んだ。ビールとかチューハイとか、そんな安手の酒だ。それが大地震の前夜の過ごし方だった。
そして一月十七日、地震が起こり、僕たちが眠りに就いていたホテルは倒壊した。僕と美希子は約二日間生き埋めになったが、二人とも命は落とさなかった。僕は助け出されてから丸一日眠り続けて目を覚ましたが、美希子は眠ったままだった。何年も眠り続け、その内に亡くなったと聞いている。結局僕は、一月十七日以来美希子には会っていない。彼女の親が会わせてくれなかったからだ。たぶんあの地震さえなければ、初体験の相手は美希子になるはずだった。
田中が京都大学から一橋大学に志望校を変えたように、僕も神戸大学から早稲田大学に志望校を変えた。「田辺くんはきっと何だってできるよ」知り合いがまるでいない東京でRadioheadのOKcomputerを聴きながら、僕は美希子に言われた言葉を反芻した。「きっと何をやってもうまくいくよ。それで素敵な奥さんをもらって可愛い子供ができて、きっと全部うまくいくよ。私はこういうの間違えたことないから、信用していいよ」
思春期の終わり頃の僕は、美希子のことを「セックスできそうでできなかった相手」として思い出していたわけではない。美希子を素材にすれば、その時期のことを感傷的に物語ることができるのだろう。でも僕はそれを慎重に避けてきた。あんな地震で彼女の人生が台無しになり、強く心に残ったが、多分ああいう終わり方でなければすぐに忘れてしまったはずだ。考えてみれば生前の彼女と過ごしたのは、せいぜい八か月程度だった。
月並みだが、自分は薄情なのだと思う。美希子に向けていたものと同じ思いを、僕は後に別の女性たちにも抱くことになった。だが、いつも後から気づくのは、それは寂しさと性欲がないまぜになった身勝手な感情であって、愛ではなかったということだ。人生半ばにも満たない年齢で死んでしまったのは可哀想だと思うが、僕は美希子を愛してはいなかったし、これまでに他の誰かを真剣に愛したこともない。
神戸から上京して、僕は線路際のアパートに住み始めた。人類が滅亡する、という当時流行していた予言の有効期限が切れる直前のことだった。「一九九九年に恐怖の大王が舞い降りる」というノストラダムスのあれだ。恐怖の大王という漠としたキーワードに、多くの人間が天災や人災を想起していた。どれほど非現実的なカタストロフィが起きたとしても、誰もがすんなり受け入れてしまいそうな、そんな諦念に満ちた空気があった。実際、大震災の後で僕が上京する前後には、世紀末的な事件が散々起きていた。地下鉄サリン事件、オウム真理教の教祖の逮捕、地元では僕より年下の少年がさらに幼い子供を手にかける事件があった。二〇〇一年問題でバグを起こしたコンピューターが核ミサイルを発射するかもしれない、などとテレビの三文番組が煽っているうちに年が明け、現実世界はあっさりと新しい世紀に突入した。
阪神・淡路大震災で倒壊したホテルの下敷きになって以降、僕は生き埋め状態のフラッシュバックに悩まされるようになっていた。その発動条件は二つで、一つは身動きの取れない状況に置かれることだ。例えばノブの壊れたトイレに知らずに入った時、高速道路を走っている車中、あるいは劇場のぎゅうぎゅう詰めの座席。ここからしばらくは出られない、と感じてしまうともう駄目だった。背筋が強張り、激しい動悸に目が眩んだまま脂汗を握りしめることになる。そして二つ目は、地震だ。この国では小さな地震がしょっちゅう起こるが、震度二か三の揺れがあると、僕の体は震えが止まらなくなった。
上京して一人暮らしを始めるにあたって、僕は逆転の発想を試みていた。避けられない地震を警戒するのではなく、逆に電車が通る度に揺れるアパートに住むことにしたのだ。揺れ自体に体を慣らし、地震の揺れを普段の揺れに紛れさせる。盛大に揺れるよう、なるべく古いアパートにした。住み始めてから最初の一週間に、フラッシュバックが二度起こった。が、気を失うほどではなかった。ひどい不安感に襲われはしたが、薬を飲まずにやり過ごせた。荒療治が功を奏し、時が経つにつれフラッシュバックの頻度は減った。上京して半年後には、日常的な地震ならばまず平気になった。
線路際に住むメリットは、他にもいろいろあった。例えば家賃が安いこと。騒音に寛大な住人が多いこと。学生時代の四年間を過ごしたぼろアパートのことは、今でも懐かしく思い出す。築五十年は経とうかという木造モルタルで、家賃は共益費込みで三万円だった。それに共用シャワーの利用料が月に三千円。実に経済的な住処だった。揺れに慣れるにつれ、僕はだんだん密室空間すら平気になっていった。シャワーボックスは庭に二つ置かれていて、その脇を電車が走り抜けると、ボックスごとがたがたと揺れた。それにも慣れた僕は、気にせずに頭を洗い、体を洗った。電車の往来は深夜過ぎまでひっきりなしだった。安普請の壁は音が筒抜けなのにもかかわらず、恋人と励む隣人もいた。特に右隣からは頻繁に悩ましい声が聞こえてきた。これを安アパートに住むメリットととるかデメリットととるかは微妙なところだ。
その頃に顔を出していたグループでは、商社や銀行やテレビ局などの有名企業へ就職するタイプの人間、起業を目指したり司法浪人をするような山っ気のある人間、あるいは映画監督や作家を志望する人間など、それぞれのタイプの人員が微妙に重なりながら、類友的な集合体が出来上がっていた。Facebookで検索してみると、ホワイトカラー組は二人以下の子持ちで、友達登録の人数が百五十人程度という人間が多かった。起業・開業組の多くは、起業した一人がやたらにビジネス関係のイベントの様子をアップしている他は、とりあえず登録だけしときました、という風情。芸術系の面々は、展覧会や映画演劇、コンサートの鑑賞記録や内省的な所感をぽつぽつアップする、といったところだった。少し意外な感じがするのは、一流企業にいる人間のFacebookの登録数が少ないことだった。いかにもSNSを活用しそうだと思っていたが、よく考えてみれば、彼らは守るべきものが多い人生を歩んでいるはずで、自身の日常をアップして何らかのリスクが発生することを避けているのだろうと気づいた。日本のエリートでもある彼らには、SNSで得られるささやかな承認など必要ないだろうし。
久しぶりに知人の近況を検索し、まだ繋がっていない友人の幾人かに友達申請を送っていると、先日見つけて友達登録だけしておいた水上からメッセージが来た。弁護士になった水上は、起業・開業カテゴリの一人だ。
『久しぶり、というか大学以来だな。今東京にいるの?』
『おお! 久しぶり。東京にいるよ。水上は元気なの?』
『久しぶりに飲みに行くか』
という簡潔な流れで、月内に飲みに行くことになった。
考えてみれば、この時こんな風に応じなければ、水上の「美希子アサイン」が始まることもなかったのだ。
(続きは本誌でお楽しみください。)