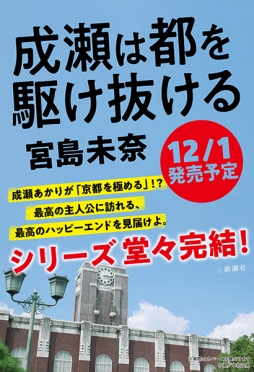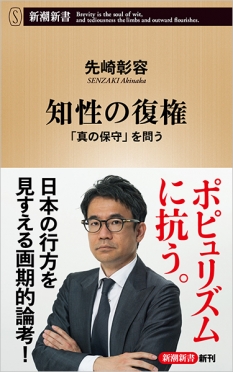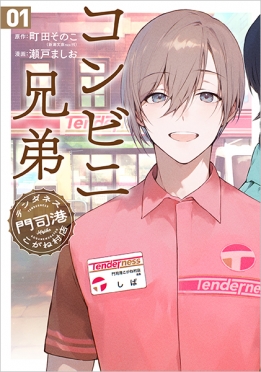『百年の孤独』との最初の出会い
池澤 『百年の孤独』は「長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになったとき、恐らくアウレリャノ・ブエンディア大佐は、父親のお供をして初めて氷というものを見た、あの遠い日の午後を思いだしたにちがいない」という語りから始まるけれども、僕も同じように長い歳月を逆にたどって、初めてこの本を手にしたときの話からしましょうか。
あれは一九七〇年だったと思います。僕はよく丸善の洋書コーナーで英語の本を買ってたんですよ。宮原さんという親しい店員がいましてね。面白い本を探してぶらぶらしていたら、彼が「これ興味ないですか?」って一冊のバウンド・プルーフ(今の日本で言うゲラ本。発売前の宣伝用の仮装版)を持ってきてくれたんです。ジョナサン・ケープってイギリスの老舗の出版社がすごく売りたがってるって言ってね。売り物じゃないからよかったら持っていってと言われてもらったのが『百年の孤独』を手にした最初でした。まだ鼓さんの訳が出る二、三年前。よくわからないままもがくように読み進めるうちに夢中になって、これはすごいと思いました。ただ、すごいのはすごいんだけど、やっぱり登場人物の動きがよくわからない。それで、家系図や登場人物一覧表なんかを作ってみました。そのときの表は「『百年の孤独』読み解き支援キット」として、今は新潮社のホームページにも公式にアップされています。あれを一生懸命作ったおかげで、だいぶわかりました。それくらい熱を入れて読みましたし、それ以来、ガルシア=マルケスの作を次々に読んで、いわば追っかけみたいな読者になりました。
星野 僕も初めて読んだとき、系図を作りました。作らないとごちゃごちゃしちゃうんですよね。しかし「読み解き支援キット」は素晴らしい図表ですね。もっと早く欲しかったと思いました(笑)。
池澤 僕は長い小説を読むときはよく系図を作ります。楽しいんですよ、自分で作るのって。「読み解き支援キット」は何度か活字にして最後に新潮選書の『世界文学を読みほどく』に入れた。少しは読者の理解の助けになるんじゃないかなと思います。
星野 池澤さんがプルーフをもらったときにはガルシア=マルケスの名前はまだ日本で知られていなかったんですか?
池澤 もちろん。ジョナサン・ケープが英語圏で売り始めたばかりの時期でしたからね。彼の名前はスペイン語圏以外では誰も知らなかった。そこから英語圏でも英訳が続々と刊行されて。『族長の秋』なんかもずいぶん早い段階で手に入れました。
星野 池澤さんのように『百年の孤独』をガルシア=マルケスの名前を知らない状態で読み始めることの幸福は、きっともう誰も味わうことのできないものでしょうね。僕は読む前からノーベル文学賞を受賞した作家として知っていましたから。何気なく本を手に取って、引き込まれたのは割とすぐでしたか?
池澤 読み始めてしばらくは、いったいどういう話なのかと不思議に思っていました。引っ張り込まれたのは、メルキアデスが持ってくるものにマコンドの人たちが出会うあの辺りからだったかな。それまでの欧米圏の小説で作ってきた常識からどんどん外れていくんです。目を留める間もなく話が次に行っちゃうあの運動感。一つひとつのエピソードのヘンテコさ加減。それらを味わうように一ページずつ読み解いていく。読書の根源的な喜びを覚えました。それが今もずっと続いているわけですから、僕にとってガルシア=マルケスは最も大事な作家です。
星野 僕が『百年の孤独』を読んだきっかけは、安部公房でした。大学時代に安部公房にハマっていまして、安部公房の言うことは全部聞こうという時期があったんです。それで安部公房の勧める本を片っ端から読んでいるときに『百年の孤独』も手に取りました。八〇年代の半ばだったと思います。池澤さんが読書における根源的な喜びとおっしゃいましたけど、僕もガルシア=マルケスの文章を読むことがとにかく楽しくて心地よくて仕方なかったんですよね。今回改めて読み直したら、ただただ気持ちがいいから時系列とかどうでも良くなっちゃうんです。適当に開いたどのページでも必ず何かが起きている、その魔力というか。全編を貫いてそれがあるのがこの本の最大の魅力だと思います。
池澤 そう。一ページ単位で面白いんですよ。だから次は何が起きるんだろうって先を追わざるを得なくなる。
星野 キリがいいところで止めようと思うんだけど、キリのいいところなんてないんですよね。次へ次へと繋がるように書かれているから。夢中になってガルシア=マルケスを読んでいるうちに、今度はどうしてこんなふうに書けるんだろうと気になり始めました。それで新聞記者を辞めて、メキシコに留学に行くことにしました。この小説の原理はなんなのかを解明しようと思ったんです。『百年の孤独』と出会ったせいで、今に至る不思議な運命に引きずり込まれてしまったわけです。
(続きは本誌でお楽しみください。)