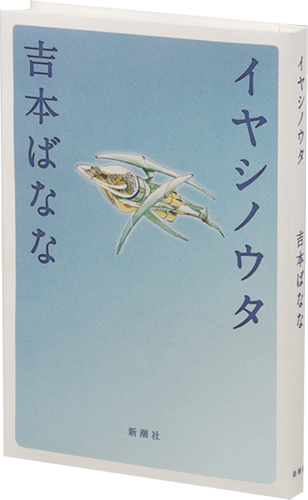吉本ばなな『イヤシノウタ』
吉本ばななさんによる朗読。
『イヤシノウタ』の一篇、「豊かさ」をお楽しみください。
新たなスタートという気持ち
吉本ばなな
――『イヤシノウタ』は吉本さんが生きてきた人生の時間そのものが入っていると言ってもよいくらいに、まだものごころつくかつかないかの頃の記憶から、若いときの恋愛の話、小説家としてデビューされてから経験してきたこと、ご家族との時間、さらには世界を旅するなかで思うことなど、たくさんのエピソードが81篇にわたって語られています。この本はどのようにして書かれたのでしょうか?
時間があわただしくなく感じられる本にしたいというのがまず最初にありました。それなので、普段からとっているメモのなかからトーンの合うものを選びながら、2年くらいかけて書きました。必ずしも時系列に沿って書かれてはいなくて、どこからひらいて読んでもいい本にできたら、と思っていました。
――最初からコンセプトのある状態で書かれることが多いのですか。
いつも本ができあがったときのことを思い浮かべながら書いているので、小説でも先のストーリーがどうなるのかわからずに書くということはないですね。
『イヤシノウタ』には、読んでいてなんだかすごく癒されるんだけど、どこかでそれをちょっと皮肉に思っているようなイメージを持っていました。やっぱり本当の意味では他人には何も癒せない、自分でしか癒せないものだと思うから。清志郎さんのあの歌にぴったりなんです。
――タイトルは、忌野清志郎さんの「イヤシノウタ」からつけられています。
この本の冒頭に引用するのはこの歌だ、と初めから心に決めていました。清志郎さんの『十年ゴム消し』という本が好きで、今回は清志郎さんへの気持ちも籠めたかったので。方法的にも、長い文章の途中に短いものが何回も入るところは、すこしだけ意識しました。
――さまざまなエピソードが語られるなかで、現代社会が抱える問題だったり、そうした状況に直面しながら、どう生きていくのか、まさに今を生きる人たちにむけて書かれた本だと感じました。
これと平行して進めているエッセイ集があって、現代社会の嫌だなと感じるところはそちらによりはっきりと書いているので、『イヤシノウタ』はそういう問題に寄り添いながらも、もうすこし淡いトーンで、あまりクレームにならないようにできたら、とは思っていました。
――疲れているのに、これだけはやりたいと夜ふかししたり、「こうしなくちゃ」といつも急き立てられていたり。順番と気持ちがぐちゃぐちゃになりやすいのが現代病という指摘に、自分にも思い当たるところがあるな、と感じながら読んだのですが、どうしてそうなってしまうと思われますか?
それは、やっぱり経済の問題が大きいと思います。私たちがそうすることで、お金が入ってくる人たちがいるわけだから。
――そうしたなか、本来の人間に備わっている自然のテンポを取り戻して生きること、また、自分がどうありたいかを知ることでお金とのつきあい方も変わってくるとも書かれています。
みんな、こうするといいよ、とまでは思っていなくて、ただ人それぞれ向き不向きがあるから、向いてないことはなるべくやらないといいんじゃないかな、と。その人に合ったペースがあるから、速いのが得意な人にゆっくりしなよ、とは思わないし、逆もそうだし。それは本当に人それぞれなんだと思います。
――ふと通りかかった代々木公園で美しい光景に出会ったり、日常のなかにある、かけがえのない瞬間がたくさん描かれているのも、本書のすばらしい魅力となっているように思いました。
日常がない人って、いないんですよね。必ずみんな洗濯とか食事とかしているし、いつも旅先にいる人も、その土地での人間関係が必ず生まれるから、人間が肉体をもって生きている限り、逃れられないのは日常なんだと常に思っています。だから、小説を書くうえでも、主人公が何に不快感をもち、どういうことに快を感じるのか、どんな日常にある人なのか、ということはすごく大事にしています。そこを書かないとリアリティがないし、そういうところに一番その人が出たりするから。
――子供の頃から、「なんてことないように思えることが、あとですごくだいじになるよ」と語りかける、未来の自分のまなざしを感じていた、というのも印象的でした。
俯瞰してものごとを見るのは、小さい頃からずっとそうでした。目の前のすごく近くを見ているか、俯瞰するか、どちらかしかないんです。それが50歳を過ぎたら、自分はどういうふうに死ぬのかとか、死ぬときに自分は何を思うんだろうな、と日常的に考えるようになりました。若いときはさすがにそういうことはなかったんですけど。死ぬときからさかのぼって、未来の自分が現在の自分を見ている感覚が最近になって出てきたので、それがこの本には強く反映されているんじゃないかな。
――その背後には、より大きな、人類の歴史のような時間も浮かび上がっています。
さらに超俯瞰して見ると、そういうなかにいるんだなあ、というのは感じますよね。
――50歳という節目の年を迎えたことで、新たに見えてきたものがあったのですね。
すこし前にペンネームを「吉本ばなな」に戻して、そうした区切りもあったものだから、この本からが新たなスタートという気持ちが自分のなかにあって、初めて本をつくるときの感覚が自分のなかによみがえってくるのを感じられたのもよかったです。
――名前を戻されたきっかけは、何かあったのですか?
「吉本ばなな」というのは画数的にすごい強い名前で、仕事をやりますよ、他のことは知りません、という名前だったから、赤ちゃんが小さいうちは、それではダメだな、と思ったんです。それで、自分の心構えを変えたかったこともあって、「よしもとばなな」とひらがなにしました。今すこし休んでいるんです、ということを表現する意味もありました。
――そうだったんですね。
あとは最近、自分が思っている状況と自分を取り巻く状況にズレが生じていたことに、気づく瞬間があったんです。30年も作家をやっていると、慣れもあるし、ルーティンのようなものが知らないうちに生まれてしまっていたんだなって。自分自身は定まっていると思っていても、それを周囲に表現できていなければ、それは定まっていないのと同じだから。
――自分をどう定めるのか、それによって変わってくることがたくさんあるというのは、『イヤシノウタ』でも大切に語られています。
改めて自分がそういう状態にあったことに気づいたきっかけのひとつに、タブラ奏者のU-zhaanさんの話にすごい共感したことがありました。タブラって、基本的にメインの楽器ではないので、ボーカルや他の楽器と組んで演奏することが多いんです。しかも彼はインド音楽に限らず、いろんな人と組んでやるから、相手によって全然違う音楽になる。でも、どれにもタブラならではの感じは入っている。タブラがあれば、彼はどこでも誰とでもセッションできて、すなわち彼にとってタブラは言語みたいなものなんです。
それと同じ感覚で、私も文章という楽器を持って、いろんなところに出かけて行くほうが自分には合っているな、と。昔は、小説がすべて、という生き方に憧れていたんですけど、よく考えたら、自分は文学オタクでもないし、あと、やっぱり時代も変わりましたよね。小説を読むよりゲームをしていたい人の気持ちもわかりますし、私自身、電子書籍の恩恵をすごく受けて生きているから、自分もそういう時代にあった生き方に変えていこうと思って。以前なら受けなかったような仕事も、セッションだと思えばできるし。そういう意味では、新人のような気持ちです。
だからといって、なんでもやるわけではなくて、セッションというのは、誰と一緒にやるかが大事なんですね。だから、これまで以上に、ひとつひとつの仕事を吟味していこうと思っています。500円でも引き受けることもあるし、1000万円でもやらないこともある。何をどう考えるか、常に自分に問うていかないといけないので大変ですけど、すごくおもしろい。これからの時代はそういうふうにしないとダメだな、変わったなあ、と素直に思いました。
――これから吉本さんの言葉が、どんなふうに広がっていくのか、すごく楽しみです。より自由に、楽しくなってきている感じなのでしょうか。
うん、きっとその一歩手前なんじゃないかな。商業的な仕事の場合は、依頼どおりにきっちり仕上げようという意識が普段以上に働くから、そこでクオリティを高めることがまた自分の小説やエッセイなどの本を書く仕事にもいい影響を与えてくれるのを感じています。
――エッセイに対する思いも変わってきているのでしょうか。
以前は、小説が本業でエッセイは副業、と思っていたんですけど、いまは小説もエッセイもどっちも本業だと思っています。
――『イヤシノウタ』はエッセイですが、読み心地や伝わってくるものは小説ととても近いものがあるように感じました。
それはそうですね、意識的に文体をまぜました。
――装画は、お姉さまで漫画家のハルノ宵子さんが描いてくださいました。ばななさんの本では初めてでしょうか?
最初で最後だと思います。人生で一回だけにしようと思っていたくらい大切なことだったので。中島英樹さんがすばらしいカバーにしてくださったので、本当にうれしいです。
時間があわただしくなく感じられる本にしたいというのがまず最初にありました。それなので、普段からとっているメモのなかからトーンの合うものを選びながら、2年くらいかけて書きました。必ずしも時系列に沿って書かれてはいなくて、どこからひらいて読んでもいい本にできたら、と思っていました。
――最初からコンセプトのある状態で書かれることが多いのですか。
いつも本ができあがったときのことを思い浮かべながら書いているので、小説でも先のストーリーがどうなるのかわからずに書くということはないですね。
『イヤシノウタ』には、読んでいてなんだかすごく癒されるんだけど、どこかでそれをちょっと皮肉に思っているようなイメージを持っていました。やっぱり本当の意味では他人には何も癒せない、自分でしか癒せないものだと思うから。清志郎さんのあの歌にぴったりなんです。
――タイトルは、忌野清志郎さんの「イヤシノウタ」からつけられています。
この本の冒頭に引用するのはこの歌だ、と初めから心に決めていました。清志郎さんの『十年ゴム消し』という本が好きで、今回は清志郎さんへの気持ちも籠めたかったので。方法的にも、長い文章の途中に短いものが何回も入るところは、すこしだけ意識しました。
――さまざまなエピソードが語られるなかで、現代社会が抱える問題だったり、そうした状況に直面しながら、どう生きていくのか、まさに今を生きる人たちにむけて書かれた本だと感じました。
これと平行して進めているエッセイ集があって、現代社会の嫌だなと感じるところはそちらによりはっきりと書いているので、『イヤシノウタ』はそういう問題に寄り添いながらも、もうすこし淡いトーンで、あまりクレームにならないようにできたら、とは思っていました。
――疲れているのに、これだけはやりたいと夜ふかししたり、「こうしなくちゃ」といつも急き立てられていたり。順番と気持ちがぐちゃぐちゃになりやすいのが現代病という指摘に、自分にも思い当たるところがあるな、と感じながら読んだのですが、どうしてそうなってしまうと思われますか?
それは、やっぱり経済の問題が大きいと思います。私たちがそうすることで、お金が入ってくる人たちがいるわけだから。
――そうしたなか、本来の人間に備わっている自然のテンポを取り戻して生きること、また、自分がどうありたいかを知ることでお金とのつきあい方も変わってくるとも書かれています。
みんな、こうするといいよ、とまでは思っていなくて、ただ人それぞれ向き不向きがあるから、向いてないことはなるべくやらないといいんじゃないかな、と。その人に合ったペースがあるから、速いのが得意な人にゆっくりしなよ、とは思わないし、逆もそうだし。それは本当に人それぞれなんだと思います。
――ふと通りかかった代々木公園で美しい光景に出会ったり、日常のなかにある、かけがえのない瞬間がたくさん描かれているのも、本書のすばらしい魅力となっているように思いました。
日常がない人って、いないんですよね。必ずみんな洗濯とか食事とかしているし、いつも旅先にいる人も、その土地での人間関係が必ず生まれるから、人間が肉体をもって生きている限り、逃れられないのは日常なんだと常に思っています。だから、小説を書くうえでも、主人公が何に不快感をもち、どういうことに快を感じるのか、どんな日常にある人なのか、ということはすごく大事にしています。そこを書かないとリアリティがないし、そういうところに一番その人が出たりするから。
――子供の頃から、「なんてことないように思えることが、あとですごくだいじになるよ」と語りかける、未来の自分のまなざしを感じていた、というのも印象的でした。
俯瞰してものごとを見るのは、小さい頃からずっとそうでした。目の前のすごく近くを見ているか、俯瞰するか、どちらかしかないんです。それが50歳を過ぎたら、自分はどういうふうに死ぬのかとか、死ぬときに自分は何を思うんだろうな、と日常的に考えるようになりました。若いときはさすがにそういうことはなかったんですけど。死ぬときからさかのぼって、未来の自分が現在の自分を見ている感覚が最近になって出てきたので、それがこの本には強く反映されているんじゃないかな。
――その背後には、より大きな、人類の歴史のような時間も浮かび上がっています。
さらに超俯瞰して見ると、そういうなかにいるんだなあ、というのは感じますよね。
――50歳という節目の年を迎えたことで、新たに見えてきたものがあったのですね。
すこし前にペンネームを「吉本ばなな」に戻して、そうした区切りもあったものだから、この本からが新たなスタートという気持ちが自分のなかにあって、初めて本をつくるときの感覚が自分のなかによみがえってくるのを感じられたのもよかったです。
――名前を戻されたきっかけは、何かあったのですか?
「吉本ばなな」というのは画数的にすごい強い名前で、仕事をやりますよ、他のことは知りません、という名前だったから、赤ちゃんが小さいうちは、それではダメだな、と思ったんです。それで、自分の心構えを変えたかったこともあって、「よしもとばなな」とひらがなにしました。今すこし休んでいるんです、ということを表現する意味もありました。
――そうだったんですね。
あとは最近、自分が思っている状況と自分を取り巻く状況にズレが生じていたことに、気づく瞬間があったんです。30年も作家をやっていると、慣れもあるし、ルーティンのようなものが知らないうちに生まれてしまっていたんだなって。自分自身は定まっていると思っていても、それを周囲に表現できていなければ、それは定まっていないのと同じだから。
――自分をどう定めるのか、それによって変わってくることがたくさんあるというのは、『イヤシノウタ』でも大切に語られています。
改めて自分がそういう状態にあったことに気づいたきっかけのひとつに、タブラ奏者のU-zhaanさんの話にすごい共感したことがありました。タブラって、基本的にメインの楽器ではないので、ボーカルや他の楽器と組んで演奏することが多いんです。しかも彼はインド音楽に限らず、いろんな人と組んでやるから、相手によって全然違う音楽になる。でも、どれにもタブラならではの感じは入っている。タブラがあれば、彼はどこでも誰とでもセッションできて、すなわち彼にとってタブラは言語みたいなものなんです。
それと同じ感覚で、私も文章という楽器を持って、いろんなところに出かけて行くほうが自分には合っているな、と。昔は、小説がすべて、という生き方に憧れていたんですけど、よく考えたら、自分は文学オタクでもないし、あと、やっぱり時代も変わりましたよね。小説を読むよりゲームをしていたい人の気持ちもわかりますし、私自身、電子書籍の恩恵をすごく受けて生きているから、自分もそういう時代にあった生き方に変えていこうと思って。以前なら受けなかったような仕事も、セッションだと思えばできるし。そういう意味では、新人のような気持ちです。
だからといって、なんでもやるわけではなくて、セッションというのは、誰と一緒にやるかが大事なんですね。だから、これまで以上に、ひとつひとつの仕事を吟味していこうと思っています。500円でも引き受けることもあるし、1000万円でもやらないこともある。何をどう考えるか、常に自分に問うていかないといけないので大変ですけど、すごくおもしろい。これからの時代はそういうふうにしないとダメだな、変わったなあ、と素直に思いました。
――これから吉本さんの言葉が、どんなふうに広がっていくのか、すごく楽しみです。より自由に、楽しくなってきている感じなのでしょうか。
うん、きっとその一歩手前なんじゃないかな。商業的な仕事の場合は、依頼どおりにきっちり仕上げようという意識が普段以上に働くから、そこでクオリティを高めることがまた自分の小説やエッセイなどの本を書く仕事にもいい影響を与えてくれるのを感じています。
――エッセイに対する思いも変わってきているのでしょうか。
以前は、小説が本業でエッセイは副業、と思っていたんですけど、いまは小説もエッセイもどっちも本業だと思っています。
――『イヤシノウタ』はエッセイですが、読み心地や伝わってくるものは小説ととても近いものがあるように感じました。
それはそうですね、意識的に文体をまぜました。
――装画は、お姉さまで漫画家のハルノ宵子さんが描いてくださいました。ばななさんの本では初めてでしょうか?
最初で最後だと思います。人生で一回だけにしようと思っていたくらい大切なことだったので。中島英樹さんがすばらしいカバーにしてくださったので、本当にうれしいです。