
 |
──この作品を書かれた理由を教えて下さい。
平野 僕は今年三十三歳でデビュー十年なのですが、その間、現代という難しい時代を描くために、小説にどういう方法が可能かという事を常に考えてきました。作品によっては、その可能性の追求に主眼を置いた作品も発表してきたのですが、三十代になるにあたって、そもそも自分が小説というものに魅了されてきた根本に立ち返って、今こそ社会に訴えたいテーマで、小説に関心のない人が手に取ったとしても、読者を引きずり込んで問題を共有出来るような作品を、文学というものの強い力を信じて書きたいと思ったんです。
今の日本には非常に複雑な問題が起きています。特に僕の世代は経済的な格差が強調され、一方でワーキングプアという深刻な状況に陥っている人もいれば、他方では大きな組織で、それはそれでいろんな矛盾を抱えながら必死に働いていても、悪しき「勝ち組」のように呼ばれてしまっている人たちもいる。どちらの立場に対しても冷淡な社会に対して、信頼感をもてずに、「自分とは何だろう」という事を手探りで考え続けて、三十代を過ごしている。そうした同世代の人に向けて、そしてその世代のことが「よく分からない」という人に向けて、自分の言葉を届けたい気持ちがありました。
――しかし、バラバラ殺人をモチーフにした小説という事で読者はとても意外に感じられると思うのですが。
平野 小説の中でごく平凡な家庭を営むサラリーマンがある日突然殺される、という絶望的な殺人事件が起こります。鍵を握っていると見られるのは、事件当夜に面会していた、エリート公務員の兄です。他方で、母親からの過剰な愛情を受けながら、自分は人から「愛されない」と煩悶している少年の物語がある。エンターテインメントの道具として「殺人」を扱うのではなくて、それに巻き込まれた人たちが、加害者の側も被害者の側も決して癒される事のない傷を負って、しかしその中で生きていかなければならないということを徹底して描きたかった。「殺人と赦し」をモチーフにして、何故人は人を殺すのか、人を赦すというのはどういう事か、絶対に赦し得ない出来事が起こったときに、人はどのように行動するのか、それを文学のテーマとして追求したかったんです。
──小説の設定を二〇〇二年とした事にはどういう意味がありますか?
平野 自分とは何だろう?という事を考える一方で、他者とは何だろう?という事も手探りしていたんですね。そうした中で二〇〇一年に9・11が起きて、自分たちが絶対に理解できないような、無限に遠い他者が敵として出現した。それから二〇〇二、三年頃からブログが出てWeb2.0的な状況になり、「一億総表現者時代」というわけで、他者というのは圧倒的豊富なバリエーションを持ってることが明らかになった。もう単に同じ時代を生きているというだけでは絶対に一括りにできないような多様性を見たあとに、じゃあ、どのように他者との間でコミュニケーションを探っていくか、そういう問題を真剣に考えるようになったんです。いろいろな意味で「一から多へ」というような流れが出来て、ある意味では大きな節目の時期だったんじゃないかなという気がしています。
――『決壊』は二〇〇六年十一月号から〇八年四月号まで「新潮」に月刊連載されたのですが、平野さんにとっては初めての連載小説ですね。
平野 今までは、最初から結末までかっちりと世界が出来上がってから書き始める事が多かったんですけれど、今回はかなり大雑把にしか決めずに始めたんです。僕自身も書いてみないとよくわからない事がたくさんあったので、書く事で読者とリアルタイムで対話したいと思ってました。そういう意味では当初予定していたものとはかなり違ってますが、逆にいうと、だからこそこの小説の結末には一つの必然として納得できているんです。
──「決壊」というタイトルは何故付けられたのでしょうか。
平野 第一には、今の社会の状況から感じたことなんです。「決壊」というのは、ダムとか堤防とかそうですけど、ギリギリまでがんばってるものが、とうとう限界を超えて一気に壊れてしまう現象ですよね。そういう危うさというのは、日々の生活を通じてみんな感じてるんじゃないかと思います。
特に、コミュニケーションの問題を重視しました。最近僕は、人間を言葉として語られる「情報」と生きている存在としての「情報源」とに分けて考えてます。情報源としての人間は、結局のところ、どこまでいっても言葉では汲み尽くせないし、言葉と完全に一致することもない。「平野啓一郎というのはこういう人間だ」という情報は、十人が語れば、十人とも違っているはずだし、僕の自己認識でさえ、どんなに言葉を尽くしてみても、情報源である僕のすべてを十分には語れない。その埋め尽くせない、一致させられない情報源というものの空白というか、穴というか、それがあるからこそ、人間は自由であり、同時にお互いに寂しいんだと思うんです。どんなに愛している人でも、最後の最後には、タッチできない部分がある。それが、現代人の孤独の根源なんじゃないかと。でも、僕は、一人の人間の言葉になりきれない、複雑でデリケートな部分に、ギュウギュウ言葉を押し込んでいったら、茶碗が割れるみたいに、いつか人間は壊れてしまうと思うんです。今の社会は、失言を捉えて、あいつはあんなヤツだと断定してしまうみたいに、人が人に対して、乱暴になりがちな傾向をもっている。僕は、何かが壊れるときに起こっていることは、大体バカげたことだと思うんです。明らかにそんなふうに扱えば壊れると分かっているはずなのに、案外丈夫だから、乱暴に扱っていたら、案の定壊れた、というような。いじめとか過剰労働とか、人間に対する扱いも同じですよ。どんなに幸せそうに見えても、それぞれの人間がギリギリのところで自分を維持している。そして、人間の耐性は限界があるというのが、僕の考えです。乱暴なことをすれば、当然のように人間は壊れるし、コミュニケーションは「決壊」する。それを改めて知ってもらいたい。子供がおもちゃを乱暴に扱ってて、「壊れるぞ」と注意するとハッとしますよね。それと同じです。
――「情報源としての人間」とサラッと口にされましたけど、人間の定義を情報によって行うという、すごく独創的な価値観、世界観じゃないかなと思います。
平野「死」という現象を考えたときに、この定義がよく当てはまると思うんです。死ぬと、情報源としての人間が消滅して、その人の情報だけが、記憶の中だとか、アルバムの中だとかに一定期間残る。それから後は、その人自身からは、もう二度と情報化されるべき何かは発信されない。オリジナルの情報源が喪失しても、その情報源から発せられるであろう情報を期待するのが「死者の声を聞く」という事ですね。今回の小説では、警察やマスコミが、事件に関わっている人間の情報をいろいろと収集して、それを情報源そのもののように扱うわけですが、やっぱりそれは、主人公当人とは必ずズレてるんですね。僕たちも、事件報道などでは、そうした情報から、犯人はこんなヤツだとつい考えてしまいがちですけど。その意味で、小説の中で「犯人が誰か」がなかなか分からないというのには、本質的な意味があるんです。
あと、僕自身の実感を込めて、「現代人の苦悩」というのを自分なりに考えました。経済的格差の問題のように、お金に還元できる話は確かにあるし、それは何とか手を打つべきですけど、それが解決されたとしても、その先に解決し切れないものがまだ残っている。僕が拘ったのは、そこのところです。生きていくための矢印というか、方向性みたいなものを現代人は明確には信じられない。この小説の主人公はエリートで、異性関係にもお金にも困ってないけれど、やっぱり満たされていない。傍目には結構な生活に見えても、本人の中ではギリギリいっぱいだったりする。だから、そこに「何か」が起きてしまえば、たちまちすべてが決壊してしまう。そうした今の時代の危うさと、この時代を生きなければならない現代人の哀しみ、孤独をどこまでも追求していきたいというのがこの小説のモチーフとなっています。
――主人公の沢野崇には、かなり平野啓一郎自身が投影されてるように感じられましたが?
平野 もちろん僕が書いてるんで、僕の実感も込められてはいますけど、やっぱりフィクショナルで過剰な主人公だと思います。文学史的に見れば多分『カラマーゾフの兄弟』のイワンとか、『罪と罰』のスヴィドリガイロフみたいな人がルーツになるんじゃないでしょうか。このところ、またよく読まれていますけど、ドストエフスキーは、やっぱり、意識しました。
――刊行直前に秋葉原で小説の中の出来事を彷彿とさせるような事件が起きましたが、どのようにお考えですか?
平野 秋葉原の事件は、恨みのある誰それを殺すというのではなくて、今の社会そのものに犯行予告を出して破壊的行動に出てるんですから、一種のテロだと思います。完全に間違った方法だと思いますが。僕は、そういう事件が起きると巻き込まれた人たちはどんな滅茶苦茶な状況に陥ってしまうか、それを丁寧に描く事で、その悲惨さと絶望的な苦悩、哀しみを小説で強く訴えたかったんです。小説執筆中にも、学校裏サイトやネットを使った犯罪、練炭自殺に硫化水素自殺など、メディアで報道されるとバーッと全国で起こるというような現象があって、現実から刺激を受けたのは事実です。『決壊』のメッセージは、そんな事をすると、殺した人間はもちろん、巻き込まれたすべての人間が取り返しのつかないまでに壊されてしまう、という事なんです。悲惨な事件は、小説の中だけでたくさんというのが、僕のあの事件に対する痛切な思いです。
『決壊』で説かれている無差別殺人の「理由」は、作者の僕というよりは、今の社会こそが語っているのだと思います。それでも、僕を含めてほとんどの人は人を殺すということはなく、一方ではやはり、人を殺す人間がいる。それは何故だろう? これは酒鬼薔薇事件とかオウム事件を経た九〇年代からの問いですよね。心情的には酒鬼薔薇に共感する人や、オウム信者の考えてる事もよくわかるという人はいたんですけど、普通は殺さない。その境目を追求して、人を殺すという事をヴァーチャルに妄想するのではなく、一つの殺人がこんな悲惨な事を招くという、もっと生身の人間に迫った想像力を持ってもらいたい。だからこそ、小説の力を信頼しつつ、小説らしい、都合の良い結末は全部疑って、本当にそんなことで済むのかと、最後まで徹底的に問題を掘り下げました。結末については、連載時から賛否両論で、分かるという人と分からないという人とがはっきり分かれましたけど、今度はそれを、単行本の読者の皆さんに委ねたいと思います。
現代という困難な時代に生きているすべての人に、僕は、小説の醍醐味を十分に味わってもらい、その感情の一番深いところまで、作品の中に生きている人たちの言葉を届かせたいと願いながら、この『決壊』という作品を書きました。読後には、小説のテーマでもある「なぜ?」という部分について、多くの人に感想を語り合ってもらいたいですし、作者の僕にも、是非その感想を届けてもらいたいと思っています。(2008年6月)
|

|


|
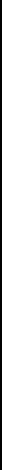 |