
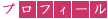
養老孟司
1937(昭和12)年神奈川県鎌倉市生まれ。1962年東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。1995年東京大学医学部教授を退官し、現在北里大学教授、東京大学名誉教授。著書に『唯脳論』『人間科学』『バカの壁』など、専門の解剖学、科学哲学から社会時評まで多数。
|
 新潮新書のサイトへ 新潮新書のサイトへ
|
 |

──『バカの壁』が売れたことについて、今はどのように考えていらっしゃいますか?
ある時点までは、いろいろと原因を分析もしたのですが、100万部を超えたあたりからはそういう分析もあまり意味がないような感じでした。赤潮状態というかなんというか。いったん増え始めると、勝手に増え始めるみたいな状態です。自動運動みたいでちょっと怖かったですね。
昨年4月に発売されて、売行きが好調ということもあって、それまで口約束で放っておいた仕事の催促が次々に来るようになりました。何だか借金の取り立てのようでした。
それも一段落しました。『死の壁』のあとはしばらく本を出すことを休もうと思っています。次は思いっきり難しいものを書いてみようかとも思っています。
──今度の『死の壁』はこれまで書かれてきた「死」に関する論考の総まとめ的な側面もあると思います。しかし、そのわりには全体を通して読むと暗い感じはしません。むしろ明るい感じもあります。これはなぜでしょうか?
商売柄、死について考えることは暗いことではないのです。大体、解剖という仕事は、死ぬ人がいないとなりたたない仕事なのですから。
また、案外「死」というのはジョークの対象にもなりやすいものです。真面目な人は怒るのですが、そういう面がある。落語でも「粗忽長屋」とか死を笑いにしたものはたくさんあります。それは生きている人間には、「関係ない」という感覚が根底にあるのでしょう。
その反面、人によっては非常に厳粛なものだと考えている。この落差が冗談になりやすい。一見厳粛なのに、何かのはずみでうっかりすると笑いだすという状況。お葬式にもそういうところがあるという覚えはみなさんにもあるのではないでしょうか。
私の場合、一般の人と違うのは解剖を30年やってきたということです。死んだ人と二人きりになるという経験は、普通はそんなにないでしょう。しかし私はそういうことがしょっちゅうでした。
学生の実習に付き合ったりすると、1対50なんてこともあった。生きているのが私1人で、向こうが50人。50人の死んだ人が並んでいる部屋に、こちらが1人で坐っているなんてこともあった。死んだ人のほうが圧倒的多数という状況は、普通は経験しません。そこであたりを見回しているうちにちょっと普通ではない気分になります。しかし変かというと変ではない。
こういう経験を積んでいると、「死ぬことと生きていることとの間には距離がない」ということが実感できるのです。しかし、そういう実感で話をすると、普通の世の中ではなかなか通じない。それは当たり前で、そんなに身近に死を感じていない。
東京都に1000万人の人が住んでいても、通りには小指一本落ちていません。私はそっちのほうが普通じゃないと思っていますが、普通の人は逆でしょう。
──本の中でも繰り返し出てくる「現代人は、『死』を遠ざけてきた」というのはそういうことですね。
普通の人はあまり死を議論できなくなってきました。だから神棚に上げたり仏壇にしまったりするようになりました。でもそれは、最近の風潮なのです。ちょっと前までは「死」は本来はもっと日常的なものだったはずなのです。
さかのぼってみると、半世紀前はそうだったのです。70歳を越えた人だと、昭和20年8月15日に「助かった」と思う人がたくさんいました。当時その人たちは中学生くらいです。それはつまり「もうすぐ死ぬ」と思っていたということでしょう。でも今の中学生で自分の死を意識している人はほとんどいません。そういう時代の変化はとても速い。死が遠くなったのです。
しかし死が遠くなったとしても、人が死ななくなったかというとそうではない。単に寿命は延びたかもしれませんが、それだけのことです。10年、20年先に延びたけれども、いずれにせよ死ぬ事に変わりはない。そうすると、何か一言言いたくなるんです。
特に私はいわゆる「まとも」というか普通の考えを持っているとされる人と話をしていて、そういう違和感を感じることがあります。以前、「年をとることと死ぬこと」をテーマにしたインタビューを受けたことがあります。そのときに、聞き手と意見が合わない。こっちの言うことをリクツかタテマエだと思っているふしがあったのです。
もちろん、私と意見が合わないことが悪いわけではありません。でも、「それは何か違うんじゃないか」と感じたのです。そういう違和感を常に私は自分なりに理屈にしてきました。
|
|

