
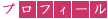
養老孟司
1937(昭和12)年神奈川県鎌倉市生まれ。1962年東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。1995年東京大学医学部教授を退官し、現在北里大学教授、東京大学名誉教授。著書に『唯脳論』『人間科学』『バカの壁』など、専門の解剖学、科学哲学から社会時評まで多数。
|
 新潮新書のサイトへ 新潮新書のサイトへ
|
 |

──「死」について考えない弊害が出てきたということでしょうか。
「死」だけではなく、「生きている」ことも実はあまり理解されていないのです。生物科学という学問は、たとえていえば「生き物を止めて説明する」ということを100年以上必死でやってきたのです。生きているものを固定化することにのみ心血を注いできた。
その最終的な形が「遺伝子」です。DNAというのは粉みたいなものです。現代では、それが生物の基本だということになってきた。それさえわかれば生命のすべてがわかると思っている方は多いのではないでしょうか。
でも粉が生き物のわけがない。その粉を情報として使っている細胞が生き物のはずなのです。その細胞を「システム」として理解することが本来の生物学の作業のはずなのに、それをなかなか生物学者はやらない。粉のほうの分析に行かないと、論文にならない。そんなふうな方向に学問がこの100年向いたおかげで、肝心の「システム」への理解が進んでいかない。細胞の方をどう理解するかを考え直さなくてはいけなくなっている。
生物学なのに、「生きている」というのはどういうことか、明確な答えを出せない。こんな基本的なことの捉え方ができなくなっているのです。
こういうところに、それが社会のいろいろな問題の根本にある。環境問題もそうです。医療でいえば医療事故の背景にもそれがある。近代科学的な、別の言い方をすればいわゆる合理的な考え方からすれば、医療事故が起きるとすぐに医者が悪い、看護婦が悪いということになります。そして裁判になります。
もちろん、それはそれでいいのですが、それを繰り返したところで事故は解決しません。現在の医療事故についての見方というのはノミで木を削っているときに、そのノミの先端部分だけを見ているようなものなのではないでしょうか。
ノミの先端で木を削っている。そこだけ見れば木を削っているのはノミですが、反対側をみれば金槌でノミのお尻を叩いているわけです。その金槌で叩いているほうが社会全体の動きです。そっちをどうにかしないと実はなにも片付かないということはハッキリわかっている。
ただし、これに関してはノミと金槌ほど単純ではなくて、もちろんもっと複雑です。風が吹けば桶屋が儲かる式の複雑さがあります。そこをどういうふうにきちんと理解できるかが非常に重要なのです。
しかしそういうことを考えることをはなはだしくさぼってきた。そのさぼってきた理由ははっきりしていて、きちんと「記述」しようとすると、そういうものは記述できない。そうなると論文を書くことができない。だから学者はそれをやらないのです。
──さきほどの「生物を固定化しようとする」というのと同じことですね。固定化できない、記述できないものは見ないようにするということ。
たとえばエイズの原因がHIVウィルスである、ということはわかる。そのウィルスの構造を規定することもできる。しかし、それが細胞に入ったときに何をするのかを説明しようとすると大変な煩雑さになる。
何も遺伝子の研究は無意味だと言っているわけではありません。ただ、その方向で研究して考えを進めても、ノミの先は見えても金槌のほうは見えない。
死から生について考えるというのは、そういう今の考え方とちょうど逆の方向性でものを考えるひとつの手段なのです。物を考えるちょうど折り返し点のようなところに「死」がある。
言い換えれば「死んでいる」ということを考えることは、そのまま逆に「生きている」とはどういうことかということを考えることになるのです。
|
|

