
許されようとは思いません
693円(税込)
発売日:2019/05/29
- 文庫
- 電子書籍あり
超弩級のどんでん返し五連発!! 絶対に読み逃せないミステリー短編集。
「これでおまえも一人前だな」入社三年目の夏、常に最下位だった営業成績を大きく上げた修哉。上司にも褒められ、誇らしい気持ちに。だが売上伝票を見返して全身が強張る。本来の注文の11倍もの誤受注をしていた――。躍進中の子役とその祖母、凄惨な運命を作品に刻む画家、姉の逮捕に混乱する主婦、祖母の納骨のため寒村を訪れた青年。人の心に潜む闇を巧緻なミステリーに昇華させた5編。
ありがとう、ばあば
絵の中の男
姉のように
許されようとは思いません
書誌情報
| 読み仮名 | ユルサレヨウトハオモイマセン |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 松本コウシ『午前零時のスケッチ』より/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 320ページ |
| ISBN | 978-4-10-101431-9 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | あ-97-1 |
| ジャンル | 文学・評論 |
| 定価 | 693円 |
| 電子書籍 価格 | 693円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/11/22 |
書評
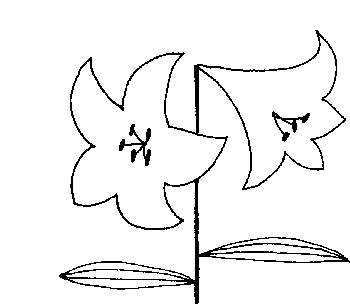
驚きに満ちて感動もある傑作サスペンス
いやあ驚いた。レベルが高いのだ。五作の短篇が収録されているが、いずれも秀作。推理作家協会賞短編部門にノミネートされた冒頭の表題作もいいが、あとに行くにしたがい、密度があがり、技巧も凝らされて、驚きの結末へともっていく。読むのが息苦しくなるほど世界が緊張にふるえている。
五篇の中でいちばんの傑作は、「姉のように」だろう。事件を起こした姉のようにはならないように、自分の娘への虐待の衝動を抑えようとする話だ。姉は童話作家として活躍した誇るべき存在で、だからこそ事件は衝撃的で、主人公の「私」は周囲の目を意識して生きていくのだけれど、三歳の娘はいうことをきかず、また夫も「私」を理解してくれず、次第に精神的に追い込まれていく。
ひとつ歯車が狂いだすとどうしようもなく悪い方向へと転がっていく。我慢もし、うまくたちまわろうとするものの、情況は容赦なく、幼児虐待に引き込まれていく主婦の心理を徹底的に捉えていて、読むのが辛くなる。いったい結末はどうなるのかと思っていると、いやはや、最後に足元をすくわれるのだ。どんでん返しがあり、世界が一変する。いままで読んできたものを根底から覆す仕掛けで、あわてて冒頭にもどって確認すると、ちゃんとそこに事実が書いてある。読者を巧みにリードしつつ、躾けと暴力のあわいというテーマを強く訴えながらも、ミステリとしての仕掛けで驚かせる。見事なまでに作り込まれた傑作サスペンスだ。
画家の深層意識に迫る「絵の中の男」もまた、実によく作り込まれている。美術画廊に勤めながら、なかば家政婦のように女性画家の家に入り込んだ「私」の回想。女性画家は幼いころに一家皆殺しにあった生き残りで、その悲劇を絵画のモチーフにしていたが、やがて描けなくなっていく。そんな時に悲劇が起き、最終的には夫を殺してしまう……。
冒頭で、女性画家がイラストレーターの夫を殺す場面が回想される。ひじょうに視覚的で鮮やかなのだが、何故そうなったのかは伏せられて、少しずつ女性画家の過去が語られていき、ゆっくりと核心へと迫っていく。
物語のスタイルは、一人称の告白体で、この形式は落ち着いた語りになり、劇的構造をもちえないのだが、本作は異なる。「私」が目撃するのは、芸術にとらわれた夫婦の地獄図で、残酷な事実が次々に語られ、ドラマティックになっていく。ミステリであるけれど、芸術家の苦悩を捉えた芸術家小説としても読ませるし、夫殺しの真実に迫るプロセスも緊迫感がみなぎり、驚きがあり、まことに素晴らしい出来だ。
驚きがあるのはほかの短篇にも共通していて、営業マンを主人公にした「目撃者はいなかった」は、受注の数を間違えた営業マンが会社に内緒で処理しようとして嘘を重ねていくサスペンスで、交通事故を目撃しながらも証言をせずにすまそうとするが、そこに思わぬ事件が起きて……という展開。意外性に充ちていて、何よりも怯えている男の心理が生々しく、読者も窮地から逃れたくなるのだが、そうはいかない。究極の選択を迫られる結末、いや、究極の選択を強いる何者かの存在が暗示されて恐ろしい。
同じく、保身のための悪意が別の形で描かれるのが、「ありがとう、ばあば」。子役として活躍しだした九歳の孫娘・杏を、必死でサポートする祖母の「わたし」と娘との確執、その間に入る杏の物語である。愛の深さが過剰な干渉になりかねない危うさをあぶりだして、やがてある“事故”を招く。タイトルの真の意味が浮かび上がる最後が見事。
以上の四作、虐待や悪意などが主で、イヤミスのような印象を与えるけれど、表題作「許されようとは思いません」は温かい余韻が残る。祖母の遺骨をもって「私」が恋人の水絵とともに母の郷里を訪ねる話で、村の寺に納骨するはずが、それに悩むことになる。なぜなら祖母は曾祖父を殺したからだ。「私は自分の意志で殺しました。許されようとは思いません」と背筋を伸ばして供述した祖母の殺人の動機は何だったのかを探っていく。
ここでも村民たちからの虐待と悪意をうちだしているけれど、祖母の動機をほりさげていく終盤の謎解きは、肉親への愛に支えられ、また水絵との結婚問題もからめてうまく機能しているし、ラストの選択はちょっと感動的ですらある。
作者の芦沢央は、2012年「罪の余白」で第三回野性時代フロンティア文学賞を受賞してデビューした作家なのに、短篇の巧さはすでにベテランの域に達している。今年の収穫、注目の作品集だ。
(いけがみ・ふゆき 文芸評論家)
波 2016年7月号より
単行本刊行時掲載
第1話「目撃者はいなかった」試し読み
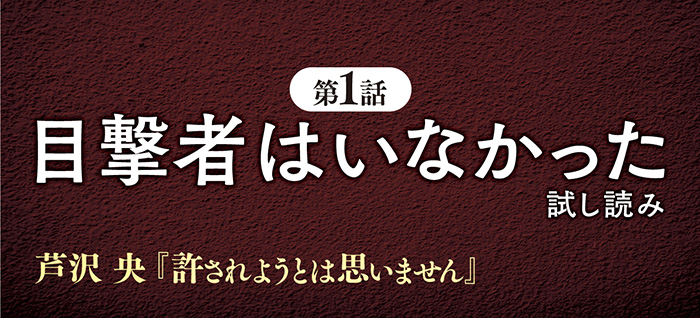
これでおまえも一人前だな。
山岸に肩を小突かれながら言われた言葉を、
え、と反射的に
これまでは部長に見上げさせられていたその表を、初めて自主的に見上げていく。
〈営業本部
いつもよりも立派にさえ感じられる名前に、目が吸い寄せられる。
「え」
もう一度、つぶやきが漏れた。
「何辛気臭い顔してんだよ。よかったじゃねえか」
山岸が豪快な笑い声を上げ、今度は修哉の後頭部をはたいた。修哉はよろめきながらようやく頬をほころばせる。
「いや、まぐれですよ。先月はたまたま他の人の成績が伸びなかっただけで」
「おいおい、嫌味か?」
山岸が大仰にのけぞる仕草をした。言われてみれば、山岸の名前は修哉の一つ下にある。修哉は目を疑った。先月に限った話とは言え、自分が、大体三カ月に一度は成績トップになる山岸より上位につけたらしいということが信じられない。
だが、山岸は屈託なく「なんてな」と
「まぐれでも何でもいいんだよ。こういうのは一回
そう言う山岸の口調にはそれこそまったく嫌味がなくて、本当に喜んでくれているのが伝わってくる。修哉はじんわりと腹の底が温かくなるのを感じた。山岸は、きっと
「ありがとうございます。山岸さんのおかげです」
修哉は心の底から言って頭を下げた。
「俺は何もしてねえって」
山岸は照れくさそうに顔の横でパタパタと手を振る。
「いえ、本当に山岸さんのご指導がなければここまで来られませんでした」
修哉は言葉を重ねながら、自分がずっとこのセリフを口にする日を夢見ていたのだとわかった。これまで、他の同期たちが誇らしげに上司にそう告げていたように。
背中に数人の視線を感じる。それは、心地良い緊張感だった。自然と背筋が伸び、口角が上がる。
自信にもなるし、そうすりゃますます契約が取りやすくなる――そうかもしれない。たしかに、今ならいつもよりも滑らかに、説得力のある口調で営業トークを口にできる気がする。
「まずは、もう一回まぐれ当たりを出せるように頑張ります」
「おう、その調子だ」
修哉が腹に力を込めて言うと、山岸は満足気にうなずいた。
「まあ、何にせよ、この数字には自信を持っていい。別に先月他のやつらが特別成績が悪かったわけじゃないよ。俺が入社三年目の頃には出せなかった売上だ」
表を見上げて目を細め、
修哉は「え」という声を今度は飲み込んだ。ぎこちなく首を動かし、改めて表を見上げる。売上額の欄に並んだ数字を一の位から順に
一瞬にして、全身が
――何だろう、これは。
自分が試算していた額とかけ離れていることはたしかだった。これなら、山岸の言う通り他の営業部員の成績が悪くなくても最下位にはならない額だ。だが、なぜ――
修哉は早鐘を打ち始めた心臓をワイシャツの上から押さえながら、自席へと向かう。震える指でマウスを操作し、先月中に作成した売上伝票を開き始めた。これは、おかしくない。これも――大丈夫だ。一つひとつ、目を通しては閉じ、目を通しては閉じを繰り返していく。見つからない。やっぱり間違いなんてないんだろうか。いや、どう考えてもこんなに売り上げていないことは自分が一番よくわかっている。どこかに間違いがあるのだ。一体どこが――
最後から二番目、昨日作成したばかりの伝票を開いて半ばまで視線を滑らせた瞬間だった。
〈株式会社ハッピーライフ・リフォーム 7月24日受注 8月2日午前納品
杉 テーブル材 204センチ×93センチ×3・7センチ
税込35000円 11枚 納品時に代引き〉
冷水を浴びせられたように血の気が引く。
――そんな、まさか。
視界が暗くなった。
単純な入力ミスだ。一枚しか注文を受けていないものを十一枚受注してしまっている。三万五千円が十枚分、三十五万円が余分に売上として計上されているのだから成績が変わってきて当然だ。
修哉は頬の内側を強く
足早に事務所を出て自動販売機のある角を回り込み、辺りを確認してから携帯を取り出した。製材所の番号を呼び出し、携帯を耳に押し当てる。
発信音が長く続いた。全員作業中だろうか。修哉は腕時計の文字盤をにらみつける。八月一日――もう製材してしまっているかどうか。
『はい、
受話口から聞こえてきたぶっきらぼうな声に、修哉は縮み上がった。
「あ、どうも。営業部の葛木です」
『何だ葛木か。内線なんか使わねえで直接来いよ。前にも言っただろうが。こっちは手が離せねえことが多いんだよ。ちゃんと商品を目で確かめる癖をつけりゃ売り込みだってもっと上手く――』
「すみません、ちょっと出先で」
『あ?』
ガラの悪い声が
『ああ、何だ外線か。で? 何か用か?』
「あ、あの」
修哉は視線を
「明日納品の杉テーブル材の件なんですけど、今どんな感じかなと……」
『杉? もう加工して積み込んであるよ。それがどうかしたか?』
ぐらり、と地面が傾いた気がした。だが、
「いえ……ちょっと先方から納品が間に合うか確認があったもので」
答えてしまってから、白状するなら今だったのだと気づいた。けれど、訂正する間もなく、『そんなことかよ』という不機嫌そうな答えが返ってくる。
『間に合わないなら間に合わないって連絡してるだろうが』
苛立ちを含んだ声と共に電話が切れた。
「あ」
修哉は携帯を見下ろして声を上げる。今、訂正しようと思っていたのに。
まぶたの裏に、山岸の笑顔が
『本当に山岸さんのご指導がなければここまで来られませんでした』
山岸がこのことを知ったら、と思うと胸を強く押されたような圧迫感を覚えた。がっかりするだろう。喜んでくれた分だけ、いや、それ以上に。二年も育ててきた部下が結局まったく成長しておらず、それどころか単純ミスまでしていたのだから。
事務所の方へ向けたつま先が宙で泳ぐ。どうしても、一歩を踏み出す気にはなれなかった。怒られる。
――嫌だ。
耳の裏が熱くなる。
「くそ!」
固めた
「くそ、くそ、くそ!」
思いきりやっているつもりなのにほとんど痛みを感じない。奥歯を噛みしめ、
――何で、こんな単純なミスなんか。
どうしてちゃんと見返さなかった。基本中の基本じゃないか。新入社員だってやらないミスだ。
手の中に握りしめた携帯を焦点の合わない目で見下ろした。
どうして、せめて今訂正しなかったんだろう。こういうのは報告が遅くなればなるほど問題が大きくなる。切り出して積み込んだ時点なら社内で怒られるだけだが、先方に届けてしまえばそちらにも謝らなければならなくなる。配送料だって余分にかかってしまうし、第一、納品先からの指摘で発覚するなんて最悪のパターンだ。今すぐ山岸に報告して発送を止め、伝票を作り直せば――それだって、三十五万円の損失だ。
ボーナスだって減らされるだろう。最悪、弁償させられることだって――そう、考えかけたときだった。
修哉は目を見開き、喉仏を上下させる。
――ごまかしてしまえば。
どくん、と心臓が跳ねた。冷えた腹の底に
そうだ。どうせボーナスだって減らされる。弁償させられる可能性だってなくはない。だったら――三十五万円分、自分で買い取ってしまえば。
固まった全身が、少しずつほぐれていくのがわかった。そうだ、そうだ、そうすればいい。奇妙な興奮に息が荒くなる。
何を用意すればいいだろう。社名の入っていない作業服? 顔を隠せる帽子?
修哉は携帯をポケットに押し込んだ。視線を宙に浮かせたまま
喉に
「すみません、あの、ちょっと体調が悪くなってしまって……今日はこのまま早退させてもらってもいいですか」

コミカルな
すかさず修哉はエンジンを停めてレンタカーの軽トラを降りる。途端に蒸した空気が全身を包んで、息苦しさが増した。作業服の襟を整え、駆け込むようにしてハッピーライフ・リフォームの敷地内へ足を踏み入れる。
資材が積み重なったスペースの端まで到達するのと、蜂のロゴマークが車体に描かれた運送業者のトラックが門から入ってくるのが同時だった。
修哉は作業場の入口から人が出てこないのを確かめながら、大きな身振りで運転席の男に合図をする。男は修哉の指示通り、高く積み上がった木材の陰に車を停めた。
「ここでいいんですか?」
運転席から顔だけを出し、空間を測るように奥を見やる。
「いえ、実はすぐに現場に持っていかなきゃいけないのでそこの軽トラに載せてもらえますか」
修哉は声が上ずりそうになるのを下腹部に力を込めて
「え?」
――怪しまれたか?
だが、運送業者には自分が本物の社員かそうでないかの区別などつけられないはずだ。
修哉は首に巻いたタオルで額を
「え、あ、はい」
男は
男は修哉の軽トラの後ろにトラックを停めると、軽い身のこなしで運転席を降りた。トラックの背後に回り、荷台の扉を開ける。ガンッという音が響いて、修哉は身をすくませた。男は胸ポケットから皺の寄った紙を取り出して広げる。
「えーと、河北木材からのお届けで、木材が十一枚。間違いないですか」
「はい大丈夫です」
修哉は答えるのもそこそこに作業服の
「運び込むの手伝います」
「え? いいですよ。重いですし」
「急いでるんで」
有無を言わさぬ口調で、勝手にトラックの荷台に飛び乗る。
「俺が下ろすんで、軽トラに載せていってください」
「あ、はい」
男はアタフタと修哉から二枚一組で
腰が
すべてを積み終えたときには、完全に息が上がってしまっていた。
「すいません、手伝ってもらっちゃって。でも助かっちゃいました」
「じゃあ俺はこれで」
ヘラヘラと笑っている男に投げつけるように言って軽トラの運転席に向かう。
「あ! ちょっと!」
背後から呼び止められた。
――バレた?
息が詰まった。振り向くことができない。
だが、男はあっさりと修哉の前に回り込んできた。
「こちら、受け取りのサインをお願いします。あと、代引きですんでお支払いも」
「え? あ」
修哉はハッとズボンのポケットを押さえる。用意してきた代金の封筒を抜き取りながら奥歯を噛みしめた。何をやってるんだ。落ち着け。男から受領証とボールペンを受け取り、〈葛木〉と書きかけて慌てて手を止める。わざと雑な字でハッピーライフ・リフォームの担当者の名前を書きつけ、封筒と一緒に男に押しつけた。
「えっと、代金が……」
「三十八万五千円に代引き手数料が二千円で三十八万七千円。ちょうど入ってる」
「あ、はい。確認させてもらいます」
男は不慣れな手つきで札束を数えていく。十枚数えるごとに数え終えたお金の置き場に困り、そのたびに修哉が手を貸した。
「ありがとうございました」
ようやく数え終えた男から領収書をひったくるようにして受け取り、修哉は踵を返す。運転席に飛び乗り、エンジンキーを回すや
走り出して最初の角を左に曲がり、サイドミラーからハッピーライフ・リフォームの看板が消えたところでようやく息をつく。
――とりあえず、第一段階はクリアだ。
疲労と
――でも、問題はここからだ。
頬を引きしめて両手でハンドルを握り直すと、くわえたままの煙草から灰がこぼれる。慌てて灰皿に灰を落とし、そのまま側面に押しつけて火を
デジタル時計に目を向け、ハンドルを回す。十一時四十二分。午前中着の配送指定なのだから、これ以上遅くなるのも疑われるもとだろう。何にせよ、早く終わらせてしまった方がいい。自分に言い聞かせてさらに角を曲がる。再びハッピーライフ・リフォームの看板が見えてきて、それだけで呼吸が荒くなった。
先ほどとは違い、今度は車のまま敷地内へ入る。作業場の入口近くに停めると、帽子を
――誰が出るだろう。
ごくりと生唾を飲み込む。担当者の
数秒して通話が
「ミツバチ運輸です。木材の納品なんですが」
『あ、はいはい。今行きます』
返ってきた声は聞き覚えのない女性のもので、少しだけ肩の力が抜けた。
――大谷は不在なんだろうか。
修哉は汗ばんだ手のひらを作業服の腹に
だが、次の瞬間、
「どうもどうも、暑い中ご苦労様」
背中から聞こえた声に再び全身が強張る。
――大谷、いたのか。
修哉はうつむいたまま振り向いた。
「遅くなりまして申し訳ありません。こちらに納品でいいですか」
普段より低い声で早口に言い、返答を待たずにポーチから受領証を取り出す。
「あ、悪いんだけど、そこの角材の横に運んでもらっていいかな」
大谷はのんびりした口調で言って修哉の背後の資材置き場を指さした。修哉は顔を
「あれ?」
大谷が上げた怪訝そうな声に、危うく板を落とすところだった。は、というかすれた声が喉から漏れる。
「いや、梱包されてないんだなと思って」
修哉は唇を開いた。けれど声が出てこない。
「なんて、君が言われても困るよね。いやさ、河北さんのとこは前回きちんと梱包してくれてたから」
「……すみ、ません」
「違う違う、君のせいじゃないんだってば」
大谷は親しげな口調で言うと「はい、ここで大丈夫」と板を下ろし始めた。修哉も足を止めて腰を
「ありがとう。悪いね」
「では、こちらにサインを」
修哉は大谷の言葉を遮って受領証とボールペンを突き出した。大谷が骨張った手で書きつけるのを見下ろしながら、震える指でポーチのチャックをいじる。
「あと、代引きですので三万五千六百円をお願いします」
「ああ、はいはい。えーと、じゃあ三万六千円からでいいかな?」
大谷はくたびれた茶封筒からお金を取り出し、眉尻を下げた。
「ごめんね、ちょうどじゃなくて」
「いえ……四百円のお返しと領収書です」
修哉は
「あ、そうだ」
心臓がぎゅっとつかまれたように痛んだ。呑んだ息が吐き出せない。
「よかったら一杯麦茶でも飲んでいくかい? この暑さだし熱中症も心配だろう」
「え……」
「僕も運ぶのを頼んじゃったし、それに、すごい汗じゃないか」
大谷の視線が自分の顔に向けられるのを感じて、慌ててキャップ帽のつばを下ろした。
「……せっかくですけど、次の配達がありますので」
「そうかい? くれぐれも水分補給には気をつけるんだよ」
大谷は少し残念そうに言ったものの、食い下がりはしなかった。修哉は
「ありがとうございました」
口をほとんど動かさずにそう言って、軽トラへ一歩歩み寄ったときだった。
大谷の肩越しに、ここから一ブロック先にある交差点が視界に飛び込んでくる。
こちらに向かってくるブルーグレイのステップワゴンを認識した瞬間、唐突にその角から白い乗用車が現れた。
あ、と思ったときにはもう遅かった。直進していたワゴン車の運転席に、乗用車が勢いよく突っ込む。
大きな衝撃音が響いた。
スローモーションのようにワゴン車が横へ傾いていき、何かの
一瞬、頭が真っ白になる。
「え?」
修哉の目の前で、大谷が
何が起こったのか、すぐには把握できなかった。たった今、目に映ったばかりの光景が信じられない。まるでドラマのワンシーンのように――いや、それよりもあっけなかった。何の
交差点では、ワゴン車が完全に横倒しになっていた。乗用車のバンパーも無残にひしゃげてしまっている。辺りに無数のガラスやプラスチックの破片が飛び散っているのが遠目にも見えた。ハッとして信号を見上げると、既にワゴン車の方の信号は赤に変わっている。
動けずにいる修哉の視線の先で、乗用車から中年女性が転がるように飛び出してきた。額から血が流れているものの、足取りはしっかりしている。
「ああ……」
大谷が嘆息する音が修哉の耳に届いた。
「よかった、とりあえず命に別条はないみたいだ」
その言葉に修哉も息を吐き出し、自分が呼吸を止めていたことに遅れて気づいた。全身を包んでいた空気がふっと緩むのを感じる。作業服の上から胸を強く押さえた。だが、速まった鼓動はなかなか治まらない。
「何かできることは……あ」
現場へ向けて足を踏み出しかけた大谷がふいに足を止める。つられるようにして修哉も顔を向けると、周囲の家やビルからたくさんの人が出てくるところだった。あっという間に事故現場には人だかりができる。
「あれなら、行かない方がいいかな」
大谷はひとりごちる口調で言い、首にかけたタオルで額を拭った。
「事故の瞬間、見ました?」
「あ、はい」
修哉は思わずうなずいてしまってから、ハッと我に返る。
「いや、えっと……」
「今のって何がどうなって、」
「すみません、次の配達があるんで」
慌てて遮り、今度こそ軽トラに乗り込んだ。大谷の方には顔を向けないように注意しながらエンジンをかける。
会釈をしてアクセルに足をかけると、「あ」と大谷が運転席の窓に手を押しつけてきた。修哉はぎょっと上体を引く。
「警察に何か訊かれたら協力した方がいいですよ」
大谷は迷いのない口調で言った。
「知り合いで目撃者がいなくて困ったやつがいたんですよ。ああいうの、水かけ論になったりすると大変だから」
「……そうですね」
修哉は低く答えながら、身体を屈めてアクセルを踏み込んだ。

ひとまず板を自宅に運び入れてレンタカーを返し、再び自宅に戻ってきたのは十五時過ぎだった。修哉は鉛を詰め込まれたように重たく感じられる身体を懸命に動かし、汗で肌に張りついた作業服を脱ぎ捨てたところでやっと一息つく。
眩暈と頭痛を
――これで、ごまかせたのだろうか。
とにかく余分な十枚の板は回収できた。本物の運送業者には伝票通りの代金を渡しているのだから、書面上矛盾はない。ハッピーライフ・リフォームからしても一枚注文して一枚納品されたのだから、何も問題はないはずだ。
修哉は急速に冷えてきた身体をタオルケットの中で丸める。目の端でキッチンの前に積み重なった板を見やり、ねばついたため息を吐き出した。
――あれは、どうしよう。
本来であれば捨ててしまうに越したことはないのだろうが、今の大きさのままでは捨てるのも難しい。細かく切ってしまえば可燃ごみに出せるにしても、今はその体力も気力もなかった。それに、と修哉は鈍痛を訴える
三十五万円分なのだと思うと、何にも役立てないまま捨ててしまうのは惜しいような気もした。誰かに転売するようなことはできないが、たとえば実家に持って帰るとか――そうだ、そうすれば父親がテーブルなり棚なりを日曜大工で自作するだろう。
そこまで考えると、少しだけ胸のつかえが取れる。何にせよ、それはほとぼりが冷めた頃に少しずつやればいいことだ。どうせ職場の人間がここに来ることはないのだから。
修哉はまぶたを下ろした。途端に激しい睡魔が襲ってくる。あとは、何か他にやっておくべきことはないだろうか――そう考えようとしながら、次の瞬間には意識を手放していた。
そのままぶっ通しで十四時間眠り、目が覚めたときにはもう早朝だった。ひどい筋肉痛で強張った身体を何とかベッドから引き剥がし、
手早く身体を洗い終えると、湯気の立つ浴槽に足を差し入れていく。温度差にざっと粟立った肌は、肩まで
――もう大丈夫だ。
自然とそう思えた。予想外の事態はあったが、
これで、すべて終わったのだ。
修哉はゆっくりとまぶたを下ろす。すると、ふいにまぶたの裏に横転したワゴン車の姿が浮かんだ。途端に口の中に苦味を感じ、目を開ける。
――そう言えば、あの運転手は大丈夫だっただろうか。
乗用車の方の女性はすぐに出てきていたが、ワゴン車の運転手の姿は見ていない。あれだけの衝撃で、横転までしていたのだから、まったくの無傷というわけにはいかないはずだ。最悪の場合、
もし、ワゴン車の運転手が亡くなったんだとしたら、自分は人が死ぬ瞬間を目撃してしまったことになる。それは、何かとても恐ろしいことに思えた。
修哉は、これまで人の死に立ち会ったことがない。母方の祖父が他界しているものの、それは幼稚園の頃の話で、葬儀に参列しただけだった。そこにあったのは死の
修哉にとって死とはドラマや映画、あるいはニュースにしか出てこない自分とはかけ離れた存在で、だからこそ、乗用車の女性の額から流れていた鮮血の赤が脳裏から離れない。――横転してしまっていたワゴン車の運転手はどれほどの
居ても立ってもいられないような落ち着かなさを覚え、修哉は勢いよく立ち上がる。全身についた水滴をバスタオルで荒々しく
――事故のその後を知ることができれば、落ち着けるだろうか。
ワゴン車の運転手が無事だとわかれば、それ以上は考えずに済むはずだ。
修哉は部屋へと戻り、テレビをつけた。朝のニュース番組を
昨日の事故について取り上げている番組は一つもなかった。ただタイミングが悪くて見つからないだけなのか、それとも普通の交通事故ではテレビのニュースで取り上げられることもないのか。修哉は頭を拭いていた手を止め、煙草に火をつける。
唇を
「あ」
修哉は口から煙草を離した。
地元――そうだ、新聞がある。地方紙の社会面であれば取り上げることもあるはずだ。
煙草の火を揉み消すと、Tシャツとスウェットをすばやく身に着けた。財布と携帯だけをポケットに突っ込み、アパートの裏手にあるコンビニへ向かう。新聞と菓子パン、缶コーヒーと煙草を買い込んで足早にアパートへ戻り、菓子パンの袋を歯で噛み切りながら
〈マンション火災で2人死傷 幸町〉〈ホームから転落 女性右足に軽傷〉〈元郵便局員に有罪 182万円着服で〉〈工事現場で鉄材落下 通行人にけが人なし〉――社会面に並んだ記事の見出しを指でなぞっていき、三段目の記事に差しかかったところで動きを止める。
〈車2台が衝突 信号無視か〉
太いゴシック体で書かれた見出しが浮かび上がって見えた。
〈2日の午前11時55分ごろ、中富町6丁目の交差点でワゴン車と乗用車が衝突する事故があった。この事故でワゴン車を運転していた中富町小岩の会社員・隅田曜平さん(29)が死亡、〉
「……あ」
思わずつぶやきが漏れた。死亡、という文字に、内臓が下に引っ張られたように重くなる。やはり、亡くなっていたのか。修哉はひと口
〈乗用車を運転していた下田市中井戸の主婦・望月佳代子さん(53)が左腕を骨折する重傷を負った。
中富署によると、ワゴン車が赤信号を無視、乗用車と衝突したものとして調べを進めている〉
「え?」
修哉は目を見開いた。拳を口元に当てる。
――どういうことだろう。
修哉が目撃した事故では、赤信号を無視したのは白い乗用車の方だったはずだ。なのになぜ――眉間の皺が濃くなっていく。
もしかして、現場に状況を判断できるような
嫌な汗が背中を伝い落ちた。
監視カメラなり、タイヤ痕なり、何か状況を証明するものがあれば、当然こんなふうに間違った方向に捜査が進んでしまってはいないだろう。もし、生存者の証言しか使えるものがないんだとしたら。
『警察に何か訊かれたら協力した方がいいですよ』
大谷の声が、耳の奥で反響した。
『ああいうの、水かけ論になったりすると大変だから』
だとすれば、水かけ論どころではない。一方は証言をすることすらできず、片方の証言だけで状況が決められつつあるのだから。死人に口なし、という言葉が浮かんで、胸がざわつく。
自分が信号を無視していたくせに、相手が反論できないのをいいことにすべての責任を
――他のって、何だ?
修哉は菓子パンの袋を卓袱台の奥に押しのけ、畳の上に転がった煙草とライターを引き寄せた。微かに震える手で煙草をつまみ、口元へ運ぶ。端が唇に当たって床に落ちた。修哉は舌打ちをして拾い上げ、ほとんど噛み
『警察に何か訊かれたら協力した方がいいですよ』
もう一度、大谷の言葉が蘇る。どう考えても、大谷の言っていることは百パーセント正しい。真実を目撃した以上、そしてそれが歪められていることを知ってしまった以上、黙って知らないふりをしていることなど許されないはずだ。言わなければならない。今すぐ警察に連絡をして、事故の瞬間を目撃したのだと証言しなければならない。
修哉は自分に言い聞かせるように思いながら、けれど自分が本当にそんなことをする気がないこともわかっている。
――言えるはずなんてない。
そんなことをすれば、名前を訊かれることになるだろう。大谷と一緒に状況を話さなければならなくなるかもしれない。そうすれば――自分が運送業者のふりをしていたことも明るみに出てしまうことになる。
修哉は根元まで吸った煙草を灰皿に押しつけ、その手で新しい煙草に火をつける。まだほとんど伸びていない灰を神経質に落とし、新聞を眺め下ろした。なぜ、こんなものをわざわざコンビニで買ってまで読んでしまったんだろう。事故のその後のことなんて、知らなければよかったのに。
――いや。
修哉は
――俺は、ワゴン車の運転手が死んでしまったことも知らなかったし、事故の捜査がどうなっているのかも知らなかった。
ライターを手にした拳を強く握りしめて口の中でつぶやく。
だから、自分の証言が必要なのかどうかもわからなかった。
意識の底まで
――そうだ。
修哉はまぶたを上げた。ワゴン車の側の信号が青だと思ったのは、自分の勘違いだったかもしれない。ほんの一瞬の出来事だ。状況を正確に目撃できたと考える方がおかしいんじゃないか。
喉元をきつくつまむ。警察がワゴン車の方が赤信号を無視したと考えたのなら、きっとそれが真実なのだろう。むしろここで自分が
修哉はゴミ箱から新聞を抜き取って広げ直し、生き残ったという女性の名前をじっと見つめた。
――それに、この人は、これからも生きていかなければならないのだ。
ただでさえ、この人はこれからの人生、人を死に至らしめてしまったという事実を背負いながら生きていかなければならなくなる。それだけで後ろ指をさされることもあるだろうし、本人も苦しむことになるだろう。だったらそれは――既に罰を受けていることになりはしないか。
修哉は唇を湿らせる。
たしかに死んでしまった男性は
だが、男性にはもうそれを悔しいと思う意識すらないのだ。
修哉は背筋を伸ばして息を吐いた。
――ここで本当のことを言ったとして、幸せになる人なんていない。証言をしたところで、ただ、自分が正しいことをしたという実感に浸れるだけだ。
そう思った途端、ふっと呼吸が楽になる。
それでも修哉は、すがるように新しい煙草に手を伸ばしていた。

その日は一日、会社を出るまで落ち着かなかった。
いつ、誰から、何を言われるか。大谷からも運送業者からも、まずい連絡が入ってくる展開は具体的には想像できないのに、漠然とした不安はなくならない。何となく営業部にかかってくる電話には即座に出てしまい、それがまた不自然だと思われるのではないかと心配になったりもした。
けれど、その一日が終わり、さらに翌日も何事もなく過ぎると、次第に修哉は二日前の出来事について考えることもなくなっていった。入力ミスをごまかした件については誰にもバレることなく
いや、と修哉は思い直す。やはり実家に運び込むのはやめよう。この杉で作られた何かを実家で目にするたびに嫌な気持ちになってしまう。それなら、三十五万円はもったいないとしてもきちんとすべて捨ててしまった方が後腐れはないはずだ。平日の夜は近所迷惑だから、休日の昼間にでものこぎりで細かくして少しずつ捨てていけばいい。
そう考えて納得し――だが、それで話は終わらなかった。
納品した日から三日後、大谷から会社に電話がかかってきたのだ。
『ハッピーライフ・リフォームの大谷といいますが、葛木さんはいらっしゃいますか』
その名前を聞いた瞬間、修哉は腰を浮かせていた。
「どうもお世話になっております。葛木です」
『あ、葛木さんですか。こないだはどうも』
「え?」
頬が引きつる。だが、大谷は穏やかな口調で言った。
『いい杉を入れていただいて。お客様にも喜んでいただけました』
「あ……いえ」
修哉はかすれた声で答え、胸を
――何だ、そっちか。
「喜んでいただけたならよかったです――あの、きちんと梱包せずに発送してしまい申し訳ありませんでした」
思わず後半をつけ足してしまってから、
『ああ、それは別にいいんですけどね。実はちょっと別件で確認したいことがありまして』
「え?」
反射的に漏れた声が上ずった。
――確認?
毛穴からどっと汗が噴き出してくる。
「えっと……何でしょうか」
『こないだ商品を納品してくれた運送業者を知りたいんですよ』
心臓が、どくんと跳ねた。
「……え?」
『いやね、実はあの納品してもらった日、会社の近くの交差点で交通事故があったんですよ。新聞には載ってたんだけど、知ってます?』
「え……いえ」
『まあ、そうですよね。小さい記事だったし』
大谷はあっさりと納得して続ける。
『それで、ちょうど事故の瞬間に交差点のそばの作業場で納品してもらってたんですよ。僕は見てなかったけど、一緒にいた運送業者の人が目撃したって言ってたんで、その人のことを知りたいんです』
修哉は口を開いた。だが、何か答えなければと思うのに声が出ない。
『実は今、警察が事情聴取に来ているんだけどね、どうも事故の状況がよくわからないらしいんですよ』
――警察が事情聴取。
わかっていたはずのことなのに、身体の
『前に納品してもらったときはたしかミツバチ運輸さんだったと思うんですけど、今回もそうですかね?』
瞬間、頭の中で思考が回った。ここで本当のことを答えるべきか否か。いや、どちらにしてもミツバチ運輸が運送を請け負ったのはすぐにわかることだ。
だが、警察がミツバチ運輸に聴取に行ったとしても、あの男は何も知らないと答えるはずだ。
――あの男が納品したと思っているのは、事故が起こるよりも何分も前のことなのだから。
足元で、何かが崩れ落ちていくような気がした。ヘラヘラと笑っていた運送業者の男の顔が脳裏で明滅する。
『あれ? もしもし? 聞こえてます?』
「あ、はい」
慌てて返事をすると、それにかぶせるようにして再び大谷が言った。
『今回使った運送業者はどこですか?』
電流に似た痺れがうなじを走る。どうしよう。どうしたらいい?――だが、答えないわけにはいかない。
「……ミツバチ運輸です」
『ああ、やっぱりそうですよね』
大谷は声を和らげて息を吐いた。
『いきなり変な電話をしてすいませんね。また木材が必要になれば、河北さんのところに発注させていただくんで』
取り繕うように声のトーンを上げる。
「ありがとうございます」
そう答えるだけで精一杯だった。修哉は切れた電話の受話器を、呆然と眺め下ろす。
警察はミツバチ運輸の男に事情を訊くだろう。けれど、男から証言が引き出せることはない。大谷の話と食い違うことを怪訝に思った警察は双方から詳しく状況を聞き出そうとするはずだ。何時何分にハッピーライフ・リフォームに着いたのか。納品するときにはどんな話をしたのか。――納品したものが何だったのか。
視界が一段暗くなる。
――納品数に食い違いがあることがわかったら、警察は会社にも話を訊きにくるかもしれない。
その後は、ほとんど仕事が手につかなかった。外回りに行かなければならないのに、自分が不在の間に警察が来てしまったらと思うと外出する気になれない。席にいるしかないのなら、せめて事務仕事を進めなければと思いながらも、目が数字の上を滑るばかりで一向に頭に入ってこなかった。
昼食に出る踏ん切りもつかず、空っぽの胃がしくしくと痛み始める。修哉は忙しなく喫煙所と自席を往復しながら、
――どうしてこんなことになってしまったんだろう。いつまで、こんなふうに怯え続けなければならないのか。
そう考えると泣き出したくなる。ミスに気づいた時点で、素直に報告するべきだったのだ。そうすれば、失望はされただろうが、まだ
この分だと、今月の営業成績は再び最下位に、しかもこれまでよりもさらに悪い数字になるはずだ。どちらにしろ失望されることになるのなら、最初に腹をくくってしまえば、せめて傷は浅くて済んだのに。
「葛木さん」
「あの、スミダさんという方がお見えです」
女性社員はおずおずと修哉を見上げてくる。修哉は慌てて小さく咳払いをした。
「スミダ? どこの?」
「さあ、会社名は言っていませんでしたけど」
「男性? 女性?」
「女性です。ひとまず受付でお待ちいただいています」
スミダ――そんな顧客、いただろうか。
「行ってみます」
修哉は怪訝に思いながら席を離れる。スーツのネクタイを締め直し、受付へと向かった。
カウンターを回り込み、そこにいた女性に足を止める。女性は、黒いシンプルなワンピースに白いカーディガンを羽織っていた。黒い髪を
――誰だ?
そう思った途端、女性が化粧気のない顔を振り向かせた。修哉はその顔を凝視するが、やはり見覚えがない。
「どうも、お待たせしました。葛木です」
修哉はひとまず営業用の笑顔を貼りつけて会釈をした。すると女性は、ピンと伸ばした背を丸めることなく頭を下げる。
「アポイントもなく押しかけてしまい申し訳ありません。スミダと申します」
まるでアナウンサーのように滑舌の良い声だった。アポイント、という発音が妙に滑らかで、かえって違和感がある。
スミダ? 再び修哉の頭の中に疑問符が浮かんだ。スミダ――墨田? 住田? 隅田? 以前外回りをした会社の内の誰かだろうか。それとも、顧客から紹介を受けた個人? 修哉は迷いながら女性に一歩歩み寄る。
「とんでもございません。何かご依頼でしょうか?」
「いえ、今日はうかがいたいことがあってまいりました」
女性はまばたきもせずに答えた。顔立ちはどちらかと言えば薄い方で、目もそれほど大きいわけではないのに、不思議な目力がある。
「はい、何でしょうか」
修哉は
女性は数秒の間を置いてから唇を開く。
「三日前にこちらからハッピーライフ・リフォームという会社に商品を納品されたと思います」
修哉は息を呑んだ。咄嗟に何の反応もできずにいると、女性が修哉を真っ直ぐに見据えて続ける。
「実はその会社の近くで交通事故がありまして、主人を亡くしたんです」

これから外出する用があるので話は外で歩きながらでもいいですか、という修哉の返答に、女性はお忙しいところ申し訳ありません、と返してきた。けれど言葉とは裏腹に、恐縮した様子は見受けられない。全体的に表情が乏しく、感情がほとんど読み取れなかった。
修哉は逃げるようにして一度自席に戻りながら、指の関節を噛む。
――あのときの運転手の、奥さん。
訊きたいことというのは何だろう。さすがに、あの事故のときにあの場にいた偽者の運送業者が自分だということは知らないはずだ。だったら、なぜ自分のところにやってくるのか。修哉は机の上に広がった書類をがむしゃらに
大谷からの電話を切った後に考えた可能性が頭に浮かんだ。大谷とミツバチ運輸の男の話にはいくつか食い違いが生じる。そこをきちんと洗い出そうと考えれば、受注者である自分のところに話を訊きにくるのは道理だ。だが――それにしても、来るのが早すぎないか?
「お待たせしてすみません」
「いえ」
女性と短く言葉を交わすと、修哉が半歩前を行く形で歩き始めた。どこへ向かうのかも決められないまま、ひたすら左右の足を交互に前に出していく。
「うかがいたいことというのは、葛木さんが担当されたという、御社からハッピーライフ・リフォームへ発送された商品についてです」
女性は前置きをせず、淡々と切り出した。
内臓がぐっと縮こまる。
女性が息を吸い込む音が左耳にだけ届いた。
「ハッピーライフ・リフォームの方から話を聞いて、先ほど運送業者のところにも行ってきたんです」
修哉は手のひらに
「御社からは、どんな商品をいくつ発送されたのでしょうか」
何を、どう答えればいいというのか。
喉がごきゅりとおかしな音を立てた。お客様の情報なので答えられませんと突っぱねる? とりあえず考えて、ホッと息を吐く。そうだ、それがいい。それならば不自然ではないはずだ。
修哉は下腹部に力を込めて口を開いた。
「申し訳ありませんが、それはお客様の情報に関わることですので、お答えすることができません」
ほとんど機械的にそう告げて、口を閉じる。女性が黙り込み、沈黙が落ちた。修哉は唇の端を引きしめて気まずさに耐える。
「どうぞ、吸ってください」
唐突に言われて手元を見下ろすと、いつの間にか手にしていたライターをカチカチと鳴らしていた。修哉は数秒迷ったものの、会釈をして煙草に火をつける。煙を大きく吸い込んで吐き出すと、ほんの少し気持ちが落ち着いた。
――そうだ、これでいい。
修哉は小刻みに人差し指を動かして灰を地面に落とす。
もし食い下がられても、これで突っぱね続けていれば、やがてあきらめて帰ってくれるだろう。相手は不快に思うだろうが、少なくともボロは出ない。
だが、予想外に女性は食い下がることなく「教えてはもらえないんですね」とつぶやいた。修哉は思わず足取りを緩める。もうあきらめてくれたのだろうか。女性が横に並び、修哉を追い抜いた。え、と思った途端に女性が振り向く。修哉はつんのめるようにして足を止めた。
「実は、今回の事故は主人が赤信号を無視して起きたものだと相手の車の方は主張しています」
女性はショルダーバッグから皺が寄った新聞を取り出し、修哉の顔の前に突きつける。
目の前の新聞は、修哉が数日前に買って読んだのと同じものだった。
「警察も、現場の状況からは判断がつかないからこのままだとその方の証言を重視すると言っています。でも」
女性はそこで一度言葉を止め、息を吸い込み直した。
「あの人は、赤信号を無視したりするような人じゃないんです」
静かな声音で断言し、まるで挑むかのように修哉を真っ直ぐに見上げる。
「夫がきちんとした人だったとか、正しい人だったとか、そうした私の主観で言っているわけではありません。夫は、本当に赤信号を無視したりするような人ではありませんでした。いえ、正確に言えば赤信号を無視したりはできなかったんです」
修哉は動けなかった。どう反応すればいいのかわからない。
「家を出るときには左足から出る。一緒にいる人がくしゃみをしたら手で自分の顔を撫でる。奇数の車両には乗らない。黒猫を見かけたら一度家に帰らなければならない。――どれも、夫が忠実に守っていたジンクスです。夫は毎日、本当にたくさんのジンクスを守って生きていて、その中に信号が赤になったら止まらなければならないというのもありました。夫にとって、赤信号で止まるというのは、ただの交通ルールではなくて絶対に破ることができないジンクスだったんです」
「……ジンクス」
修哉がつぶやくと、女性は短く顎を引く。
「あの人に限って赤信号を無視したなんてことはあり得ないんです。もし相手の方がそう主張しているんだとしたら、その方は勘違いをしているか、あるいは
女性の口調には迷いがなかった。
「ですが、警察は信じてくれません。それでは証拠にはならないと言うんです」
「それは……そうでしょうね」
修哉の
「運送業者は十一時三十五分頃に、杉の板を十一枚届けたと言っています。そのとき、会社の前で受け取ったのは若い男性で、その人に言われて軽トラックに積み直したそうです。ですが、ハッピーライフ・リフォームの方は、運送業者の人が来たのは十一時五十分頃で、受け取った板も一枚だけ、軽トラックに積んだのではなく資材置き場に運んでもらったと言っています」
何のメモも見ず、ひと息に言いきる。
「そして、ハッピーライフ・リフォームの方は、運送業者が事故の瞬間を目撃したはずだと言っているのに、運送業者は何も見ていないと証言している。つまり、到着した時間も、納品した枚数も、そのとき起こった出来事も、すべて違うんです。――おかしいとは思いませんか?」
「……何で」
修哉は思わず問い返していた。だが、自分でも何を訊きたいのかわからない。女性は、顔の横で指を二本立てた。
「考えられる可能性は二つです。どちらかが嘘をついている、あるいは、間にまったく別の第三者がいる」
瞬間、指先にちり、という痛みを感じて手を払う。いつの間にか根元まで燃えていた煙草が宙を舞い、地面に落ちた。女性が当然のようにしゃがみ込んで吸い殻を拾い上げる。
「あ」
修哉は慌てて手を伸ばしたが、女性は吸い殻をつまんだまま続けた。
「ただ、不思議なのはハッピーライフ・リフォームの方は一枚しか発注していないと言っていることなんです。一枚発注して一枚納品されたのだから、問題ないと――じゃあ、どうして運送業者は十一枚納品したと言っているんでしょうか」
修哉から視線を外すことなく微かに首を傾ける。
「そもそも発送したのは何枚だったんですか」
一枚だと答えるわけにはいかない。それだけがわかった。伝票上も実際に発送した数も十一枚になっている。
「……十一枚です」
答えてしまってから、修哉はハッと息を呑む。
――違う。答えられないと突っぱねなければならなかったのに。
奥歯を噛みしめるが、もう遅い。
「では、どうしてハッピーライフ・リフォームの方は一枚しか発注していないと言っているんですか?」
女性が、一歩前に踏み込んでくる。他人にしては近すぎる距離に、修哉はよろめくようにして二歩後ずさった。
「……わかりません」
「わからない? でも、あなたが注文を受けたんですよね」
女性は大仰に目を見開く。
「十枚はどこに行ってしまったんでしょうか」
「知りませんよ、そんなこと。誰かが盗んだんだとしても、うちとしては、十一枚受注して、十一枚発送して、十一枚分の料金をもらっているんだから問題ないんです!」
修哉はほとんど叫ぶように言い返していた。
「それ以上のことはわかりませんし、調べる必要もありません」
叩きつけるように言い捨てると、女性を避けるように横にずれる。
「これ以上お答えできることはありません。用があるので失礼します」
有無を言わさぬ口調で切り上げて歩き始めたときだった。
「なら会社の他の方に訊きます」
背後から聞こえた言葉に、修哉は弾かれたように振り返る。考える間もなく、女性の腕をつかんでしまっていた。
女性がつかまれた腕を見下ろし、それから修哉を見上げる。
「何ですか」
「……やめてくれ」
修哉は絞り出すような声音で言った。
「頼むから、会社には……」
「何か、困ることがあるんですか?」
ひゅっと喉が鳴る。
――この女は、すべて気づいているんじゃないか。
自分が、あの場にいた目撃者であること。運送業者と大谷を
修哉は女性から腕を離し、頭を下げる。
「悪かった。失礼な応対の仕方をしたことは謝るから」
「謝罪なんていりません」
女性はきっぱりと言った。
「私は、目撃者に証言さえしてもらえればそれでいいんです」
「それはできない」
そう答えた瞬間、女性がじっと見据えてくる。
「……あなたが目撃者だったんですね」
――しまった。
修哉は視線を彷徨わせた。
今度は、女性が修哉の腕をつかむ。
「お願いします。証言してください。あの人は何も悪いことをしていないんです。なのに、このままだとすべてあの人のせいにされてしまう」
「でも……」
「子どもがいるんです」
初めて、女性の声が湿り気を帯びた。
「あの子は、父親が死んでしまっただけでも充分に傷ついています。その上、父親が加害者だなんてことになったら……」
脳裏に、ワゴン車が傾いていく映像が蘇る。キラキラと宙を舞うガラスとプラスチックの破片、青から黄色へと変わっていく信号――自分が、たしかに目にしたもの。
修哉は、慌てて腕を振り払う。その拍子に鞄が地面に投げ出された。急いで拾い上げるが鞄の口まで出かかっていた財布が滑り落ちる。二つ折りの財布からは大量のレシートと運転免許証、数枚のポイントカードが散らばって、耳の裏が熱くなった。膝をついてかき集める修哉の隣で、女性が運転免許証を拾い上げてじっと見つめる。修哉は咄嗟に引ったくるようにして奪い返した。あまりに荒々しい所作に我ながら気まずさを覚えて立ち上がる。
「申し訳ないけど、」
「証言してくれないのなら、あなたの会社に行きます」
カッと頭に血が上った。
「やめろ!」
目の前が赤く染まり、何も考えられなくなる。手が細かく震えた。
「そんなことをしたら絶対に証言しない」
女性が動きを止める。
「……むしろ
女性の
「……あなたは、自分のためにしか証言できないんですね」
正面から低いつぶやき声が聞こえた。ず、と靴が地面をこする音が続いて、修哉はハッと顔を上げる。
踵を返した女性の表情は、修哉からは見えなかった。
帰宅して一服を終えると、修哉は重い腰を持ち上げてゴミ箱へ向かった。中から新聞を取り出し、社会面を開く。
〈隅田曜平〉
新聞記事の中に小さく書かれた名前の上で、視線が止まった。
スミダ――隅田。一度新聞記事を読んでいながら、自分が隅田という
――あの人は、赤信号を無視したりするような人じゃないんです。
女性の声が脳裏で響いた。
修哉はポケットから携帯を取り出してインターネットに接続する。〈隅田曜平〉と打ち込んで検索すると、一番上にSNSのページが表示された。黒い短髪に銀縁の眼鏡をかけたどこか神経質そうな男性――初めて目にする女性の夫の顔に、息を呑む。
夫はそれほどマメな性格ではなかったのか、あまり積極的にSNSを使う人間でもなかったのか、ほとんど投稿がなかった。時折、科学論文のサイトをシェアしているくらいで、アップされている写真はプロフィール画像に使われている一枚しかない。
だが、投稿を
〈無事に産まれてくれた。これでもう、書かなくていい〉
意味のわからない文章に、眉根が寄る。修哉は目を凝らしてさらに投稿を遡っていく。
すると、その投稿以後は投稿らしき投稿がないのにもかかわらず、その日付を境に一日もあけずに投稿が続いていた。
〈晴れのち曇り〉〈雨〉〈雨〉〈晴れ〉――ただし、それらはすべて、天気が書かれただけの投稿だった。修哉は天気だけの記述がずらりと並んだ画面をすばやくスクロールさせていく。それらは突然、約八カ月前のある日で止まった。
そこには、奇妙な言葉が書かれている。
〈子どもができた。毎日欠かさず天気を書くこと〉
――これは、何だ?
修哉の脳裏で、女性の声が反響する。
『家を出るときには左足から出る。一緒にいる人がくしゃみをしたら手で自分の顔を撫でる。奇数の車両には乗らない。黒猫を見かけたら一度家に帰らなければならない。――どれも、夫が忠実に守っていたジンクスです。夫は毎日、本当にたくさんのジンクスを守って生きていて、その中に信号が赤になったら止まらなければならないというのもありました。夫にとって、赤信号で止まるというのは、ただの交通ルールではなくて絶対に破ることができないジンクスだったんです』
修哉は唇を舐めて携帯の画面を見つめた。
〈無事に産まれてくれた。これでもう、書かなくていい〉
――これも、ジンクスだったのだろうか。
妊娠がわかってから実際に産まれてくるまでの八カ月間。彼は一度始めてしまったジンクスをやめることができずに、一日も忘れずに天気を記述するだけの投稿を続けたのだろうか。――子どもが無事に産まれてくることを願って。
携帯を操作する手が止まる。しばらくして、画面から光が消えた。
『あの子は、父親が死んでしまっただけでも充分に傷ついています。その上、父親が加害者だなんてことになったら……』
修哉は慌てて携帯を
――ダメだ。これ以上は知らない方がいい。
まぶたを強くつむり、睡魔が訪れるのをひたすらに待つ。結局、修哉が意識を手放したのは明け方近くなってからだった。
全身がだるく、頭がしきりに
修哉はぬるく粘ついたため息を吐き出し、身体を引きずるようにして職場へと向かう。けれど、一度仕事を始めてしまえばそれなりに気も紛れた。少なくとも作業している間は余計なことを考えずに済む。
滞っていた仕事をひたすらこなしているだけで一日が終わり、修哉は久しぶりに感じる単純な疲労に身を委ねるようにして眠りについた。
翌朝、修哉の目を覚ましたのは、携帯のアラームではなく玄関のチャイムだった。修哉は鈍い頭痛に顔をしかめながら首を持ち上げ、思い返して
――誰だよ、こんなに朝早く。
修哉は顔をしかめ、身体を丸める。
だが、もう一度チャイムが鳴った。今度は続けざまに三度鳴る。舌打ちが漏れた。仕方なくベッドから降り、玄関へ向かう。
「はい」
あからさまに不機嫌な声を投げかけながら、ドアスコープに目を押し当てた。そこにいた、見知らぬ二人組の男に息を呑む。
「どうも葛木さん、朝早くにすみません」
男の内の一人が言いながら身体の前に身分証を掲げた。どこかで見たことがあるようなエンブレムと、そこに記された「POLICE」という文字に、強い眩暈を覚える。
「葛木さん、ちょっと開けていただけますか?」
「あ……はい」
答える声が喉に絡んだ。まさか、本当に事故当日の納品内容について訊きにきたのだろうか。
震える指でサムターンを回し、恐る恐るドアを押し開ける。
「どうも葛木さん、朝早くにすみません」
中年の方の刑事が、同じ言葉を繰り返した。いえ、と答えたつもりが声にならない。あの女性と同じ質問を投げかけられたら、どう答えればいいのだろう。警察相手では、答えられないじゃ済まされない。
だが、次の瞬間、刑事は言った。
「五日前、幸町のマンションで不審火があったんですが、ご存知ですか」
は、という声が裏返る。
「不審火?」
「そうです。この辺りのみなさんに順番に訊いているんですけどね、八月二日のお昼頃にあった火事です。知っていますか?」
「……知りませんけど」
修哉は拍子抜けしてつぶやいた。身構えていた分、脱力も大きい。
――何だ、まったくの別件か。
刑事は、すっと目を細めた。
「あれ、ご存知ないんですか? この辺りでもそれなりに騒ぎになったはずですけど」
え、と思わず訊き返してから、修哉は記憶を探る。八月二日のお昼頃、幸町のマンション、不審火――たった今、刑事が口にしたばかりの言葉を
修哉は急速に渇いていく喉に生唾を流し込んだ。刑事というのは、いつもこんなふうに圧迫感を与える話し方をするものなのだろうか。事情聴取のようなものを受けるのは初めてで判断がつかないが、こんな話し方をされれば誰だって普段通りの態度なんて取れなくなるんじゃないか。
答えられずにいる修哉の前で、刑事がゆっくりと口を開いた。
「火事現場から見てこっちは風下ですからね。ご近所の方の話ではかなり煙の匂いもしたみたいですよ」
「そうなんですか」
相槌がほんの少しかすれてしまい、そのことに修哉は動揺する。自分でも、どうしてこんなに動揺してしまっているのかわからなかった。この件については
そう考えた途端、中年刑事が修哉を真っ直ぐに見据えて言った。
「葛木さん、ちなみに八月二日のお昼頃はどちらに?」
修哉は口を開きかけ、閉じる。本当のことを答える必要はないはずだ。だったらどう答えるべきか。平日の昼間の話なのだから、最も自然なのは仕事に行っていたという答えのはずだ。だが、もし会社に問い合わせられたら――いや、ただ隣町に住んでいるだけの自分の証言の裏をそこまでして取るわけがない。
「さあ、普通に仕事に行っていたと思いますけど」
「職場はどちらなんですか?」
「八城市です」
「ああ、結構遠いんですね」
刑事は世間話ともつかないような声音で相槌を打ちながら手元の手帳に何かを書きつけた。ボールペンの先を顎に当て、芝居がかった仕草で小首を傾げる。だけどおかしいな、とつぶやき、目線だけを持ち上げた。
「この近所で、葛木さんを見かけたという方がいらっしゃるんですけど」
修哉は大きく目を見開く。
――誰かに、見られていたのか。
慌てて顔を伏せ、「あ、いや」と口の中でつぶやいた。
「すみません、勘違いしていました。……八月二日は仕事を休んで家にいたんです」
「なのに、騒ぎには気づかなかったんですか?」
刑事が間髪をいれずに切り返してくる。
「……どうして」
尋ねるというより、自動的につぶやきが唇から漏れた。二人組の刑事は答えず、探るような目線を向けてくる。修哉の身体の芯に微かな震えが走った。どうして、ここで食い下がられるんだろう。疑われている?――そう考えた次の瞬間、一気に血の気が引く。
「寝込んでたんです」
修哉はもつれそうになる舌を懸命に動かして答えた。
「風邪をひいていて、熱も三十九度くらいあって頭がボーッとしてたし、それにエアコンもつけてたから窓も開けてなくて」
答える必要がないことまで話してしまい、目の前の刑事と視線を合わせられなくなる。嘘をつく人間は
もっと普通に答えなければ。自分は無関係なのだと早くわかってもらえるように。
「外にも一歩も出てないし、」
言いかけて、誰かに見られていたのならそれもおかしいかもしれないと気づく。
「……でも、食べるものがなかったんで、コンビニくらいは行ったかもしれないですけど」
「一人暮らしですか」
修哉が言い終わるのを待たずに言葉を挟んできたのは若い刑事の方だった。見たところ二十代後半といったところで、修哉とあまり変わらない。
「そうですけど」
「風邪のときに一人暮らしはつらいですよね」
若い刑事は突然親しげな口調になった。修哉の肩越しにちらりと部屋の中へと視線を投げる。修哉は反射的にドアノブをつかんだ手に力を込めたが、刑事の足がドアとの
「もう体調はいいんですか?」
「はい……まあ」
――五日間で完治するなんて不自然だと思われているんだろうか。
「それはよかった――消防車のサイレンも聞こえませんでした?」
若い刑事は唐突に話題を変えた。修哉は視線を彷徨わせる。どう答えるべきか。隣町に消防車が来たとして、まったく聞こえなかったのは不自然なんだろうか。もはや事実とは関係なく、どう答えれば納得してもらえるのかということしか考えられない。
「……寝込んでたんです」
かろうじて、それだけを答えた。けれど、その声は自分の耳にも怪しく響く。
刑事が、ふいに鼻を蠢かした。
「葛木さん、煙草を吸うんですね。銘柄は何ですか?」
「そんなこと、何の関係が……」
「現場の近くに、これを落としませんでしたか」
言いかけた言葉を刑事が遮る。
修哉は刑事の手元に視線を動かし、ハッと息を呑んだ。それは、まさしく修哉の愛用しているものと同じ銘柄の吸い殻だった。もちろん、ただの偶然のはずだ。だが、刑事たちは修哉の反応から何かを
修哉は慌てて顔の前で手を振った。
「違います。それは僕のじゃないです。大体、僕は幸町になんて行ってないですし」
「行っていない? おかしいな。あなたが現場から十メートルほど離れた駐車場で、煙草を吸いながらしばらくマンションを見上げていたっていう証言があるんですけどね」
修哉は耳を疑う。
何を言っているのだろう。そんなはずはない。自分は本当に幸町になど行っていないし、その時間にはハッピーライフ・リフォームにいたのだから。
「それで証言があった場所を調べ直してみたら、これが落ちていたわけなんですが」
「僕じゃありません!」
「それを証明できる人はいますか」
修哉は口を開いた。けれど声が喉に詰まる。
何が起きているのかわからなかった。だが、とんでもなく恐ろしい事態になっているということだけはわかる。
冷たい汗が背中を伝い落ちた。
――ハッピーライフ・リフォームにいたと答えれば。
そうすれば、容疑は晴れる。
だが――同時に、これまで必死に隠してきたことがバレてしまう。
「申し訳ありませんが、署まで一度ご同行願えますか」
「そんな、」
修哉は弾かれたように顔を上げた。
――そんな、
自分は何も悪いことはしていない。それなのに、まさか、目撃者がいたというだけで犯人にされてしまうのだろうか。
そう考えたところで、修哉は短く息を呑む。
『あの人は何も悪いことをしていないんです。なのに、このままだとすべてあの人のせいにされてしまう』
ふいに、女性の声が脳裏に蘇った。さらに、彼女が手にしていたのと同じ新聞に書かれていた記事が浮かび上がってくる。
〈マンション火災で2人死傷 幸町〉
背筋を電流のような強い悪寒が走り抜けた。
あの新聞の交通事故について書かれていた記事と同じ面に載っていた記事。そして、現場にいたはずがない自分のことを目撃したと――嘘の証言をしている人間がいるということ。
普通に考えれば、そんな証言をしたところで得をする人間なんているはずがない。そもそも自分が本当にいた場所を答えてしまえば、すぐに容疑は晴れるのだから。
修哉は、強い眩暈に座り込みそうになるのをドアノブをつかんで耐えた。
――だが、得をする人間が一人だけいるのだ。
たとえすぐに容疑が晴れたとしても構わない――いや、むしろそれこそを求めている人間が。
「詳しいお話は、署でおうかがいさせていただきますので」
「違うんです!」
修哉は叫ぶように言った。
『あなたは、自分のためにしか証言できないんですね』
唇がわななく。こめかみが軋む。彼女の言葉の意味が、頭の中で反響する。
修哉は、その場にうなだれ、呆然と唇を開いた。
つづきは文庫版『許されようとは思いません』で。購入はコチラ
著者プロフィール
芦沢央
アシザワ・ヨウ
1984(昭和59)年、東京生れ。千葉大学文学部卒業。2012(平成24)年『罪の余白』で野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。2018年『火のないところに煙は』で静岡書店大賞、2021(令和3)年『神の悪手』でほん夕メ文学賞(たくみ部門)、2022年、同書で将棋ペンクラブ大賞優秀賞(文芸部門)、2023年『夜の道標』で日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)を受賞。ほかの著書に『許されようとは思いません』『汚れた手をそこで拭かない』などがある。


































