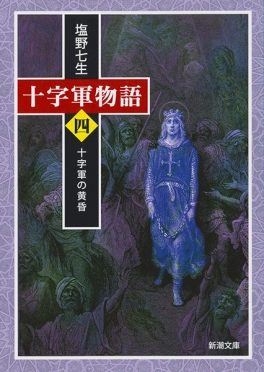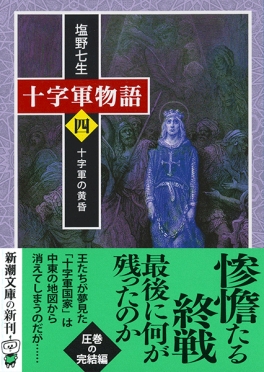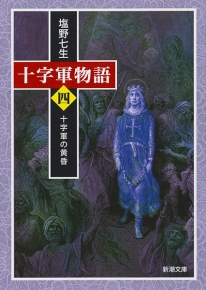
十字軍物語 第四巻―十字軍の黄昏―
737円(税込)
発売日:2019/01/29
- 文庫
- 電子書籍あり
ヨーロッパから陸続と王たち自身が参戦。しかし待ち受けるのは意外な終戦だった……。
「玉座に座った最初の近代人」と呼ばれる神聖ローマ帝国皇帝フリードリッヒ二世の巧みな外交により、イェルサレムではキリスト教徒とイスラム教徒が共存することに。しかしその平和は長続きせず、現代では「聖人」と崇められるフランス王ルイ九世が率いた二度の遠征は惨憺たる結末を迎え……。「神が望んだ戦争」の真の勝者は誰なのか――。『十字軍物語3』を文庫第三巻、第四巻として分冊。
参考文献 図版出典一覧
書誌情報
| 読み仮名 | ジュウジグンモノガタリダイヨンカンジュウジグンノタソガレ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 高橋千裕/カバー装幀、ギュスターヴ・ドレ/カバー装画 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 352ページ |
| ISBN | 978-4-10-118147-9 |
| C-CODE | 0122 |
| 整理番号 | し-12-101 |
| ジャンル | 歴史・時代小説 |
| 定価 | 737円 |
| 電子書籍 価格 | 737円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/07/19 |
書評
はじめに十字軍ありき
十字軍遠征が人類史上稀に見る集団的愚行であったことは、非キリスト教徒の目には明白である。聖地奪還というのだが、「私が信じる宗教の発祥地は私のもの」という論理はあまりに身勝手で、呆れる他はない。百歩譲ってこの論理を認めても、多大の犠牲を払って遠征を行なう合理的理由を見出せないのである。「こんな訳の分からぬ話はない」と、ずっと思っていた。
『十字軍物語』も、遠征の理由探しから始まる。ビザンチンからの救援要請を奇貨としたローマ法王の企みは、分からなくもない。しかし、参加した諸侯は、一体全体何が目的だったのか。「巡礼者が邪魔されていたため、信仰心の篤い諸侯が立ち上がった」というのなら、分かる。しかしそうではなかった。領地獲得という経済的動機もなかった。費用は自分持ちだし、領地への後顧の憂いもあったはずだ。コンスタンチノープルに着けば、邪魔はされるし、忠誠は要求される。「それでもやるのか」と、謎は深まるばかりだ。
で、何が何だかさっぱり分からないまま、第一次十字軍はオリエントの地に攻め入った。そして、十字架とともに快進撃を続け、ついにイェルサレムを奪還。神が与え給うたエネルギーのすごさには、驚くばかり。
第二次十字軍には、フランス王妃エレオノール(アリエノール・ダキテーヌ)がいる。彼女は、夫ルイ七世に同行したというより、自分で軍を編成し、夫を焚き附けたのだ。『冬のライオン』では、「裸同然の姿で乗り込んだので、兵士たちは喜んだ」と自ら語っている。彼女はトロイのヘレン並みの美人だったろうと、私は何の根拠もなしに空想している(本書がその可能性に言及していないのは、大変残念)。
十字軍全史のクライマックスは、イスラムにサラディンが登場し、ライに侵された一三歳の少年王ボードワンが十字軍国家防衛のために超人的な努力をするあたりから始まる。
そしていよいよ、「花の」第三次十字軍がヨーロッパを発ち、リチャード獅子心王とサラディンの激突が始まる。著者も力が入るが、読むほうも大いに力が入る。どこが一番いいかと問われれば、まだ少年だったアル・カミール(後のイスラムの盟主)がリチャードによって「騎士にされちゃった」場面だろう。イスラムを巻き込んでの騎士道物語だ。
全編を通じて著者は、「ダメ男」と「スゴイ男」を明確に対置する。無能男が指導者の椅子に座れば、その周りに無責任男や、甘い汁を吸おうとする者どもが群がる。しかし、他方では、聡明で使命感に燃えた人物が現われる。人望厚く、離散していた人々を固く結束させ、戦場では相手の出方を的確に読んで味方を勝利に導く。拍手大喝采!
指導者に求められる資質は何か? 傑出した能力だけでなく、「あの人になら従いて行く」という人間的魅力が必要だ、と著者は指摘する。そのとおりだ(私は大蔵省というヤクザ組織にいたことがあるので、このことが本当によく分かる)。このところ日本の政治指導者に凡庸な人しかいないのは、イタリアからでもお分かりでしょうが、塩野先生。人材枯渇は政治の世界だけではない。どの組織にも、ジャーナリストにも学者にも、「普通の人」しかいなくなってしまったのですよ。サラディン様やリチャード様には及びもないが、せめてボードワンやイベリン級は出てこないのか? 嗚呼!
もっとも、十字軍も最後はダメ男だらけになった。ルイ九世の、聞くだけでゲンナリする無残な敗けいくさで、十字軍の歴史は幕を閉じた。
こうして、蛮勇に始まり愚挙に終わった十字軍だが、いったい何をヨーロッパに残したのか? ギボンは、「十字軍にかけたエネルギーを他に向けたら、ヨーロッパはもっと発展していただろう」と言う。当然至極の意見だ。しかし、私は百パーセントは賛成できない。
まず何よりも、十字軍は、強い魔力を放射し、多くの英雄物語を生んだ。キリスト教徒にとって「十字軍」という言葉がいかに魔術的魅力に満ちていたかは、クラシックバレエの名作「ライモンダ」を見れば分かる。主人公ジャン・ド・ブリエンヌが雄々しく出征する様を婚約者ライモンダが見守る場面は、何度見ても(DVDで、ですが)涙が出る。ところが、塩野女史によれば、この男は「どうにも冴えない」老人で(何たる幻滅!)、彼が率いた第五次十字軍は「御当地十字軍」と呼ばれてしまう始末(あんまりだ!)。それが史実だったとしても(史実なのだろうが)、人々はそれには目をつぶり、凜々しいヒーローを想像するのである。
いや、バレエだけではない。十字軍は、イタリア海洋都市ヴェネツィア、ジェノヴァ、ピサに空前の繁栄をもたらした。これが本書の強調する点だ。海上力とは、輸送力だけでなく軍事力でもあった。いまで言えば、産軍複合体である。リチャードの行軍が都市国家艦隊との共同作戦だったことを、本書で初めて知った。十字軍を「支えた」というよりは、「利用した」というべきだろう。都市国家が戦争で蓄積した富が、ルネッサンスを生みだしたのである。
ところで、これらの「逆命題」は真だろうか? 私は、つぎの仮説を提起したい。すなわち、仮に十字軍がなかったとしたら、海洋都市国家は発展しえなかった。また、仮にこれらの経済的繁栄がなかったら、ルネッサンスはなかった。
さらに進んで、つぎの(大胆すぎる)仮説はどうだろう? ポルトガルとスペインによる大航海は、イタリア都市国家の衰退をもたらすことになるのだが、仮にそれらの都市がなかったら、胡椒貿易もなく、したがって大航海もなかった。
以上の仮説がすべて正しければ、十字軍の蛮勇と熱狂こそが(そして、それのみが)、現代まで続くヨーロッパの世界支配の源だということになる! 「遠征を合理的に説明できるかどうか」などは、どうでもよいことなのだ。
「十字軍がヨーロッパにもたらしたのは、アンズだけだ」と言う研究者がいる。とんでもない。十字軍はヨーロッパにルネッサンスと新大陸をもたらしたのだ。ツヴァイクは、名作『マゼラン』を、「はじめに胡椒ありき」と書き起こした。しかし、胡椒が始まりではなかった。その前に十字軍があったのだ。だから、大航海の歴史は、「はじめに十字軍ありき」と書き直さなければならない。
こうした仮説を、専門の歴史家は取り上げない。現実でなかったことを仮定しても、論文にならないからだ。大学のチェア獲得のためには、「沃野にあって枯草を食わなければ」(空想でなく論文を書かなければ)ならない。上のような勝手な想像ができるのは、キリスト教徒でなく専門の歴史研究者でもない者の特権である。塩野氏はその一人だと明言しているが、もちろん私も特権享受者である。本書に刺激されて、久々に世界史的空想の羽根を広げることが出来た。
インタビュー/対談/エッセイ

塩野七生 読者との対話
中世最大の「事件」というべき十字軍戦争。二百年にもおよぶ、イスラム教とキリスト教の血みどろの闘争史を描いた日本ではじめての通史『十字軍物語』を書いた塩野七生さん。その文庫化を記念し、神楽坂ラカグで2018年12月に行われた読者との対話をここに再現する。
塩野 十六歳の時に図書館でホメロスの「イーリアス」を読んで以来、地中海世界に魅了されました。それからはお見合いの話が出る度に「あの辺りに駐在する人なら誰でもいい」なんて答えるくらい(笑)。二十六歳の頃に当時のフィアンセと「一年だけ」という約束を交わしてイタリアに渡りましたが、彼は心配になったのか、三ヶ月もしないうちに「イタリアに行って連れて帰る」と言い出すものだから、「約束とちがう」と答えたら、彼は怒って別の人と結婚してしまったので、日本に帰る理由がなくなってしまったんです。その後偶然に、これから中央公論の編集長になるんだという人と出会って、「“ルネサンスの女たち”という題をあげるから、何か書いてみなさい」と言われて、予期せず作家になってしまってから、もう半世紀が過ぎました。つまり私がこうして五十年もの間、地中海のことを書き続けているのは偶然の産物なんですね。何でこんなに続いたのか自分でもわからないのですが、お答えできることは何でもお答えしますので、どうぞ聞いて下さい。
読者A 私はやっぱり『ローマ人の物語』が一番好きです。読んでいた頃は皇帝の名前を順に言えました。
読者B 大学生のとき、書店で『ローマ人の物語』の紫色のきれいなカバーの文庫本を読んだのが、はじめの出会いでした。それまで西洋の歴史には無知でしたが、古代ローマやその人物たちに触れ、ものの考え方や人としてのあり方まで勉強になりました。
読者C 西洋社会の基盤である古代ローマ史を身近に知り、歴史や政治、経済はもとより人間とは何か、深く考えることができました。
物語を忘れて書かれた歴史が面白いはずがない
塩野 私は不真面目な学生だったので、「教え説かれる」というのがひどく嫌いだったのね。だからそういうものは書きたくないし、読者にも私と一緒に考えてもらいたいと思っています。学者たちと作家である私と、題材について勉強する過程はまったく同じです。何がちがうかというと、学者たちは自分の知っていることを書きますが、私は自分が「知りたい」と思うことを書くということ。知っていることを書くだけでは「教え説く」になってしまいますが、私は読者と一緒に考えながら書いているのです。だから原稿を書く時でも「きっと読者はここで地図を見たくなるだろう」と思えば、原稿用紙の隅に「要・地図」とメモします。私はいわば「アマチュア」なんですね。
それからもうひとつ。私は人間を「減点方式」で見るということがありません。「この人のいいところはどこだろう」と考えながら書きます。そして書くからには、絶対にその人間を愛します。といってそれは美点だけを愛するという類の愛ではありません。
そしてその愛した人間を描き、完全に生かし切ろうと思うならば、その人間がどういう社会に生きていたか、どういう人間と会っていたか、どういう男たちに信頼されていたか、どういう男たちに裏切られたのか――そういうことをすべて描くことになります。周囲の人間もすべて描く。イタリア人とのハーフであるわが息子は「ママ、『ローマ人の物語』は“オペラ・コラーレ”だね」というんです。つまりオペラ合唱曲。ギリシャ悲劇でも「コロス」といって、合唱隊が重要な役割を果たしますが、私の書くものは合唱曲なのです。
『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』という作品を書きましたが、「この男はあまりに近代的で、中世を代表させるのはいかがなものか」と批判されました。でも私は中世という社会、中世という時代と衝突し続けたフリードリッヒという男を書くことで、中世が描けると思ったのです。中世という、大きな合唱曲が書けるはずだと。
私の作品は『ローマ人の物語』をはじめとして、すべて「物語」です。『ローマ人の歴史』というタイトルにすると学者たちが怒り出すと思いますが、歴史はやっぱり「物語」なんです。物語であることを忘れて書かれた歴史は、面白いはずがない。
「鷹の目」と「虫の目」
読者D 私はやはり『ユリウス・カエサル ルビコン以前』と『ユリウス・カエサル ルビコン以後』が好きです。カエサルはのちのヨーロッパのグランド・デザインを考え、
読者E 私は『ハンニバル戦記』が好きでした。塩野さんは戦争を書いていると筆が「乗る」ようですが、どうしてでしょう。
塩野 戦争は自分ではできないものですからね(笑)。
カエサルもハンニバルも戦争に強かった。しかしローマ史にはそうでなかった人物もいます。アウグストゥスがそうです。カエサルはそれを見抜いていたから、アウグストゥスに右腕としてアグリッパを据えた。「哲人皇帝」マルクス・アウレリウスも同じ。トライアヌスが二年でケリをつけたドナウ河の最前線に、十年もかかずらってしまった。人にはさまざま得手不得手というものがあるものなんです。戦争というのはやはり即断即決ですから。これが戦争巧者の特徴。
それにもう一つ。日本では「鳥瞰図」という言葉がありますね。鳥が上空から見たような図のことをそう呼びます。鳥なんていうと「ぴよぴよ」という感じですが、イタリアでは「鷹の視点」と言って、こちらの方が雰囲気が出ますね。戦争巧者はこの空から見た視点と、地べたから見た虫の視点「虫瞰」の両方を持っています。カエサルもアレキサンダーもそうでした。
こういうことはわれわれのようなごく普通の人間にも少しだけ意識して真似ることができるのではないかと私は思っています。足元から判断するのと同時に「鷹の視点」も同時に意識すると、ちがったものが見えてくると思いませんか。
読者F 私はあれだけの権勢を誇ったローマが滅びた理由に興味があって、現代日本人はこの歴史を踏まえ、いかに滅亡を先延ばしにできるか考えたいと思っています。
読者G ローマ帝国はローマ人がローマ人たりうる性質がいつの間にか失われていって、それで瓦解したのだとお書きでしたが、日本はどのようにして滅びると思いますか? 現代の日本を見てみると、自動車や免震装置の品質偽装であったり、詭弁がまかり通る政治や進まない財政再建、モラルハザードを起こして破綻しかかっている健康保険をはじめとする社会保障であったり、国民の勤勉さ、誠実さなど、これまでの日本人らしさが失われているように感じています。
塩野 私たちがいまニュースなどで見て、「困ったことになっちゃったな」と思うことはすべて、「平和の代償」なのです。わが日本は七十年間、戦争をしていません。戦争というものは言うまでもなく悪ですが、ひとつだけ利点があるのです。それは人々の願望が二つのことに集約されることです。一つは自分と家族の安全、そして食――明日食べるものがあるのか――この二つです。しかし長い平和の時代を過ごしてきて、われわれの願望が分散してきたのです。今風にいえば多様化している。簡単にいえば私たちは欲深くなっているのです。勤勉さが失われている理由はそういうことだと思います。

でも免震装置の偽装で誰か人が死んだでしょうか? 私たちがいま大したことではないことに一喜一憂するのは当然ですよ。明日にも自分や家族の身の安全や食が奪われるような「大したこと」がないのだから。だから私たちはこの七十年の間に、得たものと失ったものをよく認識して、少しずつ微修正していくしかない。私はそう考えています。
私は古代ローマ帝国とヴェネツィア共和国の通史を書きました。どちらも一千年続いた国ですが、一体なんでそんなに長命だったのか。それはどちらも「高度成長時代」の後にやってくる「安定時代」を続けることに腐心した国だからです。「高度成長時代」というのはどんな国にもやってきます。日本にもありましたし、中国が今そうかもしれない。しかし今のわれわれにとって重要なのは中国を真似することではないんですね。あまり小さなことにこだわらず、複眼的な視野を持つことが大切だと思います。ローマとヴェネツィアを書いた私が感じることは、そういうことです。
一神教と多神教
読者H 高校一年生の時に『コンスタンティノープルの陥落』を読みました。異なる宗教、民族の対立がスリリングに、甘美に描かれていて、塩野さんの作品にハマるきっかけとなりました。私が塩野さんの作品が好きな理由は、そのリアリズムです。描かれている当時の風俗や情景だけでなく、人間の心の奥まで覗いているような表現が大好きです。
読者I 私もイスタンブールに旅行した後に読みましたが、行く前に読んでおけば良かったと後悔しました。シュテファン・ツヴァイクの『人類の星の時間』よりもオスマン帝国がよく描けていて、立体的に理解できました。塩野さんは本当のところキリスト教というものに対してどうお考えですか? 果たしてキリスト教は人類に善きものをもたらしたのか、それとも災厄の方が大きかったのか、率直なお答えをいただければ。
塩野 私は第一に宗教というものは基本的に「個人的なもの」だと思っています。ところが厄介なことに「みんなで祈ると気持ちよくなる」という性向もある。一神教はとくにその性質が強い。これがまず問題です。
そして多神教と一神教のちがいは「神の数のちがい」ではありません。カエサル家の守護神はヴェヌス、つまりビーナス。アウグストゥスの守護神はアポロン。多神教だからといって、すべての神を愛する必要はありません。信じる神は一つでも構わないんです。それがローマの多神教です。ローマが版図を広げるに従って、ローマの街角にはカルタゴとかガリアとかの神様の像がゴロゴロ並ぶようになりました。ある民族を征服して、彼らもローマ人に同化してしまうと、彼らの信じる神様もまた取り込んでしまうのです。取り込むといっても、信じるわけではない。彼らが大切に思っているわけだから、それを尊重するという姿勢。しかし一神教はそうではありません。尊重しないし、認めないのです。それが多神教と一神教のちがいなのです。

ローマの多神教にはコーランとか聖書のような経典のようなものもない。経典がなければそれを解釈する必要もないから、専業の聖職者も不要。祭儀だって皇帝が普段から着ているトーガを頭から被って執り行って、それでおしまいです。
われわれ日本人が信じるのもやはり多神教の神だろうと思います。本質的に、本来的に多神教なのです。神戸にはユダヤ教徒のためのシナゴーグやイスラム教徒のためのモスク、それにキリスト教の教会もある。われわれはそれを許容するわけです。
寛容さというのは、何も強者が弱者に与えるものではありません。英語ならばトレランス(tolerance)という言葉がありますが、「他者の存在を我慢して耐えてあげよう」という意味合いがある。しかし本来の寛容というものはそういうものではありません。ラテン語のクレメンツィアを語源にしたクレメント(clement)の「相手の存在を認める」というものです。相手の信じる神が鰯の頭でもお稲荷さんでも、それが彼にとって大切なものなのであれば尊重しよう、それが寛容というものです。
たったそれだけのことなのですが、これはわが日本人が世界に対して堂々と主張していい美点です。もうかつてのローマ人もギリシア人もこの現代にはいないので、堂々と多神教徒であるのは、今はわれわれ日本人くらいなのです。
ところが一神教の側は相変わらず寛容ではないんですね。キリスト教の聖書を読んでみて下さい。イエスは「われらの神の前では誰もが平等である」と言っています。一応カトリック教徒であるわが息子に「イエスの言う通りならば、ママとあなたは平等ではないのよ」と私は言っています。イスラムの場合も同様です。他宗教の人間は平等どころか奴隷にすることも可能なのです。イスラム国が他の宗教を信じる人々を奴隷にしていたのはみなさんもご存知でしょう。
奴隷制というのは何も古代のものではありません。中世にもずっとあった。奴隷制がまずいということになったのは、ようやく十九世紀に入ってからですね。それまでは同じ宗教を信じている人間は奴隷にできなくとも、そうでない人間ならば奴隷にできた。
一神教徒である彼らとわれわれ日本人とでは文化がちがうのだから、彼らのやりかたを尊重して、「野蛮だ」と批判するのは控えるべきでしょうか? でも時にはわれわれ日本人もはっきり言うべきなのです。キリスト教もイスラム教も、別の宗教を信じる人間とは平等ではない、奴隷にしても構わないという部分を、なぜ経典から削らないのか、残したままなのは一体なぜなのか、と。
ちなみに『十字軍物語』ではイスラム世界の盟主となったサラディンをかなりしっかり書きましたが、それは彼が素敵な男だから(笑)。素敵な男というのは宗教に関係なく現れるものです。
十字軍戦争の「勝者」は誰か
読者J 私がはじめて読んだのは『十字軍物語』でしたが、ヨーロッパの歴史とそこにある人間ドラマを身近に感じられて、遠く知らない世界を感じられました。
読者K サラディン、リチャード一世、フリードリッヒ二世と魅力的な主人公が次々に登場して、テンプル騎士団が最後まで戦い抜く。でも戦うだけではなくて、キリスト教徒もイスラム教徒も、それぞれの生活のどこかで共生していたということが、現代の状況から考えると切なく感じられました。十字軍遠征が「聖戦」だからこそ物語になりますが、現代の自爆テロはまったく異なるものではないかと感じています。十字軍が終わってから七百年以上が経って、「聖戦」からかけ離れた戦いだけが残っていると感じます。それでもイスラムの若者は命をかけることができても、西欧の若者はそこまではできない……。七百年の間に宗教に対する熱さが変わってしまったのでしょうか? ピュアさが恐ろしくもあり、羨ましくもあると思っているのですが。
塩野 『ローマ亡き後の地中海世界』では、北アフリカのイスラム世界と南ヨーロッパの都市国家のキリスト教世界の間で戦争が起こるわけです。イタリア海軍というのは北アフリカからやってくる海賊に対応するためにできたようなものです。でも一方では彼らはビジネスもしていた。ヨーロッパの側は武具とか繊維とかの手工業製品を輸出していました。北アフリカのイスラム勢力はサハラ砂漠の向こうから運んでくる黄金をヨーロッパ人に売っていた。
黄金というのは現代の石油と同じではないかと私は思います。どちらも掘れば出てくるものです。それほど多くの人間やノウハウを必要としない。だから雇用も生まない。ところが手工業製品というのは分業になっていますから、さまざまなノウハウを持った人間が関わります。しかし中世にあってもヨーロッパの側は人々に職を与えることに成功していた。同じ時代のイスラム世界はそうではなかったんです。現代のトヨタと中東の油田では、どちらが人々に安定した職を保障するかを考えればそのちがいがおわかりでしょう。
私は古代ローマを書いていた頃に何度かチュニジアにいって、現地のイタリア大使館に紹介してもらった大学教授と一緒に街を周ったのですが、彼は三人兄弟の真ん中でした。彼を大学に進ませるために、彼の兄は軍隊に入り、弟は官吏になったそうです。つまりどちらも公務員。彼の家庭は決して貧しい家庭ではなかった。ごく普通の市民ですが、そういう家庭の子女が就く職が公務員のほかにない。お隣のリビアもエジプトもまったく同じで、民間の経済が弱い。そうするとどうなるか。若者たちが宗教に向かうのです。だから宗教に熱情をもった若者が存在するんです。

『十字軍物語』を読んでいただければわかりますが、十字軍戦争に勝ったのはイスラムの側です。しかし、負けた側のヨーロッパではルネサンスが起こり、大航海時代を迎えた。どちらも職をもった市民なくして起こり得なかったものです。
ルネサンスの出発点は、職をもって豊かになった市民たちが、自分たちの生き方に疑問を持ったことです。われわれの生きる指針はキリスト教だけでいいのか、キリスト教以前の世界とはどういうものだったのかという疑問を持ったのです。キリスト教の側は十字軍戦争に負けた後、キリスト教を疑った。そしてヨーロッパの大学では十字軍が終わる前後に、イスラム研究が盛んになります。負けたという事実を冷徹に見つめ、勝った側のことを研究した。ですから十字軍戦争の真の勝者がイスラム側だったとは、簡単には言えないのです。
職というのはことほどさように重要なのです。補助とか援助をすることは簡単です。しかし、職を作るのは簡単ではない。職さえあれば、社会にひどい格差が生まれることはありませんし、格差が固定することもない。安定成長も職なくしてはありえません。
読者L 『ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力』を書き終えて、長編はもうこれでお仕舞いとおっしゃっていました。これからのことを聞かせて下さい。
塩野 いい男はみんな書いちゃったからなあ……。もしかすると短いものは書くかもしれませんが、これから何をするかははっきり決めていません。2018年は何も書きませんでした。おかげで色々な本を読み、音楽を聞くことができました。いいですね、何もしないというのは。出版社がどう考えているかわかりませんが(笑)。でも、何もしないのにも、ちょっと飽きてきちゃったところです。(了)
(しおの・ななみ 作家)
波 2019年2月号より
著者プロフィール
塩野七生
シオノ・ナナミ
1937年7月7日、東京生れ。学習院大学文学部哲学科卒業後、イタリアに遊学。1968年に執筆活動を開始し、「ルネサンスの女たち」を「中央公論」誌に発表。初めての書下ろし長編『チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷』により1970年度毎日出版文化賞を受賞。この年からイタリアに住む。1982年、『海の都の物語』によりサントリー学芸賞。1983年、菊池寛賞。1992年より、ローマ帝国興亡の歴史を描く「ローマ人の物語」にとりくむ(2006 年に完結)。1993年、『ローマ人の物語I』により新潮学芸賞。1999年、司馬遼太郎賞。2002年、イタリア政府より国家功労勲章を授与される。2007年、文化功労者に選ばれる。2008ー2009年、『ローマ亡き後の地中海世界』(上・下)を刊行。2011年、「十字軍物語」シリーズ全4冊完結。2013年、『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』(上・下)を刊行。2017年、「ギリシア人の物語」シリーズ全3巻を完結させた。