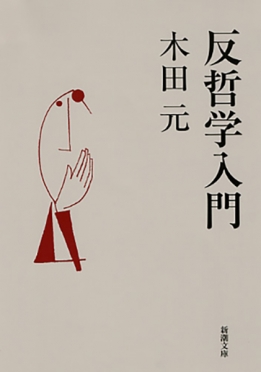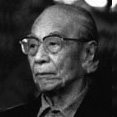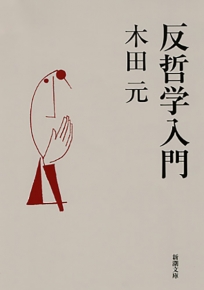
反哲学入門
693円(税込)
発売日:2010/05/28
- 文庫
哲学はわからなくて当たり前! 記念碑的名著、待望の文庫化。
「形而上学」「私は考える、ゆえに私は存在する」「超越論的主観性」──。哲学のこんな用語を見せられると、われわれは初めから、とても理解できそうにもないと諦めてしまう。だが本書は、プラトンに始まる西洋哲学の流れと、それを断ち切ることによって出現してきたニーチェ以降の反哲学の動きを区別し、その本領を平明に解き明かしてみせる。現代の思想状況をも俯瞰した名著。
〈もともと「哲学」という言葉自体が、西周による明らかな誤訳なんです〉
〈哲学の根本問題は、「存在とはなにか」を問うことだ〉
〈ソクラテスは極めつきの皮肉屋、というぐらいに考えておいた方がいい〉
〈プラトンは自分の思想、つまり「つくる」論理の芯になるものを見つけた〉
〈プラトン主義とアリストテレス主義とは覇権の交替を繰りかえしていた〉
〈学生時代も教師になってからもわたしはデカルトが苦手でした〉
〈近代の哲学書の文体はカントのあたりで大きく変わります〉
〈ヘーゲルは世界史を、人間にとっての自由の拡大の道程と――〉
〈ニヒリズムはプラトン以来すでにはじまっていたことになります〉
〈肉体を手引きとする新たな世界解釈をニーチェは提唱しようとしている〉
〈『存在と時間』は未完成の書であり、肝腎の本論をふくむ下巻が出されないでしまった〉
〈世界史を領導するような一つの民族がその生き方を変えるということになれば〉
解説 三浦雅士
書誌情報
| 読み仮名 | ハンテツガクニュウモン |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 発行形態 | 文庫 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 304ページ |
| ISBN | 978-4-10-132081-6 |
| C-CODE | 0195 |
| 整理番号 | き-33-1 |
| ジャンル | 哲学・思想、思想・社会 |
| 定価 | 693円 |
書評
いつか再読する日のために
いつか再読する日のために、大切に本棚に仕舞っている本がある。誰しもそんな本があるだろうか。今回その中から三冊を選び再読したので紹介したい。
僕に再読の喜びを教えてくれたのは大学時代のサークルの先輩だった。なぜか後輩にも敬語を使うその人は、暇を持て余した落研の部室でこう言った。「良い本を読むと良い心持ちになるじゃないですか。またあんな心持ちになりたいと思って、時間が経ってからもう一度読むんですよ」。聞いた時、「心持ち」という言葉がなんだか良いなと僕は思った。
宮部みゆき『本所深川ふしぎ草紙』は江戸の義理人情を描いた時代小説集だ。第三話「置いてけ堀」の中でその「心持ち」という言葉が出てくる。やや古風なこの表現は時代小説だからこそ自然に使われていた。
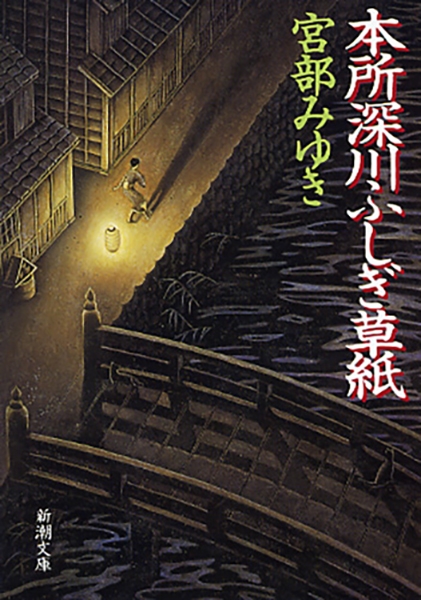
――いっそ、庄太のあとを追ってしまおうかという心持ちが、冷たい水のように身体にしみてくる。
亭主を亡くした若い女房が寂しさを募らせる場面である。置いてけ堀に現れる岸涯小僧が、もしかしたら死んだ亭主が化けた姿なのではないかと疑うところから、物語は進んでいく。
本所七不思議を題材にした七つのお話は、どれもこれも味わいある人情話に仕上がっている。不思議な出来事が起き、それにつられて人の心が動くのだが、提示された謎はスッキリ解決したり余韻という形で残ったり。暮らしの中の悲しみも苦しみも、叶わない切ない思いも描かれているのに読後感がたまらなく良く、もう一度この「心持ち」を味わえたことが嬉しい。
保坂和志『ハレルヤ』を再読して驚いたことがある。もともと大好きな小説家で、すべての著作が本棚に並んでいるのだが、表題作「ハレルヤ」を初読の際、身体を射抜かれたような心持ちになったはずの一行が、再読時どこにも見当たらなかった。どうしてそんなことが起きるのか。もしかしたら誤読や間違った記憶すらも読書の楽しみであり、また再読の喜びなのかもしれない。
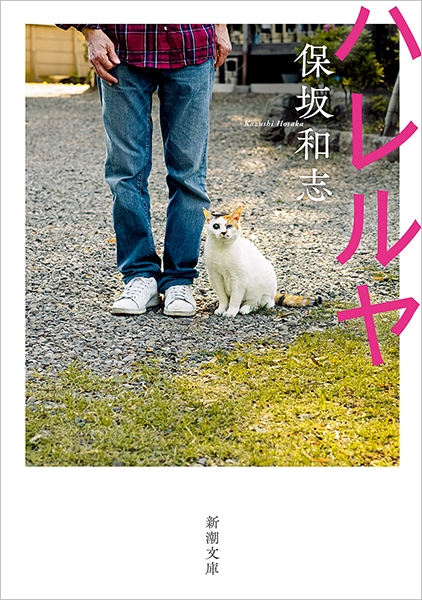
「生きる歓び」には、十八年前、谷中の墓地で偶然拾った子猫の花ちゃんのことが描かれている。花ちゃんは「生きる歓び」をその全身で表現した。片方の目が開かず、自分で餌を食べる力のない状態の花ちゃんを拾った「私」は、薬を飲ませ餌を食べさせた翌日の夕方に見違えるほど元気になった花ちゃんの様子を見て、その生きようとする力に驚く。
――「生きている歓び」とか「生きている苦しみ」という言い方があるけれど、「生きることが歓び」なのだ。
それから花ちゃんは「私」の家族になり、十八年八カ月の歳月を生きた。「ハレルヤ」では花ちゃんが旅立つ日が描かれていて、最後の花ちゃんの様子と「私」の心の中が小説になっている。
これはただの喪失を描いた物語ではない。単に命の重さを問う物語でもない。そもそも物語ですらもなく、僕はこの小説を通じて世界や人間や時間や記憶や存在について考えさせられた。きっと読了後、自分が忘れたり仕舞い込んでいた大切な何かを思い出すことになると思う。そんな小説だ。
木田元『反哲学入門』を再読した理由は、初読の時によく分からなかったからだ。再読の喜びには、あの頃「分からなかったことが分かるようになる」ことが含まれる。
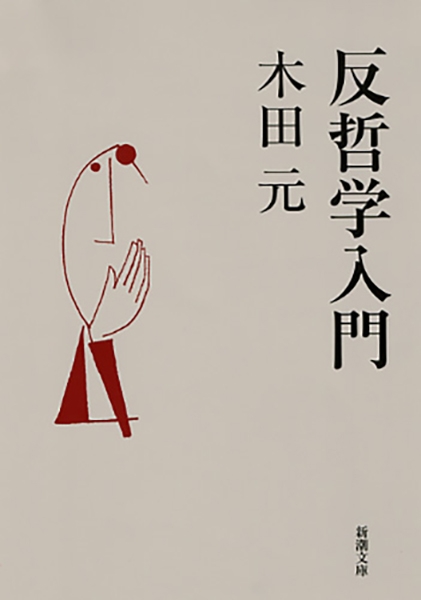
哲学史をニーチェ以前と以後に分け、以後を「反哲学」とする著者の試みは、今回とんでもなく面白く読めた。様々な哲学者たちの思索が解説されているのだが、「なぜ彼がそう考えるに至ったか」が著者の憶測も交えて細かく書かれており、そのことに初読時点では気づかなかった。
――インセスト・タブーに対するこうした反撥が心理的動機として働いて、ニーチェは西洋の文化形成の総体を批判的に見るような壮大な歴史的視野を開きえたのではないかと思っています。
哲学者というどこか遠くに感じる存在を著者が手ほどきしてくれる本であり、考えることの喜びを味わえる名著だ。
今回、再読した三冊を僕はまた本棚に大切に戻した。再再読の日が来たら、今度はどんな「心持ち」になれるだろうか。
(なつのかも 落語作家)
波 2024年2月号より
著者プロフィール
木田元
キダ・ゲン
1928(昭和3)年生れ。山形県出身。哲学者。東北大学文学部哲学科卒。中央大学名誉教授。マルティン・ハイデガー、エドムント・フッサール、モーリス・メルロ=ポンティなどの現代西洋哲学者の主要著作を分かりやすい日本語に翻訳したことで知られる。終戦直後、闇屋で暮らしを立てていたエピソードも有名。主な著書に、『現象学』『反哲学史』『現代の哲学』『ハイデガーの思想』『メルロ=ポンティの思想』『闇屋になりそこねた哲学者』『ピアノを弾くニーチェ』『哲学は人生の役に立つのか』などがある。