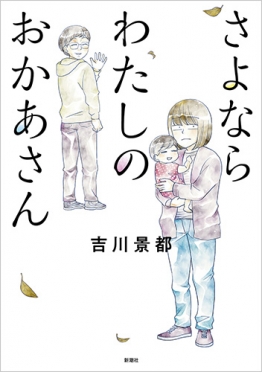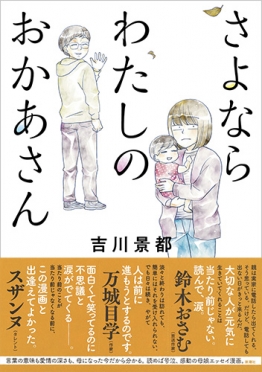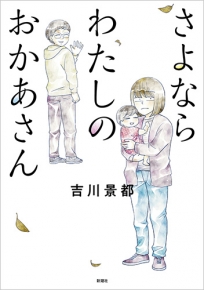
さよならわたしのおかあさん
1,100円(税込)
発売日:2018/11/30
- 書籍
- 電子書籍あり
言葉の意味も愛情の深さも、母になった今だからこそ分かる。涙腺崩壊の母娘エッセイ漫画。
亡くなるその日まで、おかあさんが死ぬなんて信じなかった。成長するたびに喜んでくれた、優しい笑顔。何度も私を笑わせた、親父ギャグみたいな冗談。がんの辛さと孤独を決して表に出さなかった、その強さ。おかあさんがくれた全てに、私は何を返せるんだろう――。連載時からSNSで話題沸騰のエッセイ漫画、待望の単行本化。
そういう風に育ててある
おかあさんだけは大丈夫
かわってあげたい
いつだってどこへだって行けたのに
ホスピスへの入院
最初で最後の弱音
想像できなかった「その日」
もうどこにもいない
さよならわたしのおかあさん
あとがき
書誌情報
| 読み仮名 | サヨナラワタシノオカアサン |
|---|---|
| 装幀 | 竹内亮輔+遠藤智美[crazy force]/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | コミックバンチwebから生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | A5判 |
| 頁数 | 144ページ |
| ISBN | 978-4-10-352171-6 |
| C-CODE | 0079 |
| ジャンル | エッセー・随筆、エッセー・随筆、コミック、コミック |
| 定価 | 1,100円 |
| 電子書籍 価格 | 1,100円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2018/11/30 |
書評
「当たり前」な今、だからこそ
普段あまり漫画は読みませんが、この作品はすごく読みやすくて、あっという間に読んでしまいました。息子を寝かしつけた後、ベッドで何気なく読み始めたら涙が止まらなくなって、リビングにティッシュを取りに起きたくらい感動しちゃって。涙の理由はいくつかあると思うのですが、肝臓がんと闘い亡くなってしまう吉川さんの「おかあさん」の姿に、祖母や母を重ねながら読んだから、というのが特に大きな理由かもしれません。
とはいっても、私の祖母も母もまだまだとても元気。祖母は八十五歳なのでそれなりに老いてはきていますが、一昨年までは仕事をしていたくらい活動的ですし、母もまだバリバリ仕事をしています。なので、悲しい涙ではありません。
吉川さんが漫画の中で描かれているように、私も、子供を育てるようになって、驚くようなことがたくさんありました。例えば子守歌。〈子どもを産んでみたら自分が歌えるんで驚いた〉というのはまさにそう。習ったわけでもないのに自然と口から出てくるそれは、母から私に受け継がれたもので、私たち娘にはそんな宝物のような思い出が溢れているのだ――と気がつかせてくれました。日常生活でも、子供と接している時にふと、自分と母や祖母の姿が重なることがあり、「ああ、愛してくれていたんだな」と、想像しながら感謝することも増えていて……。子供が生まれてますます母との距離が近づいた実感があるので、吉川さんが子供時代を振り返りながら「おかあさん」を想い、そして我が子を想う気持ちにとても強く共感したんだと思います。
三年前に離婚してから故郷熊本に住んでいるのですが、徒歩五分圏内に、母、祖父母、妹一家がいるので日々助けてもらっています。母自身も私が二歳くらいの時に離婚してからは、昼も夜も仕事をしながら私と妹を育ててくれました。母がとても忙しかったので、小・中学生の頃は平日は祖母の家で過ごしたのですが、土日に朝から晩まで全力で遊んでくれたので、不思議と寂しい気持ちはありませんでした。祖父母との関係も深まったし、色々な人にお世話され助けてもらって育ったことは、今の私の財産でもあります。
「財産」と言えば、吉川さんの「おかあさん」が落ち込む吉川さんに、「あんたなら大丈夫、そういう風に育ててあるから」と励ます場面は特に印象に残りました。素晴らしい言葉ですよね。私も、母と祖母からもらった「言葉」をいまも大事な指針にしていて、母からは「笑顔・愛嬌・挨拶を大切に」と、祖母からは「出されたものは全部食べる」と言われ続け、それは今の仕事にも大いに役に立っていると感じます。

でも息子は一月で五歳になるのですが、まだまだ甘えん坊。幼稚園のお友達と比べても幼くて、私がいる時は食べさせてもらえるまで自分からは食事をしないこともあります。恥ずかしがりやで偏食で、どうしたら母や祖母のようにできるのだろう……というのは今のちょっとした悩みです(笑)。
週に一度はランチしたりお裾分けをし合ったりと、今は母とも頻繁に会えますし、元気な姿からは「弱っていく姿」を想像できないですが、もし今急に母に何かあったら、絶対に後悔するでしょう。〈行けばよかったんだ〉と「おかあさん」が行きたがっていた場所に行けなかったことを吉川さんは後悔していますが、私も、家族旅行を先延ばしにしちゃっていて。無理やりでもスケジュールを合わせて、みんなで出かけられる機会を作ったり、もっと頻繁にみんなで集まりたいなとも思いました。それがきっと、「いつか必ずくるその日」のための、心の準備にもつながるような気がします。
「おかあさん」、吉川さん、娘さんとが重なり合う最終話の見開きの絵は本当に素敵なシーン。死は終わりなのではなくて、次の世代への繋がりでもあることを感じさせてくれました。
当たり前のことが当たり前じゃなくなる前に、この漫画と出逢えて本当によかったです。
(スザンヌ タレント)
波 2019年1月号より
単行本刊行時掲載
受け継がれていく「愛のバトン」
おかあさん、と呼ぶ人が私にはいなかった。
就学前に家を出た母が正式に父と離婚したのは、私が小学六年生のころだったか。そこに至るまで、子どもだった私の目から見ても様々なことがありすぎて(主に母のことで)、そのことはこんなに大人になった今でも、私の中で消化できていないし、きっと消化できることはないのだとどこかで諦めてもいる。
母が家を出るまでの記憶で、残っていることはほとんどない。おかあさん、と呼んでその胸に飛び込んだこともあっただろうに、おかあさん、と呼んで
おかあさん、と呼ぶ人がいなかったことはずっとずっと私の“傷”だった。いや、だった、ではなくて、今でもそれは古傷のようにある。若かったころは、かさぶたになりかけたその傷をわざわざ自分で剥がしては、じゅくじゅくと流れるその血を見たりした。癒えない傷がある、というのは、どこかで私の免罪符だった。人間関係がうまくいかないことも、恋人と別れたことも、全部その傷のせいにできた。私にはおかあさんがいなかったから、どこか人格形成に問題があるのはしょうがない、と開き直ることでしか立ち直ることができなかった。
傷は傷のまま消えないけれど、でもそれは私という人間を損なうものではない。私を損なっているのは私自身で、母とのことは関係ない。そんな当たり前のことに気付くのに、どれだけの時間がかかったことか。そのことに気付いてから、「母娘」がテーマの物語の読み方が変わった気がする。それまでは、自分にとって「母娘もの」はある意味で鬼門だった。過度に感情移入しないように意識して読んでいたため、読み終わると不必要にぐったりしていたのだ。馬鹿じゃなかろうか、と今では思えるけれど、その時はそういうふうにしかできなかった。
今では「毒親」という言葉も認知され、親子関係には呪縛という側面があることも知られているし、親子だから必ずしも仲睦まじくあらねばならないわけではない、という認識も広まってきている。その家、その家ごとのベストな家族、というものはあっても、「理想の家族」などというものはない。ベストな家族、と書いてしまったが、何がベストなのか、もまた、その家族次第なのだ。
本書は漫画家である吉川景都さんのエッセイ漫画だが、吉川さんの家族は、間違いなくベストな家族だ、と思う。末期癌である吉川さんの「おかあさん」の闘病とその旅立ちまでを描いたものなのだが、この「おかあさん」が本当に本当に素晴らしい。余命を限られた日々の中で、吉川さんの思い出に残る「おかあさん」はいつも笑顔なのだ。子育ての真っ最中でもある吉川さんは、自分の育児の日々を通して、「おかあさん」が自分にしてくれたことに、一つ、また一つと気付いていく。
胸が詰まってしまったのは、「おかあさん」が吉川さんにことあるごとにかけていた言葉を読んだ時だ。打たれ弱くて泣き虫な吉川さんは、何かあると「おかあさん」に泣きつくのだが、その都度、「おかあさん」は大丈夫、乗り越えられる、と励まし、最後にこう言うのだ。「そういう風に育ててあるから」と。「そういう風に育ててある」、なんて優しくて慈しみに満ちた呪文であることか。「おかあさん」の命の砂時計は思いがけず早くに落ちてしまうことになったけれど、「おかあさん」は吉川さんの中にずっとある。
本書は「母娘もの」の体裁をとってはいるが、テーマはもっと普遍的なものだ。それは、母から娘へ、娘からさらにその娘へ、息子へと受け継がれていく「命のバトン」「愛のバトン」なのである。本書を読んだ私たちも、そのバトンを落とさないように、大切な誰かに渡していければ、と思う。
(よしだ・のぶこ 書評家)
波 2019年1月号より
単行本刊行時掲載
プロモーションムービー
眞鍋かをりさん ナレーション[メイキング映像]
著者プロフィール
吉川景都
ヨシカワ・ケイト
神奈川県出身。漫画家。2003年少女誌「LaLa」でデビュー。『24時間サンシャイン!』で初の単行本を上梓。多岐に亘る作風が特徴的で、テンポのいい会話でみせるストーリー、エッセイコミックなどで人気を博す。著書に『片桐くん家に猫がいる』『子育てビフォーアフター』(新潮社)、『モズ』シリーズ(集英社クリエイティブ)、『鬼を飼う』(少年画報社)などがある。