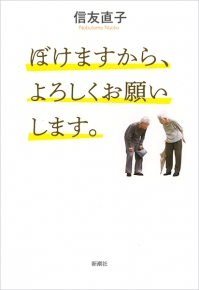
ぼけますから、よろしくお願いします。
1,500円(税込)
発売日:2019/10/24
- 書籍
母85歳に認知症診断、父93歳が初の家事に挑む!? 娘が見た老老介護のリアル!
「心配せんでもええ。あんたはあんたの仕事をした方がええわい」――両親の気丈な言葉に背中を押されても、離れて暮らすことに良心の呵責を抱く映像作家の娘。時に涙で撮り続けた超高齢夫婦の介護の日常は、ほっこりする愛と絆で溢れていた。同名映画にもなった、克明な親の「老い」の記録、そして見守り続けた子の心境を綴る。
第2話 「お母さんがおかしゅうなったけん、撮らんようになったん?」
第3話 私が帰ってきた方がええかね?
第4話 「詐欺グループの名簿に、お母さんの名前が載っていました」
第5話 「人に迷惑をかけない年寄りになりたいです」
第6話 「わしにも男の美学があるんじゃ」
第7話 「あんたはあんたの仕事をした方がええわい」
第8話 「どうしてかね、大事なときに。せっかくあんたが帰ってきとるのにね」
第9話 「この老夫婦は誰ですか?」
第10話 「あんたの仕事じゃけん、わしらは何でも協力するよ」
第11話 「これは、
第12話 「カメラマンか何か知らんが、知らんヤツをこの家に入れるなよ」
第13話 「私たちにつないでいただければ、あとは何としてでも入っていきます」
第14話 「介護はプロとシェアしなさい」
第15話 「母の認知症は、神様の親切かも」と思うに至った私
第16話 「おまえは感謝の心を忘れたんか!」
書誌情報
| 読み仮名 | ボケマスカラヨロシクオネガイシマス |
|---|---|
| 装幀 | 新潮社装幀室/装幀 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 256ページ |
| ISBN | 978-4-10-352941-5 |
| C-CODE | 0095 |
| ジャンル | ノンフィクション |
| 定価 | 1,500円 |
書評
父と母へ。最後にして最大のラブレター
ある事象を長期にわたって取材した結果を表現物として発表する手段に、映像のドキュメンタリーと活字によるノンフィクションがある。両者の大きな違いは、カメラがあるか、ないか、だ。映像のドキュメンタリーは、カメラが回っていなければ「なかったこと」と同じである。一方、活字の場合、その瞬間の直接的な記録がなくても、取材メモや記憶によって再現することができる。
どちらがその事象を、受け手により深いものとして伝えられるのか。カメラの制約がないぶん、活字の方がより細やかに、取材した内容を伝えることができるだろう。だが映像が持っている情報量もあなどれない。例えば取材対象者の表情。「目は口ほどに物を言う」の諺にもある通り、ある人のインタビューを映像として使用しても、活字にしても内容は同じだが、それがどんな表情によって発せられるのかで、受け手の印象はまったく異なる。映像業界に身を置く者としては、優れた活字ノンフィクションの存在を重々承知の上で、「映像も負けてないよ」と言いたいところだ。さて、同じ映像業界に生きる信友直子は、自ら作った映画と同名タイトルの本を、どんな風に仕立て上げたのか。
一読後、思ったのは「まいりました」だ。信友は、普段の仕事とは異なるジャンルでの表現に挑み、映像の持つ情報量の豊かさの壁を、まったく違う形で打ち破った。この本は、タイトルこそ同じだが、いわゆる「映画のノベライズ」では断じてない。その方法論の違いを中心に、書籍版『ぼけますから、よろしくお願いします。』を読み解いていきたい。
映像ドキュメンタリーを活字化した際に、宣伝の惹句などでよく使われるのは「映像には収めきれなかったエピソードがふんだんに入った……」という言葉だ。確かに、この本にもそういう場面はたくさんあるし、そのことによって内容が深まってもいる。だが私が一番に感じたのは、信友の「語り口」の違いである。映画でも一人称のナレーションで信友自身の心情が語られる場面はあるが、その分量は極めて少なく、表現も抑制的だ。これは「できるだけ“撮れているもの”で勝負したい」という、信友の映像作家としての矜持による選択だろう。
だが書籍ではその禁を破り、物語が全面的に彼女の心情吐露によって進行していく。それでいて嫌みになっていないのは、取材対象となったご両親への果てしない愛とユーモアのおかげだ。
例えば認知症と初めて診断された母を残して、信友が東京に戻る日。母は娘を広島空港行きのバス停まで送ってくれて、手を振って別れる。これは映画にもあるシーンなのだが、書籍で読んで初めて知った信友の母への思いに触れ、私は泣けて仕方がなかった。映画ではすっと通り過ごしていた何気ない場面だったのにもかかわらず、だ。
ユーモア、という点では、こんな場面がある。デイサービスの施設に初めて連れて行った際、母がかしこまって自己紹介をするくだりだ。
「『わたくしは、信友文子でございます』/『わたくし』だって? 『ございます』だって? お母さん、何を気取っとるんね?/おほほほ、と口に手を当てておしとやかそうに笑っている母に、私は思わずツッコミを入れたくなりました。(中略)これが認知症になってからの母のよくないところなんですが、自分に自信がなくなっているので、初めて会う人にばかにされたくないという意識が働くのか、必要以上にお上品ぶって、マウンティングする気満々なんです」
信友さん、この場面も映画にあったけど、こんなことを思っていたなんて聞いてないよ。この場面は、断然本の方が魅力的だわ。
信友の愛とユーモアは、取材対象となったご両親から受け継がれ、育まれたものだ。この本では、そのことがよくわかるお二人の人柄が、娘の筆によって「これでもか」と語られる。愛し抜いた両親がともに90歳を過ぎ、先が決して長くはないと知った娘が、父と母のことを世に残しておきたいと願って書いた記録であり、最後にして最大のラブレターでもある。
そして愛とユーモアに貫かれた信友家の長い記録は、終盤に信友が悩んだ末に明かした彼女の“日記”によってクライマックスを迎える。そこに記されているのは、いずれ訪れる肉親の死についての、哲学的とも呼べる考察だ。こんな表現は、映像には絶対にできない。
優れたドキュメンタリー映像作家である信友直子は、この本の発表をもって、優れたノンフィクション作家ともなったのだ。
(おおしま・あらた ドキュメンタリー映像作家)
波 2019年11月号より
単行本刊行時掲載
はじめに

「ぼけますから、よろしくお願いします。」――これは、2017年のお正月に、87歳の母が実際に私に言った言葉です。午前0時になって年が変わった瞬間、「あけましておめでとうございます」という新年の挨拶の後に、「今年はぼけますから、よろしくお願いします」と言ったのです。
私は、ディレクターとしてテレビのドキュメンタリー番組制作に携わって、30年ほどになります。多種多様な人々に取材をして、とてもたくさんの番組を作ってきましたが、2016年には思いがけず、自分の両親――現在98歳の父、90歳で認知症を患う母を取り上げたフジテレビ「Mr.サンデー」の特集も手がけました。高齢夫婦の老老介護の様子を、離れて暮らす娘である私の視点から見た内容ですが、視聴者のみなさんからの反響は予想以上に大きくシリーズ化し、その後、監督・撮影・ナレーターを務めて『ぼけますから、よろしくお願いします。』というドキュメンタリー映画にまでなったのです。
認知症の母のことを映画にしようと思ったとき、タイトルとしてすぐに浮かんだのがこの言葉でした。母の人柄と認知症という病気のことを両方表しており、これ以上ふさわしいものはないと思ったからです。
まず、母の性格。母は昔から、自虐的なことを言ったり、ブラックユーモアをちりばめたりして周りを笑わせる人でした。
たとえば、私が45歳で乳がんになったときには、親なら娘と一緒に嘆き悲しんでも不思議はないと思うのですが、普段通り、いや、それ以上の明るさで自分や私をいじって笑いに変えてくれました。手術でおっぱいの部分切除をするのを不安がる私に「お母さんの垂れたボインでよかったら、いつでもあげるんじゃけどね~」とか、抗がん剤の副作用で髪の毛が抜けてきた私に「コントによう出てくるじゃろ、ハゲのカツラ。あんた、あれかぶっとるみたいに見えるわ」とか。
そういう意味では、「わたしゃ今年はぼけますんで、よろしくお願いします」というのは、いかにも母らしい、自虐的なユーモアあふれる「今年の抱負」というわけなのです。
そして認知症という病のこと。
認知症になった人は、ぼけてしまったから病気の自覚もないのでは? と思われる方もいるかもしれませんが、実は本人が一番苦しんでいます。母をずっと側で見てきた私が言うのだから間違いありません。
自分がおかしくなってきたことは、本人が一番わかっているのです。
昔、できていたことがなぜできないのか、自分はこれからどうなってしまうのか、家族に迷惑をかけてしまうのではないか……。認知症の人の心の中は、不安や絶望でいっぱいです。母もときには「あんたらの迷惑になるけん、私はもう死にたい」と泣くこともあります。あんなに明るくて、何でも笑い飛ばす母だったのに……。
母にそう言われると、私も一緒に泣きたくなります。実際、最初の何年かは、母に思い入れしすぎて私も泣いてばかりでした。「Mr.サンデー」で母の認知症の番組を最初に作ったころが、たぶん私が一番鬱っぽくなっていた時期だと思います。両親のVTRを流した後にスタジオに出演したのですが、今、そのときの自分の映像を見ると、やつれて顔色が悪くてビックリします(まあ、今が心身ともに健康に戻って太りすぎてる、という説もありますが)。
2016年の「Mr.サンデー」のスタジオに、専門家として一緒に出演してくださった認知症専門医の今井幸充先生は、2年後に映画になってから、私とのトークショーにも来てくださったのですが、
「今だから言えるけど、よくここまで立ち直ったねえ。あのころの信友さんはお母さんと心中しそうな勢いで、痛々しくて、なんて声をかけていいかわからなかったもんなあ」
としみじみ言われました(ご心配をおかけしました!)。
人間は学習する動物だということを、私はこの数年で身をもって知りました。母の感情に引きずられて一緒に泣いても、自分の気が滅入るだけで何も解決しない、ということに、誰から指摘されたわけでもなく自分自身でだんだん気づいてきたのです。
それに、母は「私はばかになった! あんたらに迷惑かけるけん死ぬ~」とひとしきり泣きわめくと、体力を使うのか疲れて寝てしまうのですが、次に目が覚めたときには、自分が泣いていたことはすっかり忘れて、ニュートラルな状態に戻っているのです。そして、母の絶望が伝染してまだ泣いている私に、
「あんた、どうしたん? 何で泣きよるん?」
と不思議そうに聞き、「泣きなさんなや」と一生懸命慰めてくれるのです。
こっちは当然「いやいやお母さん、あんたが泣かせたんでしょう」と突っ込むんですが、本人は全く覚えていない。ズッコケてしまうというか、こうなるともはや喜劇ですよね。それで気づいたんです、こりゃあ振り回されるだけ損だな、と。それからは、母が不穏になるとすかさず「寝なさい、寝なさい」と布団に連れて行って寝かしつけるようになりました。私もひとつ学習したわけです。
こういう母の認知症からくるおとぼけエピソードは、数え上げるときりがありません。そしてそれは、母と一緒になって嘆き始めるといくらでも悲劇に思えるけれど、ちょっと引いた目で見るとけっこう笑えて、喜劇に思えてきます。
「人生はクローズアップで見ると悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ」
喜劇王チャップリンの名言です。本当にその通りだなあ、と今の私は痛感しています。
起きたことをどう感じるかは、要は自分の視点の置き方、捉え方なんです。それなら捉え方を自分で工夫して、できるだけ笑って楽しく過ごせる方がいいに決まっています。何があろうと人生やっぱり、楽しんだ者勝ちですから。そう気づいてから、父と私は、母の認知症をネタにして笑うことが増えました。「お母さんがこんなこと言うたよ~」とか、「また忘れとった~」とか。
そんな不謹慎な、と眉をひそめる方もおられるでしょうが、父と私にとってこの会話は、生活を楽しくするための潤滑油のようなものです。二人の連帯感を強める「内輪ネタ」でもあります。それに母も、元々自虐ネタやブラックユーモアを愛していた人ですから、自ら体を張って家族に笑いのネタを提供できるなら、むしろ本望なんじゃないでしょうか。
母が認知症になってから、否が応でも変わらざるを得なくなった、父と母と私の三人家族。でも決して悪いことばかりじゃなかったな、と思えるようになったとき、私は家族の記録を映画として残したいと思うようになりました。娘として映像作家として、我が家で起きたことはすべてビデオカメラで記録していたので、映像はふんだんにあったからです。
映像を見ると、母の異変にうろたえるばかりで何もできない私に比べて、90代の父が、何事にも動じず飄々と受け止めている姿に驚かされます。母のできなくなった家事を自然に引き継いで自分でやり、洗濯をしたり料理をしたり、遂には裁縫まで……。それも嫌々ではなく、鼻歌を歌いながらやっているのです。
今まで包丁なんて持ったこともなかったのに、危なっかしい手つきながら母の好きなリンゴを剥いてやる父。
母がうどんを食べたいと言えば、いそいそと買いに行って作ってやる父。
母の下着まで洗って、母がやっていたのと同じ畳み方で畳んでやる父。
母の気持ちに常に寄り添い、朝、なかなか起きない母に腹を立てるでもなく、たまに早起きした日には「今日は早う起きた。えらい!」とほめてやる父――。
カメラを回しながら客観的な目で見ていたからこそ、私は父が「妻がピンチに陥ったときにここまで尽くせるイイ男だったんだ」と気づけたのです。そして思いました。父はきっと、母を介護しているという意識はないんだろうな。ただ、今まで通り母と一緒に一生懸命、日々を生きているだけなんだろうな。
「おっ母の調子がちいと悪うなったけん、わしがやれることは代わりにやってやろうか。まあ、年をとったんじゃけん、しょうがないわい」。父はきっと母の認知症を、それくらいの自然体で受け止めているんでしょう。案外カッコイイじゃないの、お父さん!
そして母も、昔はしっかり者で、父に甘えたことなんてなかったのに、認知症になってからは、タガが外れたのか解放されたのか、何をするにも父に頼りきりです。
朝は布団にもぐったまま、
「お父さん、起きようかどうしようか? どうしたらええと思う?」
父に「朝じゃけん起きようや」と言われると、布団から手を伸ばして「じゃあお父さん起こしてや~」。そうやって甘えられると父もまんざらでもないようで、「どうしたんな~」と言いながら母の手を握ってやって……やれやれ。
こうなったらもう、二人の間には娘すら入り込めません。なんせ二人には、私が生まれる前からの、60年にも及ぶ歴史があるのですから。
そしてもうひとつ発見がありました。両親の、年老いてなお、認知症になってなお、娘の私を思ってくれる親心。父はもう90代後半で、自分が面倒をみてもらいたい年齢なのに、母の介護のために実家に帰ろうかと言う私に、「わしが元気なうちはわしがおっ母の面倒をみるけん、あんたはあんたの仕事をしんさい」とずっと言ってくれています。母は、認知症で料理ができなくなっても、私が帰省するたびに「よう帰ってきたね。晩ごはんは何にしようか。あんた何が食べたい?」と食事の心配をしてくれます。
映像を編集していると、自分が両親に愛されていることへの感謝で涙する瞬間がたくさんありました。でも思えばあれもこれも、親の愛に気づけたのは、母が認知症になったから。そう思うと母の認知症は、私たち家族に神様がくれたギフトなのかもしれない……。
そうしてできあがった作品『ぼけますから、よろしくお願いします。』は、ドキュメンタリー映画として昨年、2018年11月に劇場公開されました。
最初は東京・中野のミニシアター1館だけの上映でした。驚いたことに初日から連日満員。みなさん泣き、笑い……。客席の熱量もすごかった! 観終わった後に私に駆け寄って「うちもね……」とご自分の身の上話をされる方も多くおられました。
そして広島、大阪、名古屋、福岡……。映画上映の輪は波のように広がり、今では全国100館近くの映画館や各地の上映会で、10万人を超える方々が我が家の物語を観てくださっています。
ここまで広がったのは、みなさんがこの映画を、ご自分とご自分の家族に重ねて観てくださったからだと思います。映画に出てくるのはたまたまうちの両親ですが、みなさんがスクリーンの向こうに見ておられるのはきっと、ご自分の両親、ご自分の思い出、ご自分の将来なのでしょう。
認知症も老老介護も遠距離介護も介護離職も、どなたにとっても決して他人事ではない問題です。2025年には、認知症の患者さんは全国で700万人を超えると言われているのですから。実に65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になる計算です。
認知症は今のところ、治せる病気ではありません。だけど認知症になったからと言って、絶望する必要もありません。楽しいことだってあります。楽しいことを見つければいいんです。映画にはその思いを込めたつもりですが、映画に入りきらなかったエピソードもまだたくさんあるので、父と母のことを文章でも残そうかな……と思うようになりました。
なので、しばらくおつきあいいただけると嬉しいです。文章でも、映画と同じように、飾らずありのままを書くつもりです。
私たち家族のありのままを知っていただくことで、みなさんが「悩んでいるのはうちだけじゃなかったんだな」とか、「この先を心配していたけど、まあなるようになるか」と少し肩の力を抜いて楽な気持ちになっていただけるなら、私にとっても、私の両親にとっても、これ以上の喜びはありません。
2019年8月 信友直子
「第1話 お母さんは、認知症になったんかもしれん……」につづく
つづきは書籍版『ぼけますから、よろしくお願いします。』で。購入はコチラ
試し読み 第1話
第1話 お母さんは、認知症になったんかもしれん……
母・信友文子がアルツハイマー型認知症と診断されたのは、2014年1月8日。85歳のときでした。でも実は、私が最初に母のことを変だなと思ったのは、それより1年半ほど前まで遡ります。
母は私の故郷、広島県呉市で90代の父・良則と二人暮らし。一方、一人っ子の私は、独身のまま、映像制作の仕事をしながら東京で暮らしています。普段は離れていますから、最初にあれ? と思ったのは、母との電話のやり取りでした。
私は母と昔から仲良しで、笑いのツボが一緒なので喋っていて飽きることがなく、なんだかんだ毎日のように電話していました。「今日こんなことがあってね~」とお互いの近況をおもしろおかしく報告しあって笑いあう、というのが会話のほとんどだったと思います。でも、2012年の春ごろから、母のリアクションが少しおかしくなってきたのです。私が前回した話を、次の電話のときに全く覚えていなかったり、逆に母が一度した話を、次の電話でも初めて話すかのように一から繰り返す、ということが何度かあったのです。
最初のうちは私も、「お母さん、その話こないだもしたろ? 覚えとらんの? しっかりしてや~」と軽い感じで指摘し、母も「ありゃ? ほうじゃったかいねえ」と笑っていたのですが……。
そんなことが何度か続くと、さすがに私も「これは冗談では済まされないぞ」と思うようになりました。そしてしだいに、私なりに気を遣って、母がおかしな対応をしても気づかないふりをするようになりました。
お母さんは、認知症になったんかもしれん……。
普段は1年に一回、年末年始にしか帰省しない私ですが、この状況はさすがに心配です。ひとつの番組を作り終えたタイミングで実家に帰ることにしました。
それが2012年6月4日でした。そのときの日記が残っています。
いつもは1日数行程度の短い日記しかつけないのですが、この日からしばらくは長い文章を書いています。初めて目の当たりにする母の異変が、それだけ自分にとって衝撃的だったということです。今読み返してみても、当時の私の動揺が伝わってきます。
他人にお見せするのは少し恥ずかしい文章ではありますが、ありのままに書き写してみます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2012年6月4日(注:呉に帰る日、飛行機の中で書いたもの)
やっぱり母はおかしい。
さっき、「今日そっちに帰るからね」と電話したときにそう確信した。私の話が飲み込めていないようで、返事のしかたがあやふやなのだ。
確かに昨日の夜、母に電話して、「今日放送予定だった番組が来週に延期になったから、明日帰るはずじゃったけど帰れんようになった」とは言った。でもその後プロデューサーから、「もうVTRは完成してるんだから予定通り帰省していいよ」と言われたので、今朝また母に電話して、
「やっぱり予定通り帰れることになったよ。夜までにはそっちに着くよ」
と伝えたのだ。だけど母にはそれがうまく理解できないようで、私は同じことを何度も繰り返し話す羽目になった。
最終的に母は「ああ、そう」と言い、電話を切ったのだが……。
3分ほどで、母から電話があった。
「あんた、帰ってくるって、今日帰ってくるん?」
どうやら父に伝えるうちに自分でもわからなくなったらしい。というより、わからないまま、それ以上私に聞き返せなくて一度電話を切ったのか?
時制が絡むと話が理解できなくなる。少し話が込み入ってくると理解できなくなる。
認知症の始まりと、疑うべきなのだろうか?
2012年6月7日(注:帰省中、呉の実家で書いたもの)
母は同じ話ばかり何度もする。それも「一から」だ。
まるで初めてその話をするかのように「一から」話す。
今はとにかく、ヨウコちゃんのダンナが亡くなったから香典を1万円出したのに、その香典返しをくれもせずに「あげたじゃないの」と言われたという話が母のブームだ。
細かいディテールまで、何度も話しては怒りをあらわにする。
この話、よっぽど腹が立ったらしく私が東京にいる間にも電話で何度か聞いたが、まだまだ母の中では消化できていないようで、毎日思い出しては喋る。しかも同じ調子で。
「ヨウコちゃんはボケたんじゃないの」と言っているが、もしかして本当に受け取っていてどこかに置き忘れてる、なんていうのが真相じゃないか、と秘かに私は思っている。母にはとても言えないが。
最近の母の話は、他人にばかにされているとか、他人からこういう目に遭わされたとかの怒りを伴ったものが多い。もっと楽しいことを話せないのかと思うし、母にも、私なりに言葉を選んでそう言ってはいるのだが……。
あんなに明るくて楽しい人だったのに、いつからこんなに被害妄想的な性格になってしまったのだろう。
夜、父に「お母さん最近おかしいんじゃないの?」と聞くと、父もそう思っていた。
「昔はあんなことなかったのにのう。ばかにされとる言うて急に怒り出したり、攻撃的になったりするんよ。誰もばかにしとりゃあせん、言うても聞かんのじゃ」
父はそんな母を、とても気遣っていた。
「おまえも、お母さんを傷つけるようなことは言うなよ」と釘を刺された。
「二人だけで暮らして大丈夫なん?」と父に聞くと、今はまだ大丈夫だと言う。今は91歳の、かなり耳の遠い父を頼りにするしかない。
「私が東京に戻っても、お母さんがおかしいと思うたら言うてよ。すぐ帰るけんね」
そう伝えたら父は、「わかった」と答えた。
お風呂に入る父と、お湯の温度のことで母が言い争いをしている。
父がシャワーの温度を下げたことが、母としては気に入らないのだ。風邪をひくから45℃に上げろと言い張っている。
もうバスタブにお湯は入っているのだから、シャワーを使うには40℃でいいのだと父は言い返している。実際45℃のシャワーは熱すぎる。
それでも母が譲らないので、父は仕方なく「じゃあ45℃にして、シャワーの時には水でうすめるわ」と言ってお風呂に入って行った。
しばらくすると、わざわざお風呂のドアを開けて、父にまだ喧嘩を売ろうとする母。
「何するんじゃ!?」
父はギョッとしていた。そりゃあそうだろう。無防備な裸のところに突然踏み込まれたら誰でもビックリする。
母は私に「お父さんはおかしいと思わん?」と同意を求めるが、いや、おかしいのはお母さん、あなたの方です。
「お風呂くらい好きに入らせてあげたら?」と言うと、母はたちまち不機嫌になった。自分の思い通りにならないと、自分が軽く見られたと思って気分を害すのだ。
これでは、一緒に暮らしている父は、よほど気を遣わないといけないだろう。
父の耳が遠いことが、せめてものなぐさめか……。
6月10日(注:呉に帰省して7日目)
母の一挙手一投足が気になる。いつも母が変なことをしないか、気にかけている自分がいる。変なことをしないでくれと祈っている自分がいる。
母が何かをちゃんと覚えていたり、理解していたりすると、ホッとする。
私も母に認知症の気が出てきたことを、やはり認めたくはないのだ。
ゾッとしたことは、帰省してから何回もあった。
母が果物屋で、もうバナナがないから買う、と言うので買って帰ったら、なぜか冷蔵庫の中に、買ったばかりのバナナが何房もあったこと。バナナは冷蔵庫に入れると黒くなるから常温で保存しなさい、というのは母が私に教えてくれたことなのに……。
外科で出された湿布薬が、封の開いた状態で4つも出てきたこと。几帳面な母の性格からすると考えられないことだ。以前の母なら、1袋使い終わるまで、決して他の袋は開けなかった。
このところ全く新聞を読んでいない。活字を読んでいる姿を見たことがない。「新聞読まんの?」と聞くと「ニュースはテレビで見るけんね」と言っていたが……。
家計簿も、私が小さいころからずっとつけていたのに、もうつけていないんじゃないか? と思う。一度、夜、そろばんをはじいて家計簿に何か書き込んでいたから、「家計簿つけよるん?」と声をかけたら、慌てて閉じた。
そのときにチラッと見たら、字も汚かったし、買ったものと値段が別の欄にずれて書かれていたし、何よりその日の日付じゃないところに書いていたような気がする。すぐに閉じられてしまったので、よくは見えなかったが……。
とにかく母が自分の筆記能力がおかしくなっていると感じていることは確かだ。そうでなければ、あんなに慌てて、書いたものを隠さないだろう。
友達のやっている会社の経理を4月に辞めたのだが、それはもしかして、計算ができなくなってきたからじゃないのか? 辞めた時には母は「あそこは儲からなくなって給料が遅配だから」と言っていて、私もそれを信じていたのだが……。
もしかして、書道をやめた2年前くらいから、今までできていたことができなくなったりしていたのだろうか……。
そうだとしたら、私が母の異変に気づくのが遅かったのだろうか……。
母の気持ちを思うと、涙が出そうになる。
自分がおかしくなっていることは、家計簿がうまくつけられなくなった自分が一番よくわかるはず。だけどそれは恥ずかしいことだから、誰にも知られたくない。だからひた隠しにしたい。たとえそれが夫や娘でも。
母が何かあるとすぐに「ばかにされた」と怒り出すようになったのは、自分の異変を感じ始めたからなんじゃないか、と思えてきた。
いったい母は今、どんな気持ちでいるのだろうか……。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長い日記は、ここで終わっています。
その2日後、父とも相談して私が母を病院に連れて行ったのですが、検査の結果、「認知症ではありません」という結論になったからです。
どうしてそんなことになったのか。どうも、母を病院に連れて行くタイミングがちょっと早すぎたようなのです。
認知症の検査では、お医者さまが認知症を疑われる本人に「長谷川式認知症スケール」といわれる問診をするのが基本なのですが、母はこの問診でものすごく頑張って高得点を取ってしまったのです。逆に言えば、まだ本人が頑張れば高得点を出せるような時期に検査に連れて行ってしまった、私のミスというわけです。
ここでちょっと時間を遡って、母をどうやって説得して病院に連れて行けたのか、からお話ししましょう。
実際、母に「ちょっと病院に検査に行ってみん?」と言い出すのはかなり緊張しました。家族にそう言われて「私がぼけとるとでも言うんね!?」と怒って病院に行きたがらない人の話はよく聞くし、それでなくても母はもともとプライドが高い人なのです。
しかし、恐る恐る言葉を選びながら持ちかけると、母は意外なほどあっさり「ほうじゃねえ、それなら行ってみようかねえ」と言ってくれました。
今思えば、本人も検査したかったのだと思います。問診があるというのは本人も知識として知っていましたから(私は数年前に若年性認知症のご本人と家族のドキュメンタリー番組を作ったことがあるのですが、そのときにご本人が問診を受けて認知症と診断されるシーンを放送し、まだ元気だったころの母は「娘の作った番組」としてそれを見ていました)、問診で頑張っていい結果を出してお医者さまから「大丈夫。あなたは認知症ではありません」とお墨付きをもらって安心したかったんだと思います。
なので「長谷川式認知症スケール」の問診を受けるときは、母は異常なくらい張り切っていました。
「長谷川式認知症スケール」とは、1974年に精神科医の長谷川和夫先生が開発された「認知症の可能性がある人かどうかをスクリーニング(ふるい分け)する問診項目」です。あらかじめ決められた9通りの質問をお医者さまが順番に聞いていって、正解なら1点、間違えたら0点、と足し算をしていき、30点満点のうち20点以下だと認知症の疑いが強まる……というものです。今も一番ポピュラーな検査法なので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
質問は「お年はいくつですか?」から始まって、「今日は何年何月何日で、何曜日ですか?」「ここはどこですか?」と見当識障害がないかを確かめるもの、「100から7を引いたら?」「そこからまた7を引いたら?」と数字の把握力や計算力を確かめるもの、3つの単語を覚えさせてしばらく他のやりとりをした後に、「ところでさっき覚えてもらった3つの単語は何だったでしょう?」と記憶力を確かめるものなど、認知症になると弱っていくあらゆる機能をテストしていくものです。
母は、お医者さまの質問に前のめりになって、かなり食い気味に答えていきました。その張り切りぶりは異常なほどで、集中するあまり体がどんどん火照っていくのが隣にいてわかったくらいです。
「野菜の名前を思いつくだけ言ってください」という質問には、
「大根、ニンジン、キャベツ、玉ねぎ、ねぎ、じゃがいも、レタス、トマト……」
先生から「もういいです」とストップがかかるまで、たぶん20個以上、延々と答え続けました。そして母は見事、30点満点中29点を獲得したのです。
「そのお年にしては立派なもんですねえ」
お医者さまにほめられた母は得意満面でした。
脳のMRI検査でも、特段異変は見当たらないとのことでした。アルツハイマー型認知症の特徴である、海馬(脳内の記憶や認知機能を司る場所)の萎縮はまだ認められなかったのです。
結果を聞いた母の喜びようはすさまじいものでした。検査を受けた病院からの帰りに、わざわざかかりつけ医のところに「ぼけとりませんでした!」と報告に寄ったほどです。もちろん父にも誇らしげに報告しました。
「お父さんも直子も、私のことをぼけとると思うとったじゃろ? そんなことはないんじゃけんね!」
そう言われると父も私も、苦笑するしかありませんでした。
私が東京に戻ってからも、母は事あるごとに自分の友人に、
「直子が心配じゃ言うけん、ぼけとらんか検査しに行ったんじゃけど、30点満点で29点取ったわ~。1問だけ間違えたんが悔しゅうてねえ」
そう吹聴して回ったようです。母からその話を聞いたという人はけっこう多くいました(まあ、こうやって同じ話を何度もするというのが、もはや認知症の症状なんですが)。
そして私と父は、認知症でないという診断結果が出ると、逆にどうしようもなくなってしまいました。明らかに、私がフライング気味に検査に連れて行ったのが失敗だったのです。若年性認知症の患者さんの取材をしたことがあるので、認知症の初期症状に普通の人より敏感になっていたんだと思います。
今考えると、このころの母は認知症の一歩手前の「軽度認知障害」(MCI)という段階だったのだと思います。でも2012年ごろは、まだその概念は知られておらず、MCIから認知症に進行しないための予防法も特段発表されていない、そんな時期でした。
認知症の疑いが晴れて喜ぶ母を見ていると、秘かに「確かにおかしいんだけどなあ」と納得いかない思いを抱えながらも、私はもう、母に病気のことを持ち出しづらくなってしまいました。そしてアルツハイマー型認知症と診断が下るまでずるずると、1年半が経つことになるのです。
「第2話 お母さんがおかしゅうなったけん、撮らんようになったん?」につづく
つづきは書籍版『ぼけますから、よろしくお願いします。』で。購入はコチラ
試し読み 第2話
第2話 「お母さんがおかしゅうなったけん、撮らんようになったん?」
「あんた、前はようお父さんとお母さんをビデオで撮りよったのに、最近は撮らんようになったね。お母さんがおかしゅうなったけん、撮らんようになったん?」
2013年のお正月。一緒に台所に立っていた母に、ふいにそう言われてドキッとしました。まったく深刻な口調ではなく、大根か何かを切りながらの、半分冗談みたいなさらっとした聞き方。でもだからこそ、よけいに母の「おおごとにはしたくないけど、やっぱり気になる」という切実な思いが伝わってきて、私は胸を衝かれたのです。
「えー何それ? お母さん、おかしゅうなったんね?」
私が平静を装ってまぜっ返すと、母は「まあええわ」と、ちょっと寂しそうに笑って、それ以上は何も言わずスッと別の話題に切り替えました。
そう、母に指摘された通り、そのころ私は、実家に帰ってもビデオカメラを回さなくなっていたのです。母におかしな行動が目立つようになってきて、それを母が一生懸命、隠そう、ごまかそうとしていたので――。
「カメラが回っているときにもし何か粗相をしてしまったら、母が傷ついてしまうんじゃないか」――そう思ったら怖くなって、母にカメラを向けられなくなっていました。
私が家庭用のビデオカメラ、ソニーのハンディカムを初めて買ったのは、2000年12月です。当時はまだ高価なものだったのですが、冬のボーナスで「えいやっ!」と決断して買いました。映画に2001年お正月の、まだ背筋のピンと伸びた若々しい父と母の映像が残っているのはそのおかげです。自分のカメラを買ったことがとにかく嬉しくて、帰省した際に手近にいた両親を試し撮りしたのです。
「このカメラ、直子が買うたんよ。すごいじゃろ?」
そう言いながら最初にカメラを向けたときの両親のリアクションは、今でも鮮明に覚えています。二人とも、恥ずかしがって動きが固まってしまったり、何か言おうとしても緊張のあまりまとまらなくて支離滅裂になったり、まだまだ初々しいものでした。それに、撮っている私も、絶望的に撮影が下手でした。
それから先、私は帰省のたびに、両親の何気ない暮らしぶりを撮影するようになりました。そして、最初はガチガチだった両親もだんだん撮られることに慣れてきて、3年も経つと「カメラがあっても全然気にならんわ」と言うくらい自然体になりました。
ここで、私がどうして両親が元気なうちから、二人の何でもない日常をビデオに撮っていたのかをご説明しましょう。
ひとつは、自分でははっきり意識していませんでしたが、私自身のために思い出を残そうとしたんだと思います。私は一人っ子で、結婚もしていないので、家族といったら父と母だけ。二人がいなくなってしまったら私はどうなるんだろう、と途方に暮れることもよくあったのです。だから、将来父と母がいなくなって一人になっても、映像が残っていれば寂しさを紛らわせるかも……そんな私の防衛本能のようなものが、映像記録を残させたのだと思っています。
もうひとつは、身も蓋もない理由ですが、当初あまりにも私の撮影の腕がヘボだったので、両親に協力してもらい、撮影の練習台になってもらったという事情でした。ビデオカメラは、実は仕事のために買ったので、こちらの理由の方がより大きいかもしれません。そのころ私は仕事上、ビデオカメラを使いこなす必要に迫られていたのです。
話は少し逸れますが、ここでちょっとだけ、ドキュメンタリーディレクターという私の仕事の話をさせてください。
私がビデオカメラを買った少し前の1990年代後半ころから、テレビドキュメンタリーの取材現場にはちょっとした革命が起きていました。家庭用カメラの進出です。それまでは取材現場には、私のようなディレクター(現場の責任者)と、プロ用の大きなカメラを肩に担いだカメラマン、プロ用のマイクで音を録る音声マン、という三人一組で行っていました。でも、技術革新によってしだいに家庭用カメラの性能がよくなり、画質も音質も放送に耐えうるレベルになってきたのです。そうなると、現場には、ディレクターが一人だけで家庭用カメラを持って出かける、というケースも出てきました。
どんな番組を作りたいかで取材態勢は変わってきますが、私のようないわゆる「人間ドキュメンタリー」専門のディレクターにとっては、大きなカメラを担いで大勢で行くよりも、ディレクターが一人で行って話を聞きながら小型カメラで撮った方が、取材相手が緊張せずに自然な姿を見せてくれるのは明らかです。それに私一人で行った方が経費がかからないので、より日数をかけた丹念な取材ができるようになります。さらに私だけで行くと、取材相手とも1対1で向き合うことになるから、より親しく深くつきあえるようになるし……そう考えるといいことばかりなんです。
そんなわけで私も次第に、自分でディレクターと撮影を兼ねる取材の仕方にシフトチェンジしていきました。そしてどうせなら、自分でカメラを買っていつも手元に置いておこうと思ったのです。
そう、私が2000年にビデオカメラを買ったのは、ディレクターとして時代の流れについていくためだったのです。
でも、それまでカメラマン頼みで自分でカメラを回した経験なんてなかったので、なかなか使える映像が撮れません。それに、ディレクターの一番大切な仕事は、取材相手の気持ちを丹念に聞くこと。カメラの操作をいちいち気にしていたのでは、本当に大切なことに集中できません。とにかく、仕事現場に行ったときに取材相手に全神経を集中させられるように、カメラを意識しなくても操作できるくらいまで慣れておくことが必要でした。そのためにはひたすら練習するしかありません。
そんな私にとって、父と母は格好の練習台でした。どんなに撮っても文句は言わないし、二人ともすぐにカメラに慣れていつも自然体でいてくれたから、自分の取材がうまくなったような気がして自信がつくし(これには本当に感謝しています)。
父と母の撮影は、毎年お約束のように、私が実家に帰ってきたところから始めていました。いつも実家の1ブロック手前でカメラを取り出し、録画ボタンを押してから実家に向かっていたのです。実家に着くと、子供のころから変わらない玄関の引き戸をガラガラと開けて一言、「ただいま~」。
すると奥から母の声が「おかえり~」。
耳の遠い父が「何じゃ?」と母に聞く声がして、母が「直子よ。直子が帰ってきたんよ」。そして私は玄関を上がり、廊下を進む。母がエプロンで手を拭きながら台所から出てくる。
「おかえり。よう帰ってきたね。元気じゃったん?」
私のために煮魚を作ってくれているのだろう、台所からはお醤油のいい香り。
「お腹すいたじゃろ。すぐごはんにしようや。待っとったんじゃけん」
座敷には父が座っている。いつものように新聞を読んでいる。あーお父さんも変わってないなあ。ちょっと年をとったかな? でも元気そう。
「おかえり。早かったのう」
「元気じゃったん?」
「おう、まあまあの。あんたは元気そうなのう」
こんな感じで、私はカメラを回し続けていたのです。毎年のように。しかし……。
「お母さんがおかしゅうなったけん、ビデオを撮らんようになったん?」
2013年、母にそう指摘されて、私は気づきました。母が認知症気味になったから母を撮らなくなったなんて、考えてみれば失礼な話だと。それでは今の母を否定していることになってしまう。母は撮られて恥ずかしい人間になったわけじゃないのに。母は母のままなのに。
そしてこうも思ったんです。自分がおかしくなったのでは? と不安に駆られている母を安心させるには、今まで通り、普段通りにしていることが一番なんだと。
そして2013年、私は今まで通り、父と母の日常生活の撮影を再開しました。母がおかしなことをしても、それを指摘したり責めたりするのではなく、「ああそうなん」と母の言い分やごまかしを聞いてあげたり、ときには異変に気づかないふりをしたりして、できるだけ今まで通りに、接していこうと決めたのです。
もちろんこのころは、そうやって撮った映像を世の中に公表しようという思いは、まだ全くありませんでした。映画『ぼけますから、よろしくお願いします。』は、さまざまな偶然や奇跡が積み重なってできあがった作品なのですが(詳細は後ほど)、両親の過去の何気ない映像が残っていることも、実は偶然の産物だったことがおわかりいただけたかと思います。
「ご両親を撮り始めたのは何がきっかけなんですか?」という質問を、本当によくいただくのですが、そのときにはいつも「私が自分のビデオカメラを買ったからです。ご期待に添えるような答えじゃなくてすみません(笑)」とお答えしています。
中には「どうしてご両親が若いころの、普段の生活の映像が残っているんですか? そのころからこの映画を作ることを考えていたんですか?」と聞いてくる方もおられるのですが、さすがにそれはないです。私にはそこまでの予知能力はありません。そのころには、この先、私たち家族が、母の認知症、老老介護、遠距離介護、介護離職などという、現代日本の社会問題を抽出したかのような事態に直面することになるとは、想像すらしていなかったですから。
ということは、言葉を変えれば、私たち家族のような事態には、誰もが陥る可能性があるということです。誰にでも家族の老いや介護は訪れます。そして自分の老いや死も。それが逃れられない運命なら、どう受け止めるか、その覚悟や度量が問われる、今はそんな時代なんじゃないかと思います。
覚悟というと大袈裟かもしれませんが、私たち家族が10年近くかけてたどり着いた答えを(というより妥協案を)、こうして記すことでみなさんと共有して、それで少しでも楽な気持ちになる方が増えるのであれば、とても嬉しいです。
しかし、今つくづく思うことですが、偶然とは言え、両親の若くて元気なころの映像を撮っておいて本当によかったです。若いころの二人がキビキビ動く映像と、今の老いて腰の曲がった映像とを対比して見ることで、「人が老いてゆくこと」の無残さと、逆に「年を重ねてゆくこと」の豊かさとを、私たちは両方感じることができると思うのです。
私自身は、両親のこの20年の変遷を映像で見返して、こう感じています。
年をとると大変なことが増えていって、たぶん90代の今は二人とも生きているだけでしんどいんだろうけれど、生き様はどんどん深く、美しくなっていくように見えるなあ、と。自分の親だから、ちょっと贔屓目ですかね。
そして、認知症になる前の母がどんな人だったかがわかる映像をふんだんに撮っておいたことも幸いだったと思います。母の場合は特に、2007年に私が乳がんになったときに、私の面倒をみるために上京して大活躍していますから、その映像がたくさん残っているのです。
落ち込む私を励まそうと、冗談ばかり言って笑わせてくれたり……。実家にいるときと同じような料理を、心を込めて作ってくれたり……。友人相手に「おっぱいを切りたくない」とごねる私が席を外した瞬間に、「ごめんね、直子が面倒くさいことばっかり言うて。そんなこと言われても、あなたも困るよねえ」と代わりに友人に謝ってくれたり……。やっぱり娘の辛い気持ちもわかるから、私に面と向かっては何も言えないんですよね。
そして、手術が成功したときには思わず担当医に「ありがとうございます」と手を合わせて涙してくれて……。そんな一部始終を撮っていた映像から、私はこれでもかというくらい、たっぷりの母の愛を感じさせてもらいました。
だから、母の認知症が進んでいって、昔の母からは信じられないような暴れ方をしたり、暴言を吐いたりして、私自身かき乱されて本来の母を忘れそうになっても、映像の中の母がいつでも私を、平常心に戻してくれるんです。やさしい気持ちに戻してくれるんです。映像の中でいつでも本来の母に会えることは、今の私には大きな救いです。
母だけでなく認知症の人にはみんな、それぞれ活躍していた昔があり、人を思いやり、人から尊敬された昔があります。認知症で変わってしまっても、それは病気の症状が出ているだけで、その人自身が変わってしまったわけではないんです。
さて、ここからは、2013年以降の、再びビデオカメラを回しながらの父と母との日々です。カメラ片手に、娘半分、取材者半分の視点でいた(より正確に言えば、娘と取材者の間を行ったり来たりしていた)からこそ、少し客観的に見ることができた両親の変化を綴っていこうと思います。
つづきは書籍版『ぼけますから、よろしくお願いします。』で。購入はコチラ
試し読み 第3話
第3話 私が帰ってきた方がええかね?
2013年には、母のことが心配で3回帰省しました。まだ家事は母がやっていましたが、父曰く、
「料理が甘かったり辛かったりでのう。ちょうどええ味のときがそがいにないんじゃ」
とぼやいていました。ごはんの水加減もうまくいかないようで、柔らかかったり硬かったり、まちまちになっていたようです。でも、それを指摘すると母の機嫌が悪くなるので、父は文句も言わずに食べているようでした。味付けが薄いときには、母が見ていないところでこっそり塩を振るのだそうですが、
「おかずの味が濃いすぎるときにはどうするん?」
と聞いたら、
「『今日はお茶漬けにしようかのう』言うて、辛うて食べられんおかずをごはんに乗せて、その上から湯をかけて薄めるんよ」
そう言うので思わず想像して笑ってしまいました。と同時に切なくなりました。
もともと父はそこまで母に気を遣うような人ではなく、料理がおいしくなければ(そもそもおいしくないことはほとんどなかったのですが)母にはっきり言っていたのに、そんな父が気を遣って黙ってしまうほど、母が「文句を言わせないオーラ」を出しているのだ、と感じたからです。それは裏を返せば、母の不安や自信のなさのあらわれです。
母はもともと料理がうまく、しかも研究熱心で、ご近所の家庭科の先生が開いておられたお料理教室に何年も通ってレパートリーも多かったのです。しかしこのころはだんだん、自分の得意料理ばかり作るようになっていました。レシピが頭に入っていて、間違えない自信があるものしか、怖くて作れなくなっていたのでしょう。なので献立は、肉じゃが、おでん、煮魚の3つをグルグルと回っていたようです。
父は、今日もまた肉じゃがかぁ……と思ったある日、
「もう肉じゃがは飽きたけん、ちょうど味が薄かったし、そこにカレーのルーを入れてカレーにしてみた」
と私への電話で言っていたことがあります。
「へえ~お父さんがやったん?」
意外に思って聞くと、
「わしにもそれくらいできるわい」
と笑っていましたが、おそらくこれが、父の記念すべき料理1作目じゃないかと思います。
でも、母はどう思ったんだろう、自分の料理に手を加えられて傷ついたんじゃないかしら。心配になったので、電話を代わってもらって聞いてみると、母は夕飯にカレーを食べたことすら忘れていました。
「え~? カレーじゃったかいねえ? なんかほかのもんを食べたような気がするが」
私は、お母さんが覚えてないんならまあいいか、と思ったと同時に、母は今食べたものも忘れるようになったのか、とショックを受けたことを覚えています。
私が帰省すると、台所で母と私、どちらが料理の主導権を取るのか、静かな攻防戦が始まるようになりました。母が元気なうちは、明らかにリーダーは母で、私は助手でした。母が私に手料理を食べさせたいと張り切って台所に立ち、私は母を手伝いながら料理のコツを盗ませていただく、そんな関係でした。台所は母の城で、私は母の許可がないと、置いてある鍋の位置ひとつ変えることはできませんでした。
でも母の料理がおぼつかなくなってくると、父のためにも、私が料理を作った方がいいということになります。父は私が帰省すると「なんかおいしいもん作ってくれや~」と期待を込めた目で訴えてくるし。
でも母は文字通り台所に「立ちはだかって」いました。私が台所で何かしようとすると、「どうするん? お母さんがするけん」と、まるで通せんぼをするみたいな感じで狭い台所に立ち、入らせてくれないのです。
食料品の買い物は、母だけで行くと買い忘れがあったり、途中で何を買えばいいのかがわからなくなるので、「お母さん一緒に行こうや」と私もくっついて行って、
「今日は何にするかね? 私、お母さんの炊き込みごはんが食べたいわあ」
「ほうね、ほいじゃあ、そうしよう」
「炊き込みごはんなら、鶏肉と油揚げとニンジンを買わんといけんね~。ニンジンはもうウチになかったじゃろう」
とさりげなくフォローしていました。なのでそれほど問題は起きませんでしたが、家に帰ってからが大変です。
「お母さんがやるけん、あんたは休んどってええよ」
母は料理を自分で仕切ろうとし、私は母を立てるふりをしながら、母には野菜を切ってもらったりして忙しくしてもらい、その隙に味付けなどの重要なところは自分でやるという、ちょっと姑息な手段に出ていました。でも案外母にはバレなかったようで、それで機嫌を悪くするようなことはありませんでした。
……と思っていたけど、本当はバレていて、気づかないふりをしていただけなのかな? 今になるとそう思います。
母は一日中、探し物をするようになってきました。箪笥の引き出しを開け閉めしたり、戸棚の上に並べてある箱を下ろしてみたり、しょっちゅうガサゴソしているのです。
「何を探しよるん?」
と聞くと、あるときは健康保険証だったり、あるときはお気に入りのハンカチだったり。健康保険証は母が怪しくなってからは父が保管しているので、
「お父さんがちゃんとしとってじゃけん、大丈夫よ」
と言うと「ほうね~。えかったわあ」と安心するのですが、またしばらくすると新たな探し物が始まります。最初は私も母と一緒になって探していましたが、大したものではないことが多いので、だんだん面倒になって放っておくようになったら、そのうち、
「ありゃ、私は何を探しよったんかいねえ?」
探しているもの自体が何だったか忘れてしまい、もうええわ、ということになるのです。
一度は、夜中にトイレに起きたら、廊下の薄明りの中、トイレの前に母がしゃがみこんでいてギョッとしたこともあります。
「どうしたんお母さん! 何しよるんね?」
「ああ直子、石鹸の予備がひとつもないんよ。お中元でもろうたのがあんなにあったのに、どこへ行ったんじゃろうか。なかったら困るよねえ。今から買うてこようか」
さすがにこのときは、私も背筋が寒くなりました。お中元をもらっていたのなんて、父が会社員時代のことですからもう50年近く前の話なんです。確かにそのころは石鹸の詰め合わせが山ほど送られて来ていましたが、父が定年退職してからもう30年以上経つというのに……。
「しっかりしてや、お母さん。お中元でもらいよったのなんて何十年前の話ね。それに今、何時じゃ思うとるん? 夜中の3時よ。買いに行こう、言うたって、こんな時間に開いとる店なんかないわ」
「ほうね。ほしたら一回寝て、明日の朝買いに行こうかねえ」
母を布団に連れて行って寝かせたものの、私の方が眠れなくなってしまいました。
この年の夏には、「扇風機を盗られた」という騒動もありました。
夏に帰省すると、扇風機が新しくなっていました。それまで実家の扇風機は、私が子供のころからの年代物で、それを両親は二人して大切に使っていたのです。もともと両親は二人とも、よく言えば節約家、悪く言えばケチで、あまり物を買い換えずに古いものを大切に使う主義なので、私にとってはけっこう驚きでした。
「扇風機買い換えたん?」
と母に聞くと、
「古い扇風機はね、〇〇さんが来たけん、玄関に出して涼ましてあげよったら、知らん間に持って帰っちゃったんよ」
と言うのです。
このあまりに荒唐無稽な話に、私は思わず笑ってしまいました。ウチの扇風機は50年近く前の代物なので、室内を移動させるのも大変なくらい、重くてかさばるのです。ご近所の〇〇さんというのはかなりご年配の人なので、それをウチから持って出て、えっちらおっちら運んでいくなんてこと、できるわけがありません、人目もあるわけだし。
母によく聞くと、その人の訪問と扇風機がないと気づいたときが、同じ日だったかどうかも怪しくなってきました。それでも自説を曲げず、
「どうやって持って帰ったんじゃろうか、あがいに重たいものを」
としきりに不思議がる母に、
「近所の人にそんなこと言うたらダメよ。揉め事のもとになるけん」
父と二人で何度も言い聞かせました。
ちなみに後日談ですが、古い扇風機は、それから2年後、私が納戸を整理していたときに奥の方から無事見つかりました。
2014年お正月明けの、1月8日。父と相談して、母をもう一度検査に連れていくことにしました。
それまでは、2012年に検査をして「認知症ではありません」と言われたことが、ある意味、母の心の支えになっていて、それで自尊心を保っていたようなところがあったのですが、1年半経って、どうやらそんな事実さえも忘れたようなので……。また検査に行ってもいいタイミングかな、と思ったのです。
認知症は今の医学では、治したり進行を止めたりすることはできないのですが、いくつかの薬が開発されていて、飲めば進行を遅らせられるという臨床データもあったので、母に薬を飲ませてみたい気持ちもあったのです(まあ、同じくらい薬の副作用の心配もあるので、悩むところでしたが)。
母に話すと、1年半前に検査を受けたことは何となく覚えていて、
「やさしい先生じゃったねえ。あの先生のところならまた行ってもええわ」
と嫌がるそぶりがなかったのでホッとしました。病院に行っても母はニコニコと愛想良く、
「先生こんにちは。お世話になります」
とご挨拶し、
「娘が東京から帰ってきてね、お母さん、また検査しに行こうや言うから来ました。普段離れて暮らしとるし、私が年じゃけん心配なんでしょうねえ」
と自分から来院の目的をしっかりと話していて、お医者さまも「はあ、そうですか」と苦笑い。
しかし、1年半前の検査では「長谷川式認知症スケール」という問診テストをすごく頑張って、30点満点中29点という好成績を残した母ですが、今回は頑張れませんでした。お医者さまから「今日は何年の何月何日ですか?」と聞かれたとたんに、「どうじゃったかいねえ」 と私に助けを求めてきたのです。1問目から自分で考えるのを放棄して私に頼ろうとしてきた……これは認知症の人の典型的な反応です。
「お母さんが聞かれよるんじゃけん、お母さんが答えんにゃ」
と言っても、ごまかし笑いをするばかり――ああ、1年半の間にここまで進んだのか。
前回は得意だった「野菜の名前をできるだけ挙げてください」という質問にも、3つくらい答えたところでもう思いつかなくなってしまいました。あんなに毎日、いろんな野菜を使って、いろんな料理を作ってくれた母なのに……。
結果は30点満点中の14点。20点以下だと認知症の疑いが強いと判断されますから、母はこの時点で限りなく黒に近いということになります。
それでも私は、母が最後まで穏やかに問診テストをやり切ったことをほめてあげたいと思いました。問いに答えられないことが続いたので、途中から私は内心秘かに、「母が機嫌を悪くしたらどうしよう、自暴自棄になったらどうしよう」とハラハラしていたのです。「100から7を引いたらいくつ? なんて、子供に聞くようなことを聞いてばかにしとる」と怒り出すんじゃないかと。
でもそれは杞憂でした。意に沿わないことがあると不機嫌になるのは家族の前でだけで、人前では不甲斐ないことがあってもいい顔をしていられるんだ……母の、結果が芳しくなくても笑顔を絶やさない様子を見て、そう痛感しました。それは私には、母の社会性が失われていないことへの喜びでもありましたが、母が本当は泣きたいのを我慢しているのかなあ、と想像するとかわいそうで、私の方が泣きそうにもなりました。
脳のMRI検査の結果も出ました。今回の画像を1年半前に撮ったものと見比べると、私のような素人が見ても脳全体が萎縮して空洞ができているのがわかりました。特に記憶をつかさどる「海馬」の部分の萎縮は顕著でした。
「アルツハイマー型認知症です。もう薬を飲み始めた方がいいかもしれませんね」
私は診断にショックは受けませんでした。むしろ、やっと病名がついたことにホッとしたくらいです。それよりも私がショックだったのは、お医者さまに病名を告げられても、母がそれに反応しなかったことです。あいかわらず看護師さんたちにニコニコ愛想を振りまきながら、「最近、膝が悪うてねえ」などと全然関係ないことを喋っている母……。
母は自分が「アルツハイマー型認知症」だと言われたことの意味がわかってないのか?
そこまで状況把握能力がなくなっているのか?
実家に帰ると父はコーヒーを淹れて待っていました。父なりに、検査を頑張ってきた母をねぎらおうとしたのでしょう。私は、母が脱いだコートをしまいに行った瞬間を狙って、父に告げました。
「アルツハイマー型認知症なんだって」
検査結果の紙を渡すと、父はしばらく読んでいましたが、納得したようで、
「やっぱりのう」
と一言。そこに母が戻ってきて、冗談めかした言い方ではありましたが、
「まったく、ぼけとりもせんのに、みんながぼけとる、ぼけとる、言うんじゃけんねえ」
あ、母はわかっていたのか。私はドキッとしましたが、父がとっさに場を収めてくれました。
「ほうよ、ぼけとらんのなら、気にすることはないわい」
ありがとうお父さん。さすが家長さんだわ。その瞬間、父をものすごく頼もしく感じました。
母はメマリーという、認知症の症状の進行を抑制するといわれる薬を飲み始めることになりました。最初は用量5mgから始めて、副作用が出なければ10mg、20mgと増やしていくことになります。副作用として考えられるのは、主にめまいやふらつき、眠気などですが、人によっては痙攣を起こしたり、妄想や幻覚が現れるケースもあるそうなので、家族が注意して見守っていなければなりません。
しかし私はそろそろ、仕事のために東京に帰らなくてはなりませんでした。
このとき母は85歳、父はもう93歳でした。元気とはいえ93歳の父に、認知症が確定した母の様子をみてもらっていいのだろうか。私が呉に帰って世話をしなければいけないのではないか。
「私が帰ってきた方がええかね?」
父に問いかけると、父は言下に断ってきました。
「いやいや、あんたは帰らんでもええ。わしが元気なうちは、おっ母はわしがみるけん、あんたはあんたの仕事をしんさい」
そのときの私の気持ちを正直に言うと……父にそう言ってもらってホッとした、というのが一番でした。親不孝だとは思いますが、それが隠し事のない、ありのままの私の気持ちです。
私は独り者で、東京に家族はいないですから、夫や子供がいる人に比べれば生活拠点を実家に移しやすいとは思います。それに私はフリーランスのディレクターで、作品1本ごとに契約してギャランティーをもらう働き方です。会社の勤め人ではないので、有給休暇をいつまで取れるかとか、休職するのかそれとも退職しなくちゃいけないのか、といった心配はありません。次の作品を契約さえしなければ、すぐにでも仕事は辞められる、そういう意味では自由度が高い働き方です。
でもそれは逆に言えば、次の作品を断ってしまうと、すぐに仕事=収入源がなくなってしまうということでもあります。そんな不安定な立場で、歯を食いしばり、自分が頑張って手にしたこの職を失いたくない……そんな未練がありました。
東京で女一人、フリーランスでこの仕事で食べていくためには、やはり努力を続けてきました。好きな仕事なのであまり辛いとは思いませんでしたが、45歳で乳がんになったのも寝る間を惜しんで働いたことが原因だと思っていますし、乳がんの治療をしている間も休まず仕事は続けてきました。フリーランスで独身なので、自分が働かないと治療代も払えないし、食べていけなかったからです。まあこの仕事が好きだから、がんという大病を患っても辞められず、性懲りもなく続けてきたという言い方もできますが。
そこまでしてしがみついてきた大好きな仕事なのに、手放したくない。このころはまだ、その思いの方が強かったのです。だから父に「私が帰ってきた方がええかね?」と恐る恐る聞いてみて、まだ「帰らんでもええ」という免罪符をもらえたことで、内心ホッとしていたのです。
しかしこうやってホンネを書いてみると、本当に自分勝手な娘ですね……。我ながら嫌になります。
翌日、広島空港行きのバス停まで、母が送ると言ってくれました。バス停は実家から歩いて10分ほどのところです。このころはまだ、母もそのあたりまでは迷わず行けましたし、父も私も「お母さんはバス停から一人で帰れるんだろうか」という心配はしていませんでした。まだまだ症状は軽かったわけです。
外は雨。母はバス停への道すがら、
「仕事が忙しいけん言うて頑張りすぎんのよ。人の仕事まで買うて出ることはないんよ」
と私の体の心配ばかりしていました。
「東京に着いて雨が上がっとっても、傘を忘れんように持って帰りなさいよ」
ときっちりした性格の母らしい、細かい注意も受けました。
お母さん、傘より大切なことがあるじゃろう。昨日から認知症の薬が出とるんじゃけん、毎日忘れずに飲みなさいよ。私はそう言いたかったけれど、もう母に病気の話はしないことにしよう、と思いとどまりました。母とは普段通りに接しようと決めたじゃないか。普段通りのたわいない会話をして、普段通りに別れよう。
バスがきて、母との別れのときがやってきました。
「お母さん、元気でね」
私には、それしか言える言葉がありませんでした。次に帰ったときも、元気で、同じように私を迎えてね。
手を振る母が、どんどん遠ざかってゆきます。私はバスの中からカメラを回していましたが、今見ると母が視界から消えた後、ものすごくカメラが揺れています。プロとしては失格なほどの画面の揺れ。これは私の心の揺れなんだなあ、と今になると思います。認知症と診断された母を、93歳の父に任せて、こうやって去って行って本当によかったのだろうか。やっぱり私は救いようのない親不孝者なんじゃないか……。バスの中でも、東京への飛行機の中でも、恥ずかしいくらい泣いたのを覚えています。
母が一人でバス停まで見送りに来てくれたのは、これが最後になりました。
次の帰省からは、「お母さん見送りに来てや」と言っても、「膝が痛いけんねえ」とかいろいろな理由をつけて断られるようになったのです。おそらく、私を送った後、一人で家まで帰れるかどうか、自信がなくなったのだと思います。
そして私の、本格的に東京と呉を行ったり来たりの日々が始まりました。
つづきは書籍版『ぼけますから、よろしくお願いします。』で。購入はコチラ
著者プロフィール
信友直子
ノブトモ・ナオコ
1961(昭和36)年、広島生れ。映像作家。東京大学文学部卒。2009(平成21)年、自らの乳癌の闘病記録である『おっぱいと東京タワー~私の乳がん日記』でニューヨークフェスティバル銀賞、ギャラクシー賞奨励賞などを受賞。2018年には、初の劇場公開作として両親の老老介護の記録『ぼけますから、よろしくお願いします。』を発表し、令和元年度文化庁映画賞文化記録映画大賞などを受賞。2022(令和4)年には続編『ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえりお母さん~』が公開された。著書に『ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん』『あの世でも仲良う暮らそうや 104歳になる父がくれた人生のヒント』がある。



































