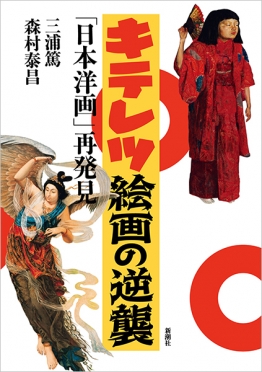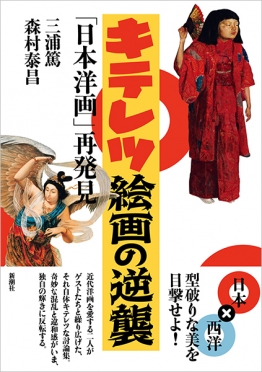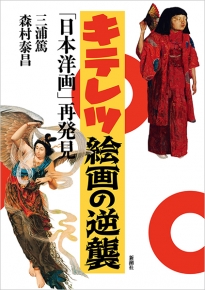
キテレツ絵画の逆襲─「日本洋画」再発見─
2,750円(税込)
発売日:2025/09/25
- 書籍
日本と西洋がぶつかり合う、型破りな美を目撃せよ!
美術史家と美術家と立場は違えど、日本近代洋画への愛をわかちあう二人が、気になるテーマごとにゲストを迎えて繰りひろげた、それ自体キテレツな討論集。知る人ぞ知る明治初期の写真画、裸体画問題、戦時中の戦争画と前衛絵画など、近代洋画から否応なく滲みでる奇妙な混乱と違和感がいま、唯一無二の輝きに反転する!
プロローグ
なぜキテレツ絵画なのか?
森村泰昌
その(1)
異文化との出会いのはじまり
その(2)
黒田清輝の功罪
【ゲスト】蔵屋美香
その(3)
高橋由一への遡上
【ゲスト】古田亮
その(4)
山本芳翠の訛り
【ゲスト】日比野克彦
その(5)
中村彝の受容と創造
【ゲスト】荒屋鋪透
その(6)
浅草から上野へ、そして戦争画の問題
【ゲスト】木下直之
その(7)
日本に裸体画は必要か
【ゲスト】蔵屋美香
その(8)
東西洋画対決
【ゲスト】田中淳 橋爪節也
その(9)
前衛絵画の行方
【ゲスト】弘中智子
その(10)
世界の中のキテレツ絵画
エピローグ
洋画行脚を終えて
三浦篤
書誌情報
| 読み仮名 | キテレツカイガノギャクシュウニホンヨウガサイハッケン |
|---|---|
| 装幀 | 岸田劉生《童女舞姿》 部分 1924年 公益財団法人大原芸術財団 大原美術館蔵/カバー表、本多錦吉郎《羽衣天女》 部分 1890年 重要文化財 兵庫県立美術館蔵/カバー表、赤波江春奈+日下潤一/ブックデザイン、ヨコカク/題字 |
| 雑誌から生まれた本 | 芸術新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | A5判 |
| 頁数 | 200ページ |
| ISBN | 978-4-10-355582-7 |
| C-CODE | 0071 |
| ジャンル | 絵画、芸術一般 |
| 定価 | 2,750円 |
書評
「洋画」は訛りが面白い!
映画における「洋画」は外国製の映画を意味する。日本で作られた映画は邦画と呼ぶ。わかりやすい分け方だ。
ところが日本美術において「洋画」は日本人が描く西洋風の油絵を指している。映画に「日本の洋画」は存在しないが、絵には存在する。
幕末、本物そっくりに描ける油絵の写実性に惹かれた高橋由一は、日本のものを西洋の写実技法で記録しようと思い立った。明治に入って由一は教科書でもおなじみの「鮭」や「豆腐」「花魁」といった愛すべき作品を生み出した。由一にとって洋画=写実だった。
一方その頃西洋では、印象派が産声をあげていた。ルネサンス以降、西洋絵画は実に長い間写実に縛られてきたが、ようやくその時代が終わったのだ。
開国後、順不同で次々に入ってくる西洋美術。明治・大正・昭和の日本の洋画家たちは、海の向こうからやってくる絵に好奇心をかられ、翻弄されるうちに「西洋ってなんなの?」「日本ってなんなの?」という問いに向き合わされることになる。写実だけでテーマになるのは由一の時代で終わっていたのだ。
本書は美術史家・三浦篤さんと美術家・森村泰昌さんがゲストを招いて繰り広げた近代洋画討論集である。〈内発的と外発的がこんがらがった、矛盾だらけでおそらくは誤読だらけの表現世界〉、〈正統とされる西洋美術史から見れば、それらは奇妙なもの、不思議なもの、場合によれば無様で恥ずかしいもの〉に見える洋画の性質を「キテレツ」と名づけている。
ちなみに「日本画」は話がスッキリしているかと言うと、実はそうでもない。「日本画」は「洋画」に対抗して作られた、近代日本がこれから目指したい日本の絵のことだった。つまりそれ以前の伊藤若冲も葛飾北斎も「日本画」には入らない。近代は日本の絵描きを悩ませる。
さて現在。ぼくは「洋画」「日本画」という区別を意識して絵を描いたりしないし、単なる画材の違いでしかないと思っている。日本のマンガやアニメは世界に支持され、日本美術も彼らに代表席を用意している。もう「洋画」だの「日本画」だの問わなくてもいいだろう。
そんなフラットな時代になったからといって、ぼくらが自由に面白い絵が描けているかというとどうなのか。ぼくは正直この本に登場する絵に嫉妬する。
ゲストの一人、日比野克彦さんが山本芳翠の絵を見て「訛り」と表現しているのが面白い(ぜひ芳翠の「浦島」を画像検索してください。THEキテレツ絵画です)。
ふるさとの訛りなくせし友といて
モカ珈琲はかくまでにがし
ぼくは高校生の時に覚えた寺山修司の短歌を思い出した。すでに寺山は故人で、昭和から平成に変わろうという時代。未だロックの本場はイギリスやアメリカで、本格的とされるものには「日本人離れした」という褒め言葉がついた。青森訛りの寺山は土着的かつ前衛的でカッコよかったのだ。
さて「洋画」において訛りなくせし友の代表は「日本近代洋画の父」と称される黒田清輝ではないだろうか。黒田はフランスに留学し、まさしく本場を見てきたが、サロンの入選作「読書」など、西洋人が描くフツーの絵なので面白くない。「読書」とともに白洲正子の実家に飾られていたという「湖畔」(湖畔で佇む団扇を持った和服美人の絵。切手にもなった)もクセがなさすぎる。
はっきり言おう。訛ってなきゃ「洋画」じゃないのである。訛ってしまうから面白いのである。創作魂の本場は訛りの中にあるのだ。
黒田清輝をちょっとフォローしておくと、三人の裸の女性が妙なポーズを取っている「智・感・情」という絵はけっこうキテレツだ。日本洋画のパパにも訛らなきゃいけない問題意識があったのだ。
フォービスムもキュビスムも目まぐるしいまでに取り入れる萬鉄五郎のピュアさ。萬は絵を描くセンスが突き抜けているので、何をやってもかわいいし面白い。
小出楢重がキテレツ入りしているのは意外だったが、確かに油絵具のねちっこさに、日本的な湿り気があり〈鰻のようなヌルヌルした感じ〉がする。岸田劉生が日記に小出楢重のことを「この男下人也」と書いているとは知らなかった。ぼくはどちらもファンなので複雑な心境です。
若冲や北斎は確かに日本人にとって誇らしい故郷だ。でも、ぼくは逆立ちしたって彼らのように描けないし、文化的断絶もあるから、帰るに帰れない遠さを感じる。
日本の「洋画」を振り返っても、誇らしい気持ちにはなれないかもしれない。いや、だからこそってやつじゃないか。故郷とはそういう場所だろう。先輩たちの絵筆の跡を辿るうちに、ぼくらはここからやってきたのだという実感を得た。キテレツ絵画こそわが故郷である。
(いの・たかゆき イラストレーター)
波 2025年10月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
三浦篤
ミウラ・アツシ
1957年、島根県生まれ。大原美術館館長。東京大学名誉教授、國學院大学教授。専門は西洋近代美術史、日仏美術交流史。主な著書に『エドゥアール・マネ─西洋絵画史の革命』、『移り棲む美術─ジャポニスム、コラン、日本近代洋画』、『大人のための印象派講座』など。
森村泰昌
モリムラ・ヤスマサ
1951年、大阪府生まれ。「自画像的作品」で知られる美術家。モリムラ@ミュージアム、ディレクター。『生き延びるために芸術は必要か』など著書も多数。2025年10月7日~11月9日に大原美術館で「森村泰昌「ノスタルジア、何処へ。」─美術・文学・音楽を出会わせる─」展開催。