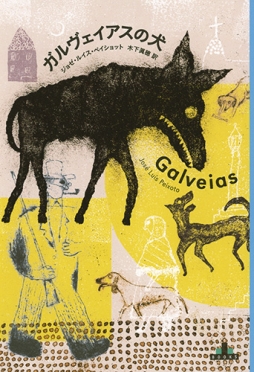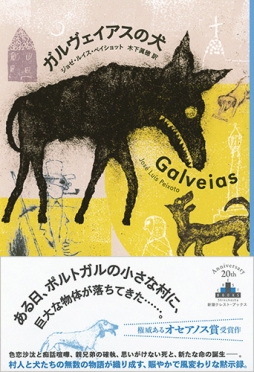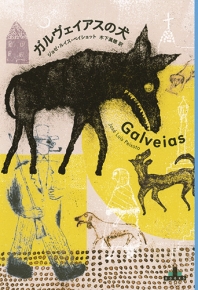
ガルヴェイアスの犬
2,640円(税込)
発売日:2018/07/31
- 書籍
巨大な物体が落ちてきて以来、村はすっかり変わってしまった――。
ポルトガルの傑作長篇。日本翻訳大賞受賞作。
ある日、ポルトガルの小さな村に、巨大な物体が落ちてきた。異様な匂いを放つその物体のことを、人々はやがて忘れてしまったが、犬たちだけは覚えていた――。村人たちの無数の物語が織り成す、にぎやかで風変わりな黙示録。デビュー長篇でサラマーゴ賞を受賞し「恐るべき新人」と絶賛された作家の代表作。オセアノス賞受賞。
書誌情報
| 読み仮名 | ガルヴェイアスノイヌ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |
| 装幀 | Jun Tada/イラストレーション、新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 288ページ |
| ISBN | 978-4-10-590149-3 |
| C-CODE | 0397 |
| ジャンル | 文芸作品、評論・文学研究 |
| 定価 | 2,640円 |
書評
幸福な悲しみ
1984年1月のある夜、ポルトガルの小さな村ガルヴェイアスが猛烈な爆音に襲われる。村人たちを恐怖に陥れたこの爆発音は、間もなく村のはずれの原っぱに墜ちて巨大な穴をつくった物体によるものだったことがわかる。村人たちによってその穴のまんなかに見つけられたものは「名のない物」と呼ばれるが、この物体については物語のおしまいまで、そのトートロジカルな呼び名以外、色も、形も、大きさも、明らかにはならない。
物語は、村人たちの目には明らかに映っているはずの「名のない物」ではなく、その謎の物体の到来以降、何かが狂ってしまった村の人々、そして犬たちの方を見ている。
作中で経過する時間は、「名のない物」の到来にはじまるおよそ十か月に過ぎない。それは村の者たちの人生のごく一部だが、彼らのあいだをわたり歩くように語られるこの物語を読み進めるのは、もっとずっと長い時間の旅のように感じる。
語りはたしかに村の者たちの方を見ているが、そこで中心に立つ者は誰もおらず、鳥瞰されるだけの人々の名前や関係性は一読ではなかなか覚えきれないだろう。読み手は、村の地図をたどるように、彼らひとりひとりと順番に付き合わなくてはならない。そこにある時間は単に人数×十か月ではないのだ。ある人のもとに起こったある出来事を語ろうとすれば、必ずその人がそれまで過ごした時間も一緒についてくる。つまり結局それは彼らの人生についての話なのであり、これはいくつもの人生の物語なのだとも言える。
概観すれば煩雑でまわりくどいとしか言いようのないこの語り口は、しかしちゃんと付き合えば付き合っただけよろこびを与えてくれる。このよろこびはいったいなにゆえだろうかと思う。というのも、語られるエピソードはどれも悲劇的なものばかりなのだ。
老夫は兄を殺す決意をし、女は夫の浮気相手に“爆弾”を投げつける。貧しい少女が男に手込めにされ、犬が毒を盛られて死ぬ。神父はアル中で、娼婦は銃で誤射される。不慮の事故、濡れ衣……不幸は後を絶たない。そして謎の物体の落下以降、村のパンはひどくまずくなった。
大勢の登場人物が、みな何かしらの不幸に見舞われている。戦争中に友人と家族を失った村の郵便配達夫は「運命には良心なんてものはない。ただ非情なだけだ」と悟る。実際、救いのない絶望的な話ばかりで、この彼もまた、別の人物に非情な言葉を投げつけて恨みを買ったりしている。
重要なことは、彼らの人生の悲しみを語るこの物語の語り手は、彼ら自身ではないということだ。村の者たちは決して雄弁ではなく口下手で、声を発するよりもむしろ、自分の人生や、自分の悲しみに、どんな言葉が与えられうるのか、その言葉を聴こうと耳をすませている。
そして、まるで「名のない物」のように姿の見えないこの物語の語り手もまた、村の者たち(犬も含む)に寄り添って、一緒に耳をすませている。語り手は、語るより前に、聞き手なのだ。そうして、声にならなかった声、言葉にならなかった声が、姿の見えない語り手のもとで語られる。悲しみに希望が宿るとするならば、言葉にならなかった声に、言葉が与えられるその瞬間においてなのではないか。
そして読み手である私たちも、読みながら一緒に耳をすますことができる。彼らの抱くものが憎悪で、彼らを襲うものが悲劇であっても、それが思い出され、語られる時、その声に帯びる希望を見つけることができる。
村からブラジルにわたって娼婦になったファティマは、そのままブラジルで生涯を終える。生前、誇らしげに故郷について語っていた彼女の姿を、遺体を村に送り届け、結局この村に娼婦として居ついたイザベラが思い出す。その姿は、「幸福な悲しみに酔いしれているように見えた」。
幸福な悲しみ、という背反的な表現を、私たちは私たちの人生の現実として知っている。ひとつの声に、ふたつの感情を聞きとること。それは他者の声を聞くこと、あるいは過去を思い出すことに、分かちがたく付随するのかもしれない。悲哀は幸福を呼び、幸福は悲哀を呼ぶ。いずれにしろ悲しい、とも言えるが、完全な絶望はない、とも言える。慎ましく真摯な語り手のおかげで、読み手もまたそこに希望を聞きとることができる。この物語によってもたらされるよろこびとは、きっとそういうものだ。
(たきぐち・ゆうしょう 作家)
波 2018年8月号より
単行本刊行時掲載
関連コンテンツ
短評
- ▼Takiguchi Yusho 滝口悠生
-
ポルトガルの小さな村の人々、そして犬たち。語られるのは村に謎の巨大物体が落ちてきた年の出来事だが、いつの間にか物語は彼らの人生を描き出す。何かを思い出せばまた別の何かが思い出され、連なる記憶が人々のあいだを渡って、いくつもの過去が重なり合い、広がっていく。「記憶もまた場所なのだ」とある者が言う通り、彼らの過去がその村の地図になる。またある者は「運命には良心なんてものはない」と嘆くが、いくつもの悲しみと絶望を語りながら、本作はどうしてこうも朗らかなのか。何かを思い出すことはきっとそれだけで希望なのだ。
- ▼The Independent インディペンデント紙
-
ペイショットの力強く魔術的な文章は、一貫して美しい。一見シンプルだが、途方もなく豊かで深い余韻を持っている。
- ▼Visao ヴィザォン紙
-
この作品の語るすべてが、ひとつの宇宙であり、その中の
埃 であり、土地の黙示録であり、文明の箴言である。人間ひとりひとりの、そして一体となって暮らす人間たち全体の、記憶のパズルである。
- ▼Premio Oceanos オセアノス賞選評
-
著者の故郷を題名とした本作は「奥深いポルトガル」に潜入する作品である。物語は、とある出来事(ガルヴェイアスへの隕石落下)をきっかけに、
古 からの世界に生きる人々を描く。暴力、荒廃、悲哀、近代との衝突のはざまに埋もれつつある村に、その出来事は宇宙的な意味をも与えている。
- ▼Time Out タイム・アウト誌
-
これはアレンテージョに実在するガルヴェイアスではない。念入りに構築されつつ、記憶によって深く形を変えた場所なのだ。ペイショットは、研ぎ澄まされた無数の鏡のようなこの多面的な作品に、とうに失われた時代を書き留めているのである。
- ▼Le Monde ル・モンド紙
-
ポルトガルで最も才能ある作家の一人である。
- ▼The Times タイムズ紙
-
ペイショットは並外れた感受性を持っており、それを他の誰にも選び得ないような独自の言語やイメージで読者に伝える。
- ▼The Guardian ガーディアン紙
-
ペイショットの文章には、類まれな、リズミカルな美しさがある。
訳者あとがき
ガルヴェイアスも、あらゆる惑星も、同時に存在してはいても、まったく違う本質をそれぞれ持っているのだから、混同されることはなかった。ガルヴェイアスはガルヴェイアスであり、宇宙のその他は宇宙のその他なのである。(本文より)
ポルトガルの作家、ジョゼ・ルイス・ペイショットの『ガルヴェイアスの犬』(原題は “Galveias”)をお届けする。ペイショットの長編第五作であり、初の邦訳となる。
ガルヴェイアスとは、ポルトガルのアレンテージョ地方の内陸部に実在する、人口千人あまりの村である。アレンテージョ地方は、夏は乾いた太陽が容赦なく照りつける酷暑、冬は極寒、と自然条件の厳しい土地だ。ポルトガルの穀倉地帯であるこのアレンテージョの人々の暮らしは昔からおおむね貧しく、厳しかった。
この小村、ガルヴェイアスの外れの原っぱに、一九八四年一月の真夜中、宇宙から何かが墜ちてくる。得体のしれないそれは強い硫黄臭を放ち、やがてそのにおいは村を覆いつくして小麦の味をも変えてしまう。豪雨のあとに続く干ばつ、蔓延する異臭。不穏な空気に押されて何かの蓋がひらいたかのごとく、つつがなく暮らしていた村の住民たちの隠された姿が次第にあらわになっていく。
五十年以上仲たがいをしたままの老兄弟、子だくさんの主婦、住民の噂に精通している郵便配達夫、若者たちの兄貴分のようなバイクの修理工、着任したばかりの若い女性教師、酒浸りの心優しい神父。都会から遠く離れた田舎暮らしでも、単純な毎日を繰り返しているようでも、ひとりひとりの深淵を覗いてみれば、そこにはそれぞれの唯一無二の物語があり、波立つ嵐、孤独と悲哀がある。
本作では、一九八四年の一月と同年の九月の二部に分かれてガルヴェイアスの内外で起きたさまざまな出来事が綴られる。一月の部で語られるのはすべて村の内部での話で、そうしてわれわれはガルヴェイアスという土地を隅々まで案内される。九月の部では、アフリカのギニアビサウ、リスボン、ブラジルを舞台にした話もあり、急に世界が広がったような感覚も覚えるが、やはりどれも本質的に深くガルヴェイアスと結びついている。
本作に登場するものは、人物はもとより、犬、山、公園、広場、通り、すべての名前が登場するたびにいちいち告げられる。「(犬が)つぎつぎと吠える声をたどればガルヴェイアスの地図が描けそう」だと本文中にあるが、こまごまとした場所の名前をたどれば、われわれにもガルヴェイアスの地図が描けそうなほどだ。
実は、作者ペイショットの故郷がこのガルヴェイアスなのである。一九七四年にここで生まれて高校卒業までを過ごし、現在も母親が暮らしている。そう、この作品に出てくるのは、どこもすべて作者自身が幼いころからなじんでいる場所なのだ。なかには、実在の人物や実話をヒントにして描かれた話もあるという。と言っても、作者自身が目にしたというより、母などから伝え聞いた話が多いそうだ。
ペイショットは、これまでもこの村を舞台にした作品を数編書いている。ただし、アレンテージョ的な要素を詰め込んで暗喩してはいるが場所の特定はしていない。あらゆるものに名前をつけて具体化させた小説を書きたいと考えたとき、題名は“Galveias”にするとすぐ決まった、と二〇一四年にソル紙(ポルトガル)のインタビューで語っている。物語はあとからついてきた。地名を特定して実在の名称を詳述し土地特有の色味を濃くした物語は、かえって普遍性をもたらすはずだ、と思ったのだそうだ。
はたして、作者の思惑は当たったのではないだろうか。日本から見れば西の果て、イベリア半島の隅っこにある遠いポルトガルという国、さらにその辺鄙な田舎の物語だというのに、そこに生きる人たちは、どこかわたしたちに似てはいないか。
ところが、そうした感慨や共感は硫黄のにおいに阻まれる。ページをめくる指にもうつるのではないかと気がかりになりそうなほどの強烈な異臭。どこにでもありそうなガルヴェイアスの村には、どこにもない宇宙からの落下物があり、すべてを毒す硫黄臭がある。そして、雨は、なぜだかガルヴェイアスに降ることをやめてしまった。過去作でも異界のものとの共生、境界の曖昧な世界を一貫して描いてきたペイショットは、本作で自らの故郷に異物を居座らせた。
しかし、それでも読後感は暗くない。宇宙に狙い定められた場所であるガルヴェイアスは、今後どういう道を選ぶのか。「黙示的」と評されもする本作は、あらたな世界の始まりを示唆しているかのようでもある。過疎化が進む故郷を思い、「このままの状態が続けばガルヴェイアスは消失するだろう、だが、そうはならないと信じたい、ガルヴェイアスには未来があると信じたい」と語ったペイショットにとって、その「ガルヴェイアス」とは、自分の故郷に限らず、変わりつつあり失われつつあるすべての小さな場所、誰かの故郷のことを指しているはずである。
さて、この小村ガルヴェイアスが生んだ作家、ジョゼ・ルイス・ペイショットについて簡単に紹介したい。二十歳で父を亡くし、その経験を中編“Morreste-me”と題して発表し、二〇〇〇年に作家デビュー。この父の死は、その後の作品のテーマに大きな影響を残し、複雑な親子関係、閉鎖的な田舎の村、そして死が、ほとんどの作品においてモチーフとなっている。同年に刊行した長編第一作“Nenhum Olhar”も、巨人が
ところで、本作の設定が一九八四年であるという背景について、簡単な説明があってもよいかもしれない。一九八四年といえば日本ではバブル直前、各家庭にカラーテレビは当たり前、ビデオデッキもだいぶ普及して、若者たちはウォークマンや家庭用ゲーム機などを気軽に楽しんでいたころだ。ポルトガルでは、その十年前の一九七四年、四十年以上に及ぶ独裁政権が「カーネーション革命」と呼ばれる無血革命によって終結を迎え、ようやく民主化が始まった。革命前後からアフリカ植民地が次々に独立を求めて泥沼の戦争となり、ポルトガルの六〇年~七〇年代は混沌の時代だった。アフリカで築いたすべてを捨てて「本国」ポルトガルへの帰還を余儀なくされた人たち、戦争へと駆り出された男たちとその家族、小さな国のポルトガルでは誰もが、なんらかの形でアフリカ戦争に関わったと言っても過言ではない。当時は、国民の多くにとって、ファシズムもアフリカの戦争もまだ過去のものとはなり切っていなかった。独裁政権時代には国民の教育が手薄だったためそのころの識字率は八割ほど。農村に限っていえば、もっと低かっただろう。だが、一九八六年にポルトガルは欧州経済共同体(EEC)に加盟、その後急速な発展を遂げる。その前夜にあたる一九八四年は、貧しく暗かった過去が終わり近代化へと舵を切る過渡期に当たると言える。いわゆるグローバル化が始まる前の、ある意味でポルトガルがもっともポルトガルらしかった最後の時だったと言えよう。
一九八四年にはペイショット自身は十歳、作中に出てくるロドリゴと同じ年ごろだ。周囲への理解力が芽生えるのと同時に、年の離れたふたりの姉が家を出たことで、村の外の世界にも目が行きはじめたころだったろう。当時は子どももまだたくさん村に住んでいて賑やかだったそうだ。田舎といえども、みんながロバに乗って畑仕事をしていたわけではない、テレビドラマも見ていたし、バイク乗りもいたし、そういうあの時代の空気も描きたかったとペイショットは言う。
私は二〇一七年九月、本作訳了の前にポルトガルを訪れてペイショット本人にガルヴェイアスを案内してもらった。物語のように暑い日で、シコ・フランシスコのカフェのモデルというバルの前では、初老の男性がたむろしておしゃべりしていた(なぜかポルトガルでは路上で立ち話をしているのは男性のほうが多い)。若い教師が足をすべらせないようにそろりそろりと降りた急勾配の坂道では、やはり女性がひとり、ゆっくりと歩いていた。白い漆喰塗りの長屋のような建物の玄関のひとつは「カベッサの家だ」と教えられた。パン屋もあった(売っているのはパンだけだったそうだけれど)。そうやって歩いていると、すれちがう人たちが親し気にペイショットに挨拶していく。聖サトゥルニノ教会も訪ねた。小高い丘の上にぽつりと建つ無人の小さなチャペルの周囲には、枯れかけた草が茂っていた。そこから見下ろすガルヴェイアスはどこまでも平穏で、車が一台通る音がかすかに聞こえるだけだった。そして「名のない物」が墜落した原っぱに向かう途中の乾いた道路では、犬が一匹、どこへ急ぐのか一心不乱に歩いていた。
そう、ガルヴェイアスの犬たちを忘れてはならない。人間とはちがい「名のない物」の存在を片時も忘れることなく、言葉にならない言葉で訴えていた犬たちを。彼らの役割については、そのなかの一匹の、カサンドラという名前が表しているだろう。カサンドラとは、ギリシャ神話で祖国の滅亡を予言したのに誰にも信じてもらえなかったトロイの王女の名である。
本書の翻訳にあたり、多くの方々にご協力をいただいた。企画段階から伴走してくださった新潮社の佐々木一彦さん、訳文の丁寧な確認をしてくださった同社校閲部の井上孝夫さん、ペイショット特有の、時に難解なポルトガル語の表現の解釈をお手伝いくださったポルトガル大使館の清水ユミさんには特にお礼申し上げたい。
この素晴らしい物語を私に預けてくれ、多くの質問にも丁寧に答えて現地に案内までしてくれた作者のジョゼ・ルイス・ペイショットと奥さまのパトリシアにも深い感謝を捧げる。日本での翻訳が決まったと報せたときの「彼はいま、歓喜のあまり言葉をうしなっている」というパトリシアの返事は忘れがたい。
日本ではまだまだポルトガル現代文学の紹介が進まないなかで、本書を翻訳し出版できることは望外の喜びである。今後、さらに多くのポルトガルの作品が邦訳されていくことを願う。
最後に、さまざまな形で応援し、励ましつづけてくれた家族と友人たちにも、心からの感謝を。ありがとうございました。
二〇一八年六月
木下眞穂
著者ビデオメッセージ
字幕翻訳:木下眞穂
イベント/書店情報
著者プロフィール
ジョゼ・ルイス・ペイショット
Peixoto,Jose Luis
1974年、ポルトガル内陸部アレンテージョ地方、ガルヴェイアス生まれ。2000年に発表した初長篇『無のまなざし』でサラマーゴ賞を受賞、新世代の旗手として絶賛を受ける。スペインやイタリアの文学賞を受賞するなど、ヨーロッパを中心に世界的に高い評価を受け、『ガルヴェイアスの犬』でポルトガル語圏のブッカー賞とも称されるオセアノス賞(ブラジル)を受賞した。詩人としても評価が高く、紀行作家としても活躍。作品はこれまで20以上の言語に翻訳されている。現代ポルトガル文学を代表する作家の一人。
木下眞穂
キノシタ・マホ
ポルトガル語翻訳家。上智大学ポルトガル語学科卒業。訳書にジビア・ガスパレット『永遠の絆』、パウロ・コエーリョ『ブリーダ』『ザ・スパイ』など。2019年、ジョゼ・ルイス・ペイショット『ガルヴェイアスの犬』で第5回日本翻訳大賞受賞。