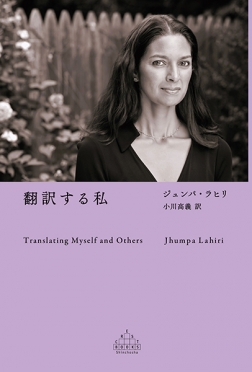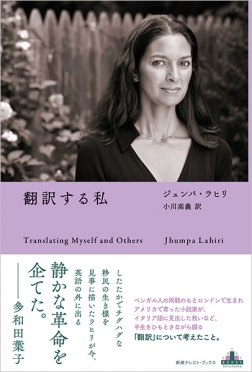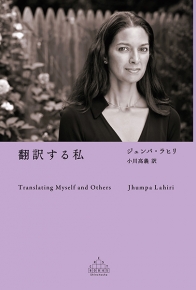
翻訳する私
2,145円(税込)
発売日:2025/04/24
- 書籍
自分自身をべつの言葉に置き換え、変化を恐れずに生きてきた──。
ベンガル人の両親のもとロンドンで生まれ、アメリカで育った著者は、幼い頃から自らや家族のことを、頭のなかで常にベンガル語から英語に「翻訳」してきた。大人になってから習得したイタリア語に見出した救い、母の看取りなど、自身の半生をひもときながら綴られる、小説を書くことを鼓舞してくれる「翻訳」について考えたこと。
序文
1 なぜイタリア語なのか
2 容器 ドメニコ・スタルノーネ『靴ひも』の訳者序文
3 対置 ドメニコ・スタルノーネ『トリック』の訳者序文
4 エコー礼讃 翻訳の意味を考える
5 強力な希求法への頌歌 自称翻訳家の覚え書き
6 私のいるところ 自作の翻訳について
7 代替 ドメニコ・スタルノーネ『トラスト』への「あとがき」
8 普通の(普通ではない)翻訳/Traduzione(stra)ordinaria グラムシについて
9 リングア/ランゲージ
10 外国でのカルヴィーノ
あとがき 変容を翻訳する オウィディウス
謝辞
初出一覧
訳者あとがき
書誌情報
| 読み仮名 | ホンヤクスルワタシ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |
| 装幀 | Dan Callister/Photograph、新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 192ページ |
| ISBN | 978-4-10-590199-8 |
| C-CODE | 0397 |
| ジャンル | 文学・評論 |
| 定価 | 2,145円 |
書評
変容を続ける作家の到達点
なぜ、外国語で書くのか。創作という行為を能力の問題と考えれば、母語ではない言葉で書くのは困難をあえて引きうけることであり、なぜわざわざそんなことを、と疑問に思っても不思議はない。もちろん移民の場合、母語が話されるのは家庭の中だけで、一歩外へ出ればその国の公用語である別の言語に囲まれることになり、それが長じて自分の創作言語になることはままある。
インドオリジンのジュンパ・ラヒリの場合も例外でなく、ベンガル語で話す家庭に生まれながら、英語を創作言語としてアメリカでデビューする。ここまでは移民二世の作家に典型的な二言語状況だが、彼女に独特なのは、作家として名をなして随分経ってから、イタリア語での執筆もはじめていることだ。成人してから習いはじめた全くの外国語であり、最初は複数のネイティブチェックを経て掲載にいたっている。そもそも英語での執筆の際も、ベンガル語を話す人たちの物語を「頭の中で英語に訳す」ことで成りたっているという彼女は、創作の中にすでに複数の言語を複雑に絡ませていることになる。
本書『翻訳する私』は、そんな彼女がプリンストン大学で文芸翻訳演習を担当することになり、イタリア文学を英語に翻訳し、正真正銘の翻訳家になり、さらには自分がイタリア語で書いた作品を自分で訳すことになる時点で考えたことが綴られている。と言っても小説家のラヒリのこと、翻訳に関する技術的な事柄だけを巡るエッセイには留まらない。オウィディウスの『変身物語』の翻訳を通奏低音として、様々な変容が語られる。まずは翻訳される作品の変身。
ラヒリは「作家と翻訳家を兼ねることは、『ある』と『なる』の双方に価値を見ることだ」と書く。書かれて「ある」ものが、翻訳されることで別のものに「なる」。翻訳の醍醐味とは詰まるところこの「なる」にあるだろう。ある存在として自明であると思われているものがゆらぎ、別の言語のなかで異なる生を生きはじめる。一度きりの人間の生であれば不可能な変身が可能になる。翻訳者が翻訳をしつづけるのは、まさにこの変容に強く惹かれてのことだ。
しかし多言語の間を行き来することで姿を変えるのは作品だけではない。書き手自身もまた別の自分になる。「イタリア語で書くのは、解放感を求めてのことである」と彼女は説明するが、それが何語であれ、母語以外の言語で書くことは、生まれそだつにつれ習得する母の言葉のタブーから解放されることであり、母語以外を創作言語とするものは誰しもこのかけがえのない解放感を味わっている。
しかし作家としてこの変身を内に抱えることにはリスクも伴う。ジュンパ・ラヒリは「人は誰しも何かしら別のものを求め、探しに行きたくなる。顔を、ジェンダーを、住む街を変えることもできる」と、彼女のようなケースが誰にも起こりうるかのように述べているが、自分自身の変容を求める人はむしろ少数だろう。「想像という観点からは、安全ほど危険なものはない」と考え、「子供の頃から、わたしはわたしの言葉だけに属している。わたしには祖国も特定の文化もない」と断言するラヒリだからこそ飛び込める言語の境地がある。そこから生まれてくるのは、「物事への驚きの感情、驚愕がなくては、何も書くことはできない」と言いきる作家の文学だ。
そして、本書にはさらなる変容が重ねられる。それは、母語の化身である彼女の母親、ラヒリの創作の題材にもインスピレーションにもなったという人間の変身だ。彼女がオウィディウス『変身物語』のラテン語から英語への翻訳という大きなプロジェクトに取りかかったとき、彼女の母親は人生を終えようとしていた。彼女の死期が近づいていることを感じつつ、登場人物が変身を繰り広げる二千年前に書かれた文学を翻訳しながら、彼女は不思議な感覚を得る。それは、母親が彼岸に旅立とうとしているのではなく、今後はこの世界に異なる姿で存在しつづけるのかもしれない、ということだった。物語にも、登場人物にも、そしてもしかしたらこの世界の人間にも変身が可能だと信じることで、彼女は、母親の死をひとつの変身物語ととらえることができた。まるで、翻訳が、この世とあの世の間に橋を架けることができるかのように。文学における様々な多言語使用を論じた本書は、こうして、文学や物語への信を語る稀有な書物となった。
実際のところ、文学とは、世界の変容という奇跡を可能にするもの以外のなにものでもない。それが特に如実に現れるのが翻訳という作業であり、だからこそ人は、困難や、ときには無力感に打ちひしがれながらも、言語の間を行き来する翻訳という作業を今日も続けるのだろう。
(せきぐち・りょうこ 翻訳家、詩人、作家)
波 2025年5月号より
単行本刊行時掲載
関連コンテンツ
短評
- ▼Tawada Yoko 多和田葉子
-
「英語で執筆するインド系アメリカ人? ああ、そうですか」と人々はあまりにも簡単に納得してしまう。英国の元植民地に祖先を持ち、英語中心の大国アメリカの住人だから彼女は当然英語作家だ、と簡単に納得し、いつの間にか歴史や政治の押し付けてくる運命を肯定し、文化の真の多様性への驚きを忘れがちな私たち。個々のエクソフォニー体験には、接木みたいなゴツゴツとした手触りがあるはずだ。小説『その名にちなんで』で、したたかでチグハグな移民の生き様を見事に描いた作者が今、英語の外に出る静かな革命を企てた。
- ▼Chicago Review of Books シカゴ・レビュー・オブ・ブックス
-
著者が自己翻訳について重ねる思考に、つい引き込まれそうになる。……翻訳のみならず広く文芸批評へのラブレターとして読めるだろう。
- ▼Harper's Bazaar UK ハーパーズ・バザーUK
-
言葉があって自身を知る。その知識はいつでも拡大可能であるのだとわかる。
- ▼The Sydney Morning Herald シドニー・モーニング・ヘラルド
-
作家・翻訳家としてのラヒリの原動力は何なのか、その両面(二つの「容器」でもある)から、どのように啓発され、刺激されて、自己の再創造にいたるのか。そんな発見の旅に、読者もどっぷり漬かることになる。
著者プロフィール
ジュンパ・ラヒリ
Lahiri,Jhumpa
1967年、ロンドン生まれ。両親ともコルカタ出身のベンガル人。2歳で渡米。コロンビア大学、ボストン大学大学院を経て、1999年「病気の通訳」でO・ヘンリー賞、同作収録の『停電の夜に』でピュリツァー賞、PEN/ヘミングウェイ賞、ニューヨーカー新人賞ほか受賞。2003年、長篇小説『その名にちなんで』発表。2008年刊行の『見知らぬ場所』でフランク・オコナー国際短篇賞を受賞。2013年、長篇小説『低地』を発表。家族とともにローマに移住し、イタリア語での創作を開始。2015年、エッセイ『ベつの言葉で』、2018年、長篇小説『わたしのいるところ』を発表。2022年からコロンビア大学で教鞭を執る。
小川高義
オガワ・タカヨシ
1956年横浜生まれ。東大大学院修士課程修了。翻訳家。ホーソーン『緋文字』、ヘミングウェイ『老人と海』、ジェイムズ『ねじの回転』、ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『見知らぬ場所』『低地』、トム・ハンクス『変わったタイプ』、『ここから世界が始まる トルーマン・カポーティ初期短篇集』、エリザベス・ストラウト『ああ、ウィリアム!』など訳書多数。著書に『翻訳の秘密』がある。