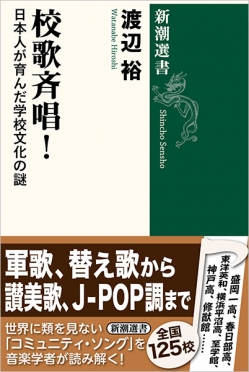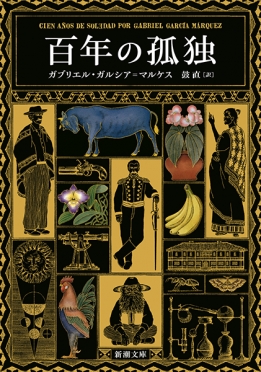髑髏となってもかまわない
1,210円(税込)
発売日:2012/05/25
- 書籍
- 電子書籍あり
人生の「ラスト20年」をどう生きるか? 死を覚悟した時に輝く生とは?
人は必ず死ぬ。にもかかわらず、現代の日本人は長生きこそ善とばかりに、死を不浄なものであるかの如く忌み嫌うようになってしまった。しかしかつての日本人は死生観をもって生き、だからこそ輝く晩年を送ったのではなかったか。良寛や芭蕉から鴎外、漱石、子規、茂吉、賢治まで、先人たちの末期を読み、彼らの「涅槃」を想う。
書誌情報
| 読み仮名 | ドクロトナッテモカマワナイ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮選書 |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮45から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 176ページ |
| ISBN | 978-4-10-603704-7 |
| C-CODE | 0395 |
| 定価 | 1,210円 |
| 電子書籍 価格 | 968円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2012/11/23 |
インタビュー/対談/エッセイ
波 2012年6月号より 日本人の奥底にあるもの
日本列島はモンスーン気候ですから、湿度が非常に高い。その気候的な特徴によって、発酵食品の文化も発達した。納豆、醤油、味噌、日本酒、いずれも素材を腐敗させ発酵させた結果、結晶体としての作品を作ることができた。
かつて日本にあった風葬も、戦前までは一般的だった土葬も、最後には遺体を微生物の分解に任せていた。それによって白骨結晶を手にしたのだが、最終的には骨まで溶けて土に帰る。それが芭蕉も書いた「野ざらし」の究極の意味でしょう。野にさらして、やがて土に帰る。最後には自然に帰るというのが、我々日本人の奥底に潜む感情だと思うんです。
故郷でもないのに、東北に対して郷愁を持つ人は多いですよね。なぜなんでしょうか? 山岳や田園の風景、名湯や食素材の豊富さのせいもあるんだろうけど、いつしか包み込まれるような、自分の故郷の原風景であるような気がしてしまう。演歌も東北を歌ったものが多いでしょう。
西行も芭蕉も東北にあこがれていました。芭蕉には「奥の細道」があるし、西行も平泉へ旅している。
二〇一一年に世界遺産に登録されましたけれど、岩手県の中尊寺にある金色堂には、藤原四代のミイラがおさめられています。ミイラは、阿弥陀堂という阿弥陀三尊を祀った須弥壇の下に祀られていました。これは、死者と生者の世界が非常に近いということを意味するわけです。生きている人間が、死後の世界と隣り合って生きているという、その二者の間に、格別の亀裂とか溝があるとは陸奥の人間は考えなかったんですね。
一方で、西国にあった王朝政権は、死者の世界と生きている者の世界というものを、画然と区別しました。平城京、平安京を見ればわかりますが、天皇が亡くなった時、宮中に葬るなんてことはしませんでした。王宮の外、古墳の形をとった。これはルーツをたどっていくと中国に辿りつきますが、その話はここではおくとします。
権力とは関係のない多くの人間は、日本列島のモンスーン風土において、最後は野に帰る、自然に帰るという死生観で長い間、生きてきました。だから、平泉の藤原政権が象徴しているような、生の世界と死後の世界の間に区別のない東国へのあこがれ、郷愁がにじみ出てきたのではないかと僕は考えているんです。
ところが近代以降、日本はさまざまなものを海外から受け入れてきた。思想、技術、宗教。そのおかげで、戦後豊かな国になることができたのも確かですが、一方で西洋の死生観に影響されるようにもなった。そのひとつがマルクスの言った「死は敗北である」という価値観です。
レヴィ=ストロースも構造主義の立場から西洋中心主義を批判しているなかでいっていることですが、僕も日本は重層構造だとすごく感じる。日本人は、上層部分は近代主義的な価値観に覆われているのだけれど、根底には「自然に帰る」という死生観がある。大切なのは、そうした感情が我々の心の奥底に巣食っていることを認識することだと思うんです。
死と向き合う
僕の父は岩手県で寺の住職をしていました。そのせいもあって去年、僕は被災直後の東北に行きました。海岸沿いの、あのすべてが破壊し尽くされた風景を目にして、しばし言葉を失いました。しばらくして、ふっと浮かんだ言葉が、大伴家持の「海ゆかば」でした。
海行かば 水漬く屍
山行かば 草生す屍……
この歌では「屍」という言葉が繰り返されます。しかし家持は、屍から離脱して山野、自然に鎮まっている魂の行方にじっと思いをひそめているんだと僕は思う。魂よ鎮まってほしいという思いがあの歌にはこめられている。被災地に立ってあの歌が頭に浮かんだ時、ああ、俺の身体の奥底に隠されていたベーシックな価値観が浮かび上がってきたんだと感じた。
この本の中には、多くの作家、歌人、俳人らが出てきます。若くして亡くなった人もいるし、自ら命を絶った人もいる。ただ、共通していることは、死ときちんと向き合っていた。やがて、ローソクの火がゆるやかに消えていくように、涅槃の願望を抱くようになっていったことがわかる。その後どう生を閉じていったかは人それぞれですが。
多くの人がそうだと思いますが、年をとるにしたがって、「自然」というカードが重要になってきます。人間が死ななければならないということを納得できる最大のありがたい存在は、「自然」です。春夏秋冬があるように、生まれた命はやがて朽ちていく。そして、つぎの生命を繋ぎ、再び芽吹いていく。
これは日本人の何千年の歴史の中、ずっと受け継がれてきた最もベーシックな感覚でしょう。本書は、最後は「自然」に帰ることができる、帰るべきところに帰りなさい、という本なんです。
担当編集者のひとこと
髑髏(どくろ)となってもかまわない
夕べには白骨となれる身なり 学生の頃に父親を亡くした。その時初めて、我が家が浄土真宗であることを知った。法事になると、お坊さんがやってきてお経を読み、浄土真宗の中興の祖である蓮如上人の「御文章」を、決まって最後に読んだ。その中のひとつのフレーズが、今も私の頭に残っている。
「朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり」
だいぶあとで、それは「白骨の章」という「御文章」の中でも有名な一篇であることを知った。
そのフレーズが、自分の深層に残っているせいなのかもしれないが、時々、美人だったり、口やかましい人と対峙する時、こんなことをしらっと思う。
「目の前にいるこの人も、やがては白骨になるのだなあ」
すると、絶世の美人の面の皮の奥にある、シャレコウベが見えてきたりする。口うるさいヤツも同じこと。そいつの場合は、髑髏の口あたりががくがく言ってたりして。
なんだか、そうすると、少しだけ気持ちが楽になる。美人を目の前にしたプレッシャーが少しばかり和らぐし、ガミガミ何かを訴えている人も、少しだけ許せる気持ちになってくる。
何の書物だったか忘れてしまったが、解剖学者の養老孟司さんが、「人間は致死率100%ですから」と書いていたことがある。うまいことを言うものだなあと思ったが、考えてみれば当たり前のことである。当たり前のことなのだが、果たして、どれだけの人が「100%、私は死ぬのだ」と意識して生きているんだろう。
少なくとも私は、40代までそうは思っていなかった。50歳を過ぎた今、さすがにいつかは死ぬのだなあとは思うけれど、それを強く意識して今を生きてはいない。
本書を読むと、「いつか死ぬのだ」と死を意識して生き始めると、今までとちがった安寧な生があることを、何人かの先達の人生を通して知ることとなる。
著者の山折哲雄さんは今、80歳を超えて、毎晩、少しばかり晩酌をして、9時くらいには床に就いてしまうという。その時、「ああ、明日の朝はもう目が覚めないかもしれないなあ」と、決まって思うのだと話してくれた。そして朝、無事に目覚めると、「ああ、今日も、生きられるのか」と思うのだそうだ。そのことを話してくれた山折さんの表情はとても穏やかで、そうして毎日生きていけるのも悪くはないなと思うのである。
本書を読むと、少しだけ、年をとるのが楽しみになってくる。
2016/04/27
著者プロフィール
山折哲雄
ヤマオリ・テツオ
宗教学者、評論家。1931(昭和6)年、サンフランシスコ生まれ。1954年、東北大学インド哲学科卒業。国際日本文化研究センター名誉教授(元所長)、国立歴史民俗博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。著書に『義理と人情 長谷川伸と日本人のこころ』『これを語りて日本人を戦慄せしめよ 柳田国男が言いたかったこと』『「ひとり」の哲学』など多数。