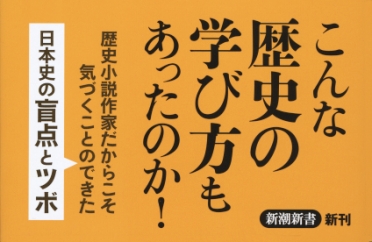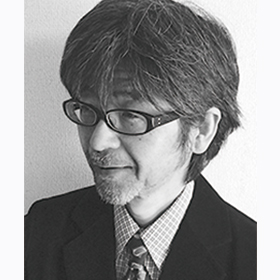秘伝・日本史解読術
880円(税込)
発売日:2017/05/17
- 新書
- 電子書籍あり
こんな歴史の学び方もあったのか! 歴史小説作家だからこそ気づくことのできた日本史の盲点とツボ。
こんな方法があったのか! 多くの人が早くから日本史につまずくのは何故か。歴史を学ぶのに欠かせない基礎トレーニングとは何か。縄文時代から幕末まで日本史の流れをたどりながら、真に押さえるべきポイントを解説。ときに中国史、朝鮮史もまじえ、古代史学の妄説や日本仏教への誤解なども追究し、作家ならではの視点で傑作、名作歴史小説の読みどころも開陳。誰でも日本史がすっきりわかる秘伝をここに伝授する。
書誌情報
| 読み仮名 | ヒデン・ニホンシカイドクジュツ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 波から生まれた本 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 256ページ |
| ISBN | 978-4-10-610716-0 |
| C-CODE | 0221 |
| 整理番号 | 716 |
| ジャンル | 日本史 |
| 定価 | 880円 |
| 電子書籍 価格 | 880円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2017/05/26 |
インタビュー/対談/エッセイ
奇想を育むためにも、もっと史実を
ずっと「伝奇時代小説」という特殊ジャンルで書いて参りましたが、初めて歴史指南、歴史時代小説指南めいた本を出すことになりました。
わたしの伝奇時代小説といったら、まず朝鮮柳生であり、妖術師や怪獣が跳梁跋扈し、徳川家康の影武者が文禄の役の韓人捕虜であったり、シスコンの柳生十兵衛がエロな夢を見て夢精し褌を汚したり、敵剣士のペニスを瞬時に三段切りにしてダンゴ三兄弟のように串刺しにしたり――と、そんな荒唐無稽で顰蹙もの。良識ある読者にはやりすぎと眉をひそめられ、疎んじられる作品ばかりですので、今回の新書も愛読者の方々におかれましては非常な期待をお寄せくださっているものと拝察いたします。タイトルに「秘伝」の2文字が入っているからにはなおのことでしょう。
けれども、まことに申しわけないのですが、そのような持ち味は構えて慎みました。日本史を学び、歴史時代小説をより楽しむためには、どんな方法があるのかというメソッドを極めてまじめに開陳した内容だからです。けっ、伝奇を売り物にしているような野郎が、そのようなものを書けるはずがない、読むに値しねえ、ネタなくして何が荒山徹ぞ、という声には敢えてこう反論いたしましょう。
伝奇時代小説は一見すると史実から遊離して奔放な面白さを紡いでいるかに見えて、その実、史実と表裏一体なのであり、史実の厳しい掣肘、制約、拘束、羈絆を受けています。史料と史料の間の矛盾が奇想を生み出し、その奇想がどれほど荒唐無稽に展開しようとも、最終的には史実に着地し、還元、終熄する――というのが正しい伝奇時代小説です。史実という花壇に発芽し、妖しく咲き誇る奇想の花なのです。
奇想を育むためには史実という土壌の手入れが欠かせません。そのようなわけで、長らく歴史に苦手意識を持っていたわたしですが、史実の庭師となって丹精を尽くすうち、気がつくと「歴史って面白いよ。こんな学び方があるんだよ」と少しは人さまに語れるようになっていました。その一端を臆面もなく披瀝することにしたのが今回の新書です。歴史はどうしたら効率よく、しかも面白く学べるのかの技術や、そうして得た「背景知識」で読みなおす歴史時代小説の新しい楽しみ方などをつづりました。歴史教育、歴史認識などについても歯に衣着せず書きました。
(あらやま・とおる 作家)
波 2017年6月号より
担当編集者のひとこと
人が、日本史につまずくのは何故か? 作家が明かした学習法とは?
著者の荒山徹さんは、歴史小説作家として戦国時代や幕末などを舞台に、柳生一族や真田一族などが妖術、忍術、陰陽術を駆使して闘うといった、いわゆる「伝奇小説」分野の作品を多く書いてきていらっしゃいます。
となると、その作者が書いた歴史の本なんて、またトンデモナイものでは、と思われるかもしれませんが、本書はじつに「正統派」です。
荒山さんは、小説作品で「奇」をきちんと際立たせるためには、むしろその基礎となる歴史知識はきちんと固めなければならないと、作家になられてからも歴史をどう学ぶかに苦心惨憺したと言います。つまり本書は、その苦心の末に得た「解読術」を惜しげもなく開陳し、読者の皆さんに秘伝しようというものなのです。
たしかに、荒山さん同様に日本史には関心があるのに、一方で、「年代や用語が絡み合って、どうしても頭にすっきり入って行かない」と言う人も多いのが現状です。荒山さんは、教科書に沿った歴史の学びが、基礎トレーニングを抜きにして、いきなり旧石器時代の細々とした事項の解説から始まるのが、そもそも歴史嫌いを生み出す原因ではないかと指摘します。
それでは、歴史の基礎とは何か? たとえば、5W1Hをきちんとおさえることだと荒山さんは説きます。そう言われると、「やっぱり年代暗記か」と思われるかもしれませんが、そうではありません。When(いつ)にばかり気を取られ、他の4W1Hを軽視しているのが、歴史教育の落し穴ではないかと指摘するのです。
なるほど、とくにWhere(どこ)などというのは結構軽視されているようです。歴史では必ず出てくる出雲、武蔵などという旧国名も、教科書の見返しなどには一覧図が載っていたりしますが、これをきちんと習った記憶のある人は少ないはず。「摂津とは今のどこですか?」と聞かれて、パッと答えられない人は結構多いのでは。最近、NHKの「ブラタモリ」が人気なのも、歴史と地理が融合されないままだったことへの反動なのでしょう。
この他、中国史や朝鮮史、さらには歴史小説の名作、傑作などもまじえながら、日本史の奥深さを見せてくれる本書。歴史好きの人にも、歴史嫌いの人にも、どちらにもおすすめできる一冊です。
2017/05/25
著者プロフィール
荒山徹
アラヤマ・トオル
1961(昭和36)年富山県生まれ。上智大学卒。新聞社、出版社に勤務の後、韓国へ留学して朝鮮半島の歴史・文化を学ぶ。帰国後の1999年に『高麗秘帖』で作家デビュー。伝奇的な作風の歴史小説でとくに注目される。主な作品に『白村江』『柳生大作戦』『魔風海峡』など。