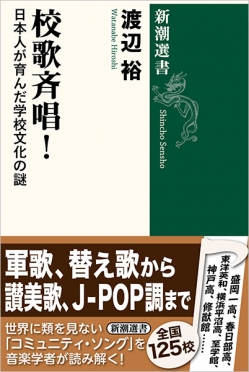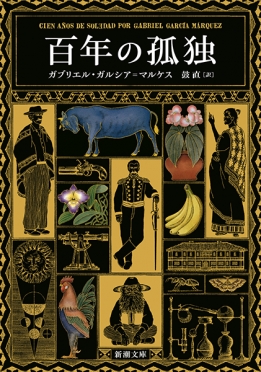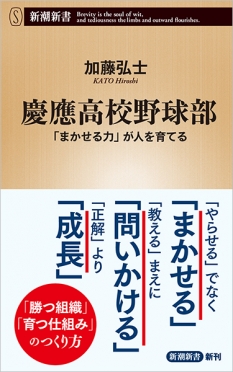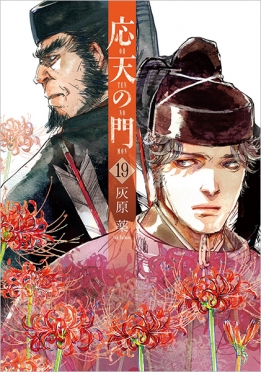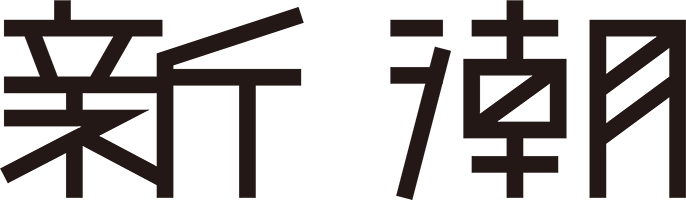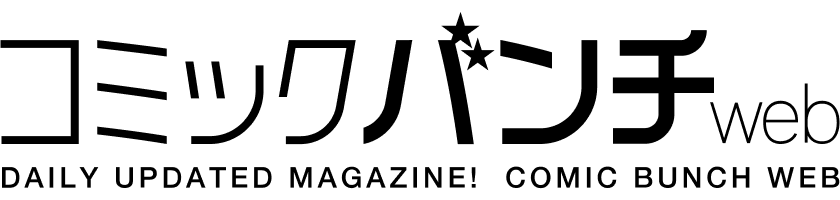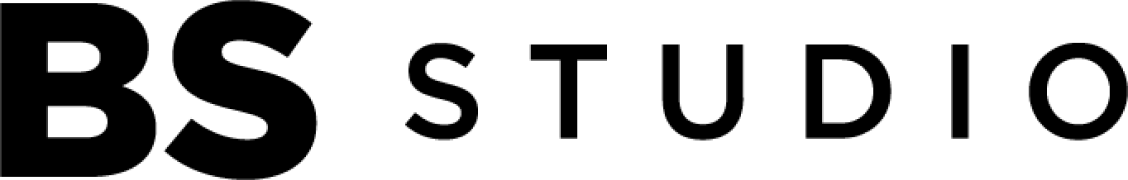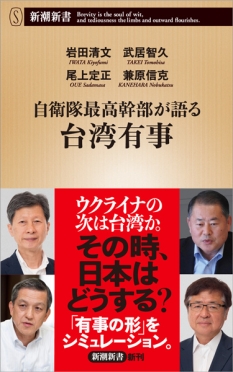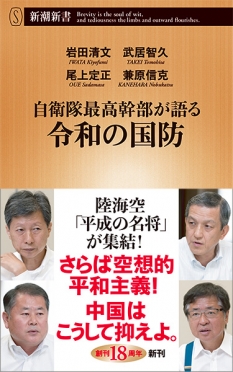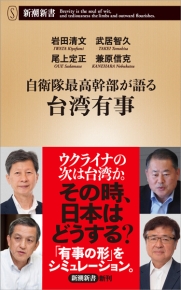
自衛隊最高幹部が語る台湾有事
990円(税込)
発売日:2022/05/18
- 新書
- 電子書籍あり
ウクライナの次は台湾か。その時、日本はどうする? 「有事の形」をシミュレーション。
現実味を増す台湾有事に備え、自衛隊の元最高幹部たちが「有りうるかも知れない有事の形」をシミュレーションしてみた。シナリオは、グレーゾーンでの戦いの継続、物理的な台湾の封鎖、全面的軍事侵攻、終戦工作の4本。実際に有事が発生したら政府は、自衛隊は、そして国民は、どのような決断を迫られるのか。リアルなストーリーを通じて、「戦争に直面する日本」の課題をあぶり出す。
書誌情報
| 読み仮名 | ジエイタイサイコウカンブガカタルタイワンユウジ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 304ページ |
| ISBN | 978-4-10-610951-5 |
| C-CODE | 0231 |
| 整理番号 | 951 |
| ジャンル | ノンフィクション |
| 定価 | 990円 |
| 電子書籍 価格 | 990円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2022/05/18 |
薀蓄倉庫
台湾人のアイデンティティ
台湾で初めて総統の直接選挙が実施されたのは1996年。台湾が完全な民主主義国になってから生まれた子供たちが、すでに成人になりはじめています。本書の中で、元外交官の兼原氏は、こう述べています。「台湾の人に『何人ですか?』と聞くと、10年前は『台湾人兼中国人』と言っていましたが、今では9割以上が『私は台湾人です』と言い切ります」。「台湾独立」は政治的なハードルが高いですが、意識の上では台湾人の「独立」はすでになされているようです。
掲載:2022年5月25日
担当編集者のひとこと
ウクライナの次は台湾?
ロシアによるウクライナ侵略が続く中、「次に狙われるのは台湾ではないか」との懸念も高まってきています。「争うのは台湾と中国でしょ? 日本は関係ないね」などと思ったら大間違い。台湾有事が発生したら、日本も否応なく巻き込まれることになります。
台湾と、日本の最西端の与那国島の間の距離はわずか110キロ。これは、航空戦が行われるとしたら「同じ戦域」に括られる近さです。しかも、中国が台湾占領を狙うとしたら、事前に周辺地域の「整理」にもかかるので、尖閣諸島の領有はもちろん、先島諸島にも陸上部隊が送られてくるかも知れません。沖縄の米軍基地も、ミサイル攻撃のターゲットになるかも知れない。中国の内陸部には、嘉手納基地を模した軍事訓練施設があることはすでに知られています。
「いや、さすがにそこまでハードな軍事侵攻はないんじゃね? 中国共産党もウクライナを見て学んだはずだし」と思うかも知れませんが、独裁者の頭の中は誰にも分からない。また、仮に直接的な台湾への軍事侵攻はなかったとしても、中国が台湾海峡やバシー海峡を扼して台湾を孤立化させ、日本のシーレーンも断ち、サイバー攻撃や情報戦などの準軍事的な手段を使って「じわじわ」台湾を締め上げる、というシナリオもありえます。実際、サイバー攻撃や情報戦について言えば、我々はすでに戦時とも平時とも言えないグレーゾーンの中にあるわけで、中国がその強度を上げてくる、ということは十分に考えられるのです。
では、実際の有事の形はどうなるのか。その時、日本はどのような対応をすべきなのか。日本に十分な備えはあるのか。それを探るために、本書の著者たちは東京・市ヶ谷の「日本戦略研究フォーラム(JFSS)」において、台湾有事に関する政策シミュレーションを企画しました。
このシミュレーションは、安全保障に関する知見を有する現職国会議員や、近年まで日本国に奉職していた政府関係者の参加を得て、昨年の8月14日、15日の二日間にわたって実施されました。その様子は、同年12月に放映された「NHKスペシャル 台湾海峡で何が〜米中“新冷戦”と日本〜」でも取り上げられているので、御覧になった方もいるかも知れません。
本書は、その政策シミュレーションに基づいたシナリオ(全4本)を再掲する第一部と、著者たち4人による「振り返り座談会」を掲載した第二部の二部構成になっています。
第一部では、事態に対して決断を迫られる「国家安全保障会議」でのやりとりが何度も出てきます。限られた情報、刻々と変化する状況の中で、どのような決断を迫られるのか。高みの見物ではなく、近未来に起こりうるリアルな事態を想像しながら、「自分ごと」として考えながら読める構成になっています。
本書の編集を通じて学んだことはいろいろあるのですが、最も強く思ったのは、「果たして日本の政治に、戦争という事態をマネージできるのだろうか?」ということでした。
戦争に直面しても、自衛隊の手足を縛っている日本では、「事態認定」をしないと弾を撃つことすらできません。しかし、戦場においては状況は常に変化する。「事態認定」をめぐって小田原評定をしている間に敵の攻撃が始まっていた、領土を取られていた、という事態が発生しうるのです。本書で展開されているシミュレーションを見ると、そんな日本の現状が見えてきます。
戦争がマネージできないのなら、「そもそも中国に付け入る隙を与えないくらい、日米台で準備を完璧に整えておく」という選択が正しいように思えますが、その面でも問題は山積みです。具体的にどんな問題があるかは、第二部の座談会で詳しく触れられています。
本書は、昨年4月に刊行して好評を博した(4刷2万1000部)『自衛隊最高幹部が語る令和の国防』の続編、台湾有事限定版としても読むことができます。ユーラシア大陸で起きている19世紀みたいな戦争が東アジアで起こらないことを望みますが、戦争を起こさないためにも戦争の準備を怠るわけにはいきません。こうした軍事のパラドックスはなかなか理解されにくいですが、戦争をリアルに考えてきた自衛官の言葉がもう少し世間に聞かれるようになれば、軍事問題に関する常識も変わってくるかも知れません。
ぜひご一読ください。
2022/05/25
著者プロフィール
岩田清文
イワタ・キヨフミ
1957年生まれ。元陸将、陸上幕僚長。防衛大学校(電気工学)を卒業後、1979年に陸上自衛隊に入隊。戦車部隊勤務などを経て、米陸軍指揮幕僚大学(カンザス州)にて学ぶ。第71戦車連隊長、陸上幕僚監部人事部長、第7師団長、統合幕僚副長、北部方面総監などを経て2013年に第34代陸上幕僚長に就任。2016年に退官。著書に『中国、日本侵攻のリアル』(飛鳥新社)がある。
武居智久
タケイ・トモヒサ
1957年生まれ。元海将、海上幕僚長。防衛大学校(電気工学)を卒業後、1979年に海上自衛隊入隊。筑波大学大学院地域研究研究科修了(地域研究学修士)、米国海軍大学指揮課程卒。海上幕僚監部防衛部長、大湊地方総監、海上幕僚副長、横須賀地方総監を経て、2014年に第32代海上幕僚長に就任。2016年に退官。2017年、米国海軍大学教授兼米国海軍作戦部長特別インターナショナルフェロー。2022年5月現在、三波工業株式会社特別顧問。
尾上定正
オウエ・サダマサ
1959年生まれ。元空将。防衛大学校(管理学)を卒業後、1982年に航空自衛隊入隊。ハーバード大学ケネディ行政大学院修士。米国国防総合大学・国家戦略修士。統合幕僚監部防衛計画部長、航空自衛隊幹部学校長、北部航空方面隊司令官、航空自衛隊補給本部長などを歴任し、2017年に退官。2022年5月現在、API(アジア・パシフィック・イニシアティブ)シニアフェロー。
兼原信克
カネハラ・ノブカツ
1959年山口県生まれ。同志社大学特別客員教授、笹川平和財団常務理事。東京大学法学部卒業後、1981年に外務省入省。フランス国立行政学院(ENA)で研修の後、ブリュッセル、ニューヨーク、ワシントン、ソウルなどで在外勤務。2012年、外務省国際法局長から内閣官房副長官補(外政担当)に転じる。2014年から新設の国家安全保障局次長も兼務。2019年に退官。著書に『歴史の教訓』『日本人のための安全保障入門』など。