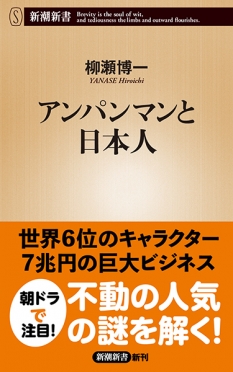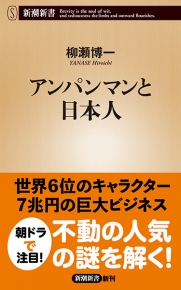
アンパンマンと日本人
968円(税込)
発売日:2025/03/17
- 新書
- 電子書籍あり
世界6位のキャラクター。7兆円の巨大ビジネス。朝ドラで注目! 不動の人気の謎を解く!
乳幼児の人気は不動のトップ、アニメや本におもちゃや食品など関連グッズを含めれば今や7兆円の巨大ビジネス。おなかが空いた人に自分の顔を食べさせる不思議なキャラクター、アンパンマンはどのように誕生し、国民的ヒーローとなったのか。愛する人たちとの別れ、過酷な戦争体験、幾多の天才からの高い評価、最愛の妻の支え……生みの親である漫画家やなせたかしの生涯をたどりながら、その秘密を解き明かす。
はじめに
第1章 世界6位、7兆円の巨大ビジネス
平成以降のヒーロー/テレビアニメで大ブレイク/不動の国内ナンバーワン人気/学生の87%がアンパンマン消費者/日本の乳幼児中心なのに世界6位/年間1500億円のキャラクタービジネス/本格化する海外展開/「幼児は大人のグループの中にいる」/泣き声がピタッと止まる/平日でも予約完売のミュージアム/最高のベビーシッター/私費を投じた記念館/妻・暢への感謝と鎮魂
第2章 高知の自然とデザインと死と
文化資本に恵まれた家庭環境/挿絵と抒情画と漫画/漫画家を志した決定的瞬間/ふるさとの風景、先駆的なデザイン/愛する肉親たちの相次ぐ死/東京高等工芸学校で学んだ商業美術/学校と銀ブラで身につけた現場主義/製薬会社のサラリーマン、そして従軍/屑屋稼業から編集者に転身/全てをこなした『月刊高知』時代/生涯の伴侶、小松暢との出会い/三越の包装紙と『まんが入門』/目標は新聞連載の4コマ漫画/手塚治虫らと劇画の台頭/ビールのキャラクター「ビールの王様」/「困ったときのやなせさん」/週刊朝日の漫画賞と「ボオ氏」
第3章 アンパンマンはこうして生まれた
最初の登場はラジオコント/アンパンを買ってくれたおじさん/中国戦線、仲間の死、紙芝居/「喰わないと死ぬ」という当たり前/敗戦とともに消えた「正義」/正義は逆転するが、空腹は真実/アンパンマンの母「やさしいライオン」/「子ども向け」には作らない/スーパーマンの否定形/向こう見ずなロイス・レイン=小松暢?/「本当の正義」を示した「怪傑ゼロ」/中年スーパーマン「アンパンマン」誕生/絵本『あんぱんまん』誕生/顔を食べさせるという発明/「残酷」「くだらない」評判は最悪/幻の大傑作『熱血メルヘン 怪傑アンパンマン』/敵役「ばいきんまん」誕生/そして奇跡が始まった/発見したのは幼児たち/当初大反対にあった「それいけ!アンパンマン」/盛り上がらない現場、妥協しない作品づくり/高視聴率でそのまま37年続く/アンパンマンのマーチが被災地の心の支えに
第4章 天才たちが愛した天才、やなせたかし
「遅すぎた」ではなく「早すぎた」天才/自宅に押しかけた永六輔/宮城まり子の舞台衣装/いずみ・たくと「手のひらを太陽に」/羽仁進が命じたラフストーリー/若き向田邦子と「父の詫び状」の挿絵/サンリオの創始者、突然の来訪/詩集『愛する歌』がベストセラーに/手塚治虫と「千夜一夜物語」/キャラクター創造術の原点/天才たちが見込んだ「勇気と好奇心」/頼まれ仕事で母屋を乗っ取らない/ライフワークとしての『詩とメルヘン』/メルヘンの会社に変身したサンリオ/アンパンマンは、やなせたかしだった
第5章 「困った人を助ける」利他的本能
「お客さん」がいるかいないか/ご当地キャラは全国で200/震災で注目された「詩」の力/「やなせメルヘン」の誕生/絵のデザイン、ことばのデザインの集大成/アンパンマン=人工知能=AI?/「ポカポカする」/人間にある普遍的な利他性
おわりに
書誌情報
| 読み仮名 | アンパンマントニホンジン |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-611080-1 |
| C-CODE | 0270 |
| 整理番号 | 1080 |
| ジャンル | 自伝・伝記、アート・建築・デザイン |
| 定価 | 968円 |
| 電子書籍 価格 | 968円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/03/17 |
書評
アンパンマンで語る野心的な「戦後文化論」
「アンパンマン」についての紋切り型の理解はざっと以下のようなものだろう。アンパンマンはお腹が空いている子供たちに、自らの「顔」を与える。決して正義の名の下に悪を撃つことに酔うタイプの、ありふれた幼稚な「ヒーロー」ではなく、あくまで空腹者に自己犠牲を払い手を差し伸べる真の強さと正しさに溢れた本当の「ヒーロー」なのだ、と。これにやなせたかしの戦争体験のエピソードを加えてそこに「戦後民主主義の精神」でも見出せば完璧だ。
嫌味な書き方をしたが、本書の著者柳瀬はこうした紋切り型の理解を「否定」しはしない。それはやなせたかしの人生を振り返れば、自ずと見えてくる背景であり、アンパンマンとは作者の戦争体験から与えられたものとその後に経験した戦後民主主義が輝いていた時代のメンタリティを踏襲したものであることは自明だからだ。
しかし本書がこうした紋切り型の「文化論」に収まらない長い射程をもつのは、そのクリエイションの背景を総合的に探究しているからに他ならない。本書はこうした幼児向けの作品としては異様にイデオロギッシュな姿勢を含め、なぜこのようなある意味奇異(であるにもかかわらず、長く、広く愛されるよう)なキャラクターが生まれたのか、そのメカニズムを問うものに視点をアップデートする一冊なのだ。
おそらく次期の「朝ドラ」の題材となることでよりひろく知られることになるやなせたかしの(今日でいうところの)マルチクリエイター性を、著者柳瀬は当時のメディアの世界の手探りの、しかし爆発的な拡大への否応なき対応の結果として位置付ける。
物語作家として、詩人として、そしてデザイナーとして、縦横無尽に活躍してきたやなせたかしだが、そのアイデンティティはあくまで「漫画家」であった。しかし手塚治虫以降のストーリーマンガに国内市場は席巻され、ひと世代前の一コママンガを得意としていたやなせたかしはテレビや広告デザイン、音楽など周辺の文化産業でその才能を発揮せざるを得なかった。それが彼の「マルチ」な能力を育てたというのが本書の見立てであり、そしてその見立ては取り上げられる伝記的エピソードからも、作品内の表現の分析からも極めて説得力がある。
そして、やなせたかしが結果的に手がけることになった「絵本」のなかで生まれたアンパンマンには、やなせの思想とさまざまな分野の仕事で培われたスキルが当然のように注ぎ込まれた。誕生後のアンパンマンは昭和末期の、消費社会化する日本の幼児たちの心を少しずつ捉えていく。そしてバブル経済の絶頂期にテレビアニメ化されたアンパンマンは、そのブレイクにより今日に至るまで、全国の幼児たちの心を掴み続けている。
ここまで来れば、本書の裏テーマともいうべきものも、そして著者柳瀬のメタ・メッセージも明白だ。本書は「アンパンマン」というキャラクター成立の背景を探る文化論であり、同時に戦後論でもあるのだ。
もはや「日曜劇場」をポルノ的に消費して当時の記憶を上書きしてしまった老人たちくらいしか信じていない「ジャパン・アズ・ナンバーワン」的な物語をある種の「ケア」として「あの頃は良かった」と持ち上げるのも、こうした欺瞞を叩きのめして「そんなものは幻想だ」と批判するのも簡単だ。しかし本当に大事なのは「あの頃」から、今を生きる僕たちが何を持ち帰るかなのではないか? 端的に言えば著者柳瀬はその代表としてアンパンマンとやなせたかしの仕事を取り上げているのではないか。
戦後日本の達成と限界をフェアに吟味した上で、「あの頃」にしか絶対に成立せず、それでいてこの2020年代の「いま」も通用する作品から「戦後」というものの、あまり語られてこなかった側面にスポットを当てているのではないか。それはわかりやすく述べれば拙速さと混沌さが、半ば暴力的に人間の創造性を育んでいた時代の豊かさのようなものだ。その側面を描き出す試みは本書において、アカデミックな視点とジャーナリスティックな語り口を器用に使い分けながら実現されている。ノスタルジックな戦後文化「語り」のなかでハートフルなエピソードが先行してしまいがちな当時のカオティックなメディアの現場を平易に、しかし芯を食った分析を伴って提示する、リーダブルだが、総合的で、そして野心的な仕事……この巧みさと強いメッセージを両立させる著者「柳瀬」博一の手捌きに、本書が伝えるかつての「やなせ」たかしの姿を、多くの読者は重ね合わせざるを得ないだろう。
(うの・つねひろ 批評家)
「7兆円ビジネス」アンパンマンの深み
「大正」生まれの作家やなせたかしが、「昭和」の戦争経験を通じて生み出したアンパンマンが、「平成」のテレビアニメ化後に人気になった。約1世紀にも及ぶやなせたかしの人生と並走するだけで、日本自体のめくるめく100年史を追体験するかのようだ。「アンパンマンと日本人」という本タイトルにはそうしたメッセージが込められているように思う。
1973年発行の絵本で確立されたアンパンマンというキャラクターが大人気となるのは1988年のアニメ化以降、平成に入ってからのことだ。ゆえに、その人気を世代的に知らない方も多いと思うのだが、平成にはいってから0~12歳の子供がいる親へのアンケートでアンパンマンはほとんど1位、断トツの認知度を誇っている。
そして、その人気はビジネス面にも反映されることになる。フレーベル館がやなせ氏と生み出した子供向けの絵本の発行部数はすでに8000万部を超えていて、トムス・エンタテインメント社の制作したアニメが日本テレビの電波にのって拡散され、そのままバンダイやアガツマ、ジョイパレット、セガトイズといった玩具・グッズメーカーの手により商品化された。1996年に故郷の高知県で“自費”も投じてやなせ氏がつくったアンパンマンミュージアムは毎年10万人が来場するテーマパーク的な機能を担ったが、それが2007年の横浜から、名古屋(2010年)、仙台(2011年)、神戸(2013年)、福岡(2014年)と日本中に広がり、6カ所のミュージアムに毎年来場する人数は約300万人クラスとなる。こうしたビジネスの連鎖によって“30年近くアンパンマングッズ市場は1500億円を下回ったことがない”というほどの経済圏を確立した。
これは『ドラゴンボール』や『NARUTO』などの集英社トップ作品よりも大きな規模である。アメリカの金融会社による調査では、アンパンマンが成立させたビジネスはキャラクター別に見た推計で世界6位、2018年時点で累計600億ドル(当時の為替レートで6・6兆円)。バットマンやスパイダーマン、ディズニープリンセスを上回る。なにより驚くのは、この規模でありながらほとんどが日本国内の売上で、対象は乳幼児限定ということだ。そして、大市場の中国では2023年に「ウルトラマン」『名探偵コナン』などを展開・成功させたSCLA社が初めてライセンス契約を締結したくらいで、まさにこれから中国を中心にアジアや欧米にアンパンマンが新規展開していこう、という状態にあるのだ。このビジネスモデルに言及したことも、本書の大きな功績である。
なぜ、これほどアンパンマンは子供たちに人気があるのか? その理由を、本書を読んでようやく得心した。大正、昭和、平成とやなせたかしの人生が投影された「深み」が作品に通底しているのだ。
食わないと死ぬという過酷な戦争体験、父も母も弟も喪い、ひたすら働き続けたやなせ氏。マンガ家の同期たちの背中は遥か遠く、コンプレックスも入り交じりながら70歳を過ぎて初めて花開いた『アンパンマン』。自ら犠牲になってその身を差し出さないことには、本当に相手を救うことはできないし、正義と悪は表裏一体、決して悪を一方的に裁くことなどできないのだ。あんぱんの外側は洋食のパンでも、中身は国産のあんこ。アンパンマンには、大正モダニズムから戦前、戦中、アメリカの占領期、戦後までの様々な要素が詰まっている。そんなヒストリーは令和の今だからこそもう一度見直されるべきである。
本当に大事なことは、時間をかけて、届く人には届く。「なんのために生まれて なにをして生きるのか こたえられないなんて そんなのは いやだ!」、日本一有名ともいえるやなせ氏自身が作詞を手掛けたこのマーチは、東日本大震災でも多く歌われた。「ぼくは感動しましたね。自分の歌がね、いくらか役に立ったと思って、ほんとうに感動しました」といったやなせ氏が残した言葉など、多岐にわたるエピソードが本書にはおさめられている。
奇しくもそんなやなせたかしと同じ姓をもつ柳瀬博一氏は、編集者として『ポケモン・ストーリー』などでキャラクター創造の裏側を解き明かし、自身がマルチクリエイターとしてカワセミから国道から教育まで、博覧強記に執筆活動を続けている。そんな彼がまとめあげた『アンパンマンと日本人』はまさに才能が引き合って生まれたとしか思えない出来で、アンパンマンの「深み」を見事に表現している。NHK連続テレビ小説「あんぱん」とともに、ぜひ彼の筆致を通して大正/昭和/平成の日本とやなせたかし夫妻やアンパンマンの歩みに、いま一度令和の目線から向き合ってほしい。
(なかやま・あつお エンタメ社会学者)
蘊蓄倉庫
キティちゃんとやなせたかしの深い関係
やなせたかしはアンパンマンが大ブレイクする前から、手塚治虫や立川談志、宮城まり子、いずみ・たく、向田邦子ら多くの天才たちから愛されてきましたが、キティちゃんで有名なサンリオの創始者・辻信太郎氏とも深い深い関係でした。
辻氏が商品のデザインを頼むために、やなせたかしの元を訪れたのが関係の始まり。その後、辻氏はやなせたかしの詩集を大ヒットさせ、やなせは1973年に雑誌『詩とメルヘン』を立ち上げ、サンリオから出版します。そのあたりからサンリオは一気に巨大企業に成長し始め、1974年には「ハローキティ」を開発、1970年代後半にはハローキティブームが訪れます。そのサンリオ社躍進の核として『詩とメルヘン』の存在があった、とやなせは確信していました。雑誌によるブランドイメージの向上により優秀な人材が集まり始め、それがキティちゃんの誕生・発展につながったというわけです。やなせたかしとサンリオ社の出会いがなければ、キティちゃんも生まれてなかったのかもしれません。
掲載:2025年3月25日
担当編集者のひとこと
なぜうちの子は、あんなにアンパンマンが好きだったんだろう?
数年前、当時妊娠していた妻と、「アカチャンホンポ」に各種用品を買いに行ったことがありました。そこで、アンパンマン関連商品のあまりの寡占的存在感に圧倒され(とにかくアンパンマンだらけなんです)、それ以来、アンパンマンはなぜこんなに支持されるのだろうか、という疑問を持ち続けてきました。
そこへ2025年度の朝ドラが「あんぱん」に決まったという報道です。以前からの疑問に答える本を出したい。誰がこの疑問に答えてくれるだろう? もしかしたら、博覧強記の柳瀬さんなら期待に応えてくれるかもしれない。とりあえずキャラタービジネスや、サブカル的な観点からの興味はお持ちだろう、と恐る恐るメールしたところ、柳瀬さんからは「これから行きます!」と返答があり、こちらのメールから30分後には弊社で打ち合わせが始まっていました。びっくり仰天の展開。柳瀬さんも、娘さんが幼いころになぜあんなにアンパンマンを好きだったのだろうか、という疑問を持ち続けていたとのことでした。
2025/03/25
著者プロフィール
柳瀬博一
ヤナセ・ヒロイチ
1964年、静岡県浜松市生まれ。東京科学大学教授(メディア論)。慶應義塾大学経済学部卒業後、日経BP社入社。2018年より現職。『国道16号線』『カワセミ都市トーキョー』『上野がすごい』(滝久雄と共著)『「奇跡の自然」の守りかた』(岸由二と共著)など著書多数。