第20回 日本ファンタジーノベル大賞
主催:読売新聞社 清水建設 後援:新潮社 発表誌:「小説新潮」
第20回 日本ファンタジーノベル大賞 受賞作品
大賞
天界の都 ある建築家をめぐる物語
※「天使の歩廊 ある建築家をめぐる物語」に改題
優秀賞
彼女の知らない彼女
第20回 日本ファンタジーノベル大賞 候補作品
| 大賞 天界の都 ある建築家をめぐる物語※『天使の歩廊 ある建築家をめぐる物語』に改題 | 中村弦 | |
|---|---|---|
| 龍守の末裔 | 真山遥 | |
| イデアル | 松崎祐 | |
| 優秀賞 彼女の知らない彼女 | 里見蘭 |
選評

荒俣宏アラマタ・ヒロシ
意欲的なテーマの挑戦に拍手
第二十回を迎えた賞にふさわしい、じつに意欲的なテーマに取り組んだ作品が二本そろい、選考委員としても心躍る読書体験となった。『イデアル』は、いわば現代哲学や科学技術の発展を支えた数学が、秘術として非公開となっている世界を描く。難解な数学問題を解く競技会に参加する女性数学師をめぐる物語だ。宇宙や運命までが数学でどう表現されるかという課題をファンタジーに持ち込んだ蛮勇に、心底ほれ込んだが、しかし大きな不満も感じた。数学への考察が、競技会の課題という枠を脱しきれず、物語全体を解明する「手がかり」になっていない点だ。たとえば、難問の証明が女性的発想(物語では女性は数学師になれない)の関与によってしか達成できない、といった結末になれば、どんなに興味深い傑作になっていたろうか。数学理論と男女の運命をも関係づける、真にプラトン的な力業に拡大されることを、切に期待したい。この作者には、その力がある。
『天使の歩廊 ある建築家をめぐる物語』も、建築という画期的なテーマを引っさげての本賞挑戦に拍手した。しかも、時代設定など、わたしの個人的な趣味にも合致し、読書中は終始楽しかった。しかし、読了の際に大きな失望も味わわされた。最大の問題は、建築家が設計する建築物がどれも単に装飾的な怪奇味を越えておらず、建築に潜む神秘性や危険性にまで踏み込んでいないことだ。この作者に新しい伝奇ロマンの開拓者となる素質を見たものとして、あえて書きたい。残念なことに、ここに登場する建物は、たとえば浄瑠璃寺にある日時計としての菩薩像や、パリ万博のエッフェル塔改造計画など現実にあった奇想建築に比べ、「構造的」な発想を欠いている。たとえば、作中の建築家は天界へ届かせる建物に天使像を置く。だが、天使像の本質は天界をイメージさせる装飾にすぎない。それだけなら、画家の仕事である。いっぽう、立体すなわち空間を創始する建築家は、「天使的な構造」を想像できなければいけない。エッフェル塔は、まさに重力に逆らって天へ伸びたアーチ型という「天使的構造」だったから、意味があった。これがないと、主人公は怪奇建築の設計家にはなりえても、神聖な天界を招き寄せ、心病んだ人たちを癒せるような夢の建築家にはなりえない。大賞受賞で驕ることなく、さらなる完成をめざしてほしい。
ともあれ、大テーマを選んだ二人はすばらしい。あとの二編は一転して、すらすらと読み進められる作品で、物語自体のおもしろさが勝負となった。『龍守の末裔』は変形の学園小説とも読め、目下コミック界に流行するテイストとも一致する。悪くはないが、読んだら記憶から消える綿飴のようなはかなさだった。龍守という設定も、ちょっと持て余した。いっぽう『彼女の知らない彼女』は、これまたおどろくぐらいフツウ感覚あふれる「タイムトラヴェル」ものだった。「フツウ」で始まるファンタジーは、多くは、「異常」で終わるのだが、この作品は後半がもっと本格的にフツウなスポーツ小説となる。パラレルワールド体験すら主人公たちには「ただ昨日のこと」にすぎないようにみえる。だが、このアッケラカンとしたフツウさが、普通ではないのだ。この作品にも、コミックとの親和性を強く感じた。節目となる第二十回候補作が、硬軟二方向にはっきりと分かれたことが、選考後まことに興味深く思われた。

井上ひさしイノウエ・ヒサシ
着想と構造と文体と詩
この賞の水準は高い。
着想のよさはむろんのこと、その着想にしてもだれもがびっくりするような、これまでの文学的常識の外に出たものが要求される。それに桁はずれの文学的な腕力がいる。それがないと五百枚も書き切れるものではない。作品の構造もよほど頑丈にできていないと、途中でかならず筆折れしてしまう。なによりも文学は一から十まで言葉でつくるもの、言語運用能力も抜群のものでなければならないし、ファンタジーというからには作品の芯にキラリと輝く詩心が埋め込まれていなくてはならぬ。なんという難関だろう。その難関に六百四十六編もの作品が寄せられたと聞き、これこそ天下の一美観だと——関係者のタワゴトかもしれないが——誇らしくおもった。
中村弦氏の『天使の歩廊 ある建築家をめぐる物語』は、右の難関突破条件をほぼ充たしている。
明治初年の銀座で、父の経営する西洋洗濯屋の物干し場にひるがえる真っ白なワイシャツの列を飛翔する天使たちと見た少年が、地上と天界をつなごうと志して、いくつかふしぎな建物を設計し、昭和初期に大日本帝国の傀儡国家満洲へと旅立つ……。海外では建築小説はそう珍しくないが、わが国ではここまでがっぷりと建築に取り組んだ小説は寡聞にして知らない。評者はまずこの着想に惹かれた。
さらに作者は、この建築家の半生を時の流れにそって順番に書くやり方を捨てて、その半生の一齣一齣を挿話に仕立て上げて、時間軸に逆らって近過去の次に大過去、大過去の次に中過去というふうに乱雑に並べ換えた。もちろんこの乱雑さにはしたたかな計算がはたらいている。したがって読者は、建築家の半生をジグザグに辿ることになり、そのジグザグするすきまに、天使が現われ、初恋が息を吹き返し、人生の謎が加速し、ひっくるめて独特の詩情が立ちのぼる。巧みな構造だ。文章は明快、文体も安定、とてもおもしろい。
ただし、地上と天界をつなごうとして設計された建物が案外、平凡だった。ひょっとしたらこの建築家は行った先の満洲で、地上と天界をつなぐような建物を設計したかもしれず、満洲の挿話が欠けていると話が終わらないような気もする。そこで「ほぼ充たしている」と書いたわけだ。もう一つ、この建築家の思想はかならずや権力側と衝突するはずで、そこへ筆が届いていないのも惜しまれるが、しかしながらそういった瑕を覆い隠すほどの美点をたくさん備えていることもたしかなので、この作を大賞に推した。
里見蘭氏の『彼女の知らない彼女』の着想は並行世界である。怪我をした女子マラソンの名選手の替え玉を、彼女のコーチが別世界へ探しに行くというのが前半のたくらみ。理想的な替え玉のいる世界へなかなか行き着けないでまごつくおもしろさを巧みに書いたのはりっぱな手柄だった。後半は一転して、替え玉に対する猛練習のあれこれ、本番レースの駆け引きなど、スポーツ小説に変身し、おしまいは自己発見の成長小説へと三転して完結する。まったく質のちがう三つのタイプの物語を上手につないで、全編をすらすらと読ませてしまう才筆に感心した。これはみごとな小説的軽業である。
時はピストルが出回りはじめたころの近世後期か、所は中欧あたりの学問都市か(二つとも評者の個人的な感想)……。とにかく川を抱いた学問都市で、男装の天才少女数学者がいくつもの難問に挑戦する。これが松崎祐氏の『イデアル』の道具立てだが、しかしなんというすばらしい着想だろうか。この着想に堅固な構造が与えられ、そして文章と文体に冴えがあれば、たいへんすぐれた作品になったはずだが、作者は女性数学者という自分の発明を粗末に扱ってしまった。「女性の数学者だからこそ、これこれしかじかの物語になりました」という展開がまったくない。せっかくのすぐれた着想なのに、もったいない話だ。数学の難問に向き合うときの知性、男性に向き合うときの感情。この二つの相克からもっとすばらしい物語が導きだされたはずなのに、作者は後者(感情)を無菌室に閉じこめてしまった。これではドラマもリズムも生まれない、ぜひ書きなおしてください。きっと傑作になる。
真山遥氏の『龍守の末裔』は、ひどいことをいうようだが、だらだらとだらしなく、なんでもありの、緩くて温い作品である。作者はご自分の着想と読者とに、もっと誠意をこめて向き合う必要がある。文章力はあるのだから一から出直せば、なんとかなるはずだ。

小谷真理コタニ・マリ
かけひきなし、接戦なしの構築物
今年で二十回目を迎える本賞は、応募数が六百を超えたという。裾が拡がるとレベルの高い作品が増えるはず、という見込みをたてていたら、やはり四編はどれも小説として水準以上。接戦の選考委員会ほど、読書会的なやりとりと雰囲気で雌雄を決する方角へ向かうものなのだが、のっけから鈴木光司委員より、全体的なイメージを各自正直に述べるようにという提案が出て、その通りにしてみたら、一作に集中して大賞がすんなりきまってしまった。なんという年なのだ!
しかも、文句なしのかけひきなしで首位にきたのが、建築をめぐるファンタジー『天使の歩廊 ある建築家をめぐる物語』。物語へひきこんでいく力がすごい、と感嘆した。読み始めるやいなや、先が気になり、続きを知りたくてたまらなくなった。鹿鳴館の謎や夭折した友人の亡霊や、幼なじみとの奇妙なやりとりが、走馬灯のように浮かんでくる。ただし、肝心の建築家自身の秘密は解き明かされず、天使の建築の意味(ナゾ)もあかされぬまま、昭和七年で話が途切れてしまう。受賞して、どうかこの続きを明かしてくれないかと念じながら、強く推した。無駄のない文体に、透明感のある筋立て、建築という沃野にまつわるファンタスティックな思索と、すべての点でバランスのとれたすばらしい作品と思った。
いっぽう、不思議な感触を抱いたのが、『彼女の知らない彼女』。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ばりのパラレルワールドの設定は乱暴きわまりない、掟破りをやっているのだが、人の気持ちとしては非常に入れこみやすい、一種間口の広さをもっている作品だ。並行世界をまたいだ本人同士が出会っていいのだろうか、とか、スポーツマン精神として、代役を立てるというこの展開はどうよ、とか、いろいろ突っ込みたくなる部分がとても多い。けれども、なんだか妙にさわやかで細かいところが気にならなくなってしまう。なんというか、人徳のようなものが備わっている、ちょっと役得な作品なのである。
『龍守の末裔』は、妖怪などの不思議と共存する世界が、実は学生時代のあの猥雑で楽しいごった煮の世界に似ているのでは? と想像たくましくさせる話だった。現代の龍守として生きる女性主人公が、男言葉を話し、明治時代のジジイのような人相風体で、芸術家として生きている、という様子がほのぼのと描かれ、こういう性差のゆらいだ変態的性格設定、ちょっとヘンなキャラクターの快さが不思議世界のリアリティに直結しているようで愉快だった。惜しむらくは、龍守としての本来の運命のほうが貧弱になってしまっているところ。楽しさの裏側の残酷さ、おぞましさがもうすこし前面にでてきてもよかったかな、と思う。
『イデアル』は、数学の才能に秀でた女性主人公が男装して数学師の学院に学び、異民の出身たる数学の天才らとともに、学問所のなかで閉塞し秘教的になっていた数学を解き放つようになる、というストーリー。女性でなければ解けない数学という、実に大胆な着眼点が浮かび上がってきたときには、わたし自身、たいへん興奮した。とはいえ、過去に惨殺された女数学師、海のある村から来たトールなど、忘れがたいエピソードや魅力的な可能性のある設定を多く提示しながらも、中心をなす数学的な主題と性差の関係ではいまひとつ未消化に終わっている。欠落したピースが完全に揃ったら末恐ろしい傑作になったのではと思わせるだけに、残念でならない。
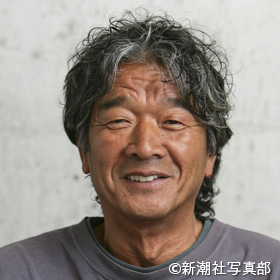
椎名誠シイナ・マコト
静かなる圧勝
応募総数が飛躍的にのびていると聞いて、かかわっているものとしては嬉しいかぎり。過去の受賞者がプロの作家になっていく率もこの賞は非常に高いときいた。時代が後押ししているところもあるのだろうが、ファンタジーというわかったようでいても具体的に説明せよ、となるとどうも言っているほうもよくわからない曖昧で怪しい文学村である。
要はなんでもありの世界。騎馬武者がオリンピックの槍投げのメダリストとパンクラチオンで戦ってもいいようなゆるさだ。
そのわりには今回読んで感じたのは「小さい」ぞ諸君。ということだった。こっちは夏の暑苦しいさかりに読む。汗をかくのも忘れるようなでっかい世界につれていけ。
SFのパラレルワールドにたちむかった里見さん。文章が素直でハナシも面白かったけれどダン・シモンズの『ハイペリオン』の時空間移動や量子物理学の入門書などを読んで少し書き直したらもっと面白くなると思う。
真山遥さんの作品は何をもって誰をハメル小説にしているのかよくわからなかった。
『イデアル』の松崎さん。遠い過去なのか、はるかな未来なのか。こういう舞台背景は効果的だ。全体がモノトーン。夢の中の中世の空気。そして宗教ではなくて数学支配の世界。芝居にしたら舞台監督が張り切る第一幕だ。でも語られている中身が、ややきまじめすぎる。掛け算ぐらいしか知らない読者にとってここで語られる数学のタタカイがどうにも異常で難解でつまらない。なんでもアリのジャンルなんだからもっとなんでも面白いのがアリでしょう。たとえば、
「内分方程式から導きだされた十七角形がいかに真四角の大皿に載った白ソーセージ五本分と存在意義として同等か否か、解の置換の概念を導入した方程式によって五分以内に答えよ」(おれのウソですよ)なんていわれたらちゃんと五分以内にわかりやすく(ウソでいいから)過激に解いて感動のあまりまわりの百人ぐらいが気絶する、というぐらいのメリハリの利いたホラ小説を読みたい。
結局『天使の歩廊 ある建築家をめぐる物語』という語り口のちゃんとした、かなり目のこんだ作品が相対的に価値を高めたようだった。
これは独立した作品が全体に関連していく構成で、そのひとつひとつがきちんと小説として読ませるようになっている。とくに登場人物の貌がそこそこ実体感をもって見えてくるところに筆の安定を感じる。このジャンルに詳しい荒俣さんなどはご当人のその異常なる博識から多少の不満はあったようだけれど、一般の読者にはさまたげにならないような気がする。静かに着実に高みに上り詰めた傑作の登場だろうと思う。
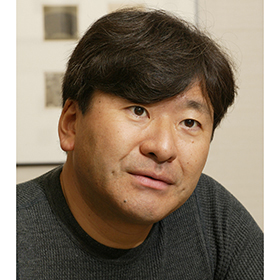
鈴木光司スズキ・コウジ
二番煎じは通用しない
記念すべき二十回目となる今回、応募総数は六百四十六点に上った。昨年と比べて約四十二%の増加。これもひとえに、ファンタジーノベル大賞歴代出身者の活躍に刺激された結果であろう。他の新人賞と比較して、この賞から出た作家の定着率は格段に高い。実に喜ばしいことであるが、ここにちょっとした罠が隠されている。活躍する作家が多ければ、過去の作品を読んで傾向と対策がたてやすく、その色に染まって、二番煎じに陥る可能性も高くなる。意図的に真似ているつもりはなくても、自然と似てしまうのだ。具体的に例を上げれば、「森見登美彦風」「しゃばけ風」ということになる。どんな表現世界であっても、自分独自の地平を切り開くのと、二番煎じに甘んじるのとでは、開発の困難さに雲泥の差がある。二番煎じが賞に到達することはないと心得てほしい。
『龍守の末裔』の主人公は、女性でありながら「ぼく」と自称して中性的だ。今時風の要素をすべて盛り込んで、度の過ぎた優しさを漂わす。小説執筆でもっとも心血を注ぐべきは、最初の一行と最後の一行であるべきにもかかわらず、「んな、アホな」という台詞で終わらせるのは、あまりに乱暴である。書いて捨てる作業によって、成長してほしいと願う。『イデアル』の主人公もまた男性を装う女性という中性的存在である。純粋数学を物語りの骨格とした点は独創的で、数論の展開部分は評価に値するが、肝心の小説技法が未熟なせいで、キャラクターが類型に陥っている。テーマをさらに掘り下げ、数論と物理世界との関わりを描いてくれれば、すごい作品になったのに。
『彼女の知らない彼女』の舞台は、パラレルワールド間の自由通行が可能となった世界である。シュレーディンガーの猫をちらちら登場させたりと、一夜漬けで量子論を勉強した形跡が随所に見られる。だが、扱いは表面的で自家薬籠中の物となってはいない。特に、異世界を移動する手段であるパラレルトリッパーが、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場するデロリアンなのにはがっかり。ところが、後半のスポーツ小説になると、少々の矛盾など吹き飛ばしておもしろくなる。コーチから、技術、科学、戦術等の指南を受け、ゴールに向かって走るマラソンランナーの姿はすがすがしく、ラストが近づくにつれてテーマが明瞭になっていく。不覚にも、さわやかな感動を味わってしまった。実に優秀賞らしい作品というべきだろう。
『天使の歩廊 ある建築家をめぐる物語』は、ひとりの天才によって建てられた建築物が、現実世界と天の世界との結び目の役割を負って、あたかも主人公のように振る舞う。その周辺で様々な物語りが紡ぎ出される連作風の作品というべきか。冒頭から話しに引き込まれ、読みやすく、無駄がない。新しい登場人物を説明するところなど、簡潔で当を得ているのは、確かな腕を持つ証しである。細部にまで思考は行き届き、文章は安定して、描写も的確、まさに小説の王道をいっている。選考委員という立場を忘れ、最後までおもしろく読めた。自信を持って大賞に推せる作品である。
選考委員
過去の受賞作品
- 大賞 今年の贈り物※「星の民のクリスマス」に改題優秀賞 きのこ村の女英雄※「忘れ村のイェンと深海の犬」に改題
- 優秀賞 朝の容花※「かおばな憑依帖」に改題優秀賞 ワーカー※「絶対服従者(ワーカー)」に改題
- 大賞 さざなみの国優秀賞 吉田キグルマレナイト
- 大賞 わだつみの鎮魂歌※「前夜の航跡」に改題優秀賞 しずかの海※「月のさなぎ」に改題






























