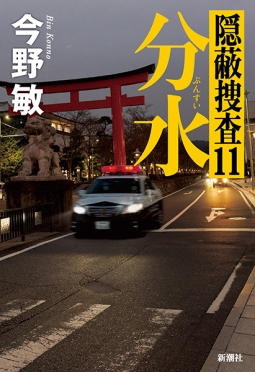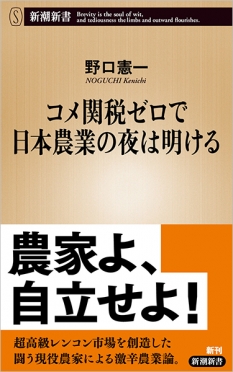──このたびはおめでとうございます。内田さんが小説を書き始めたのはいつ頃からですか?
高校一年生の頃に綿矢りささんと金原ひとみさんの芥川賞同時受賞の会見を見て、自分と年の近い人たちが著名な賞を受賞されたことに驚き、その頃から小説を読むのは好きだったので、憧れを抱いた記憶はあります。その後どのように書き始めたのかは覚えていないのですが、遊びで書いた小説を自作のHPに載せて仲間内で見せていました。本格的に書き始めたのは大学生になってからで、当時愛読していた吉本ばななさんの影響を受けた、詩的で綺麗な小説を目指していたように思います。
新人賞に初めて応募したのは二十歳くらいの頃で、一次選考を通過した嬉しさもあってそれから書き続けてきました。
──受賞の連絡が入った時は、どのようなお気持ちでしたか?
連絡日まで、これが最後のチャンスかもしれないとそわそわしている時期と、別に落選しても構わないと妙に気持ちが落ち着いている時期と、波がありました。自己防衛として落選した時のことを想像して気持ちの準備をしていたので、連絡日間際は割と落ち着いていました。
当日は意識するのが嫌だったので、普段通りに仕事をしようと思っていたのに、子供が朝から熱を出して仕事を休むことになり、さらにコロナ陽性の診断。仕事を休むための調整と看病で気持ちが忙しなくて、こんなにぐちゃぐちゃな状況ならもうどうなってもしょうがないとかえって吹っ切れた感じがありました。
受賞の連絡はもちろんうれしかったです。でもその日は、看病のために余韻に浸る間もなく、誰にも受賞のことは言わずに早寝しました。
──最初の応募から時間が経ちましたが、心境の変化はありましたか?
初投稿から10作~15作くらい応募してきたなかで、三十代前半の何年間か、書くのが苦しくてしょうがない時期があって、その頃は無意識ながら自分のことを書いていたように思うんですが、本作の前の前の小説を書き上げた時にもう自分のことは書かなくていい、これからはもっと書ける、ともやが晴れるような感覚がありました。それからは楽しんで書けるようになり、だんだんと自分から離れたところに小説が行ってくれる手ごたえがありました。
──自分以外のことというと、受賞作ではご自身より高齢の方を描いていますね。
高齢者に焦点を合わせて書いたのは初めてですが、最初から自分と年齢の離れた主人公を書こうと思ったわけではありませんでした。母親が行方不明になったあと、その土地で暮らし続ける年を取った娘を書いてみようと思ったんです。現在は地域で過ごす高齢者の支援に関わる仕事をしているのですが、仕事で本作の主人公世代の人と関わるなかで、この年齢の方がどんなことを考えているのだろうということに興味が湧きました。
──高齢者の方をどのように捉えられたのでしょうか?
自分の十年二十年前を思い返すと、そんなに考えていることは変わっていません。だから年をとったからといって達観しているわけじゃなくて、人間関係に悩んだり、他人に対して苛々したりしているんじゃないのかなと思います。誰かの息子・娘として成長して、仕事や家庭で責任を果たし、年をとればおばあさんおじいさんと呼ばれ、体は痛いし思うように動かないし、これから悪くはなっても良くなるわけではなく、表面上はそれを受け入れているように見えるけれど、心の奥底には若い頃と同じ自分がいる。そこに書く対象としての魅力を感じます。
──題名となった「赤いベスト」の物としての存在感や、主人公・跡野が平気で噓をつく姿が印象的です。
主人公の跡野は度々噓をつきますが、噓をついてしまうときの心情や、そうせざるを得ない人物を書いてみたかったんです。人生のままならなさを、苦しんでいる姿以外で表現したいと考えているうちに、自然とそうなりました。そんな主人公の前に母の幻影が出てきたとき、何か印象的で、高齢者らしさと不気味さのある服を着ていてほしいと考えて、思いついたのが赤いベストでした。
──不気味さはこの小説の大きな特徴ですよね。高齢者が集住する地域の不気味さには、広島の土地柄や言葉も関係するのでしょうか?
小説の舞台となるのは狭いコミュニティですが、どんなコミュニティでも暮らしていくしんどさは普遍的なものだと思います。実は、地元の広島をはっきりと舞台にするのも、作中で方言を使うのも初めてでした。自分がこの年齢になったときどういうことを考えているだろうと考えたとき、やっぱりべたべたの広島弁が私の中で一番自然だったんです。狭いコミュニティの不気味な雰囲気を出すうえでも効果的なんじゃないかなと。
──広島弁への挑戦はいかがでしたか?
若者が使う方言と高齢者が使う方言の使い分けには苦労しました。ベタベタな方言で喋る高齢者は多いのですが、若い人って敬語になるとけっこう方言が抜けちゃうんですよね。「何々しておられた」とかも高齢者が話すと「何々しとっちゃった」とくだけた感じになったり。私の世代はそこまで強い方言は使わないんですが、高齢者と日々接しているので、同じ口調で話すのが癖になっています。
──本作は応募前に誰かに読んでもらいましたか?
文芸サークルに十年前ぐらいから通っているので、そこのメンバーに読んでもらいました。基本的には合評を目的とした、公民館で活動している小さなサークルで、先生はおらず、お互いの作品を読んで意見しあいます。私は新人賞に出す小説を読んでもらうという参加の仕方をしていて、受賞作は比較的褒めてもらえましたが、指摘を受けて修正した部分も多いです。
──サークル内で交わされる意見はどのようなものでしたか?
ムラ社会の嫌な面の表現と、ホラーっぽさが良いと褒めてもらいました。主人公の年齢や性格については、サークル内でやや否定的な意見ももらいました。「赤いベスト」で跡野は、弟が死んだ家で、子供たちが外で騒いでいる声からエネルギーみたいなものを感じ取り、これをひとりで聞いていた弟の気持ちを想像します。日常にあふれているなんでもないようなことをキャッチして心を揺さぶられることを書きたかったのですが、そういうものを書くには自分に近い主人公じゃないと難しいんじゃないかって。
──小説は変わらず書き続けてこられていますが、学生のころから執筆環境は変わりましたか?
家族と一緒に暮らしているので、ひとりの時間を確保するために、今は夜九時には寝て、朝三時に起きて書くような生活です。小説を読み書きする以外だと漫画を読むのが好きで、最近は『夏目アラタの結婚』や『HUNTER×HUNTER』を読み返しました。あとは、ひとりカラオケによく行きますね。最近は子供がついてきてくれるようになったので、ひとりではないこともあるんですが。川谷絵音さんのファンで、ゲスの極み乙女やジェニーハイといった彼のバンドの曲をよく歌っています。ゆらゆら帝国も好きですね。男性ボーカルの曲を歌うことが多いです。
──内田さんの読書遍歴を教えていただけますか。
大学に入ってからは現代の純文学作家をいろいろと読んできました。好きな作家は挙げきれないほどいるのですが、ずっと読んでいるのは角田光代さんや今村夏子さんです。角田さんの作品の他の人も気づいているけれど拾い上げようと思わないところを拾い上げているところ、今村さんの作品の不穏とユーモアの絶妙なバランスに惹かれます。角田さんは商店街での閉塞感みたいな感じの作品をいくつか書いておられて、私はそういうものがやっぱり好きなのかな。自分にも身近なところで、なかなか言葉にできていなかったことを気づかせてくれることで、カタルシスを感じるんです。それと、どっちかというとファンみたいな気持ちなんですけど、太宰治に憧れています。
──今後は、どのような小説を書いていきたいですか?
今までは自分の強みが出せるもの、自分が書けるものを書いてきた実感があったのですが、最近になって自分が好きだと思えるものをだんだん書けるようになってきた感覚があります。なので、そうした予感を逃さないように、自分の枠からも自由になって書いていきたいです。
この小説を書いていたときに九段理江さんのデビュー作「悪い音楽」や、そのあとに書かれた「しをかくうま」を読んでいたのですが、私が好きな純文学って、これくらい自由なものだったな、と再認識できたんです。物語に振り回される感覚があって、でもそれが、知らないところに連れて行ってくれるようで、新鮮で心地良い。私ももっと自由でいいんだと思えました。これから自分がどんなものを書くのかわからないことにも、ワクワクしています。