

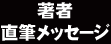


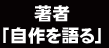
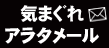
↑
今回が最終回になります。第五部まで読み終えた方のみクリックしてください。 |
|
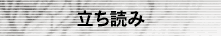
東京、新宿区の落合付近にある小さな公園の八重桜が満開だった。
厚く重なり合った花びらが、街灯の光で、幻想的な色合いに浮かび上がっている。赤信号でタクシーが公園脇に止まり、タイミングよく車内からも鑑賞できた。
氷崎游子はしかし八重桜が好きではない。淡白なソメイヨシノに比べ、ほぼ一ヵ月遅れで満開となる花は、濃厚で、複合的な美を感じさせる一方、美を無秩序に集め過ぎて、毒々しい肉腫のように見えてしまう。
「今夜が最後の見頃ですね。明日には散ってしまうでしょう」
タクシーの運転手が言った。
今日は一日中曇っていたが、夜になって冷たい風が吹きはじめ、じきに雨になると予報が出ている。
信号が青に変わった。後続車がないため、高齢の運転手は気をきかせたつもりか、すぐには車を出そうとしない。
游子は、身を乗り出して、
「急いでいただけます」とうながした。
車が発進した。同じ姿勢のまま、フロントガラス越しに、夜の住宅地を見つめる。以前昼間に一度だけ訪れたことがあるが、似たような細い道とカーブがつづき、いまどのあたりにいるか見きわめがつかない。
彼女は、焦りもあって、
「やはり警察に連絡すべきじゃないですか」
隣に座っている、ひと回り以上年上の奥浦という男に言った。
「どうかなぁ。向こうで、してるでしょ」
奥浦は、東京都の児童相談センターに勤める、児童福祉司だった。もともと児童問題の専門家というわけではなく、都の職員として、保健や福祉方面の仕事を担当したのち、今年度から児童福祉司として配属されてきた。四十代後半らしいが、白髪が多く、十歳以上老けて見える。
「念のために、こちらからも連絡しておいたほうがよいと思います」
游子はもう一度勧めた。彼女は、同じ児童相談センターで心理職員として働いていた。先日三十歳になったばかりだが、大学時代から児童心理学を学んできて、児童相談所関係の仕事ももう七年目になる。
「でも二重の出動になって、あとで、こちらが叱られてもねえ……きっと連絡してますよ。酔って暴れてるっていうんだから」
奥浦が面倒くさそうに言った。
相談の対象となる問題家庭や学校などへは、原則として児童福祉司が訪問することになっている。虐待があるなど、児童の精神的ケアが必要と考えられる場合は、心理の専門家が同行することも少なくない。そのため現場処理の経験は、奥浦より、游子のほうが豊富だった。ただし現場の責任者はあくまで児童福祉司であるため、奥浦の意向を、游子もできるだけ尊重しなければならない。
「二重出動になっても、謝ればすみます。大切なのは、当事者の安全だと思います」
「しかし、我々も状況がわかりませんしね……確かめてからにしましょう」
「……そうですか」
游子は、仕方なく自分の携帯電話を出し、番号を押した。
「あ、氷崎さん、だめですよ」
奥浦が慌てて止めようとする。
「一時保護所にです」
ほどなく電話に出た宿直の保母は、游子とは年齢も近く、気心が知れていた。
「ひとり、緊急に保護しても、大丈夫?」
危機的な状況にある児童を一時的に保護する施設は、常に満員で、新たに児童を収容する余裕はほとんどなかった。それでも緊急時には、職員のベッドを空けるなどして、規則を少し逸脱した形で対応している。
「どうしても保護が必要なんですか」
二歳年下の保母が訊き返す。
「そうならなきゃ、一番いいんだけど」
「游子さん、お休みだったのに大変ですね」
「毎度のことだから」
この日、児童相談センターは休館だったが、一時保護所だけは、子どもを預かっているため閉めるわけにいかない。游子も休日だったが、気になっていた児童の心理相談のため、いわゆるサービス出勤をしていた。彼女が、プレイルームで子どもたちと遊びながら心理面のケアをし、つい遅くなって八時頃に本棟の事務室に戻ったとき、ちょうど宿直当番だった奥浦が、外から掛かった電話を受けていた。
落合にあるアパートの住民からの通報だった。隣の部屋で、男性が酒に酔って暴れ、子どもが泣いているという。くわしく訊くと、去年十一月、奥浦の前任の児童福祉司が担当した親子だった。八歳の少女への虐待が疑われ、小学校からの通報で児童相談センターが介入した。游子もその少女と一度だけ会っている。無口で、感情をあまり表にあらわさない子だった。
「住所で言うと、この辺なんですけどねえ……」
タクシーの運転手が、車のスピードをゆるめた。
うろ覚えだが家々の並びに記憶があり、
「いいです、ここで」
游子が答えた。車が止まり、彼女とは反対側のドアが開く。児童相談センターの車は、駐車場が確保できないという理由で、今回は使われなかった。奥浦が、端数もきちんと払おうとして、小銭を床に落とした。游子は、時間がもったいなく思え、
「先にすみません」
自分の側のドアを勝手に開き、外へ出た。
「氷崎さん、部屋の前で待っててくださいよ」
奥浦の声が追ってきた。聞き流して、暗い路地を小走りに進んでゆく。彼女の左膝には、ボルトが入っていた。ずいぶん古いもので、長年のリハビリと慣れのおかげで、少し引きずりはするが、いまは健常者とほとんど変わらない速さで動ける。
彼女は、ジーンズにシャツ、ブレザーを着て、運動に適した軽快なシューズをはいていた。どれも汚れてもいい安物ばかりだ。髪はショートに切り、化粧も基礎的なものしか使っていない。
家々を見回すうちに記憶がよみがえり、路地をまたひとつ曲がって、古いアパートの前で止まった。中年の女性が二人、道路からアパートの二階を見上げている。
「児童相談センターの者です」
游子は名乗った。
「遅いじゃない」
女性の一人が言った。連絡をしたのは彼女だった。去年の介入時に、また何かあったときにはぜひ連絡してほしいと、前任の児童福祉司が頼んでいた。
問題の男性の名は、駒田という。通報した女性の話によれば、三日前、駒田は勤めていた電気設備会社をクビになっていた。アルバイトだったため、失業保険も下りず、しばらく控えていた酒を、今日また飲みはじめたらしい。七時過ぎに、部屋から意味不明の叫び声がして、やがて少女の泣き声が聞こえてきた。一時間ほど前には、何かが割れる音がし、子どもの声もひどくなったため、住民同士で話し合い、児童相談センターに連絡をとったということだった。
「警察にも連絡されましたか?」
「いえ……してないけど」
相手は怪訝そうな表情を浮かべた。「あなたたちに判断してもらったほうがいいでしょ。あとで妙な言いがかりをつけられても、いやだし」
「でも、女の子は泣いていたのでしょう。そうした場合、どなたでもまず警察に通報してくださいという法律ができたんです」
「あとで何かされても困るじゃない。八つ当たりで刺されたりする事件、けっこう多いわよ。いざってとき誰が守ってくれんの。だからさぁ、ほら、おたくへ連絡したのも黙っててほしいのよ」
二階の部屋から、陶器か何かが割れる音がした。すさんだ印象の男の声も聞こえる。
「すぐ後ろから男性職員が来ます。警察へ連絡するように言ってください」
游子は、女性たちに言って、アパートの外階段をのぼった。 |
|
 |