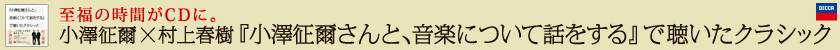別の本の話からはじめる。オンダーチェはスリランカ生れのカナダの作家。その『イギリス人の患者』(土屋政雄訳、新潮社)はいま一息で傑作といふことになりかねない長篇小説だつた。書評で褒めちぎつた記憶がある。映画化もされたが、見てゐない。今年、彼が映画編集の名手マーチ(『イギリス人の患者』が映画化された際の編集もマーチ)と語り合つて出来た『映画もまた編集である』(吉田俊太郎訳、みすず書房)が刊行された。これがじつにいい本で、映画を見のがしたことを悔んだ。
マーチの編集といふのは画面だけではなく音響を含む。そしてわたしがこの本で一番感銘を受けたのは、彼が、現在の映画の父として三人の名をあげるくだりだつた。エジソン、フローベール、ベートーヴェン。
初期映画の技術的側面、つまり機械や化学物質といつた面を発明した人々の代表がエジソン。これは当り前だが、たとへばがらんとした部屋の家具や埃など、平凡きはまるもののディテイルを徹底的に観察し描写して映画にリアリズムといふ方法を教へたのがフローベール、といふ指摘にはびつくりした。なるほど、あれはジェイン・オースティンでもなければバルザックでもない。たしかにフローベールの創始。しかしもつと驚いたのは、ベートーヴェンが彼以前の作曲家たち、たとへばハイドンと異り、フル・オーケストラを駆使しての大音響がとつぜんフルート一本になるやうなダイナミズムを発明し、その手法が応用されることで映画が飛躍的に発達したといふ、思ひがけない方向からの洞察だつた。この映画史のパースペクティヴは広大だし、清新で、わたしは心ひそかに、自分は今まで映画をずいぶんたくさん見てゐたはずなのにどうして映画史をかういふ具合にとらへなかつたのかと恥ぢた。
でも、仕方がない。条件が違ふ。向うは二人がかりで、しかも一人は映画の編集にかけては世界的な人物で、もう一人は自作が原作のときその編集につきあつた親密な仲だし、彼の長篇小説は優れて編集的な作風だし、その両人が何日もかけて知的閑談を楽しんでゐるのだから、かういふ興味深い充実した意見が続々と出るのは当り前だ。こちらは一人。衆寡敵せず、と自分を慰めることにした。
実は似たやうな感想を、小澤征爾さんと村上春樹さんの『小澤征爾さんと、音楽について話をする』を読んでゐていだいた。読みごたへがあつて楽しい。いい気持になる。かういふ幸福感を読者に与へる本はおれには無理だな、と思つた。
もちろんこの感想は滑稽である。小澤さんは世界的な指揮者だし、春樹さんはクラシックとジャズの双方に詳しい。しかもここが大事な所だが、二人とも人柄がじつによくて、知的な談笑を得意業としてゐる。さういふいろんな条件が重なり、しかも加ふるに、二人がたまたま親しくなるといふ偶然がさいはひして、このおもしろい本が成り立つた。わたしはただ愛読すればそれでいいのである。
たとへばどういふ所がいいか。ちよつと長くなるけど、引用。
- 村上
- 「普通、協奏曲を演奏する場合、指揮者とソリスト、どっちが曲の方針みたいなものを決めるんですか?」
- 小澤
- 「協奏曲の場合はだいたいにおいて、ソリストの方がより濃密に練習しているんです。指揮者の場合はまあ、二週間くらい前から練習に入りますよね。でもソリストは半年くらい前からその曲に取り組んでいます。そこにもうしっかり入っちゃってますからね」
- 村上
- 「でも圧倒的に指揮者の方が位が上という場合は、指揮者が有無を言わせずいろんなことを決めちゃう、みたいなことはないんですか?」
- 小澤
- 「そういうことはあるかもしれない。たとえばヴァイオリンのアンネ=ゾフィー・ムターね。あの人はカラヤン先生が見つけ出してきて、最初にモーツァルト、次にベートーヴェンのコンチェルトを録音しているんですよ。それなんかもう圧倒的にカラヤン先生の世界ですよね。それでたまには違う指揮者でやろうっていうことで、選ばれたのが僕なんですよ。カラヤン先生が『今度はセイジとやりなさい』と言って、僕が指揮をした。ラロの、なんたっけなあ、スペインなんとかっていう曲……。彼女がまだ十四とか十五とかそれくらいのとき」
- 村上
- 「『スペイン交響曲』。僕はたしかそのレコード持ってますよ」
- ごそごそとレコード棚を探す。やっと見つかる。
- 小澤
- 「ああ、これだ、これだ。懐かしいなあ……ラジオ・フランスのオーケストラ(フランス国立管弦楽団)。こんなの持っているんだ。信じられないなあ。僕なんかもうこれ、持ってないですよ。昔は何枚かうちにあったんだけど、人にあげちゃったり、誰かが持っていったり」
村上さんがまとめてゐるから当り前だけれど、二人の友情とホスピタリティにみちた会話に立会ふ気分になるでせう。臨場感がすごい。音楽界の内幕もよくわかるし(わたしは協奏曲のソリストはせいぜい三カ月くらゐ前から準備するだらうな、なんて見当をつけてゐた)、カラヤン先生(といふ呼び方もなんだか嬉しい)の小澤さんに対する面倒見のよさも感謝したくなるし、春樹さんの、かなりマニアックで好奇心に富んだレコードの集め方にも感心する。もうすこしはつきり言ふと、呆れる。といふ具合にとにかく楽しいんですね。
さう言へば途中に「レコード・マニアについて」といふ余談みたいな章があつて、ここで小澤さんは、「僕はもともとレコード・マニアみたいな人たちがあまり好きじゃなかったんです。(中略)でもね、あなたと話していて僕がいちばん感心したのは、あなたの音楽の聴き方がとても深かったということなんです。(中略)いわゆるマニア的な聴き方じゃないんですね」と言ふ。この率直さも小澤さんらしくて、と言ふか、いささかつきあひのあるわたしに言はせると小澤征爾まるだしでおもしろいが、これを受けての春樹さんの答へ方が絶妙。「わかりました。マニアが読んで、なるべく面白くないようなものにしていきましょう(笑)」
春樹さんの住ひでレコードをかけて聴きながら、春樹さんが口にすることは、たしかに、例のレコード・マニアたちの雑学的な情報ではなくて、もつと内容のある、自分の音楽的な体験から出て来た感想である。たとへば彼は反省して言ふ。自分がするやうな音楽の聴き方(いろんなレコードを買つて、あるいはコンサートに通つて、同じ曲を違ふ演奏家で聴きくらべる)と違つて、小澤さんのやうに楽譜を読むことを中心にして音楽とかかはつてゐると、音楽はもつと純粋で内的なものになつてゆくだらう、それは翻訳ではなく原書で文学を読むことができる楽しさ、自由さとすこし似てるのぢやないか。
わたしはこの思ひがけない比喩に妙に感動して、なるほどと思つたり、ちよつと違ふのぢやないかと疑つたり、いろいろ忙しかつたが、しかし感動は薄れなかつた。卓越した言葉の使ひ手が自分の体験を自分の言葉で表現してゐるせいだらう。
もうそろそろ紙数が尽きるから、気に入つた一問一答や逸話の紹介は諦めるしかないが、たとへば小澤さんがクライバーについて語るくだりなど、クライバーびいきのわたしには興味津々だつた。村上さんが、クライバーの『ラ・ボエーム』はそんなにすばらしかつたのかと訊ねると、小澤さんは紅茶を飲みながら、「あのね、指揮者がもう、あの芝居の中にずっぽり入り込んでしまっているんです」と答へる。後でどうしてあんなことができるかと訊くと、「セイジ。俺はね、『ラ・ボエーム』なんて眠ってたって指揮できるんだ」と威張つた由。それを聞いて村上さんは、リカルド・ムーティがワグナーの『指環』を指揮したとき、楽屋に来たクライバーとおしやべりすると、一度も『指環』を指揮したことのないクライバーがじつによく知つてゐた、といふムーティの回想を思ひ浮べる。そしてここから、何しろクライバーはキャンセルの名人だから、ごく自然に、「小澤さんは指揮をキャンセルしたことってあります?」といふ質問になつて、一ぺんベルリン・フィルの若い打楽器奏者に腹を立ててニュー・ヨークに帰らうと決心したといふ秘話がはじまる。その一部始終がいかにも小澤さんらしくて、わたしは微笑し、哄笑した。
おや、もう、ほんとに紙数がない。で、最後に一言。
この本を読んで、ブルクハルトが『イタリア・ルネサンスの文化』で、藝術品としての国家を成立させる重要条件は社交で、社交のために大切なのは会話だと述べてゐることを思ひ出した。日本が藝術品としての国家になるのはいつのことか、あまり期待が持てないやうな気がしてゐたけれど、この本はわたしの見通しを改めさせた。代表的な作家と代表的な指揮者の会話がこんなに充実してゐて、何か光り輝いてゐて、楽しいのを見ると、希望の曙光が見えてくる。
(まるや・さいいち 作家)