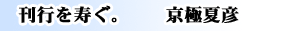
当然ながら小説は文字の連なりに過ぎない。しかし意味をもつ文字を或る形に配置することによって、文字の連なりは異形の「世界」を生み出すのである。日本語で構築される異世界=小説は、当然他の言語で綴られるそれとは作法が違う筈である。二十八年の長きに亙り文字を連ね続けた馬琴の偉業は、本邦の小説史を語る上で欠かせないものであるだろう。挿画にまで気を配り、徹底して完結性に拘泥し続けたそのスタイルこそを、私は範としたいのである。膨大かつ複雑なテクストの校訂作業を完遂された濱田先生の労に心から感謝すると共に、この度の刊行を喜びたい。 |
 |

『南総里見八犬伝』は、黙読より音読が読書のメジャーな方法だった江戸時代、まさにスター的な存在だった。ストーリーの面白さはいうまでもないが、文章のテンポやリズムの心地よさも大きな理由であった。そしてその愉しさをいっそう増幅したのがルビである。作者馬琴は、用いた漢語に自ら大和言葉で絶妙なルビを振っている。「烏夜」に「やみ」、「密語」に「ささやき」、さらには「鳥觜銃」と書いて右側に「てっぽう」、左側に「タネガシマ」なんて振っている。こういうルビがどんどん出てくる。今度の新潮社版は文字も大きい。あっというまにハマるだろう。 |