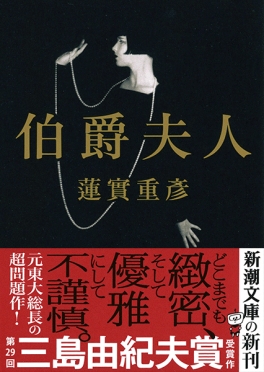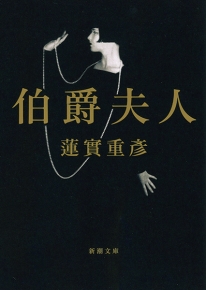
伯爵夫人
506円(税込)
発売日:2018/12/22
- 文庫
- 電子書籍あり
戦時下帝都、〈伯爵夫人〉が青年に授く性と闘争の手ほどき。80歳元東大総長の問題作。
ばふりばふりとまわる回転扉の向こう、帝大受験を控えた二朗の前に現れた和装の女。「金玉潰し」の凄技で男を懲らしめるという妖艶な〈伯爵夫人〉が、二朗に授けた性と闘争の手ほどきとは。ボブヘアーの従妹・蓬子(よもぎこ)や魅惑的な女たちも従え、戦時下の帝都に虚実周到に張り巡らされた物語が蠢く。東大総長も務めた文芸批評の大家が80歳で突如発表し、読書界を騒然とさせた三島由紀夫賞受賞作。
書誌情報
| 読み仮名 | ハクシャクフジン |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | Moviepix/カバー写真、Getty Images/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-100391-7 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | は-74-1 |
| ジャンル | 文芸作品 |
| 定価 | 506円 |
| 電子書籍 価格 | 506円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/06/21 |
書評
情欲と戦争
元東大総長にして話題の新鋭作家による本年度三島由紀夫賞受賞作――。
この優雅で退嬰的で巧緻極まる長編小説を筒井康隆、黒田夏子、瀬川昌久の三氏が読む。
江戸切子のグラスで芳醇なバーボンをロックで飲んだ。そんな読後感の作品である。
主人公の二朗は旧制の高等学校に通い東大を目指している晩稲の青年で、作中にも暗示されるプルーストの少年時代のように、女性と抱擁しただけで射精してしまうという純真さだ。時代は戦前、舞台は主に帝国ホテル。ロビーに入ると「焦げたブラウン・ソースとバターの入りまじった匂い」が漂ってくるというあたりでたちまちかの良き時代に引き込まれてしまう。タイトルの「伯爵夫人」も貴族でありながら突然傳法肌になったりして驚かせてくれる。ここから先は二朗や伯爵夫人その他の人物の回想との入れ子構造になっての展開となるのだが、挿入されるのは丸木戸佐渡ばりの情欲場面と、憚り乍らわが「ダンシング・ヴァニティ」が先鞭をつけた繰り返される戦争場面である。
奇妙で魅力的な人物が次つぎと登場するのが嬉しい。宝塚かSKDかという男装の麗人だの、友人の濱尾が投げたボールをワンバウンドで股間に受けてしまった二朗を介抱してしきりにその金玉を弄り回したがる女中頭や女中たちだの、正体は伊勢忠という魚屋のご用聞きなのだが病的に変装が好きな男だの、名前だけだが「魔羅切りのお仙」だの「金玉潰しのお龍」だのが出てきて笑ってしまう。他にもヴァレリーや吉田健一や三島由紀夫の陰が見え隠れする。当時はボブ・ヘアと呼ばれていた断髪の従妹蓬子も魅力的だが、そのスタイルで有名だったルイーズ・ブルックスよりも、キャラクターとしてはクララ・ボウに近い。さらに嬉しいことには懐かしい映画や俳優たちが続出。伯爵夫人に出逢う最初のシーンで二朗はアメリカ映画の「街のをんな」を見てきたばかりなのだが、伯爵夫人と抱き合う時にその演技をなぞるケイ・フランシスとジョエル・マクリーの主演者に加えて往年のギャングスターであるジョージ・バンクロフトまで登場させているので笑ってしまう。この二朗はずいぶんと映画好きで、全部上映すると六時間かかるという気ちがいじみたシュトロハイムの「愚なる妻」まで見ている。シュトロハイムが偽伯爵を演じた故の連想である。情欲場面ではヘディ・キースラーが絶頂に達する演技で有名になったチェコの映画「春の調べ」(原題「エクスタシー」)を思い出したり、戦争がらみでは主演ヘレン・ヘイズ、ゲイリー・クーパー、アドルフ・マンジュウの「戦場よさらば(武器よさらば)」が出てきたり、なんと無声映画時代の小津安二郎「母を恋はずや」における吉川満子の母と大日方伝の兄と三井秀男の弟との微妙な確執が死んだ兄の思い出に繋がったりもする。さてこの辺で、いったいこの話、時代はいつなのか、二朗の年齢はいくつなのかという疑問に囚われる。というのも前記の映画はいずれも昭和六年から十年あたりに公開されたものであり、そして二朗が一日の記憶を語った最後、「ふと夕刊に目をやると、『帝國・米英に宣戰を布告す』の文字がその一面に踊っている」、つまり昭和十六年十二月八日なのである。ここでやっとこの一篇、目醒めたばかりの二朗が一瞬にして思い出した夢だったのだなと納得するのだ。
戦争と愛欲の場面が入れ子構造の中で交錯するうち似たような表現が繰り返され、金玉に打撃を受けるたびに「見えているはずもない白っぽい空が奥行きもなく拡がっているのが、首筋越しに見えているような気が」し、そしてまた「ぷへー」とうめいて失神するのはエクスタシーの場合と同じで、ホテルの回転ドアは常に「ばふりばふり」と回っている。前記わが「ダンヴァニ」で用いて自信がなかった繰り返しが他でもないこの作者によって文学的になり得た上、しかも笑いさえ伴うのだと教えられ、安心させられた。
たとえいつの時代を描こうと小説作品は常に現代を表現している。作者が現代に生きているのだから何を書こうがそうなのだ。大正時代から昭和初期にかけて性的頽廃が徐徐に充満しつつあったあの時代の中、次第に軍人や憲兵の姿が何やらきな臭く彷徨しはじめ、そして破滅に繋がる戦争へと突入していくのはまさに現代に重なる姿であろう。そしてあの時まだ子供だった小生が楽しくエノケン映画を見ながらも、近づいてくる戦争に、戦争は悪いものなどとは夢にも思わずなぜか胸ときめかせわくわくし、面白がっていたことが今のように思い出されてならないのだ。
(つつい・やすたか 作家)
波 2016年7月号より
単行本刊行時掲載
危険な感情教育
元東大総長にして話題の新鋭作家による本年度三島由紀夫賞受賞作――。
この優雅で退嬰的で巧緻極まる長編小説を筒井康隆、黒田夏子、瀬川昌久の三氏が読む。
息つぎのすきもないことばの勢いに乗ってあちこちを長い年月にわたって引きまわされたようにおもうのだが、じつのところこの作中時間は、冒頭「傾きかけた西日を受けて」から終景「…時間が時間でございますから、今日は夕刊をお持ちしました…」までちょうど一昼夜、しかもその大半を中心人物は熟睡してすごし、そのあいだに戦争が始まっていたという鮮やかな設定になっている。
この朝、ラヂオの臨時ニュースは、つぎつぎと“大本営発表”を伝えていたはずで、作品全体の背中に戦争が重く貼りついていることは随所に書きこまれてもいるとおりだが、読み手としては、せっかく睡らせてもらえた作中人物にあやかって、“諜報機関”だの“特務工作”だのはあくまでも裏側にひそませ、その前夜の実質わずか数時間の個人としての激動のほうに素直にかまけていることにする。
そうたどれば全篇は、極度に凝縮された成人儀礼の時間であり、“伯爵夫人”による手荒な授業時間である。
この、翌年に帝国大学法科の入学試験を、翌々年に徴兵検査をひかえた旧制高等学校生にとって、“伯爵夫人”とは、異性すなわち他者すなわち全ての外界であり、それゆえ極端な怖れと憧れの対象、謎の塊、虚実の不分明として現前する。そしてその言動と、語り聞かす経歴中の所業とは、その妄想を埒を超えて拡大し、方図もない強烈さで二面性をつきつけ、あげく、両親の寝所から聞こえる嬌声の“レコード”のそもそもの音源はだれのものかとか、“伯爵夫人”が産んだという祖父の子“一朗”と自分“二朗”とはどちらがどちらかとか、自己同一性さえゆさぶりつくして、突如、手のとどかない闇世界に去っていってしまう。「…正体を本気で探ろうとなさったりすると、かろうじて保たれているあぶなっかしいこの世界の均衡がどこかでぐらりと崩れかねませんから…」と言いつつ、迫る危難の時代に備えて“ココア缶”と“絹の靴下”とのひとかかえを置きみやげとして託していったりするのが、この苛酷な両極性の教師の情の形なのだ。
二朗が“伯爵夫人”と最後に一緒にいたのは、作中現実としては冒頭の回転扉のあるビルヂング地下二階の“茶室”だが、そこの風景は「…さる活動写真の美術の方が季節ごと作り変えている」人工物で、ここは「どこでもない場所」「存在すらしない場所」「何が起ころうと、あたかも何ごとも起こりはしなかったかのように事態が推移してしまった場所」、「…だから、わたくしは、いま、あなたとここで会ってなどいないし、あなたもまた、わたくしとここで会ってなどいない」と“伯爵夫人”は言う。
この“場所”は、ごく初めのほうで“級友”が“同級生”として言及する“あの虚弱児童”の原型らしい実在の作家の、最終長篇最終景での八十老の感慨である「記憶もなければ何もないところへ、自分は来てしまった」とまっすぐにひびきかわす。ちなみにこの“同級生”の広く知られている実年齢によって作品の時代の空気が早くから特定できるなど、人も事もさりげなく適切な布置それ自体で説明ぬきに納得されるのは端的に“活動写真”の手法で、それらおびただしい語句章句、視覚的聴覚的形象はいずれも単独に放置されることなく、反復や相似や対比をかさね、たてよこななめに照応し、読み手がともすれば流れの速さに足を取られ、重層する虚構に踏みまよう構造を、限定してしまうのではない微妙な律儀さで支えていく。
この律儀さは、もうさっさと睡らせてやれと言いたくなる疲労困憊のはずの帰宅の寝間に届いていた“従妹”の長手紙に「さっそく返事をしたため」る作中人物のありようにもかよって、読み手がつい楽しくなるほどの律儀さで、とても一度読んだだけでは拾いきれない、また読もうと誘ってくる蠱惑として、この作品をいっそう豊かに充実させている。
(くろだ・なつこ 作家)
波 2016年7月号より
単行本刊行時掲載
随想 『伯爵夫人』の時代と私のかかわり
元東大総長にして話題の新鋭作家による本年度三島由紀夫賞受賞作――。
この優雅で退嬰的で巧緻極まる長編小説を筒井康隆、黒田夏子、瀬川昌久の三氏が読む。
かねがね敬愛する蓮實重彦さんが「新潮」四月号に「伯爵夫人」という小説を書いて評判になっている、と聞いて早速本屋に走ったが、既にどこも品切れだった。間もなく第29回三島由紀夫賞を受賞された時の記者会見で、小説を書くきっかけの一つに、「ある先輩が日米開戦の夜にジャズをきいていたこと」を上げられた、という情報を友人たちが連絡してきて、「あれは貴方のことだよ」と告げてくれた。どういう意味でか判らぬながらも、受賞そのものは非常に嬉しく思っていたところ、やっと本を入手して急いで目を通してみると、主人公の二朗が長い遍歴の末帰宅して眠り込みやっと目をさますと、夕刊に米英との開戦が報じられている、と末尾に書いてある。
「新潮」七月号の受賞インタビューの中で、蓮實さんは、私の名前を出して「トミー・ドーシー楽団による『Cocktails for Two(愛のカクテル)』のレコードを派手にかけられたら、ご両親から『今晩だけはおやめなさい』とたしなめられた」ことを引用して、私が戦争中もジャズをずっときいていたのは、戦前の日本に豊かな文化的環境があった証左だと述べておられる。これを読んで、今度は私の方が深い感銘を受けた次第であるが、小説「伯爵夫人」の中には、残念ながら音楽の話は出てこない。しかし蓮實さんは、映画を通じて、音楽にも極めて造詣が深く、昨年映画と音楽について対談した時に、日本映画がいかにアメリカのモダンな手法を採り入れていたかの例として、エディ・カンター主演の「突貫勘太」(1931年)の冒頭の歌が、PCL映画「ほろよひ人生」(1933年)にそっくり流され、更にエノケンの「青春酔虎伝」(1934年)のオープニングに、ダンサーやエノケン、二村定一らの長々と歌い踊っている場面を映像を通じて説明された。その時エディ・カンターを囲んで華麗に歌い踊るゴールドウィン・ガールズのまばゆいばかりの大群舞の場面を指して、「みんな背中は何もつけてないガールズの一糸乱れぬグループを使ってこんな題材を作っちゃうんだから、そんな国との戦争など勝てるはずもない」と申されたので皆大笑いした。
次に文中出てくる二朗の数人の級友の中に、「文士を気どるあの虚弱児童」の「平岡」の名が出てくる。「新潮」のインタビューでも「仮面の告白」評が出てくるので明らかに三島由紀夫(本名平岡公威)のことであろう。私はたまたま三島とは初等科から大学まで同級で、文学面を離れて親しく友達付き合いを重ねた。彼が体育や教練を好まず見学することが多かったのは事実だが、病弱で休むことはなかった。勿論作文の才には秀で、高校時代から小説を書いて注目されていた。大学にも一緒に入ったが、兵役は丙種不合格で、私の新調したばかりの制服を彼に貸した覚えがある。小説にはよくいわれる彼の変質性が強調されている嫌いがあるが、それは彼の一種の遊び心であったと思う。戦後学生のダンスパーティが盛んになった時は、我々の仲間の常連になって、きれいな女性パートナーを追っかけ廻したものだ。彼の著書「旅の絵本」にも出てくるが、彼が昭和32年夏にニューヨークに来た時私も前年から滞在していたので、始終顔を合わせた。彼は戯曲「近代能楽集」をブロードウェイで上演する話がすすんで、プロデューサーを決めて出演俳優のオーディションや劇場の手配を行うのに立ち会い、年内オープニングを目指していた。親友のドナルド・キーンの手配によるものだったが、その手順が次々に延びてしまって、彼はイライラしていた。流石の彼も資金を節約するためグリニッチ・ヴィレッジの安宿に引っ越して耐乏生活を始めたので、慰労の意味で、彼の好きなスパニッシュダンスを見せるスペインレストランに誘ったりした。「何故これ程芝居公演にこだわるのか」と訊ねると、彼はいたずらっぽく笑って答えた。――「先ずニューヨーク・タイムズ紙の日曜日の演劇欄に、僕の芝居の記事がいかに書かれるかを読みたい。それは芝居の初日、芝居がハネると、プロデューサーや劇評家たちが続々と集まる『サーディス』というレストラン・バーで、彼等が作品について議論する結果によって、作品の運命が決るんだ。僕は当日『サーディス』の片隅にそっと座って、彼等の議論に耳を傾けるスリルを味わいたいんだ。それだけだよ」。残念ながらその時は上演に至らず、彼は失意のまま帰国した。その彼は結婚して白い塔のある豪奢な自宅に、ドナルド・キーンと私共夫妻をよんで会食しながら、あの時のことを語ったものだ。「仮面の告白」にある「下司ごっこ」などについては、何れ蓮實さんと二人だけでワインでも飲みながらお互いの体験を語り合う機会を楽しみにしたい。
(せがわ・まさひさ 評論家)
波 2016年7月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
蓮實重彦
ハスミ・シゲヒコ
1936年東京生まれ。近著に『ショットとは何か』『ジョン・フォード論』。