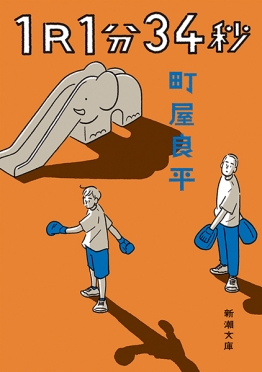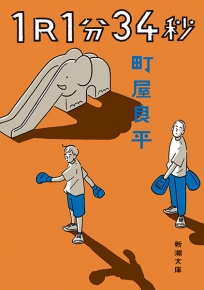
1R1分34秒
539円(税込)
発売日:2021/11/27
- 文庫
- 電子書籍あり
自分を失いたくない。だったら勝つしかない。若者の葛藤と成長を描く圧巻の青春小説。
デビュー戦を初回KOで華々しく飾ってから、3敗1分けと敗けが込むプロボクサーのぼく。そもそも才能もないのになぜボクシングをやっているのかわからない。ついに長年のトレーナーに見捨てられるも、変わり者の新トレーナー、ウメキチとの練習の日々がぼくを変えていく。これ以上自分を見失いたくないから、3日後の試合、1R1分34秒で――。青春小説の雄、会心の一撃。芥川賞受賞作。
書誌情報
| 読み仮名 | イチラウンドイップンサンジュウヨンビョウ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 小幡彩貴/カバー装画、新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 192ページ |
| ISBN | 978-4-10-103441-6 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | ま-63-1 |
| ジャンル | 文学・評論 |
| 定価 | 539円 |
| 電子書籍 価格 | 539円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2021/11/27 |
書評
「友だち」という秘密の扉
「友だち」という言葉は奇妙なほどに曖昧だ。「彼は私の友だちだよ」と言われたところで、辛うじて判るのは両者が知り合いであることくらいで、具体的な距離感や関係性を知ることはできない。それでも「友だち」という言葉には近さや温かさの感覚がなんとなく織り込まれていて、だから友だちがいないことはいかにも寂しいことだと感じられる。
町屋良平『1R1分34秒』は「友だち」を探す物語である。プロボクサーの「ぼく」にとって「趣味で映画を撮っている友だち」が「唯一の友だち」で、彼は日ごろのぼくの生活と感情をそのまま記録している。
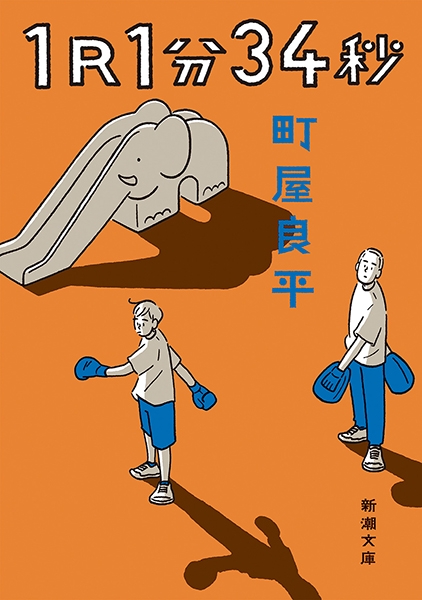
ぼくには夢のなかで対戦相手とかならず親友になってしまう習性がある。相手に憑依するようにその輪郭を何度も味わおうとする描写には、友だち以上の関係性を求めるエロティックな欲望を感じさせる。対戦相手のひとり、心くんとは夜のコンビニでふたりいっしょにエロ本を読んで勃起するという生々しい夢を見る。ぼくと友だちの周りにはいつもエロスがほんのりと漂っている。
友だちと対照的な関係として、コーチ(先生)としてのウメキチが登場するが、ぼくはウメキチに対して欲望のままにタメ口の関係、つまり友だちの関係への移行を促し、しまいにはお互いに自分の弱さをさらけ出すような間柄になる。
他に友だちや先生との関係性の交錯を描いた作品として真っ先に浮かぶのは、やはり夏目漱石『こころ』である。「私」は「先生」と海辺でお互い裸の姿で出会い、念願叶って先生と関わり合う機会を得た私は「自由と歓喜に充ちた筋肉を動かして海の中で躍り狂った」と肉体で喜びを表現する。先生に「異性と抱き合う順序として、まず同性の私の所へ動いて来たのです」と看破される私は恋をするように先生を慕っていて、先生はそんな彼に「あなた限りに打ち明けられた私の秘密として、凡てを腹の中にしまって置いて下さい」と手紙を遺して死を選ぶ。先生が死んだのは、かつて裏切った友だちKの死が引き寄せる強い力に抗えなかったからであり、つまり先生はKに憑依するように死んだのである。そして同時に先生は自らに憑依する「私」に秘密を託して死んだのである。

千葉雅也『デッドライン』では、中国哲学をめぐる対話の中で、「秘密」とは「偶然性によって自己と他者がワンセットになる」ような近さにおいて共有されるものだと語られる。それは文字通り他者に「なる」ことであり、この物語の中では、ゲイの主人公である「僕」が(友人のKに告白して振られた経験を持つ)知子という別の女友達と「ワンセットになる」実験が刻まれている(読者は作中で突如として「僕」と知子の人称が「ひとつになる」ことに気づくはずだ)。

しかし「僕」が知子に「なる」ことは憑依と少し異なる。別の箇所で、僕は他の誰かに「なる」ことを「彼女になって、彼女自身が自らに挿入してイクような状態」と語るが、相手への憑依と元の自分とが混濁して欲望の器になり、それが自分の肉体を受け入れる。つまり、欲望が自身の身体と一線を越えてしまうのが「僕」なのだ。これは『こころ』において先生がKと(そして「私」と)ホモソーシャルな関係性から抜け出せなかったことと比較すると、ただならぬことである。
一方、『1R1分34秒』で、自身の身体を持て余したプロボクサーの「ぼく」の支えとなったのは、「友だち」のカメラの記録であり、部屋の日照を妨げる立派な木だった。「木とのあいだで、友情が結ばれていた」ことに気づいたぼくは、木から「ぼくがいまのぼくでないぼくを生きている可能性」を教えられ、そういう別の可能性を生きるパラレルな自分こそが友だちなのだと気づかされる。
『こころ』の先生はKという友だちとの関係をやり損なってしまったために、死線を踏み越えてしまった。そんな先生を救うことができた道がここに二つ示される。一つ目には、今の自分ではない自分を生きた可能性に気づき、パラレルな自分が今の自分を明るく照射していることを感じられたらよかったのだ。そして二つ目には、先生が御嬢さん(=妻)に「なる」ことを通して、虎視眈々とその機をうかがいながら、友だちのKと、そして自らと交わればよかったのである。
(とば・かずひさ 教育者・作家)
波 2023年2月号より
ボクシングという螺旋
所属する小熊ジムあてに依頼が届いて、ボクサーのコンディショニングについて、町屋さんから昨年取材を受けました。「コンディショニング」というのは、選手の体調管理全般のことです。減量はもちろん、たとえば前日計量を終えたあと、試合までのあいだに何を食べればよいか。つまり、ゴングが鳴るまでに、自分の体調をピークに近づけていく技術のことを言います。
完成した作品を読むと、プロボクサーの目から見ても、この小説のボクシング描写はすごくリアルに伝わってきました。身体の展開、構え、目線の動き、ぜんぶ頭に浮かんでくる。表現が豊かで綿密で、読んでいる自分が「主観」になれた。なかでもいちばん共感したのは、主人公「ぼく」の人物像です。デビュー戦をKOで勝ったあと、負けが込んできた二十一歳の主人公は、とてもナイーヴな人間で、考えすぎてしまったり、うまくプレッシャーを発散できずに他人と衝突してしまったりして、ボクシングと相思相愛になりにいかないところがある。僕とどこか似ているんです。自分で自分が分からなくなってきて、自己が一定でなくなってしまう彼のことを、まるで僕自身を見ているかのように読みました。
例を挙げれば、主人公がKO負けして病院でCT検査を受けて、「ちいさな出血でもみつかってあらたな人生のフェーズに移行したいというきもちが、まったくないとはいいきれなかった」と思考する場面。僕もKO負けしたあとの検診で同じことを考えたことがあります。どうしようもない状況に陥りたい気持ちというか、周りのみんなが納得できる辞め方はこれしかないな、という投げやりな気持ち。そのとき、結果的には「異常なし」と言われてほっとしたけれど、正確に言うと多分、ほっとした自分にほっとしていたんです。自分はまだ続けたい気持ちがあるんだ、と……。町屋さんはなぜこんなことが分かるのだろうと驚きました。
主人公はボクシングに対するネガティブなイメージを捨てられず、いくつかの自分と戦いながら、葛藤しながらリングに上がります。かつての僕も、主人公と同じくらいの熱量でボクシングに触れていました。別に勝てなくてもいいし、惰性で試合をして、一、二回負けたら辞めよう、くらいの感じ。僕が唯一持っているタイトルは東日本新人王なのですが、タイトルを取ったあとに初めて負けたとき、奈落の底に突き落とされました。敗北者の烙印を押されて、なんて残酷な、怖い世界なのだろうと思ったんです。もちろんボクシングは大好きです。大好きでありながら、ボクシングが怖くなった。パンチをもらうのも、血が出るのも怖くない。ただ負けることが怖い。存在を全否定されることが怖い。リングの上では、ハンコで押されたように結果を突きつけられて、勝つか負けるかの結果しかないんです。勝つためにやってきたすべての選択肢は、結果のためだけにある。
だからこそ、その結果に至る過程で主人公と心を通わせていくトレーナーのウメキチは、ボクサーにとってとても大きな存在です。最初は距離を置いていて、作ってくれた弁当を捨てたり、タメ口を利いたりして反抗するけれど、徐々にウメキチに心を開いていく。主人公は、体重がオーバーしたらあいつのせいにしてやる、とまで念じるようになり、ウメキチもただ甘やかすのではなくて、教えることはしっかり教えたうえで主人公の心に入っていく、という関係性。僕のトレーナーは、元世界チャンピオンの小熊正二というジムの会長で、ウメキチとは少し違って放任主義なのですが、僕が負けた時には、自分と同じくらい、ひょっとしたら自分以上に悔しがってくれるんです。僕が一番頼れるのは会長で、自分はこの人のボクシングでチャンピオンを目指したい。スランプになって辞めることを考えても、「この人が降りていないのに、僕が降りるわけにはいかない」と思う。ラウンドが終わってインターバルでコーナーに帰ったとき、この人の言うことさえ聞けば大丈夫だ、この人だけが勝つために何が必要かを教えてくれる、といった信頼関係はなかなかできません。この小説の主人公にとって、その相手はウメキチなんです。
「1R1分34秒」というタイトルが指すものはほんの一瞬の数字にすぎないけれど、リングの上は数値化できない濃密な時間で、その時間には「今」しかない。だからボクシングは面白くて、やめられないんです。僕は螺旋という言い方をするのですが、主人公も、これからきっとボクシングの螺旋にはまっていくと思います。それに飲み込まれていって、ボクシングそのものになっていくような螺旋に。
(たのおか・じょう プロボクサー)
波 2019年2月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
町屋良平
マチヤ・リョウヘイ
1983年、東京生まれ。2016年、「青が破れる」で文藝賞を受賞しデビュー。2019年、「1R1分34秒」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『ほんのこども』で野間文芸新人賞を受賞。2024年、「私の批評」で川端康成文学賞を受賞。同年、『生きる演技』で織田作之助賞を受賞。2025年、『私の小説』で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。他の著作に『しき』『愛が嫌い』『ショパンゾンビ・コンテスタント』など。