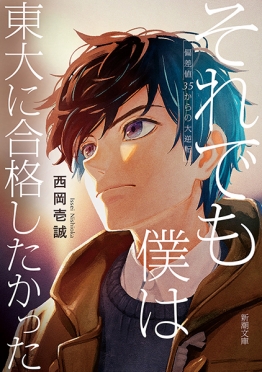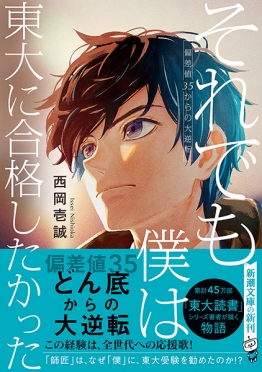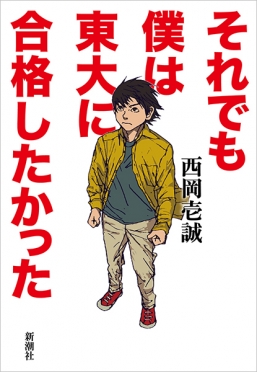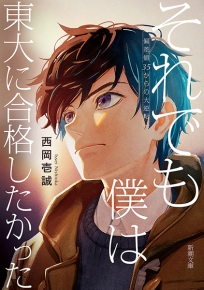
それでも僕は東大に合格したかった─偏差値35からの大逆転─
880円(税込)
発売日:2025/03/28
- 文庫
- 電子書籍あり
成績最下位の僕に、担任は「東大を目指してみろ」と──「僕」が経験した本当の話。
成績最下位でいじめられっ子で、将来に希望を抱けなかった「僕」に、担任が途轍もない提案をした。自分を変えたければ、東大を目指してみろ、と。その日から、初めての挑戦が始まった。高校3年で35だった偏差値は二浪して70、東大模試でもトップレベルに。そして合格発表までの8日間、これまで関わってきた人々と再会するなか、僕が気づいたこととは──。これは「僕」が経験した本当の話。
0章 2月26日 試験当日(闘う僕の唄を、闘わない奴等が笑うだろう)
1章 3月2日 合格発表まであと8日
2章 3月3日 合格発表まであと7日
3章 3月4日 合格発表まであと6日
4章 3月5日 合格発表まであと5日
5章 3月6日 合格発表まであと4日
6章 3月7日 合格発表まであと3日
7章 3月8日 合格発表まであと2日
8章 3月9日 合格発表まであと1日
終章 3月10日 合格発表当日
解説 渋谷牧人
書誌情報
| 読み仮名 | ソレデモボクハトウダイニゴウカクシタカッタヘンサチサンジュウゴカラノダイギャクテン |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | くにたろ/カバー装画、新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 464ページ |
| ISBN | 978-4-10-105941-9 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | に-36-1 |
| ジャンル | 文学・評論、ノンフィクション |
| 定価 | 880円 |
| 電子書籍 価格 | 880円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/03/28 |
インタビュー/対談/エッセイ

いつか、東京大学で
西岡壱誠さんは偏差値35から東大に合格し、現役東大生ながら、シリーズ累計45万部を突破した『東大読書』を執筆、ドラマ「ドラゴン桜」の監修者としても活躍している。一方、池田渓さんは東大卒業後、同大学大学院を経て、現在は文筆家として活動し「東大に人生を狂わされた」卒業生たちの姿を追っている。東大は、幸せへの扉か、それとも不幸への落とし穴か……東大をめぐる文庫新刊を出した二人が、縦横無尽に語り合った。
池田 西岡さんの『それでも僕は東大に合格したかった─偏差値35からの大逆転─』は、三回目の東大入試を受験した主人公が、試験から合格発表までの八日間に、“今までの人生で関わった人”に会っていく物語です。今回この本を読んで、受験当日の朝に緊張で嘔吐してしまう感覚とか、合格発表を待つまでのとても嫌な気分を、二十数年ぶりに思い出しました。
西岡 僕は二浪でしたし、本当に恐ろしい時間でした。
池田 審判が下されるのを待っているわけですからね。そして、この物語はダンテの『神曲』の「煉獄篇」だと感じました。主人公は、合格発表まで毎日一人ずつと会うわけですが、主人公が「師匠」と呼ぶ中三のときの担任の先生の導きで、先に大学生になった高校時代の後輩、高三で同じクラスだった女子、中学時代に主人公をいじめていた同級生、予備校時代の親友の妹など七人が登場します。これらの人との再会をとおし、主人公は自己を内省して、いじけた魂が浄化されていく……。
西岡 そんなふうに読んでくれたとは。
池田 主人公の名前は「西岡壱誠」ですし、実体験をもとにしたノンフィクションノベルだと聞いていますが。
西岡 そうですね、ほぼ実話です。
池田 高三のときに同じクラスだった女の子への恋心も実話なの?
西岡 ノーコメント(笑)。僕がこの本で書きたかったのは「東大に入るための努力」なんです。最後はもう「合格とか不合格なんて関係ない」という気持ちで。最近、努力を冷笑する風潮を感じますが、僕は、努力の過程で自身を成長させていくことこそが重要だと思うんです。そもそも東大を受験するって、とても愚かな行為なんですよ。試験科目が増えるし、形式が独特だから東大以外つぶしが利かなくなる。
池田 そうそう。よく、東大の受験勉強していれば早慶も受かるよねなんて言われるけど、短距離走と長距離走くらい違いますから。東大に受かって早慶に落ちる人もいます。
西岡 東大受験といえば、東大が推薦入試(学校推薦型選抜)を始めて、今年で十年になりました。累計の合格者数を見ていくと、一位が渋谷教育学園渋谷高校の二十人、二位が日比谷高校の十七人、三位が秋田高校の十五人、四位が広島高校の十四人、五位が灘高校の十三人でした。
池田 秋田と広島の地方公立高校が、灘高より上というのは驚きですね。
西岡 気になって秋田高校を調べました。でも、特別なことはしていないらしい。印象的だったのは、合格した生徒が推薦入試を受けたきっかけを「先生から勧められた」と答えていたこと。「君ならいける!」と背中を押してあげる先生がいたんですね。人間って、人間によって変われるんだと思いました。
池田 それって、この物語の主人公西岡くんと同じですね。
社長として東大生を引っ張る
池田 西岡さんはいま、現役東大生として東大に通いながら、執筆を行い、さらにカルペ・ディエムという会社の社長もされているとか。
西岡 うちの会社は、東大生たちに「拡声器」を渡し、情報発信できるようにする「場」なんです。東大生の中にはいろいろな経験をした人間がいる。週三でアルバイトしながら受験した人、ヤングケアラーで東大に受かった人。彼らに、じゃあ本を書いてみようとか、テレビに出てみようとか、情報発信の機会を作る。それによって個人の経験がパブリックなものになれば、別の人の人生にもプラスになると思うんです。それから、メディアの世界には東大生を「食い物」にしようとする人もいる。だから僕は、東大生が自分たち自身でやってけるシステムを作りたいんです。
池田 僕も学生時代から本を書いてきたので、食い物にされる怖さはわかる。今、書店にはカルペ・ディエムが関わった東大本がたくさん並んでいますね。
西岡 本当は、社長やりたくないんですよ。向いてないと思う。でも僕は、苦手なものって克服したいんです。
池田 東大の受験勉強で苦手科目を克服していったのと同じですね。
西岡 社長をやっているもう一つの理由は、僕が会社で一番「遊び」がうまいからだと思います。東大生は小さな頃から勉強勉強で、あまり遊んでこなかった人が多い。会社で働く東大生と黒部に旅行したことがあったんですが、ダムを見に行くとか、トロッコに乗るとかいろいろ遊べたはずなのに、あいつら足湯に浸かってスマホを取り出し、延々クイズ大会してたんです(苦笑)
池田 作中で、主人公が東大に合格するためやったことの一つが「東大に行くのだと周りに公言する」ことでした。先ほど「システムを作る」と周囲に公言したのは、同じ目的からですね?
西岡 声に出せ、師匠の教えです。ちなみに今回の文庫解説を書いてくれたのは、実在の渋谷先生なんですよ。
東大という幻想
西岡 東大に合格するのにはたくさんの努力が必要です。苦労が大きいからこそ入学後には「楽園」が待っているという“幻想”を抱く人は多い。でもそんな学生たちは、「ここから先はあなたの人生だから好きにしていいよ」って言われると、どうしたらいいかわからなくなる。だけど苦労して手に入れた「東大生」というプライドは手放せないから、どんどんこじらせていく。
池田 そういう学生は、就職活動で「東大までの人」と言われています。
西岡 池田さんの『東大なんか入らなきゃよかった』に登場しますね。僕のまわりにも、そういう人います。
池田 「東大」を冠したテレビ番組が人気ですが、ステレオタイプな「東大像」に大きな違和感があって。だから、違った視点から東大を書きたかった。
西岡 池田さんの単行本は2020年に出ましたが、衝撃が大きくて、面識がなかったのにもかかわらず池田さんに直接メッセージを送ってしまいました。
池田 じつは今回の文庫化に際し、ほぼ全文をリライトしたんですよ。データを最新にするのはもちろん、新規トピックも加えました。
西岡 読みながら「すげー、ここも新しくなってる!」と何度も叫んでしまいました。この本は二部構成で、第一部「あなたの知らない東大」では、学生たちの家庭環境や東大生の就職状況など、世間ではあまり知られていない「東大の実態」が書かれていますね。
池田 担当編集者は東大独自の進級制度「進振り(進学選択)」に驚いてました。東大生の学部学科が最終的に確定するのは二年生後半で、入学後の成績が悪いと希望学科に進めない。だから獣医師になりたいと思って東大に入学しても、「進振り」で獣医学科に入れないと、獣医師への道が絶たれてしまう。受験時に他大学の獣医学部を選んでいれば獣医師になれたのに、東大に入ったために夢が破れてしまうんです。
西岡 第二部「東大に人生を狂わされた人たち」では、東大卒業後、つらい現実にあえぐ人を取材されましたね。
池田 話を聞いたのは、メガバンクの銀行員、キャリア官僚、市役所職員、大学院生、地下街の警備員の五人。メガバンクで働く銀行員は、職場の慶應卒の先輩からいじめられたこともあり、心を壊して休職に追い込まれた。「東大卒」という肩書きを理由に、職場でいじめられるケースは他にもありました。
西岡 東大を卒業したらエリートコースまっしぐら、人生の勝ち組みたいに思ってる人も多いですから、反響も大きかったんじゃないですか?
池田 単行本の内容を抜粋したネット記事は三百万ページビューを超えたと聞きました。月二百時間超の残業に苦しむ官僚は、東大に入らなければ官僚にはならなかった、悲惨な人生を送ることもなかった、と語っていました。
西岡 最近は東大生の官僚離れも進んでいますからね……。
池田 今回は全員に対して追加取材を行いました。五年経つとみなさん状況が変わっていて。たとえば警備員だった齋藤さんはイラストレーターとして活動しており、この誌面で僕の写真に重ねられている絵は、齋藤さんに描いてもらいました。今回の文庫化では、最終的に約百四十ページ増えたんですよ。
西岡 この本は、まさに「裏の東大本」ですよね。アメリカなど海外でこういうアプローチの本が出ていたのは知っていましたが、日本では誰もやっていなかった。東大には、テレビをはじめとしたメディアから強い光が当てられています。でも、光が強いほど、影、闇も濃くなる。池田さんの本には、その闇がしっかり書かれていた。
池田 僕は新規性を重視していて、これまで世の中にはなかったという本にしたかったので、嬉しいです。
西岡 池田さんは東大生を「天才型」「秀才型」「要領型」に分けていましたが、とても腑に落ちる分析でした。
池田 僕は自分のことを「要領型」だと思っていますが、西岡さんは、ご自身はどのタイプだと思いますか?
西岡 うーん、天才じゃないし、要領もよくないから、「秀才型」かなあ?
池田 僕は、西岡さんは「外れ値」だと思っています。
西岡 ええ!?
池田 東大には毎年約三千人が入学しますが、西岡さんみたいなことする人は十人もいませんよ。大学側も興味を持って、じーっと観察しているのでは。
西岡 「出る杭」は嫌われるから(笑)
池田 「東大なんか入らなきゃよかった」と思ったことはありますか?
西岡 僕ほど「東大に入ってよかった」と感じてる人間はいないと思いますよ。僕が東大に合格したかったのは、自分を変えたかったから。東大に入っていなかったら、今の自分はない。本を書いたり、社長をすることもなかった。
池田 僕は、東大ってものすごく複雑な形をした立体だと思うんですよ。どこから見るか、誰から見るかでまったく違う形に見える。東大に入って幸せになった人もいれば、人生が狂ったり、不幸になってしまった人もいる。たとえば「進振り」について、僕たち二人の本は異なった評価をしていますし。
西岡 テレビなんかで取り上げられている東大は、同じ方向から見ているものばかり。でも、一つの視点からじゃ、東大という複雑な立体は正しく理解できない。
池田 だから僕たちの本は、ぜひ二冊セットで読んでほしいですね。

現役東大生はもちろん、東大をめざす受験生や東大に入らなかったかつての受験生にぜひ読んでほしい2冊
(にしおか・いっせい 文筆家)
(いけだ・けい 文筆家)

リアル「ドラゴン桜」から贈る受験生へのメッセージ!
中学3年生のある日、恩師のムチャぶりで、偏差値35から東大受験を目指すこととなった著者。自身を主人公として初挑戦した「小説」について、そして波瀾万丈の「受験」を語る。
――まず、小説に初挑戦した感想を教えてください。
本には、「思い」をベースにしたものと「スキル」をベースにしたものがあると思います。僕がこれまでに書いてきた『東大読書』『東大作文』などの実用書は、自分の経験を活かした後者になるわけですが、意外と「思い」の部分も含まれていたのかもしれない。それを感じ取って、小説の依頼をいただいたのだと思います。確かに自分の経験をどこかで書きたいという感覚はありました。
――実際に執筆してみて、苦労された点はありますか。
小説を書くことは、自分の内面と向き合って折り合いをつける孤独な行為だと感じました。例えば経験した出来事を写実的に語ることはできますけど、どう感じて行動したのかという理由は意外に自分もわかってなかったりする。何年か経って、そのときの自分の行動を一つ一つひもといていくことが小説を書くということだなと思いました。つまり自分の感情がどういうものなのか名前を付けていく行為だと。楽しい上に、自分と向き合えたような気がします。物語のそもそもは、「目標がないなら東大を受けてみろ」という恩師の提案でした。現役は偏差値35で落ち、2回目も合格できず、3回目の受験を終えて、また恩師と再会し、新たなムチャぶりの課題を描いたのが今回の小説になります。冒頭は3回目の受験当日の朝からスタートして、いったいどうなるんだろうという始まり方にしてみました。
――構成にも拘ったと伺いました。
実用書は、ある意味デパートの売場のように求められていることが明確なので、提示することが解りやすい。でも小説の場合は、読む人たちにこういうふうに生きてくださいと提案するわけにはいかない難しさがありました。そこで、章ごとにテーマを決めました。例えば3章は、知っていることを人に教える演技をすることで自分を変えていく、5章では死者との向き合い方だったり、戦うというのはどういうことなのかだったり……。メッセージ性を委ねられたのは実用書との一番の違いだと思います。
――小説以前、西岡さんの幼少期はどんな子どもでしたか?
3月が誕生日の早生まれで、身体が小さかったんです。人と話すのも嫌いじゃないけれど、あまり馴染めなかった。小学校時代やっていたサッカーも、うまくいかないことを繰り返して失敗経験に繋がってしまいました。家庭では一人っ子で、父親が単身赴任だったので母親と二人暮らしみたいな環境で。母も働いていた時には、一人で食事したりして過ごしていました。母親は明るい性格なのですが、小学生の頃は勉強にはうるさいほうでした。ただ、僕がそれに応えられなかったんですよね。中学では特に英語が全然できなかった。理科の実験とか、動物とかにも興味をもつ人間じゃなかったんです。勉強で好きな科目はなかったですね。でも、今思い出しましたけど、小学6年の時に、小説を書いて提出する小説家大会というのがあったんです。サッカーは下手だけど、小説だったら参加できると思って、サッカーをテーマにして書いた記憶があります。
――まさに小説の原体験ですね。
勉強は全般的に不得意でしたが、文章を書くことは苦手ではなく、漫画やアニメや小説の感想を、誰に見せるわけでもなく書いていました。それから、他人の感想も読みたいんですよね。2ちゃんねるやTwitterでも、いろんな人のレビューを見るのが好きなので、ニコニコ動画みたいにリアルタイムで感想が流れてきたりするのが好きでした。同じものに対して、自分以外の人がどこを観てどういう反応をするかを知ることが楽しい人間なんです。もともとはニンテンドーDSのゲームに夢中になって、それをきっかけに漫画やアニメに興味を持っていきました。
――どんな漫画がお好きですか。
何でも好きで、中学時代は毎週10冊ずつぐらい借りて読んでいました。とくに、高津カリノ先生の四コマ漫画『WORKING!!』とか『ダストボックス2・5』にハマりました。それから、ラブコメが好きなんです。とくに登場人物に思い入れがあるわけではなく、二人の恋愛に発展していく過程を見て楽しんでいましたね。
――特に『3月のライオン』は何度も読まれたとか。
そうです。ただ、この漫画は自分が努力する側の人間になってから好きになったという感じはあります。一番好きなシーンは、いじめの問題でベテランの男性教師が何回も面談するんですが、淡々としていて読者に感情移入させてくれない。でも最後に、いじめた側の生徒に、「お前は多分、何もやったことがないから、自分の大きさすら解らない。不安の原因はソコだ」と言うんです。そして、「ガッカリしても大丈夫だ。『自分の大きさ』が解ったら、『何をしたらいいか』がやっと解る」と。生徒が言われたことに気づいたかどうかも描写されていない。ただその言葉を残して去って行く先生が、あまりにもリアルに感じましたね。それから、主人公は養子ですが、実の子の才能を見限った瞬間の笑顔を見て、とても怖くなったことを憶えています。人の意見を読むと、自分とは違う点に感動していることが多く、共有できることは少ないのですが。
――自身の感想をまとめることが、後の文章を書く力に繋がったと言えますね。小説はどうですか。
小説は西尾維新さんや伊坂幸太郎さんが好きで、東野圭吾さんも全部読みました。漫画にしても小説にしても様々な刺激を受けて、自作のワンシーンはあの場面からインスピレーションを受けていると自分で読み返してもわかることがあります。
――高校では、どんな生徒でしたか。
基本的に僕は漫画「ドラゴン桜2」に登場する藤井くんと同じなので、性格の良い人間ではないのですよね。漫画のプロジェクトに参加するなかで、作者の三田紀房先生から東大受験に失敗した理由を訊かれ、自分勝手で独りよがりだったからと答えました。現役のときは先生に頼ることも、誰かに勉強法を訊いたり一緒に勉強しようということもなかった。人と関わって勉強することができなかったから受験に失敗したんだと後悔することはあります。生徒会でもいろいろ失敗したのは、頑張っても誰にも見てもらえないみたいな考えがあったからです。周りが敵に見えて、孤独になってしまうときがあるんです。劣等感にまみれているんですが、ほんの1ミリだけ、もしかしたら他の人にできない何かが自分にはあって、ウルトラマンになれるんじゃないか、みたいなプライドがある。そういう点が「藤井くん」のモデルになったんでしょう。
――その扉を開いたのが、恩師の渋谷先生ということですね。
東大を受験するよう勧められたのと同じく、生徒会長になれと言われたことが大きかったですね。何か名前を持つ存在になったとき何が起こるかを、自分の目で確かめてみろということだと思うんです。東大生って生徒会長経験者が多いんですよ。推薦入試だったら生徒会長やったほうが有利だったりしますけど一般入試では関係ない。でも、生徒会長だから生活態度を改めるようになるとか、その経験をもってして成長することによって東大入試も突破できるということに繋がるのかもしれない。

――「東大生にはギフテッドが多い」という話を耳にしますが、実際はどうなのですか。
結構な割合でいますが、僕のように「ドラゴン桜」的な存在もいます。ギフテッドって才能がある人という意味になりますが、じゃあ東大に合格するための才能って何だろうって考えると5個とか10個じゃ足りないんです。例えば、記憶力がいい、探究心がある、進捗管理ができるとか、粘り強さや集中力が必要だとか、無限にあるんです。いくつかを持っているから東大に入れるほど簡単ではない。また、日常会話のレベルの高さも大切です。例えば、テレビのバラエティーが面白かったよねと話している人と、政治について話している人たちとでは学力に差がついてしまう。環境によって人間は変わるという感覚があります。だからこそ、環境を超えていけるような人間を作りたいと考えています。
――この小説で西岡さんが伝えたかったこととは。
僕が伝えたいことはとてもシンプルで、西岡壱誠が特別だから東大に合格できた訳ではなく、みんな、リアル「ドラゴン桜」になれるんです。例えば宇宙飛行士になれるはずだったのに叶わなかったと思うのも、東大に行けたはずなのに行けなかったと思うのも同じで、頑張れば宇宙飛行士にも東大生にもなれたんです。「できなかった」と思っていても、実は、やり通したら叶ったはずなんだよと伝えたい。もちろん運もありますが、選択肢があって選ばなかっただけなんだよって言いたいんですよね。少なくとも、偏差値が低いところからでも東大合格できるということは僕が証明しておいたからさ、ということなんです。最後まで目標を捨てずに頑張り続けるという、それだけの話だと思うんです。
――今後の具体的な活動について教えてください。
これまでも学校や塾と提携して、「ドラゴン桜コース」を作り、実社会へアプローチする活動をしてきましたが、さらに拡充していきます。そんなに偏差値は高くない学校でも、現役東大生の体験談やいろんな話を聞かせて、学び方を教えますということをやりたい。それは三田先生のチームとしての企画なので、漫画を配って説明したり、どんどん活動の規模が広がっていけば嬉しいですね。同じような経験者たちの話に接することによって、生徒たちがレベルアップしてくれたらいいなと思います。
――最後に、受験生に向けてメッセージをお願いします。
受験を通して、泣いたり笑ったりする。すごく頑張ったら、たぶん嬉しくて自然と涙が出てきて、負けたら悔しくて泣くと思う。でも、そんなことは一瞬の話で、東大合格したから人生全てがプラスになるというわけじゃない。ただやっぱり、すごく努力してぶつかって出た結果なら、その過程に価値があると思うんです。逆に、努力しないで合格しても嬉しくないし、何も努力しないで落ちても別に悲しくもない。だから全力でやって、泣いたり笑ったりしよう! 勝ったり負けたりしよう! と伝えたいです。
(にしおか・いっせい 作家)
波 2023年2月号より
単行本刊行時掲載
人生大逆転! まさに、リアル「ドラゴン桜」だ。
成績はビリで運動神経はゼロ、いじめられっ子で人生に何も希望を持てなかった西岡くんは、渋谷先生なる人物が放った、「それなら、東大を受けてみろ」という途轍もない言葉で人生が一変する。渋谷先生と西岡くんの関係性は、まるで『ドラゴン桜』の桜木と生徒たちのように見えるが、これは実際にあった出来事である。
『ドラゴン桜』の作者・三田紀房さんに聞いた。
三田 西岡壱誠くんは、漫画『ドラゴン桜2』から、ストーリーに厚みを持たせるために参加してもらった、現役東大生スタッフの中の一人でした。
はじめは、あまり目立つ印象はなかったのですが、打ち合わせを重ねるうち、彼を中心にグループが動き出していることに気づいたのです。自分から積極的に発言する内容が簡潔で、要点が頭の中で整理されており、まったく無駄がない――いかにも東大生らしい優秀な人だなという感想を持ちました。なので、プロフィールを事前に聞かされていなかったこともあり、一緒に仕事をするうちに偏差値35から東大を目指したことを知って、本当に驚きました。他のメンバーは高校時代から成績優秀な学生ばかりで、現役合格が一人、ほとんどは一浪だけで合格していたはず。私が知る東大生の中で、西岡くんのような二浪で三回受験というケースはとてもレアでした。
すでに彼は『東大読書』や『東大作文』をはじめ、自身の経験を基にした実用書を出版していましたが、今作の『それでも僕は東大に合格したかった』は自分のリアルな受験体験を描いた小説と聞いて、更に驚きました。
東大生は、「なぜ東大を目指したのか」と、よく質問されるそうですが、ほとんどの学生には理由らしい理由はないと聞きます。「なんとなく」とか「ここまで勉強しているなら受けてみよう」とか「先生から言われた」など、それほど強い動機はないのが現実です。西岡くんは先生の言葉をきっかけに、それを信じて、「受けてみよう」と行動に移すことが出来た。その勇気こそが、一番の成功の「鍵」だったと思います。
偏差値35からの東大合格、つまり彼の経験には、「人生大逆転」、つまり人生をどうマネジメントするかというヒントが詰まっています。苦しい状況から受験をテコにして、人生のファーストアタックを見事に成功させた点がとても興味深い。受験勉強は孤独な闘いだと思っていた西岡くんは、発表を待つ八日間の中で、様々な人との繋がりに気づいていきます。この気づきこそが、現在の彼を形作ったのではないでしょうか。
彼は並大抵ではない努力を重ねて東大受験に挑むものの、現実はそう甘くない。この小説は、三回目の受験を終えた後、合格発表までの日々を描いているが、そこには、もがき苦しみ続けて、ある意味、カッコよくない、本当の西岡壱誠がいる。
三田 『ドラゴン桜』では、よく登場人物それぞれの人間性に触れることがあります。キャラクター設定のための打ち合わせで、どんなタイプが受験に失敗するのか、と西岡くんに尋ねたところ、彼は「僕みたいに性格が悪いと落ちます」と口にしたのです。人の言うことは聞かない、反発ばかりして身勝手な行動をする。それをヒントに生まれたのが、プライドが高くて独りよがりな高校生、「藤井くん」です。『ドラゴン桜2』は、ある視点から見れば藤井くんの成長物語でもあり、西岡くんは、まさに自分だと言っていました。現在の西岡くんは、とても冷静で穏やかな印象なので信じ難いのですが、受験生活の苦悩を垣間見た気がします。
受験に対するイメージは、誰から影響を受けるかによって変わるものです。辛くて苦しいものではなくて、誰にでもそれを乗り越える可能性があり、自分を成長させるひとつのきっかけだということを、西岡くんには「現役東大生」の立場から伝え続けてほしい。実際の体験を経た言葉には説得力があります。
『ドラゴン桜』チームでも、現在、新たな取り組みを始めているのですが、西岡くんと組んで仕事を進めることで大きく変わると実感しています。この小説にも、桜木の新たなストーリーのヒントが隠されているのかもしれません。
挫折を何度も乗り越えてつかんだ東大合格。その日々を記したノンフィクション・ノベル『それでも僕は東大に合格したかった』は、受験生だけではなく、それを支える親世代も勇気をもらえる作品だと思います。
(みた・のりふさ 漫画家)
波 2022年10月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
西岡壱誠
ニシオカ・イッセイ
1996(平成8)年生れ。東京大学在学中。偏差値35から、担任の勧めで東大を目指すことに。二浪を経験するなか、受験勉強の視点を変えたことから偏差値70まで上がり、東大模試で全国4位となり東京大学合格を果たす。そのノウハウを受験生や教師たちに教えるため、株式会社カルペ・ディエムを設立。全国の高校で「リアルドラゴン桜プロジェクト」を実施。著書に、体験を活かし、多角的に勉強法を説く『東大読書』をはじめとする「東大」シリーズ他多数。『それでも僕は東大に合格したかった』が初めての小説となる。