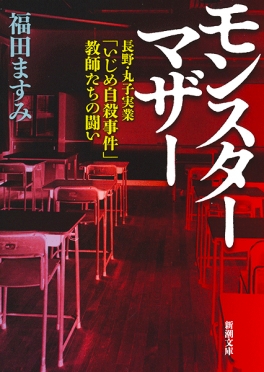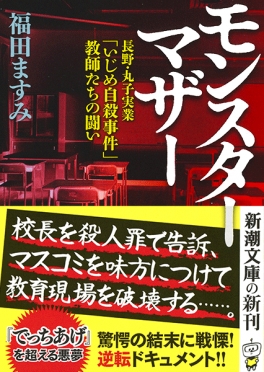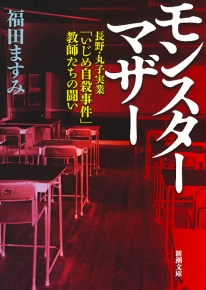
モンスターマザー―長野・丸子実業「いじめ自殺事件」教師たちの闘い―
737円(税込)
発売日:2019/01/29
- 文庫
- 電子書籍あり
息子の自殺を執拗に学校の責任にする母親と遺された遺書の謎。真実はどこにある?
不登校の男子高校生が久々の登校を目前にして自殺する事件が発生した。かねてから学校の責任を異常ともいえる執念で追及していた母親は、校長を殺人罪で刑事告訴する。弁護士、県会議員、マスコミも加わっての執拗な攻勢を前に、崩壊寸前まで追い込まれる高校側。だが教師たちは真実を求め、反撃に転じる。そして裁判で次々明らかになる驚愕の事実。恐怖の隣人を描いた戦慄のノンフィクション。
第二章 不登校
第三章 悲報
第四章 最後通牒
第五章 対決
第六章 反撃
第七章 悪魔の証明
第八章 判決
第九章 懲戒
終章 加害者は誰だったのか
書誌情報
| 読み仮名 | モンスターマザーナガノマルコジツギョウイジメジサツジケンキョウシタチノタタカイ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 広瀬達郎(新潮社写真部)/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮45から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 336ページ |
| ISBN | 978-4-10-131183-8 |
| C-CODE | 0195 |
| 整理番号 | ふ-41-3 |
| ジャンル | ノンフィクション |
| 定価 | 737円 |
| 電子書籍 価格 | 605円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/07/19 |
書評
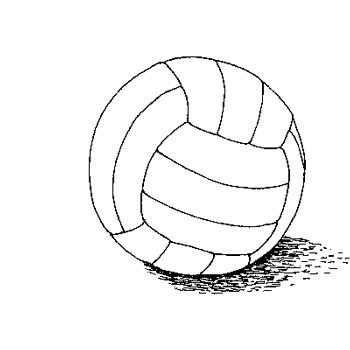
「いじめ自殺」の常識を問い直す
衝撃的な一冊だった。「中高生の自殺=いじめが原因」という私たちの先入観に鋭く切り込む労作である。作者は、福田ますみ氏。『でっちあげ―福岡「殺人教師」事件の真相―』(第6回新潮ドキュメント賞受賞)でも知られるノンフィクション作家である。
本書は、「丸子実業高校『いじめ自殺事件』」として語られてきた事案を、丹念な取材によってまったく新たな角度から問い直した作品である。事件は、2005年12月にさかのぼる。長野県立丸子実業高校1年の高山裕太さんが、自宅自室で首をつりみずから命を絶った。本事案では自死以前から、裕太さんへの対応をめぐって、学校と母親との間に意見の相違が生じていた。そして裕太さんの自死という最悪の事態を経て、学校と母親との対立は複数の訴訟に発展していく。
本書を特徴づけるのは、私たちが想起する「いじめ自殺」とはまるで異なる視点からのアプローチである。「モンスターマザー」というタイトルにあらわれているように、本書が焦点化するのは、被害者としての遺族ではなく、加害者としての遺族である。読者のなかには、息子を亡くした母親を「モンスター」と呼ぶことに、大きな抵抗感をもつ人もいることだろう。私自身も、少しばかり抵抗を直感した。だが本書は、「自殺=いじめが原因」を一方的に連想させてしまうこの世の中において、どうしてもいま必要な書である。親こそが問題であるという答えを得るためでもなく、また学校が諸悪の根源であるという答えを得るためでもなく、私たちが物事を多角的に見るための、開眼の書として高く評価すべきことをまずもって強調したい。
本書では、学校関係者の視点を軸にして、裕太さんが高校に入ってから自死に至るまでの経過と、その後に乱立した訴訟合戦について、章を追って説明が展開されている。「第1章 家出」と「第2章 不登校」では、生前の裕太さんの2度にわたる家出とその後の不登校について、学校と母親とのやりとりが描かれている。2度目の家出とそれに続く不登校において、母親は担任や部活動顧問、校長らの学校関係者を非難・罵倒していく。その過程で顕在化してきたのが、バレー部の先輩が裕太さんの物まねをしたりハンガーで頭を叩いたりしたという「いじめ」である。これが後に「いじめ自殺」の理由としてクローズアップされていくことになる。
「第3章 悲報」には、裕太さんの自殺直後、マスコミによる校長バッシングが起きたことが記されている。だがすでに、学校側から見た母親のパーソナリティの大部分が描き出されている。裕太さんを支配し、学校関係者に罵詈雑言を浴びせる攻撃的存在として、である。そのような母親像を前提にすると、当時のマスコミが依拠した「母親=被害家族」「学校=加害者」という構図はどうにも理解が難しくなる。
「第4章 最後通牒」から「第9章 懲戒」では、裕太さんの自死以降における訴訟合戦の過程が明らかにされている。とりわけ校長が殺人罪で母親側から告訴されるという事態は、衝撃的だ。告訴状によると自死3日前に裕太さんと母親と学校関係者でもった話し合いのなかで、裕太さんに登校圧力がかかりそれが裕太さんに絶望と不安をもたらし、自死に追いやったとのことである。しかしその話し合いの場には母親も同席しており、その意味では同席した関係者全員が自死にかかわっているとも言える。いずれにせよ、校長への殺人罪の適用には諸々の点で無理や矛盾があり、実際に校長は起訴されることはなかった。最終的には告訴した弁護士自身が所属する東京弁護士会により戒告処分を受け、日本弁護士連合会に不服を申し立てるも棄却される。そして民事訴訟においては、バレー部の先輩が裕太さんの頭をハンガーで叩いたことについて1万円の支払い命令が下されたものの、自殺との因果関係は否定される結果となった。
子どもは学校で苦しむこともあれば、家庭で苦しむこともある。学校内の人間関係がときに陰湿で過酷であるのと同様に、家庭内の状況もまた不可視的で残酷である。私たち第三者はまずもって、中高生の自殺をめぐっては、学校も家庭も同列に扱わなければならない。さらに言えば、それはけっして学校 vs.家庭という問題提起ではない。自死に至る過程で生徒は学校でも家庭でももがき苦しむことだってある。私たち第三者は一人の人間がどのように苦しみ、またどこで救われていくのか、その事実を丹念に追いながら、自死を防ぐためのセーフティーネットの構築に進んでいかなければならない。そのために本書がはたす役割は、大きい。
(うちだ・りょう 名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授)
波 2016年3月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ
嘘と冤罪のあいだ
新春から民放三社で弁護士を主人公とするリーガルドラマがスタートして話題となっているが、99・9パーセントの被告が有罪になるという、日本の異様な刑事司法のなかで、14件もの無罪判決を勝ち取っている異色の弁護士、今村核氏のことをご存知だろうか。その今村弁護士に取材して番組『ブレイブ 勇敢なる者「えん罪弁護士」』を制作したNHKエデュケーショナル・ディレクターの佐々木健一さんと、保護者の「嘘」によって窮地に追いやられた教師たちの苦闘を描いたルポ『でっちあげ―福岡「殺人教師」事件の真相―』『モンスターマザー―長野・丸子実業「いじめ自殺事件」教師たちの闘い―』の著者・福田ますみさんに語り合ってもらった。TVドラマでは描かれない、日本の司法制度の歪みとは何か――。
話題の弁護士ドラマでは描かれない刑事司法の「不条理」
福田 私が取材したふたつの事件では、濡れ衣を着せられた教諭や学校の弁護を買って出た弁護士さんに、山のように資料を提供してもらってずいぶん助けてもらいましたが、裁判は弁護士の力の入れ方によってまったくちがう結末を迎えてしまうのだと実感しました。しかも依頼人の無罪を信じて弁護するということは「殺人教師の肩を持つのか」とか「痴漢を弁護するのか」と世間から厳しく批判されるということ。『モンスターマザー』の弁護士には嫌がらせの電話がかかってきたり、長年の顧客を失ったりということもあったそうです。
佐々木 ぼくが取材した今村核弁護士にも深い葛藤がありました。冤罪を証明するのに手間暇ばかりかかる案件が彼の元にくるんです。刑事事件の弁護ばかりしていると周囲からは変人扱いされますし、民事裁判に比べて金銭的にも報われない仕事です。今村弁護士は誰も滑ったりしないごく普通の廊下で何度も足を滑らせたりするんですが、真相究明のためにひたすら歩いて、新しい靴も買わないので、靴底がツルツルになっていたんです。
福田 無罪を立証するために火災の再現実験をしたりして、真相を求める情熱が凄まじい。「疑わしきは罰せず」が原則のはずなのに、日本の司法制度では被告側が無罪を立証しないといけないという欠陥があって、それをやむをえず引き受けている。
佐々木 そうした実験の費用だって弁護団の持ち出しなんです。火災実験には百万円以上かかっていますが、国民救援会などのカンパで捻出したそうです。
福田 いまならクラウド・ファンディングが使えるかも。
佐々木 これからはそういう発想をもつ弁護士も出てくると思います。でも裁判で冤罪を証明できても、そういった費用がかえってくるわけではない。クラクラするような不条理です。いまのままでは、冤罪が疑われる事件に手を挙げる弁護士がいなくなってしまう。
福田 冤罪ではない案件だって舞い込みますよね。今村弁護士はどうやってそれを見極めるんでしょうね。
佐々木 本当はやったんだけど、やってないという人も当然いるでしょうね。彼はすぐに判断しないで、まずは資料を送ってほしいと言うそうです。そして徹底的に精査する。依頼を引き受けるべきか、真相を見極める手間を惜しまないんです。
福田 でもなんで今村弁護士のようなすごい実績がある人がこれまで知られていなかったんでしょう。
佐々木 比較的世間に知られていない小さな事件が多かったからかもしれません。無口で一見、偏屈者に見えますし。しかしあの葛藤を抱えながらも絶対に妥協しない執念は人並みではありません。
フェイクニュース時代に「真相」を見極めるたったひとつの方法
佐々木 福田さんが取材した丸子実業高校の「いじめ自殺事件」のことはぼくもリアルタイムで見ていて、「いじめを苦にして自殺した」という高校生の母親の主張をうのみにしていた一人でもあるんですが、マスコミにもでっちあげに加担してしまった人と「この事件おかしいんじゃないか」という人、どちらもいたと思います。その別れ道はどこにあったんでしょうか。
福田 もともと冤罪事件には興味があったからかもしれません。70年代に甲山事件というのが起こりました。兵庫県の甲山学園という知的障害者施設で園児二人が溺死しているのが発見されて、沢崎悦子さんという保母さんが逮捕されたんです。彼女は何日間も拘束されて、よくある刑事ドラマと同じように、一人の刑事に「お前が殺したんだろう!」と怒鳴られ、もう一人には優しく諭すように「えっちゃん、本当のことを言いなさい」と説かれて、嘘の「自白」をしてしまうんですが、一度は証拠不十分で釈放されます。ところが若くて熱意のある弁護士に「証拠不十分で起訴見送りというのは、完全にあなたの不名誉が雪がれたわけではないということ」と言われて、沢崎さんは国家賠償請求訴訟を起こすんですね。そして報復かどうかはわかりませんが、警察は彼女を再逮捕するわけです。しかし彼女はその後20年にわたる裁判のなかで一度も有罪判決を受けませんでした。『でっちあげ』で取材した事件については、保護者に言いがかりをつけられた教諭が自らマスコミに潔白を主張しなければ誰も守ってくれないと気がついたタイミングで、長時間話を聞くことができた幸運に恵まれただけなのですが……。
佐々木 テレビの報道記者も新聞記者もすぐに記事を出すことを求められるので、手っ取り早く取材しやすい人を取材して済ませてしまう傾向はあると思います。大学時代にドキュメンタリーを作ろうと、ハンセン病の元患者たちが国家賠償請求訴訟を提訴した頃だったので、ハンセン病の元患者の療養所である多磨全生園に通っていたのですが、マスコミが入所者の中でも取材しやすい人にばかり取材しているのを見て、とても驚きました。いわゆる共産党系で原告団に入っている人になるんですが、そういう方々は当時、入所者の2割くらいだったんですね。入所者にも一般社会と同じように自民党系の人や無派閥の人も当然いるのに、2割の人が語ることを全体の意見として伝えているように見えました。ぼく自身は政治運動にかかわったこともない、ただの大学生で、国賠訴訟の原告団の支援者に頼まれてビラ配りを手伝いましたが、中には受け取ってもくれない入所者の方もいました。療養所で暮らす人もさまざまで複雑な感情を抱いていることを目の当たりにしたんです。事実を丁寧に取材しなければならないと思う原体験になりました。
福田 ハンセン病のことは、隔離政策は不要だといって学会から追放された小笠原登医師に強い関心を持って、私も一時期調べましたが、欧米ではかなりはやい時期に特効薬ができて隔離や断種をやめているのに、日本はつい最近まで続けていました。
佐々木 入所者の元患者たちは、らい予防法の成立の中心にいて、のちに「悪の権化」のように言われる光田健輔に対しても複雑な感情を持っていました。隔離や断種、堕胎といった政策についても、「強制された」という一言ではとても括れないものを感じました。印象的だったのは当時、信濃毎日新聞だけが原告団に入っていない元患者にも取材して、彼らの多重性、複雑性をきちんと踏まえた上で報道していたことです。「療養所があったからこそ生きながらえた」と語る元患者がいる現実も含めて報道していたんです。「隔離を是認するのか!」と批判されるでしょうから、これはこれで勇気のいる報道です。なにより取材に手間をかけないとそうした立体的な報道はできない。結局、真相に迫ろうと思えば、愚直に取材し、あらゆる情報を集めるしかありません。これをぼくは“トロール作戦”と呼んでいますが。
福田 しかも読者がその報道から真相を見極めるのもまた大変です。
佐々木 『でっちあげ』の事件でも『モンスターマザー』の事件でも、ネットで検索すると教諭や学校側を陥れた保護者側の主張がいまだに「真相」のように出てきてしまいますね。
福田 教諭の名前や写真も出てしまっていますし。
佐々木 真相に近づくのがとてもむずかしい世の中になってしまって、ジレンマを感じますね。ネット記事やニュース動画だって、短いものしか見てもらえませんから、現代はさらに冤罪が起こりやすい社会構造になっているのかもしれません。
被害者に寄り添う「正義感」が冤罪を生む?
福田 私の取材した事件では、保護者の嘘を真に受けた弁護士が山のようにいました。保護者の周辺に取材すれば、『でっちあげ』の母親が言っていることがおかしいことは簡単にわかるのですが、それでも彼女の弁護団は結局数百人規模にのぼりました。被害者、弱者を守らねばという「正義感」が判断力を鈍らせるんですね。
佐々木 「人を信じる」というのは本当にむずかしいですね。そしてまちがいに気づいて軌道修正することもまたむずかしい。『でっちあげ』の母親の弁護士たちは、これだけ真相が明らかになっても、「彼女は真実を語っているんだ」という態度を改めることはできませんでした。
福田 記者を集めて派手に「こんなひどい教師がいる」とぶちあげてしまった手前、引き返せなくなったのかもしれません。
佐々木 検察官も、立件して裁判に持ち込んでしまうと、絶対に引き返せないということもあるでしょうね。
福田 「自分は被害者だ」と自称している人の言うことならば、すべて正しいんだと頭から信じる「正義感」が冤罪を生むんだと思います。
佐々木 冤罪被害者の汚名が雪がれて、壊れてしまった個人の人生が補償される機会はきわめて少ない。それに比べれば、検察官が自分の主張を軌道修正することはまだ容易いはずなんですが、大きな組織の一員だからか、それがなかなかできない。自戒の念を込めていいますが、マスコミも同じですね。
福田 締切が厳しくなればなるほど声の大きい被害者からばかり話を聞いてしまうし、書いたことをなかなか引っ込められない。私が主に記事を書いてきた「新潮45」のような月刊誌はもう少し余裕があります。雑誌ももちろん締切はありますが、私のように物好きで風来坊みたいなフリーライターならば「まだ確かなことは書けないな」と思えば「書かないという選択肢」もあります。もちろん原稿料がもらえなくて生活は困りますが。大マスコミが捕捉しきれないテーマに目をつけるという点で“ニッチ産業”のようでもあります(笑)。
佐々木 ぼくは「真実」という言葉をあまり使わないようにしているんです。番組を作ったり本を書くにあたっては、たくさんの「事実」を集めますが、「これが真実です」と言い切ってしまうと冤罪を生む側と同じように、もしそれが間違っていた時に軌道修正をしなくなりそうな気がするんです。
福田 カルロス・ゴーンが逮捕されて、取り調べに弁護士が同席できないとか、否認すると保釈されないという日本独自のルールが海外から批判されつつありますが、司法制度にも問題がありそうです。
佐々木 日本の司法制度が国際的に見てかなり古いことはたしかでしょうね。2006年に取り調べの一部可視化が始まりましたが、検察側に有利に使われる懸念があります。たとえやっていなくても、さっさと嘘の自白をしてしまって罰金を払ったり和解に応じてしまった方がいい、長年裁判で争うよりはマシだということにもなっていきますよね。こうした日本の刑事司法の歪みが冤罪を生んでいる面もあります。
(ささき・けんいち テレビ番組ディレクター)
(ふくだ・ますみ ノンフィクションライター)
波 2019年2月号より

人はなぜ嘘をつくのか
たった一人の保護者の嘘で、教育現場が破壊されてしまう――悪夢のような実話ノンフィクション『でっちあげ―福岡「殺人教師」事件の真相―」(新潮文庫)『モンスターマザー―長野・丸子実業「いじめ自殺事件」教師たちの闘い―』(新潮社)を書いてきた福田ますみさんと、最新の研究成果から、平気で嘘をついて罪悪感を持たない人の精神構造を分析した『サイコパス』(文春新書)がロングセラーとなっている中野信子さん。ノンフィクションライターと脳科学者という、まったく異なる立場から「嘘」をテーマに語り合ってもらった。
弁護士や精神科医こそ騙されやすい?
福田 これまで虚言で周囲の人を過剰に攻撃して、学校を破壊してしまう人を取材してきたので、今日は脳科学や精神医学の観点で色々お聞きしたいと思っています。『でっちあげ』ではありもしない教師のいじめを捏造したお母さん、『モンスターマザー』では息子の自殺の責任があると執拗に学校を責め続けて教育現場を壊してしまったお母さんに取材しました。二人とも中野さんが『サイコパス』で書いている女性サイコパスの条件と重なっていて驚きました。「か弱さ」をアピールするとか、そのことで「標的」を惹き寄せて、ある程度関係性が出来上がると豹変するとか。すぐに自殺するって喚くという点でもそうです。
中野 便宜的に「サイコパス」という言葉を使いますが、精神医学では「反社会性人格障害」という言葉を使います。他者に対する共感性や痛みを認識する脳の部分の動きが、他の人とちょっと異なる人がいるということが近年わかってきました。大企業のCEOに代表される、重大な決断を下さないといけない職種に多いという研究結果もあるくらいで、サイコパス=犯罪者というわけではないという点にも注意が必要です。
福田 二人のお母さんはともに躊躇なく嘘をついて、周囲の人間をとても巧妙に騙すことができるんです。「うちの息子が教師にひどい体罰を受けている」「耳をつかんで千切れるくらい体を振り回した」「みんな見ていた」という嘘で周囲を騙してしまう。普通に考えたら簡単にばれてしまうような嘘なのに。
中野 おそらく自分で作り上げた「心的事実」のなかで生きているんだと思います。そのなかでは彼女たちのいう嘘が、真実なんでしょう。
福田 まさにそういう感じでした。
中野 そもそも人間の脳って、あんまり論理的にはできていないんです。ちょっと頑張らないと論理的な考え方ができない。私たちの脳は二つのシステムでできていて、ひとつが論理的に考える「遅いシステム」、もうひとつは論理的に考えず、感情で動く「速いシステム」です。前者は使っていないと鈍りやすい上に、すごくエネルギーも使うので、普段はあまり使いません。例えばトランプ大統領の言っていることは滅茶苦茶ですが、「速いシステム」に訴えるのが上手なんですね。福田さんが取材した方々はどうでしたか?
福田 矢継ぎ早にセンセーショナルな嘘をつくんです。
中野 私たちは感情に訴えられると、理性で判断するよりも、何かすぐに応急処置をしなくてはいけないと思いがちです。
福田 弁護士や精神科医のような方々がみんな騙されました。
中野 トランプ大統領を支持している人は当初、「プア・ホワイト」と呼ばれる貧しい労働者階級が中心だと言われていましたが、インテリ層も多く含まれていたことがのちにわかりました。インテリほど「自分は理性で判断している」と思い込みがちで、かえって危ないとも言えます。実際は「速いシステム」で物事を判断しているのに、「速いシステム」を補強するために「遅いシステム」を使ってしまったりします。
福田 そういう人まで取り込まれてしまうのが恐ろしいところですね。
中野 弁護士とか医師のような方々は「人を助けたい」というモチベーションを持っていますので「頼ってくる人に弱い」という性質を、人よりはちょっと多めに持っていることになります。心理学や精神医学に携わろうという人は教科書の最初に「患者さんと共依存にならないよう注意せよ」と戒めとして書いてあるのを目にするはずなんですが、教科書にそう書いてあるということは、書かないとそういうことになってしまうということです。自分が患者を助けていることに依存するんですね。快感を感じてしまう。
福田 ドーパミンなんかも出ちゃう?
中野 ものすごく出ると思います。自分が役に立っているという状態に興奮してしまう。弁護士がそういう戒めを持っているかどうかは知りませんが、危ない部分を抱えていると思います。
福田 マスコミも同じです。『でっちあげ』は、週刊文春が〈『死に方教えたろうか』と教え子を恫喝した『殺人教師』〉という大見出しで報道して、「後追い取材をしてきて」と言われて取材現場に入って書いた本ですが、私もはじめは「先生は児童をいじめたり体罰したりして、ひどい悪人のはずだ」と思っていたんです。ところが先生に何度も会って取材していくうちに、とてもそんな人には見えなくなりました。もちろん取材している途中は、どちらが嘘をついているかわからないのですが、私自身、先生に感情移入してしまって、お母さん側に立って憤っている人と、私の義憤とが対立して、客観性を保つのが大変でした。
中野 戦争にも似たところがあります。正義対正義の戦い。二つの集団の正義は異なることもあるので、それがぶつかりあってしまう。福田さんが取材してきた人たちは、その軋轢の中心にいることで自分の身を守る戦略に長けているんでしょう。
福田 『モンスターマザー』のお母さんはミクシィを駆使して、自分の主張に賛同する人を大量に集めました。
中野 児童など、自分の代理になるものを傷つけて周囲の注目を集めようとする「代理ミュンヒハウゼン症候群」という精神疾患がありますが、そのバリエーションの可能性も感じます。
福田 『でっちあげ』のケースでは「教師にひどい体罰を受けた」というお母さんの話を真に受けて、精神科医が子どもをひどいPTSDだと診断し、閉鎖病棟に入れてしまいました。強い薬を処方されてしまって、子どもも被害者ではないかと思いました。こういう親に育てられた子どもはどうなっちゃうんだろう。
中野 反社会性人格障害は遺伝する可能性があるという研究があります。後天的に獲得するものをソシオパス=社会病質と呼びますが、トランプ大統領に対してアメリカの名だたる精神科医や心理学者が「彼はソシオパスだ」と言っています。ソシオパスとサイコパスで見分けはほぼつかないんですが……。彼にも娘や息子がいるので配慮してそう言っているだけで、サイコパスだと言いたいのだと思います。
「サイコパス」その特異な生存戦略
中野 サイコパスの生存戦略は、そもそも私たちのそれとちがうんです。
福田 ちがうというのは……?
中野 異常心理学の専門家で彼らのことを人間の「亜種」だという人もいますが、それは言い過ぎだとしても、一般の人と思考形態がかなりちがうようなんです。
福田 ホモ・サピエンスというより……。
中野 いわば「ホモ・サイコパス」。彼らは一般的なホモ・サピエンスとちがう生存戦略で生き延びているんです。その戦略は非常に巧妙で、ホモ・サピエンスが集団を作り、それを守ることで生き延びてきたのに対して、サイコパスはその性質に乗っかって生きてきました。
福田 中野さんの本では「フリーライダー」(タダ乗りする人)という言葉を使っていますね。
中野 そうなんです。私たちが守っている社会や集団を搾取することで生き延びてきたのがサイコパスなんです。そういう意味では彼らは生態系のピラミッドではホモ・サピエンスよりも上にいる。ですから大企業のCEOとか政治家に向いているという言い方もできるんです。アメリカの大統領にもサイコパスが多いという報告もあります。
福田 クリントンやケネディがサイコパスの傾向が強いという研究結果には驚きました。ヒトラーとかスターリンなんかがサイコパスだと言われても驚きませんが、ケネディは意外。
中野 そう指摘する人がいるのはたしかです。恐れ知らずで、大衆にアピールするのがうまい。まだ私たちが彼らの「嘘」に騙され続けているだけだと解釈することは可能かもしれません。
福田 でも、サイコパスが世界から淘汰されていないということは……。
中野 彼らの生存戦略が成功しているということです。生存戦略が成功していればサイコパスの遺伝子は残っていくので。
福田 サイコパスすなわち悪とはいえないというか、世の中にとって必要な存在なんだろうか。
中野 良い/悪い、正しい/正しくないというのは一言では言えないものですが、大事なことはサイコパスの側がそういう判断基準を持っていないということです。そして持っていない方が、生物としては強い。判断基準って、集団を維持するためのものです。「みんなが頑張っているのにズルをする人は悪い」「みんなが守っているルールを破る人は良くない」。しかしそういうルールの存在を知り尽くしていて、なおかつ縛られないで集団を操ることができる人がいたとしたら、自動的にそういうルールのことを考えてしまう人よりも巧みにゲームをプレーできてしまいます。そして生存戦略では良い/悪い、正しい/正しくないではなく、勝つか負けるかが重要なんです。そしてサイコパスは生存競争に勝ってきた。
福田 良い/悪いとか、正義とか、そういうことを考えないわけですよね。
中野 「そういうことを考える領域を持っていない」という感じに近いと思います。サイコパスというのは「正義の領域」「良心の領域」がない人たちということです。
織田信長はサイコパスだった?
中野 世界の百人に一人に「正義の領域」が欠けている人がいて、日本人の場合は四百人に一人程度だという研究があります。
福田 農耕民族であることが関係していたりしますか?
中野 東アジアには比較的少ないとされています。サイコパスは流動性の低い社会では生存しにくいんです。子孫を残しにくくなって、淘汰されてしまう。サイコパスの生存戦略が合わない土地柄なんでしょう。逆に流動性の高い社会だとサイコパスの嘘が暴かれないので、戦略が有効になってしまうんです。
福田 戦国時代の武将なんかはサイコパス傾向が強い方が天下が獲れそうですね。織田信長なんかサイコパスだったんじゃないかなあ。
中野 戦国時代って極度に流動性の高い社会ですよね。彼らは痛みを感じにくい性質もあるので、そういう時代に活躍します。
福田 戦場でものすごく勇敢に戦って、勲章をもらうような人もサイコパスの度合いが高いのかもしれませんね。
中野 『戦争における「人殺し」の心理学』という本を書いたD・グロスマンによれば、「撃墜王」なんて呼ばれるパイロットがいて、彼が一人で全体の四〇パーセントを撃墜するそうです。戦争ではそういう人を「英雄」と呼ぶわけです。
福田 ナチスのユダヤ人の収容所では、最初はユダヤ人を銃殺していたらしいんです。やっぱり普通の人にはそれが心の負担で、つまり良心が痛んで、続けられなくなってくる。それで考案されたのがチクロンBによる殺害だったという説があるそうです。より効率的に大量殺害をする目的もあったと思いますが。
中野 良心が痛むというのは前頭前野が健全に働いている証拠です。
か弱い女性サイコパスは批判しにくい
福田 『モンスターマザー』のお母さんは夫にひどい暴力を振るったり、つばを吐いたり、それはもうひどいんです。でも女性のドメスティック・バイオレンスは顕在化しにくいですね。逆のケースならすぐ逮捕されてしまうはずなんですが。
中野 女性によるドメスティック・バイオレンスは近年になってようやく注目されるようになってきたばかりです。夫があまり告発しないそうですね。
福田 彼女は何度か結婚しているんですが、再婚しても同じようなことを繰り返していて。元旦那さんたちにも取材したところ、出会った当初は普通の、しおらしい女性だったというんですが、結婚の約束をした途端に豹変するんだそうです。でも彼女個人には生計を立てる能力はないから離婚するのは損なはずなのに、なんで豹変するんでしょうか。
中野 計画性みたいなことを司るのは別の部分なので、サイコパスがみな無計画なわけではないですし、みな計画的というわけでもないんです。
福田 驚いちゃうんですが、暴力を振るっているのは自分なのに、堂々と警察に通報するんです。それで正当防衛だと言い張る。
中野 自分が弱者だという自認がそうさせるんでしょうね。
福田 自分は弱者、被害者だという「心的事実」のなかで生きているということなんでしょうね。
中野 女性を攻撃してはいけないという社会通念をうまく利用できる人がいるのはたしかです。また、攻撃されるかもしれないから先手を打つというパターンが多いようです。サイコパスは潜在的には女性の方に多いかもしれないと指摘する人もいます。もちろん逆の意見もあるんですが、男性のように暴力に訴えるケースが少ないため、顕在化しにくいということは考えられます。
福田 私が『でっちあげ』や『モンスターマザー』で取材してきた人たちは、一見か弱い女性たちなので、彼女たちが「学校でいじめがあった」「息子が体罰を受けている」「自殺の原因は学校だ」と訴えていると、それを疑ってかかったり、「嘘をついているのでは」と批判するのは難しいんです。しかも嘘だということが明らかになっても美談にはなりませんから……。『でっちあげ』も『モンスターマザー』も「史上最悪の読後感」とか言われました(笑)。
中野 いや、世の中に必要な本だと思います。感動本とか礼賛本とかが増え過ぎて、「世の中本当にそうなのか」という思いが膨れ上がる時に読まれるんだと思います。
(ふくだ・ますみ ノンフィクションライター)
(なかの・のぶこ 脳科学者)
波 2019年1月号より
著者プロフィール
福田ますみ
フクダ・マスミ
1956(昭和31)年横浜市生れ。立教大学社会学部卒。専門誌、編集プロダクション勤務を経て、フリーに。犯罪、ロシアなどをテーマに取材、執筆活動を行なっている。『でっちあげ』で第六回新潮ドキュメント賞を受賞。他の著書に『スターリン 家族の肖像』『暗殺国家ロシア』『モンスターマザー』などがある。