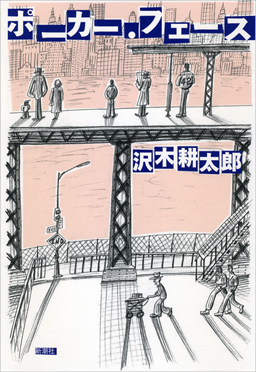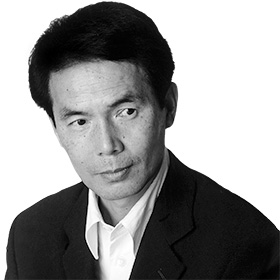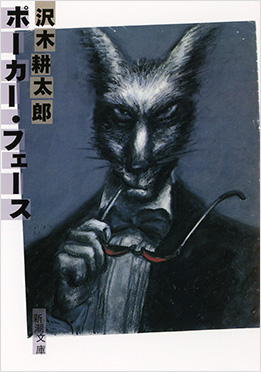ポーカー・フェース
1,760円(税込)
発売日:2011/10/21
- 書籍
冷静さの裏に潜むのは、しびれるように真摯なダンディズム──。
靴磨きの老女の節くれだった指。高峰秀子の潔さ、尾崎豊への後悔。ビートルズになり損ねた男たち。そして、あのサリンジャーが死んだ――彼我の人生が連なり、ひとつの環を成してゆく。圧倒的な清潔感と独自の美意識に溢れた13篇を収録。『バーボン・ストリート』『チェーン・スモーキング』を超える、エッセイ集の金字塔!
どこかでだれかが
悟りの構造
マリーとメアリー
なりすます
恐怖の報酬
春にはならない
ブーメランのように
ゆびきりげんまん
挽歌、ひとつ
言葉もあだに
アンラッキー・ブルース
沖ゆく船を見送って
書誌情報
| 読み仮名 | ポーカーフェース |
|---|---|
| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判 |
| 頁数 | 304ページ |
| ISBN | 978-4-10-327515-2 |
| C-CODE | 0095 |
| ジャンル | エッセー・随筆 |
| 定価 | 1,760円 |
書評
「ポーカー・フェース」ではいられません
1994年の夏、私は沢木耕太郎さんのエッセイをはじめて読んだ。
私は予備校生で十八歳だった。世間はコメ不足で騒がしく、安い予備校の学食のライスは輸入米に切り替えられ、改めて日本の米がうまいことを思い知らされた夏だった。
当時、受験テクニックを偏重する、予備校の現代文の授業が嫌いで仕方がなく、私はその授業の間は、講師の言うことを無視し、ひたすら「新潮文庫の100冊」を読むという行を自らに課していた。なぜ「新潮文庫の100冊」だったかというと、今と異なり、当時の100冊はかなり保守的なラインナップで、いわゆる名作どころを読んでみようというこちらの意図にぴたりと合致していたからである。
その94年に読破を目指していた100冊、若き日の宮沢りえがイメージキャラクターだったやつ(本屋に古いぶんが残っていたのだろう。実際は92年の100冊だった)のなかに、沢木さんの『バーボン・ストリート』があった。私はそこから『深夜特急』の存在を知った。夏休みを使って一気に読み切り、本の中にこれでもかとあふれる自由の空気、翻ってこの不自由極まりない浪人生という現実――、そのあまりの落差に泣いた。
世の多くの若者の未来を狂わせたことでも有名な『深夜特急』だが、かくいう私も、大学に入ったのち海外にひとり旅に出かけ、少なからず未来を狂わされた口である。その結果、紆余曲折を経て物書きになった。もちろん今のところ、いい方向に狂ったと思っている。ならば、もしもあの予備校時代、『バーボン・ストリート』を読まなかったら、この書評を担当することもなかっただろう――、と言ったら言い過ぎか。言い過ぎだ。すみません。
さて、今作『ポーカー・フェース』は、あとがきによると、同じスタイルのエッセイ集として、『バーボン・ストリート』『チェーン・スモーキング』に続く三冊目になる。故小島武さんによるイラストも前二作と同じだ。
沢木さんのエッセイは心に静かに残る。今作を読むにあたり、『バーボン・ストリート』を読み返してみたら、予備校生以来、十七年ぶりだったにもかかわらず、トイレで貴ノ花(先代)に出会ったときの話をくっきりと覚えていて我ながら驚いた。沢木さんの書くエッセイは、何かひとつの印象的な出来事を杭のように地中深く打ちこむ、といった一撃必殺のやり方を取らない。のらりくらりと、ときに右へ傾き、ときに左へ寄り道し、こちらも付き合って結構歩いているはずが、まったくそれを感じさせず、いつの間にかすっと幕が引かれている。そんな不思議な読後感がある。それでいて、十七年経っても覚えている。とてもじゃないが、私にはこんな魔術のようなエッセイの書き方はできない。
いったい、このエッセイの秘密は何なのか。
私はマジック台の脇に貼りつき、何とかしてカードを操るマジシャンからそのトリックを見破ってやろうと気張る子どもの如くページをめくった。
かくして、私はひとつの発見をした。
それは沢木さんのエッセイは「野球型」だということである。
つまり、野球の試合が一回から九回まで、それぞれ表裏に攻守のドラマがあるように、沢木さんのエッセイは話題をいくつも入れ替えつつ回を経ていくのだ。各イニングには旅の出来事があり、過ぎ去った人の思い出があり、財布を持たずに生きているという仰天エピソードがあり、と局所戦のみどころが詰まっている。それでいて九回までの攻防を見終えたとき、一試合を通じての印象が新たに立ち上るよう、沢木さんのエッセイはその多くが構成されているのである。
それに気づいたとき、私はただただ驚嘆した。
たとえば、私が書くエッセイは典型的な「ゴルフ型」だ。はるかグリーンのカップに向け、ひたすら球を飛ばす。カップはすなわち話のオチであり、最短でイーグルを狙うときもあれば、わざと打数を稼ぐこともある。つまり、終着点は打つ前から決まっている。それ以上には最初からなり得ない。
世の多くのエッセイはもちろん、この「野球型」を取らない。いや、取ろうと思っても取れない。各イニングてんでバラバラの話をするのは誰でもできる。だが、全体を見渡したとき、ひとつの野球の試合としてちゃんと成立するよう、人知れずコントロールするのは至難の業であろう。しかも、「コントロールしきらない」コントロールまでされている。
そう、いくら魔術の仕掛けを見破ろうとしても無駄なのだ。こんなおそろしい魔術は、沢木さんしか使えないのだから。
(まきめ・まなぶ 作家)
波 2011年11月号より
インタビュー/対談/エッセイ
ふと、目を凝らし、ふと、耳を澄まして――
――文章のスタイルとして考えたとき、『バーボン・ストリート』『チェーン・スモーキング』と同列に並べられると思うのですが、二十年を経た今、再びお書きになられていかがでしたか?
『チェーン・スモーキング』を書き終えた時点で、また同じようなエッセイ集を出すならば、「飲む」「喫う」の次は「打つ」だと、タイトルだけは決めていました。二つの単語の組み合わせで両方に音引き「ー」がつき、しかも、博打そのものをダイレクトに表す言葉ではない――『ポーカー・フェース』はすべて満たしていました。
いくつもの挿話を連鎖させ、あるひとつのイメージに膨らませていくというスタイルで十編以上書くのはそれなりに大変なのですが、いざ書き出してみると、前二作ほど苦労はしませんでした。僕自身の経験が増えたことで、話のタネのようなものが蓄積されていったのだと思います。ある結末を目指していたのにもう一歩先の結末が見えてきたり、書いているうちに最初の挿話とのつながりが揺らいできたりと、イメージ通りにはいかない面白さもあって、これは同じ時期に書いた短編小説集『あなたがいる場所』でも感じたことでした。結末を決めないまま――全体の八、九割しかわからないまま書くというのは、ノンフィクションの執筆では考えられないことなのですが。
――文庫版『チェーン・スモーキング』の解説で、高見浩さんが、「自分も楽しみながら読者を楽しませようとする」と評されています。今作でも、とにかく楽しんで書かれているように思いました。
それは多分、「このエッセイでは冗談を言ってもいいだろう」という、ある種の軽やかな気持ちがあるからでしょう。酒を呑んでいる時や親しい人と会話をしているときの、普段の僕とかなり近い感じが出ていると自分では思っています。それに、書かれていることは、特別に珍しい出来事ばかりではありません。もちろん、僕がライターという仕事をしているからこそ出会えた特異な人物や物事との関わり合いも含まれていますが、このエッセイを書くために、歩みを早めたりどこかに分け入ったりはしていません。むしろ、日常に起きるごく普通のことに、ふと、目を凝らし、ふと、耳を澄まして、考えてみているのです。そうすると、見えてきたり聞こえてきたりするものがある。無意識でも意識的でもなく、出来事に対してそのように接するのは、前二作を書いた若いときから変わっていない気がします。
――そのように「見えてきたり」「聞こえてきた」中から、何を良きものと判断するか――その価値基準が、ぶれずにずっと在り続けていると感じます。これぞ本物の大人の格好良さだ!と、声を大にして触れ回りたくなりました。
なんという褒め言葉(笑)。でも、価値基準というか、“生き方の好み”とは、それほど簡単に変わらないものだと思います。僕の中で不変なのは、「何が好きか」よりも「何が嫌いか」ということで、嫌いなこと、自分がすべきでないことはしないということを、生きていく上でのささやかな指針としてきました。永くフリーランスとして生きてきたので、ある意味で無限の自由の中にあるわけですが、その自由さを維持するために、多くの不自由さで自分を縛ってきたとも言えるでしょう。極めて逆説的な言い方になってしまいますが。
それに、もうひとつ言えば、これまで知り合った方々の素敵だなと感じたある部分、ある側面を「模倣」しながら、今の僕が出来上がってきたということがあります。例えば、前二作に画を描いて頂いた小島武さんにしても、無頼派と呼べる彼の生き方――自分で自分の身を滅ぼしてしまう、ある種の破滅的な部分に、強く惹かれてきました。今作の連載が始まる前、二〇〇九年に亡くなられてしまいましたが、以前に他の何かで使われている可能性があるとしても、やはり『ポーカー・フェース』の挿画は小島さんにやって頂きたくて、遺族の方の手元に残った画を使わせてもらったのです。
――高峰秀子さん、井上ひさしさんなど、ちょうど連載時に亡くなられた方々のお名前も出てきました。
そこがこれまでの二作と決定的に違うところです。ノンフィクションやエッセイで僕が書いた主人公たちの中で最初に世を去ったのは、競走馬のイシノヒカルでしたが、ここ最近は、立て続けに亡くなってしまっています。僕もそういう年回りになったというわけですが、一緒に酒を飲んだり話をさせてもらったことで教わったことは本当にたくさんありました。有名な方に限らず、今回書いた、ある床屋の主人にしても、あるレストランの店主にしても、市井のごく普通の方から聞く話も、僕にとっては常に新鮮な驚きに満ちています。つまりこのエッセイ集は、僕が普通に生きてきた日々の集積であり、これまでの人生の報告書のようなものかもしれません。
――最後になりますが、「飲む」「喫う」「打つ」ときたら……と、どうしても四作目を期待してしまいます。
実はもし次作を書くならば、タイトルだけは既に決まっています。またタイトルだけ……(笑)。担当してくれた編集者の方たちと酒の席で雑談していたとき小説新潮の編集長が即座に思いついた名タイトルで、先の三条件もちゃんと満たしているのですが、これはまだ明かせません。また二十年後になってしまうかもしれませんし(笑)。
(さわき・こうたろう 作家)
波 2011年11月号より
著者プロフィール
沢木耕太郎
サワキ・コウタロウ
1947年、東京生れ。横浜国大卒業。『若き実力者たち』でルポライターとしてデビューし、1979年『テロルの決算』で大宅壮一ノンフィクション賞、1982年『一瞬の夏』で新田次郎文学賞、1985年『バーボン・ストリート』で講談社エッセイ賞を受賞。1986年から刊行が始まった『深夜特急』三部作では、1993年、JTB紀行文学大賞を受賞した。ノンフィクションの新たな可能性を追求し続け、1995年、檀一雄未亡人の一人称話法に徹した『檀』を発表、2000年には初の書き下ろし長編小説『血の味』を刊行。2006年『凍』で講談社ノンフィクション賞を、2013年『キャパの十字架』で司馬遼太郎賞を、2023年『天路の旅人』で読売文学賞を受賞。ノンフィクション分野の作品の集大成として「沢木耕太郎ノンフィクション」が刊行されている。