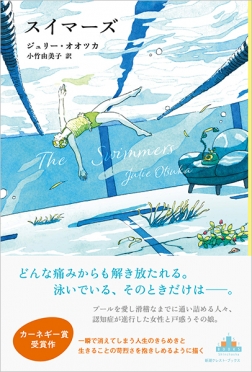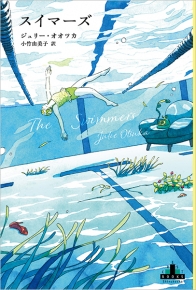
スイマーズ
2,035円(税込)
発売日:2024/06/27
- 書籍
わたしたちはどんな痛みからも解き放たれる。泳いでいる、そのときだけは。
過食、リストラ、憂鬱症――地下の市民プールを愛し、通いつめる人達は、日常では様々なことに悩み苦しんでいる。そのうちのひとり、アリスは認知症になり、娘が会いに来ても誰なのかわからなくなって、ついに施設に入ることになる。瞬時にきえてしまうような、かけがえのない人生のきらめきを捉えた米カーネギー賞受賞作。
書誌情報
| 読み仮名 | スイマーズ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |
| 装幀 | Kashiwai/Illustration、新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 160ページ |
| ISBN | 978-4-10-590195-0 |
| C-CODE | 0397 |
| ジャンル | 文学・評論 |
| 定価 | 2,035円 |
書評
かけがえのない記憶を泳ぐ
ジュリー・オオツカは声の作家だ。繊細に編み上げられた語りがもたらすそのささやくような声は、時に詠唱、時に多声音楽のように美しく、深い哀しみも小さな喜びも鮮明に映し出す。デビュー作『あのころ、天皇は神だった』と第二作『屋根裏の仏さま』では、それぞれ日系アメリカ人強制収容と写真花嫁という、歴史の大きな物語に隠れた、名もなき人々の声を行間に響かせた。
三作目となる本書で、オオツカは一人の女性とその娘の個人史へぐっとフォーカスを絞っている。本書の独特な構成と語りに最初は戸惑うかもしれないが、読み進めるにつれて変化する声にぜひ耳を傾けてほしい。そこに響くのは人生のかけがえのない美しさそのものだ。
第一章は地下深くにある公営プールで泳ぐ「わたしたち」のスケッチから始まる。断片的な描写がリズミカルに連なって、それぞれの個性と、どこかユーモラスで不思議な共同体のディテールが浮かび上がる。年齢も職業も社会階級も違う、地上ではおよそ接点のない彼らは、このプールではどのレーンで泳ぐか、という属性しか持たない。速いか、ゆっくりか、中くらいか。プールは彼らにとって、地上で背負ってしまった責任や病や悩みをひととき忘れ、自分自身に戻り、自由になれる場所だ。その得も言われぬ解放感を共有するのが、スイマーズなのだ。
続く章は、プールの底に生じた小さなひびに端を発する、スイマーズの揺らぎを描き出す。ひびの存在を受け入れられず、目の錯覚だと思う者や、超自然的な啓示と捉える者、自分の過失かもと罪悪感を覚える者など、人々の反応は様々で、まるで理不尽を前にした人間図鑑の様相を呈する。ひびの原因と対応について専門家たちが大仰な自説を述べ、スイマーズがそれぞれ独断と偏見に満ちた解釈を語るくだりは、ひたすらおもしろい。ひびは消えたり増えたりしながらいよいよ存在感を増し、やがてプールは最後の夏を迎える。
三つ目の章では、語りが「彼女」とその娘である「あなた」へがらりと変わる。「彼女」は前二章でゆるく焦点の当たっていた、「認知症の初期段階にある」アリスだ。彼女が覚えていること・覚えていないこと・忘れないことが輪舞曲のように繰り返され、日系アメリカ人であるアリスの人生と家族の歴史が垣間見える。ささやかな日常の瞬間から、人生を左右する出来事まで、喜びも哀しみも、繊細に掬われた記憶の欠片は、否応なく私たち自身の記憶と呼応する。十数ページ前まで覚えていたいくつかの物事は忘れられ、あるいは別のものに置き換り、彼女たちと共に読者である私たちもまた、記憶の儚さの前に立ちすくむ。
四つ目の章ではオオツカのブラックユーモアが炸裂する。介護施設「ベラヴィスタ」の職員が「あなた」に向けて、設備や暮らしの詳細をセールスマンのように滔々と語るのだが、その内容は、営業トークにあるまじき不都合な現実や痛烈な皮肉に満ちている。例えば介護スタッフは仕事を掛け持ちしている有色人種ばかりだとか、食事や睡眠における馬鹿馬鹿しいほど多様な特別サービスはオプション料金がかかるとか。ここでは入所者の記憶、つまり過去は何の意味もなさず、回復する見込みはなく、緩やかに終わりを迎えるための場所であることが突きつけられる。「あなた」はアリスなのだ。
最終章は、「あなた」とその母アリスである「彼女」の過去と現在がより詳らかになる。作者本人を思わせる「あなた」は深い後悔を抱きながら、次第に記憶を失っていく母親と、一番近くで彼女を支える父親の悲嘆に寄り添う。認知症を前にしたそれぞれの戸惑いは滑稽ですらあり、ひびを前にしたスイマーズのようだ。自分自身に戻れるプールは、永遠にはないのだ。彼女から記憶が失われ、名前が失われ、いつしか声も失われ、長くすれ違っていた母娘の視線は、永遠に一方通行のままになってしまう。描写が淡々と続くからこそ、せつなさが胸に迫り、深い余韻を残す。
私たちの人生は、ひとつひとつの記憶で形づくられている。でも私たちはすべてを覚えていることはできない。そのかけがえのなさ、愛おしさ。本書を読み終えたとき、大切な人たちとの記憶を、楽しいものも苦しいものもくだらないものも、これまでにこぼれ落ちてしまったささやかな瞬間や、忘れてしまった感情、忘れまいとする意志、それでも忘れてしまうという現実ごとすべて、抱きしめていたい、と強く願わずにはいられなかった。
(しらお・はるか 小説家)
波 2024年7月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ

浮かび上がる人生の断片
『屋根裏の仏さま』に続く最新作『スイマーズ』で米カーネギー賞を受賞したオオツカ。滑稽なまでにプールを愛し通い詰める人々と認知症の女性、それぞれの日常のきらめきを捉えた本作はどのようにして生まれたのか。
聞き手 スティーブン・スポサト
翻訳 小竹由美子
――『スイマーズ』はあるユニークなコミュニティの活気溢れる描写で始まります。コミュニティというものに意図的に焦点を当てようと考えていたのですか?
はい、公共プールにおけるこだわりスイマーたちの奇妙な仲間意識について書いてみたいと、長年思っていました。泳ぐのが好きなだけではなく、泳ぐために生きているような人たちのことを。とびきりの題材ですし、たっぷりユーモアを込められますしね。でもそれをどう小説にすればいいかよくわからなくって。このコミュニティを描写するだけでは十分じゃないでしょ――ほら、このクレージーなスイマーたちを見てよ、ではね。何かが起こらなくては。そうしたら「ひび」を思いついたんです。わたしは心のどこかで、こういう完全な想像の世界を作り上げては打ち壊すのを楽しんでいるのかもしれません。わたしの作品にはこのテーマが繰り返し現れるようですね。
――プールという隠れ家が、あの底に生じるひびに脅かされる、それはまた極めて象徴的にも感じられます。この世界であなたが特に憂慮なさっているひびはありますか?
この惑星は、ぱっくり割れる寸前のように思えます。湖は干上がり、氷河は融け、海面は上昇し、空から死んだ鳥が落ちてきます。昆虫は消えてゆき、子どもたちは元気がありません。何かがひどく間違っているんです。そしてこの国はかつてないほど分裂しているように感じられます。独裁政治へと向かう流れ、投票権の後退、中絶やトランスジェンダーの権利を巡る論争、非白人の歴史の抹消、こうしたすべてが国家という布の裂け目となっていて、わたしはそれを憂慮しています。とはいえ、わたしはあのひびを、文字通り、正真正銘のプールの底にできたひびとして書いたのですが。
――本書はその後、スイマーの一人であるアリスと、その家族に焦点をあてますね。このユニークなストーリー構成はどういうところから思いついたのですか?
本書は基本的にリバースエンジニアリングの手法で書かれています。アリスと彼女の認知症について書きたいということはわかっていました、そしてプールの世界についてもね、でも、この二つの途方もなく異なったテーマをどう繋げたらいいかわからなかった。するとある日、ただ単にアリスをプールに入れてしまえばいい、スイマーたちの一人にしてしまえばいいじゃないかと気づいたんです。彼女はこの本の半分と半分を繋ぐ糸になるとね。
――本書では、ちょっと変わった視点が使われています(一人称複数、二人称)、しかも完璧に滑らかに。この小説の技法は終始非の打ちどころがありません。あなたは美術を学ばれましたが、それは小説のアプローチに何か影響していますか?
確かに表現形式の構成についてはよく考えますね。要素をどう組み立てるか。書くということの多くはわたしにとって、題材のための適切な形式を見つけるということなのです。そしてそれには、適切な語りのヴォイスを見つけるということも含まれます。絵画と彫刻を学んだことは、確かにわたしの執筆プロセスに影響を及ぼしていますね。絵を描いていた時は、情景をキャンバスにざっと下描きし、それからゆっくりとディテールを描きこんでいきました。そして、小説を書いているときも同じことをしています、パラグラフの概略をざっと、表現には気を配らずに書いておいて、それから戻ってディテールを埋めていくと、徐々に情景がはっきりしてくるんです。
――この小説における認知症とそれが家族に与える影響の描写は、じつに胸を打つ、陰影に富んだ印象的なものです。どういうところから着想を得られたのでしょう?
自分の母親が前頭側頭型認知症によって長い年月をかけて徐々に衰えていくのを見守り、母の病気のせいで家族全員が様々な辛い、相反する感情を味わうのを目にしてきました。そのことについて書きたいと思ったんです。ただしユーモアと思いやりをこめてね、悲惨な長い道のりをゆっくりとぼとぼ最後へと向かう、などというものではなく。陰鬱な認知症小説なんて書きたくありませんでした。母の場合は 、ときおり新事実が出てくるんです。すごく可笑しなことも多く、びっくりするほど明晰になったり。こういうときのことも書いておきたくて。ひとつ、非常に興味深かったのが、第二次大戦の記憶は鮮明なままだったということです、人生の他の部分のことはとうに忘れてしまったずっとあとまで。こうした断片的な記憶が表面へ浮かび上がってくる様は、認知症になるまえのアリスがどんな人間だったかを読者に随時示すには、とても自然な方法のように思えました。
First published on BOOKLIST ONLINE, June 1, 2023.
https://www.booklistonline.com/The-Booklist-Carnegie-Interview-Julie-Otsuka-By-Stephen-Sposato/pid=9781176
(ジュリー・オオツカ)
波 2024年9月号より
単行本刊行時掲載
短評
- ▼Shirao Haruka 白尾 悠
-
地下深くにあるプールで泳ぐ“わたしたち”スイマーの日々から、章を追うごとに“彼女”そして“あなた”と人称や視点人物を変えて浮かび上がってくるのは、認知症の一人の女性とその娘の、人生の断片だ。詩的な語りが鋭く繊細に掬い取る、母と娘の特別でない日々の些細な瞬間は、優しいものも、残酷なものも、どれも愛おしい。それらの記憶が次第に失われていく痛切さは、読者である私たちの、すでに存在すら忘れてしまった瞬間と呼応する。この小説の息をのむほどの美しさは、私たちの人生のかけがえのない美しさそのものだ。
- ▼The New York Times ニューヨーク・タイムズ
-
答えのない問いに答えてはくれないものの、本書の静かな主張は心に響く。つまり、我々を我々たらしめるのは至極ふつうの性癖に他ならないのだ、ということだ。もちろん結末はわかっている。我々みなにとって、それは死だ。でもその時が来るまでは、さまざまなことがあり、さまざまな活動がある、去る時が来るまで、ぐるぐる泳ぐのだ。
- ▼Minneapolis Star-Tribune ミネアポリス・スター・トリビューン
-
オオツカはじつに見事に、代名詞をも含めたあらゆる単語で生きるということの詳細を存分に描き出す。描写は一見客観的に思えるのだが、その細部から感情が滲みだすので、アリスや彼女を気遣う人たちのことがよくわかるのだ。人生を映しだすこの結晶のような物語の一片一片を、オオツカはじつに巧みに示してくれる――ページのあいだには忘れがたい記憶が詰まっている。
著者プロフィール
ジュリー・オオツカ
Otsuka,Julie
1962年、戦後アメリカに移住した航空宇宙エンジニアである父と、日系二世の母とのあいだにカリフォルニア州に生まれる。イェール大学で絵画を学び、コロンビア大学大学院で美術学修士号取得。2002年、小説『あのころ、天皇は神だった』を発表、高評を博す。2011年刊行の『屋根裏の仏さま』は、PEN/フォークナー賞、フランスのフェミナ賞外国小説賞ほかを受賞、全米図書賞最終候補作となった。『スイマーズ』で米カーネギー文学賞受賞。
小竹由美子
コタケ・ユミコ
1954年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。訳書にマギー・オファーレル『ハムネット』『ルクレツィアの肖像』、アリス・マンロー『イラクサ』『林檎の木の下で』『小説のように』『ディア・ライフ』『善き女の愛』『ジュリエット』『ピアノ・レッスン』、ジョン・アーヴィング『神秘大通り』、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』、ジュリー・オオツカ『あのころ、天皇は神だった』『屋根裏の仏さま』(共訳)、ディーマ・アルザヤット『マナートの娘たち』ほか多数。