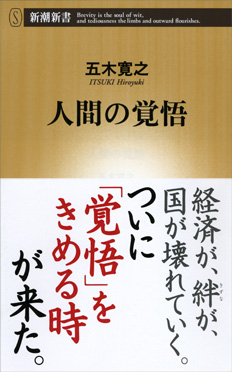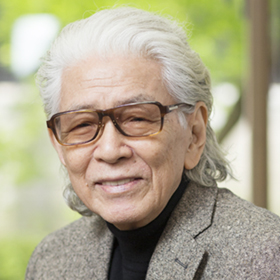人間の覚悟
836円(税込)
発売日:2008/11/17
- 新書
- 電子書籍あり
経済が、絆が、国が壊れていく。ついに「覚悟」をきめる時が来た。
そろそろ覚悟をきめなければならない。「覚悟」とはあきらめることであり、「明らかに究める」こと。希望でも、絶望でもなく、事実を真正面から受けとめることである。これから数十年は続くであろう下山の時代のなかで、国家にも、人の絆にも頼ることなく、人はどのように自分の人生と向き合えばいいのか。たとえこの先が地獄であっても、だれもが生き生きした人生を歩めるように、人間存在の根底から語られる全七章。
書誌情報
| 読み仮名 | ニンゲンノカクゴ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 192ページ |
| ISBN | 978-4-10-610287-5 |
| C-CODE | 0210 |
| 整理番号 | 287 |
| ジャンル | 文学賞受賞作家、倫理学・道徳、教育・自己啓発、趣味・実用 |
| 定価 | 836円 |
| 電子書籍 価格 | 660円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2012/06/29 |
インタビュー/対談/エッセイ
新書という「覚悟」
「なで肩」のメディア
五木 先日、田勢さんが司会をなさっているテレビ東京の「週刊ニュース新書」に出させていただきました。テレビに出るといつも後悔するんですが、おかげさまで、今回だけは周りの人にも好評で(笑)。だけどあの番組は、なぜ新書というタイトルなんですか?
田勢 はじめは「テレビもタイトルより中身が大事」とえらそうに言ってたら、番組のスタートが迫って、つい苦しまぎれで(笑)。ただ、新書がいま一番勢いのあるメディアじゃないか、という感じがあったのは確かですね。五木さんは、『人間の覚悟』がベストセラーになっていますが、ご自分も新書は読まれますか。
五木 ええ。このあいだ数えてみたら、一週間で読んだ本の半分が新書だったので、自分でもちょっと驚きました。新書はこの三、四年で、ずいぶん変わりましたよね。かつての岩波、中公新書のような教養ものから、趣味、実用、健康、スポーツ、ハウツー本まですごく幅広い。全体としてながめると、百科全書みたいな感じがします。
田勢 私も、新書はよく読みますね。必要に迫られて急いでいる場合が多いのですが、新幹線で東京から大阪に行くあいだに一冊読める。出来のいいものは濃いエキスが詰まっていて、単行本みたいによけいなことが書いてないから、私のような余裕のない人間にとっては、とてもありがたいです。
五木 それと新書というメディアには、「なで肩」の良さがあるんですね。肩をいからせず、うまく力が抜けていて、高名な学者でも、誰にでもわかりやすく読ませようという姿勢がある。ハードカバーの「ヘーゲル」には身がまえても、新書だと手が出しやすい。
田勢 私も学生時代は、読みもしないヘーゲルの本を抱えて歩きました。それは興味があるというより、知的な見栄をはっていただけでしたけど。
五木 かつては新書というとスノッブなイメージがあって、ちょっとみばがよかったんです。岩波でいえば吉川幸次郎の『漱石詩注』、斎藤茂吉の『万葉秀歌』など、みな持っていましたね。1990年代半ばに永六輔さんの『大往生』がベストセラーになってから、徐々に新書がカルチャーからサブカルチャーまでを包含するようになったと思います。
田勢 昔とくらべたら、ずいぶん変わりましたね。岩波といえば、『ルポ 貧困大国アメリカ』を書いた堤未果さんのお父さん、意外な方なんですね。五木さんはご存知でしたか?
五木 知ってるも何も、彼にはどれだけやられたか。かつての雀友、ばばこういちさん。無頼派ジャーナリストの彼に、あんな優秀なお嬢さんがいたとは……時代は変わったなあ(笑)。
田勢 でも、彼女は例外的だとして、大学で教えていて痛感するのが、若者たちの知的深度の浅さですね。まず基礎的な学力がない、好奇心が薄い、教養を求めない。三拍子揃っていて、なんだか海の浅瀬でアサリ採りでもしているような気がしてしまうんです。
五木 まあ、1960年代、学生運動の塹壕の中にも「平凡パンチ」は落ちていたわけですから。教養主義にも良いところと悪いところがあって、その鎧を着たがるのも問題だし、といってジーンズにアロハ姿でオペラ観劇をするような文化への態度もどうかな、とは思います。
田勢 昭和35(1960)年の安保闘争のころ、私はまだ高校一年生でしたが、国会周辺のデモに参加していました。右も左も分らないし、別に活動家でもないのに、なぜか、あの場に行かなくては、と思ってしまったんです。
五木 そうでしたか。当時、私は業界誌の記者をしていました。スピグラとよばれる大判カメラを抱えて、警官隊とデモ隊の中を走り回ってました。同じ時代、同じ場所にいた。流行歌のような、時代の共通体験ということなんでしょうね。
田勢 五木さんは『青春の門』や『大河の一滴』のように、時代を象徴する作品を書いておられますが、時代をパッとつかまえたすばらしいタイトルが多い。いつも、ご自分で考えるのですか?
五木 はい。カントやドストエフスキーみたいに、自著のオビ文や宣伝文までは書かないまでも、タイトルは自分で考えます。『人間の覚悟』に関してだけは編集部の提案でしたが、その言葉にピンと来て引き受けてしまったら、新聞連載が迫ってきて大慌てで(笑)。ただ、一行言葉の引力というのか、オバマの「Yes we can!」もそうですが、時代をビクリとさせる言葉、というのがどこかにあるものなんですね。
田勢 五木さんの文章、作詞された歌の中にも、ハッとさせるフレーズがしばしば出てきますね。私は五木ひろしさんの「ふりむけば日本海」にある、「如月の白い風が吹く」という部分が大好きで。吹雪でも雪でもない、ああいう絶妙の表現は、どうしたらできるんでしょう?
五木 さすが、『島倉千代子という人生』を書かれただけあって、よくご存知ですね。以前、PR誌やCMソングを作っていたこともありますが、旅先などで退屈したときに、よくそういう言葉を探しています。習い性というか、そういうことが好きなのかもしれません。
田勢 思いつきみたいなものですが、新書がよく読まれることと、俳句ブームには、似たところがある気がするんです。ちょっと知的で、あまり手間がかからない、空いている時間を有意義に満たしてくれる。私の同世代は、みなちょうど定年退職ですが、会社を辞めると、きまって俳句か、畑仕事をはじめます。
五木 なるほど、ひとつの見方ですね。私は旅が多いので、地方に行くとあちこちで吟行のグループを目にします。ほとんど例外なく高齢者で、アマチュアで、みなデジタルカメラをもっている。
田勢 私も俳句は好きですが、句会とか吟行のようなものはちょっと遠慮したいタイプでして……。
五木 私もそうですね。子供のころから俳句は好きでしたけど、何かを見るたび、こう詠めるな、ああ詠めるかな、と考えていたら人間まで俳句的になってしまう気がして、句作そのものは封印してきました。ところで田勢さんは、新書はお書きにならないんですか?
田勢 ええ。編集者が目次から小見出しまで全部作って、この通りに書いてくれ、と企画を持ってこられたことは何度かあります。でも私は元新聞記者といっても、本を書くことに関してはアマチュアで、エネルギーの消耗が激しいんですよ。
五木 確かに、昔は新書三冊書けば家が建つとか、三十年は本屋に並ぶといわれたものですが、今は毎月どんどん新刊と入れ替わるから、本としての寿命が短くなった。単行本みたいに文庫にもならないし、単価も安いから、書き手にとっては不利なところがありますね。
田勢 最初はおだてられても、いざ売れなかったりすると、急に相手が冷たくなるのが目に見えるようで(笑)。
五木 編集者も変わりました。自分を含めて、かつては「行方不明」になる作家がたくさんいて、編集者が箸の上げ下げまで日夜つきあうような感じがあった。最近は大手の出版社でも、起用するタレントを決めて企画を提案するのが仕事で、あとは編集プロダクション、本の宣伝はPR会社に委ねて、編集者はコスト計算だけというところが出てきたそうです。
田勢 そういうものですか。まあ、学生しかり、活字メディアしかり、すべては社会の反映なんでしょうけどね。
五木 ただ私は物書きとしてやってきましたが、活字だから押し戴かなくては、という気持ちはまったくないんです。仏典、聖書、論語、いずれをみても活字が二次的な記録手段にすぎないことが分かります。コミュニケーションにおいて、その場で、人間の声によって語られるものに勝るものはありませんからね。
ジャーナリズムへの懐疑
五木 最近は、テレビで話題になれば本が売れる、書評はあまり効かないという声をよく耳にします。でも、今も人気の高い『遠野物語』だって、はじめは数百部からですよ。だから、本も三、四千部売れたらそれで充分じゃないかとも思うけど。テレビも視聴率ばかり気にかけると、傍目には賑やかなようでも、どんどん奥行きがなくなります。近ごろのように、現場も演出も編集もバラバラに分業化されていくと、効率はあがっても、どこか味わいがなくなりますよね。
田勢 私自身は、テレビの仕事はできれば早くやめたい、視聴率は低くてもいいじゃないか、と言い続けてるんです。もちろん逆説的な意味もありますが、半分は本心ですね。
五木 それは大事なことですね。でも「ニュース新書」は、いい番組ですよ。そういう欲をかかないスタンスで、視聴者も増えていくのが理想的なんです。
田勢 おほめいただいて恐縮です。週末というと、なんだか叱りつけるような報道番組が多くて。私はそういう柄じゃないですし、生放送にもかかわらずネコが気ままにスタジオをうろついているぐらいがちょうどいい(笑)。
五木 私はもともと、日本のジャーナリズムというものに対して懐疑的なんです。たとえば、戦後六十年以上もたつのに、いまだにアメリカは物質主義のプラグマティックな国というイメージでしょう。大統領就任式の宣誓でも聖書がフレームアウトされるし、通貨まで「神の御名のもとに」発行されるキリスト教信仰の深さなどは、まず伝えられません。
田勢 確かにそうですね。そういうことを新聞のコラムでちょっと突いたりしても、まったく反応がないですから。
五木 知識人はよく大衆の愚かさ、残酷さ、軽挙妄動ぶりを嘆きますが、それなら貴族たち、言い換えるとジャーナリズムはちがうかというと、そんなことはないと思いますね。
田勢 実際、新聞、テレビ、雑誌を含めて、日本のジャーナリズムは明治以降に日本が行った戦争に対して、すべて賛成しています。本当の意味で、国家権力と対決したことなどありません。個々の記者の頭の中に、反権力という単語はあっても、やっぱり戦後与えられた民主主義の中でのものにすぎないんです。
五木 五歳の時かな、南京が陥落したというので父に連れられて町に行ったら、花電車が通るわ、提灯行列も出るわの大騒ぎでした。でも実際にはその日は、南京の一部に日本兵が入っただけだった。先の大戦も、軍部だけが暴走したのではなくて、イケイケどんどんで国民世論を作った新聞、それでさらに燃え上がった民意に責任があったといわざるをえない。
田勢 その通りですね。話はちがいますが、先日、民主党の小沢代表の秘書が逮捕されてからの報道ぶりをみても、検察のリークを「関係者によれば」としてそのまま全メディアが報じる。そういうことでいいのかな、と思います。
五木 いずれにしても、マスコミのまとまり方には、非常に危うい感じがします。先月のWBC大会で、野球のルールを知らない人までがあれほど大騒ぎすることには、いささか違和感を覚えました。報道がひとつの方向に煽ったこともあるでしょうが、他に楽しみや希望はないのか、とも思ってしまいましたね。
新書はゲリラ
田勢 先日おかしなことがあって、研究室にお菓子が送られてきて、何の気なしにあけて食べてから、ふと気がついたら現金が底に敷いてある。もちろん返送しましたが、誰がこんなことするのかと思って、送り主の住所からネットを使って調べてみたら、しまいにはその人の家の間取りまで分かってしまった。
五木 私も少し前に新型携帯電話の売り場で、日本列島の全図から自宅マンションの玄関まで、画像をたどって見せられて、たじろいでしまいました。
田勢 ウィキペディアも困りもので、確かにうまく整理されていて、A4二、三枚ぐらいでまとまった情報が得られる。学生がそれをコピー・ペーストしてレポートを作ると、「教授」としては、それを見つけてハネるのがたいへんで……。
五木 同情しますね。私の知人の大学教授も、「親鸞と尺八」という何とも斬新な題のレポートをわくわくしながら読んだら、それぞれの生涯と成り立ちが貼り付けられていて、最後に一言、「結論として両者に共通項はない」だったとあきれかえってました。
田勢 それはひどい。けど、ありがちなことですよ。
五木 最近の大きな本屋さんは、文庫の海、新書の海、新刊の海、溺れ死にでもしそうな気がします。店員をつかまえて「松本清張の――」と聞くと、「せいちょう、字はどう書きますか?」なんていいながらキーボードを叩きだす(笑)。
田勢 書店にも本のプロが減ってきたということでしょうか。それは困りますね。
五木 ネットだと飛行機の座席も安い、ETCなら高速料金が安くなる、今度はデジタル放送にする、こちらはもういいっていうのに、そうしないと世の中に取り残されてしまうような錯覚さえある。あらゆることがデータ化されていくのは、裏を返せば監視の網目にもなりますからね。透明でやわらかそうな規制、いわば「ビニール質のファシズム」が近づいているような気がしています。
田勢 地デジは、チャンネル数がどうのこうのというより、国が主導する壮大な景気対策という面がありますからね。
五木 ただ私は、ネットやケータイによって現代人が劣化したとは言いません。驚くほどに、変質したのだと思います。メディアの側も、どんどん分化していますよね。年代性別を問わず、誰もが知っている流行歌がなくなり、今はJポップのミリオンセラーでも、世代によってはまったく知らない。同じ世代でも、趣味嗜好によってまるで畑がちがう。なんだかレンガの壁みたいに、日本人が縦横に割れているような感じがする。
田勢 なるほど。
五木 このところ、朝日の「論座」や文藝春秋の「諸君!」、講談社の「現代」と月刊誌が次々と休刊に追い込まれました。
田勢 私もその休刊雑誌の定期執筆者の一人でしたけど、以前は仕事上、総合雑誌は読んでいないと困ることがあったのですが、近頃は不便どころか、まったく困らないのが困りものです。
五木 活字メディアにとってはむずかしい時代ですね。それでも、本屋さんに行って、出版がまだ健全だな、と思うのは高度な学術書からはじまって、いったい誰が読むのか、みたいな少部数の本でも、幅広く並べられていること。売れる本しか作らない、という薄っぺらなことになれば、もはやカルチャーを支えていく底力がなくなりますからね。
田勢 たしかに、そうかもしれませんね。でも最近、「~力」という本がホントに多いですね。新書にもあんまり多すぎて、そのうち「力を抜く力」までいってしまいそうな(笑)。
五木 私も十年以上前から、『他力』『情の力』『不安の力』『鬱の力』と出し続けてますから、ミコシをかついだ一人です(笑)。ただ、活字文化の中の新書について考えると、サブカルチャー、トンデモ本みたいな行儀の悪い本でもどんどん出してみたらいい、と思うことがありますね。他が正規軍だとすれば、新書というのはゲリラ。学術、評論であれ、ジャーナリズムであれ、何でもできます。和しやすい国民性、マスコミも一方向にどっと流れる。そんなときには冷や水をかけることも必要でしょう。七百円程度の吹けば飛ぶような一冊、たかが新書、されど新書。教養主義的な衣も脱ぎすてて、いまは死語に近いですが、「出版界の無頼派」として頑張ってくれることを期待しています。
(いつき・ひろゆき 作家)
(たせ・やすひろ ジャーナリスト)
波 2009年5月号より
蘊蓄倉庫
心のうめき声
「憂鬱」は、国や時代を問わず、誰もが自分の内に抱え込んでいるものだと著者は言います。その性質も程度も、あらわれ方も人それぞれですが、石川啄木などは年少の頃からその自覚が顕著だったのではないか、と。愁いに満ちた歌集『一握の砂』に、こんな一首があります――「人といふ人のこころに 一人づつ囚人がゐて うめくかなしさ」。社会生活者としてはほとんど失格だった天才歌人は、自分の中に別の何者かがいることを鋭敏に感じとっていたようです。
掲載:2008年11月25日
担当編集者のひとこと
変わるものと変わらぬもの
著者の五木氏は『蒼ざめた馬を見よ』『青春の門』ほか数々の小説作品をはじめ、エッセイ集『風に吹かれて』や、『大河の一滴』『他力』など多くのベストセラーでも知られています。
常に変わりゆく時代の流れに対して独特のアンテナをはたらかせながら、その一方では、どんな時代でも変わらない「人間のさが」を見つめ続けるという姿勢。それは、連載開始から33年をすぎ、ギネスブックにも載る夕刊紙のコラムで「今」を問い、他方では小説「親鸞」(全国ブロック紙・地方紙で連載中)において、人間存在の根底を追究していくところにも、あらわれているように思います。
人はいつもポジティブに明るく生きるべきだ、そのように説く自己啓発本は数多くあります。しかし、人間はそれほど単純なものではないということは、本書を読むとよく分かります。
軍国少年だった頃、悲惨な引揚げの記憶、旅多き四十二年間の作家生活のなかで出あった苦しみや様ざまな想い……来年には喜寿を迎える著者がたどりついた「覚悟」をぜひお読みください。
2008/11/25
著者プロフィール
五木寛之
イツキ・ヒロユキ
1932(昭和7)年、福岡県生れ。1947年に北朝鮮より引き揚げ。早稲田大学文学部ロシア文学科に学ぶ。1966年「さらばモスクワ愚連隊」で小説現代新人賞、1967年「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞、1976年『青春の門』で吉川英治文学賞を受賞。著書に『朱鷺の墓』『戒厳令の夜』『風の王国』『風に吹かれて』『親鸞』『大河の一滴』『他力』『孤独のすすめ』『私の親鸞』『こころは今日も旅をする』など多数。バック『かもめのジョナサン』など訳書もある。