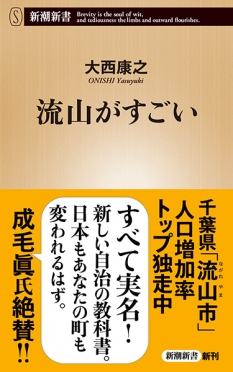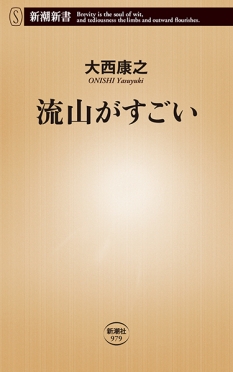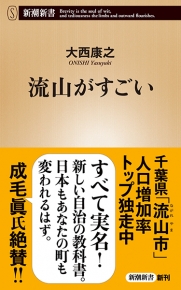
流山がすごい
858円(税込)
発売日:2022/12/19
- 新書
- 電子書籍あり
千葉県「流山(ながれやま)市」。人口増加率トップ独走中。すべて実名! 新しい自治の教科書。日本もあなたの町も変われるはず。成毛眞氏絶賛!!
「母になるなら、流山(ながれやま)市。」のキャッチコピーで、6年連続人口増加率全国トップ――。かつては数多ある東京のベッドタウンの一つにすぎなかった千葉県流山市がいま、脚光を浴びている。「子育て中の共働き世代」に的を絞った政策をはじめ、人材活用、産業振興、都市計画、環境保全まで、あらゆるテーマを同時並行で推し進める。流山市在住30年、気鋭の経済ジャーナリストが、徹底取材でその魅力と秘密に迫る。
書誌情報
| 読み仮名 | ナガレヤマガスゴイ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-610979-9 |
| C-CODE | 0230 |
| 整理番号 | 979 |
| ジャンル | 政治 |
| 定価 | 858円 |
| 電子書籍 価格 | 858円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2022/12/19 |
書評
流山=女性が主役のサクセスストーリー
書名を初めて耳にした瞬間から、これは読まなければと思っていた。できればその上で、書評を書きたいものだと思っていた。そこへ執筆依頼を頂戴したのだから、さすがは新潮社さん、こういうのを「以心伝心」というのだろうか。
それというのも評者は、千葉県流山市の隣に位置する柏市に家を買って30年となる。本書を書いた大西康之氏が、流山市に戸建てを買って日本経済新聞社に通っていた時期とほぼ重なる。要は地方出身の「千葉都民」同志ということになる。そして近年の流山市の発展ぶりを横目で見ながら、「おぬし、なかなかやるな」と感心していた。本書はそのサクセスストーリーを解剖してくれる。
「今風だな」と感じるのは、流山市には無数のヒーローが存在することだ。その中で強いて主役を求めるならば、井崎義治市長ということになるだろう。
日本における街づくりの多くは、「デベロッパーが作って終わり」である。ところがアメリカには、価値の高い街をつくる「アーバン・プランナー」という仕事があり、井崎はもともとヒューストンで働く都市計画コンサルタントであった。それが家庭の事情から帰国することとなり、データだけから「将来的に最もポテンシャルが高い」と判断して、1988年に流山駅から徒歩12分のマンションを「実物を一度も見ることなく」購入する。
ところが実際に住んでみると、流山市の都市計画はあまりにも「素人レベル」であった。「見ちゃいられない」と井崎は一市民として行政に携わるが、地付きの「名士」から「あんたはマンション住まいだから、新住民ですらない。仮住民だな」と言われてしまう始末。
ついには、「自分がやるしかない」と市長選に立候補する。既成政党の支持を受けない候補者であったが、景観保全や自然保護運動をしている女性たちや定年退職後のサラリーマンたちの支持を集めて、2度目の挑戦で当選を果たす。それが2003年のことである。
井崎は市役所に「マーケティング課」を新設し、「母になるなら、流山市。」というキャッチコピーを打ち出す。このときのことは、お隣の柏市住民として「思い切ったことを言うものだな」と驚いたことを覚えている。都心に通う共働き家庭にとって、子育ては最重要課題である。ところが保育所などの子育て支援は、行政にとってまことに扱いが難しい問題だ。「保育園落ちた日本死ね!!!」という匿名の書き込みが、2016年の流行語大賞に選ばれたことはどなたもがご記憶のことだろう。
そこへ流山市は、われわれは「保育の楽園」を目指します、と広言したのである。そして実際に、駅前の送迎保育ステーション設置など、共働きの子育て世代向けのサービスを実施する。おりしもTXこと「つくばエクスプレス」が開通し、新たな都市住民が流山市に押し寄せてきていた。現在、実に6年連続で、流山市は人口増加率全国トップを独走中なのである。
ただし、行政にできるのはここまでだ。後は実際に新しく住み始めた人たちの出番となる。本書は流山に住み始めた人たちの姿を描いているが、その多くは女性である。エンジニアとしてバリバリ働いていた近藤みほは、子育てをきっかけに流山市に転居し、ついには市議となって活動するようになる。松戸市生まれの稲葉なつきは、流山旧市街地の古民家を改装し、31歳で和菓子屋のオーナー店長となる。リクルートでモーレツサラリーマンをやっていた小野内裕治は、退職後に流山市の耕作放棄地で有機農業に挑戦している。
こうした「外から来た人たち」が、流山市を舞台に小さな冒険を積み重ねているところが、いかにも今風の「サクセスストーリーズ」と言えよう。なかには既に流山市を「卒業」し、次の場所に向かっている人も居る。大事なのは「変化」なのである。
逆に流山市の地付きの人たちが、昨今の変化をどのように感じているのかも気になるところで、著者の筆がそこまで伸びていないことが惜しまれる。とはいえ、人口減少社会のこの国においては、全国各地で行われている「街おこし」の成否が重要な意味を持つ。昨今盛んに言われる「少子化対策」も、地域社会の助けがなければ大きな成果を挙げることは望み薄であろう。
「たかが人口20万人の市政じゃないか」との声もあるかもしれない。が、中央が機能不全に陥って久しく、国全体にも疲弊感が漂う中にあって、「こういう話を聞きたかった!」という読者は少なくないのではないだろうか。
(よしざき・たつひこ エコノミスト)
波 2023年2月号より
流山=地方自治と都市計画の「生きた教科書」
「柳瀬さん、今、一番すごいビジネス街に行ってみない?」
大西康之さんが誘ってくれたのは2021年3月のことだった。その日、私は千葉県柏市の蔦屋書店で、前年に刊行した拙著『国道16号線―「日本」を創った道―』のPRのため、目の前を走る国道16号線がいかにすごい道なのか、地域住民を洗脳していた。
その中に大西さんもいた。隣街の流山市民として、ライバル柏市の模様を偵察に来たのだ。柏市民の皆さんをすっかり16号線至上主義者に変えた私は、彼に導かれるまま車で流山市の「流山おおたかの森」駅前を抜け、台地を降りて江戸川沿いの河川敷に向かうのであった。
河川敷じゃん! どこがすごいビジネス街? と思うまもなく、ずらりと並んだ巨大な建物群が目に飛び込んできた。
アマゾン、楽天、ヤマト運輸、大和ハウス、GLP……。通販や物流大手の看板が掲げられた物流センターが数キロにわたって並んでいる。「流山の最新ビジネス街です」。大西さんはニヤリと笑った。
『流山がすごい』を手に取ったとき、あの時の大西さんのニヤリを思い出した。彼はすでに調べ始めていたのだ。この街の秘密を。
2023年現在、首都圏で「子育て」用に家探しをしていて、流山の名前を知らない人はいないはずだ。「SUUMO住みたい街ランキング2022首都圏版」で得点ジャンプアップした街ランキング1位、人口増加率は全国の市の中で6年連続日本一。0~4歳の人口転入数も首都圏で一番多い。名実ともに大人気である。
かつて、流山は千葉の田舎っぽさの代名詞的存在だった。その名がメディアに登場したのは1970年代後半。江口寿史のギャグ野球漫画『すすめ!!パイレーツ』でお荷物プロ野球球団の本拠地という不本意なデビューである。その後も都心からの交通が不便なことから「千葉のチベット」などと呼ばれた。
なぜ、そんな流山に子育て世代が次々と移り住むようになったのか?
よく知られているのは、秋葉原からつくばまでを結ぶ鉄道「つくばエクスプレス」が開通し、3つの駅ができたこと、その駅の1つ、「流山おおたかの森」の開発が成功し、イケてるショッピング街と素敵な住宅街がオープンしたこと、などである。
ただし、似たような条件を満たし、流山よりも都心からもっと通勤至便な街は、首都圏に数多くある。流山がすごくなった謎を、大西氏は「インタビュー」で解き明かす。なぜインタビューか。現在の流山が成ったのは、数多くのキーパーソンたちがいたからだ。自らの手で夢を描き、計画をたて、困難を撥ね除け、マーケティングし、街の形を作り上げた人々がいたからだ。
米国の大学院で街づくりのいろはを学び、腕を振るってきた都市計画のコンサルタント。キャリアウーマンとしてばりばり仕事をしてきたが、結婚、出産ときて、都心での子育てに限界を感じた女性たち。二子玉川=ニコタマを、鉄道と自動車の両方でアクセスできる未来型のショッピングタウンに変身させたビジネスパーソン。リクルートを飛び出て、有機農法をビジネスにした起業家。少年時代に近くのサッカークラブで頭角を現し、プロサッカークラブを流山に設立した男。そして、「千葉のチベット」と呼ばれるほど不便だった流山に、あの田中角栄を口説き、「つくばエクスプレス」の駅を3つも開設することに成功した、地元政治家。
流山のコピーは、「母になるなら、流山市。」である。コピーに偽りはない。保育の充実ぶり、共働き夫婦が安心して子育てできるハードとソフトの品揃え、鉄道と徒歩と自動車、複数の移動手段を自在に使える交通インフラ。都心から30分圏内にもかかわらず、自然豊かでスポーツ施設が充実し、買い物も娯楽も揃っている。偶然できたのではない。さまざまなジャンルのプロたちが当事者として参加した結果である。
そう、『流山がすごい』は、街づくり革命の物語だ。流山というプロジェクトが形になっていくプロセスを、大西さんは当事者たちの「声」で明らかにしていく。その生々しさは、彼でなければ文字にできなかったろう。30年来の地元住民で、経験ゼロから子供サッカークラブのコーチとして汗を流す大西さんもまた、すごい流山を創った一人なのである。
地方自治と都市計画の、文字通り「生きた教科書」にして、最高のエンタテインメント。それが本書である。
(やなせ・ひろいち 東京工業大学教授)
波 2023年1月号より
蘊蓄倉庫
田中角栄を口説いた「流山の恩人」
6年連続人口増加率日本一となり、今や全国の自治体関係者からの注目を浴びる存在となった千葉県流山市。人口が増えたのは、「共働き子育て世代」向けの政策が成功した結果、というのはもちろんなのだが、とはいえ、かつては「陸の孤島」だった流山につくばエクスプレスを通した人物がいたことを忘れてはならない。1983年から流山市長を2期務めた秋元大吉郎氏。流山の発展に鉄道が必要であることを痛感していた同氏はまず、当時も絶大な権力を誇っていた田中角栄元首相を口説く。その後も永田町・霞ヶ関詣でを繰り返し、流山市に「常磐新線」(当時の仮称)の駅を3つ作ることを決定させた。角栄氏を口説いたのは、氏が脳梗塞で倒れる13日前という、その影響力を利用できるギリギリのタイミングだった。秋元市長の努力がなければ、流山おおたかの森駅はなく、「千葉のニコタマ」もなかった。流山は1日にしてならず。
掲載:2022年12月23日
担当編集者のひとこと
柏出身者から見た流山の変貌
実は担当編集者は隣りの柏市で育ちましたので、流山のことは昔からそれなりに知っています。しかし、この本の打ち合わせのために、著者の大西康之さんと何度か「流山おおたかの森」駅周辺で打ち合わせたところ、昔とは大違いの未来的な景観に驚き、おしゃれなカフェで談笑する素敵な女性たちに感慨を覚えました。こんな人たちは、昔はこの辺にはいなかったなあ、と。
かつては高島屋やそごうなどのデパートが駅前で栄えていた柏のほうが地域の先端を行っていたはずなのですが、今は「繁栄度」が流山と逆転した感があります。柏に流山ほどの「物語」が見つかれば、そんな本も企画してみたいものです。
2022/12/23
著者プロフィール
大西康之
オオニシ・ヤスユキ
1965(昭和40)年生れ。愛知県出身。1988年、早稲田大学法学部卒業、日本経済新聞社入社。1998(平成10)年、欧州総局(ロンドン)、日本経済新聞編集委員、日経ビジネス編集委員を経て2016年に独立。著書に『ロケット・ササキ ジョブズが憧れた伝説のエンジニア・佐々木正』『流山がすごい』『起業の天才! 江副浩正8兆円企業リクルートをつくった男』『三洋電機 井植敏の告白』『稲盛和夫 最後の闘い JAL再生にかけた経営者人生』『会社が消えた日 三洋電機10万人のそれから』『ファースト・ペンギン 楽天・三木谷浩史の挑戦』などがある。