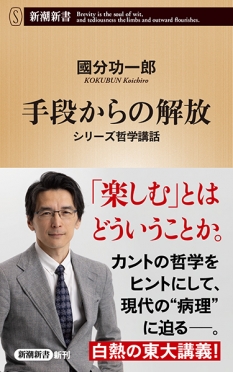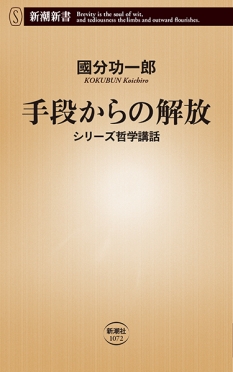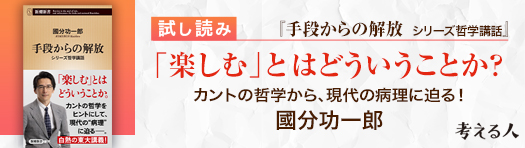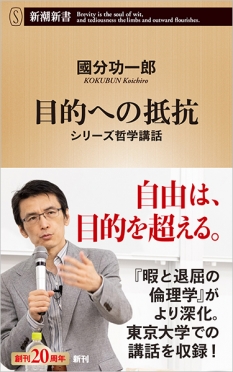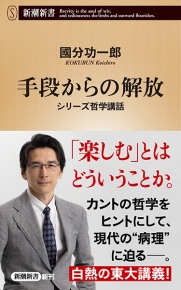
手段からの解放―シリーズ哲学講話―
968円(税込)
発売日:2025/01/17
- 新書
- 電子書籍あり
「楽しむ」とはどういうことか。カントの哲学をヒントにして、現代の“病理”に迫る──。白熱の東大講義!
「楽しむ」とはどういうことか? 『暇と退屈の倫理学』にはじまる哲学的な問いは、『目的への抵抗』を経て、本書に至る。カントによる「快」の議論をヒントに、「嗜好=享受」の概念を検証。やがて明らかになる、人間の行為を目的と手段に従属させようとする現代社会の病理。剥奪された「享受の快」を取り戻せ。「何かのため」ばかりでは、人生を楽しめない──。見過ごされがちな問いに果敢に挑む、國分哲学の真骨頂!
はじめに――楽しむことについての哲学的探究
第一章 享受の快――カント、嗜好品、依存症
生存にとっての余白/消費と浪費/楽しむとはどういうことか/嗜好品という語/ドイツ語の或る単語/嗜好品についての哲学的考察/近代になって現れた嗜好品/「嗜好品」という造語にこだわること/カントのタバコ論/嗜好の低い地位/嗜好=享受の概念/享受の対象としての快適なもの/批判哲学の三部門/快の対象/四つの象限/善いもの/道徳的であることがもたらす快/善行の困難、不正の可能性/目的を自身のうちにもつ存在としての人間/享受するだけの生/美しいもの/快適なものは私にとって好ましい/構想力と悟性の通常の働き/構想力と悟性の自由な戯れ/目的なき合目的性/崇高なもの/構想力の挫折/構想力の奮起/崇高の合目的性/快適なもの/快適なものと美しいもの/各人に固有の趣味/快適なものと善いもの/欲求能力の低次の実現とは/第三象限と第四象限の結びつき/第三象限と第四象限の区別/目的から自由である快適なもの/四つの快の対象の関係/第四象限と第一および第二象限との関係/第四象限と第三象限との関係/第三象限と第四象限の区別、再び/享受の快が手段にされる時/病的になること/目的に駆り立てられる生/病的であることからの二つの脱出路/嗜好品の定義について/依存症の問題/目的への抵抗、手段からの解放/アドルノたちの文化産業批判/固有の趣味ならば/生活の手段化/カントにおける享受への理解
【注】
【参考文献】
第二章 手段化する現代社会
初めてのカント論/インフラからアーキテクチャーへ/浪費と消費、ふたたび/『暇と退屈の倫理学』で書き残したこと/目的に対立する嗜好品――嗜好品とは何か/「嗜好品」というドイツ語/カントのタバコ論/「快適なもの」は人間を成長させない/カントの三つの“批判”/一致の関係――『純粋理性批判』(認識能力)/因果関係――『実践理性批判』(欲求能力)/効果の関係――『判断力批判』(感情能力)/快適・美・崇高・善――四つの「快」/気持ちよくなるから親切にする?――善について/「善であるから善を為す」/「どうしてなのかはよくわからないけれども」/カントの「目的」/「このバラは美しい」――美について/快適なものの判断が人それぞれでなくなる社会/構想力と悟性/逆転する関係性/目的なき合目的性/不快から快へ――崇高について/目的からの自由――快適なもの/低次の欲求能力/第四象限を第三象限から区別すること/手段化の問題/全四象限の関係/第四象限の手段化――健康について/享受の快の消滅/問題はむしろ手段/違法薬物の問題/依存症と自己治療仮説/最後に――享受の快を剥奪された生
おわりに――経験と習慣
書誌情報
| 読み仮名 | シュダンカラノカイホウシリーズテツガクコウワ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮新書 |
| 装幀 | 新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 新書、電子書籍 |
| 判型 | 新潮新書 |
| 頁数 | 208ページ |
| ISBN | 978-4-10-611072-6 |
| C-CODE | 0210 |
| 整理番号 | 1072 |
| ジャンル | 哲学・思想、思想・社会 |
| 定価 | 968円 |
| 電子書籍 価格 | 968円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2025/01/17 |
関連コンテンツ
担当編集者のひとこと
「楽しむ」とはどういうことか?
國分功一郎さんの最新刊『手段からの解放―シリーズ哲学講話―』は、「楽しむとはどういうことなのか?」について、哲学的に探究した一書です。その問題意識は、2011年刊行のロングセラー『暇と退屈の倫理学』にすでにあり、以来「この十数年あまりずっと考え続けて」きたものであると國分さんは語っています。
そのヒントとなるのが、大哲学者のイマニュエル・カントの議論です。200年以上前にカントが「嗜好品」を論じた文章をとっかかりにして、「嗜好=享受」の概念を検討していきます。そして明らかになるのは、人間の行為すべてを目的と手段に従属させようとする現代社会の病理(そのひとつが依存症)です。
「目的」と「手段」、そのどちらも現代を生きる人間にとって欠かせないものだと認識されています。適切な「目的」を設定し、それを達成するための最良の「手段」を選択すること──それこそが仕事や学業を遂行するために最も大切なことであると。
しかし、そればかりに囚われてしまうことで、「嗜好」や「享受」といった「楽しむ」という純粋な喜びが失われつつあるのではないか? 失われるだけではなく、それが「依存症」のような病理を生み出しているのではないか──ということを、カントの議論を精緻に辿りながら明らかにしていくのが、本書の醍醐味です。
2023年刊行の『目的への抵抗―シリーズ哲学講話―』(新潮新書)に続く、哲学講話シリーズの第二弾でもある本書は、前作同様、東京大学の講話をベースにしています(ただし、前半は文芸誌「新潮」掲載の論文)。「語り」をベースにしているため、「哲学」をテーマとしていても、語り口はソフト。「目的」と「手段」という、これまであまり批判的に検討されることのなかった概念についてのスリリングな論考をお楽しみください。
2025/01/24
著者プロフィール
國分功一郎
コクブン・コウイチロウ
1974(昭和49)年生れ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。2025(令和7)年3月現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。専攻は哲学。2017(平成29)年、『中動態の世界』で小林秀雄賞を受賞。著書に『暇と退屈の倫理学』、『ドゥルーズの哲学原理』、『近代政治哲学』、『スピノザ──読む人の肖像』、『目的への抵抗』、『手段からの解放』、『〈責任〉の生成──中動態と当事者研究』(熊谷晋一郎と共著)ほか。