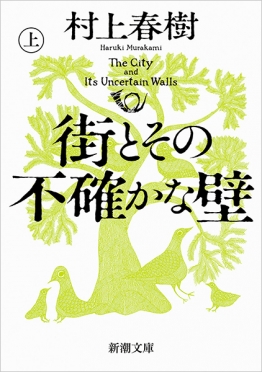リッツ・ホテルの一室に全員、集まっていた。中庭が見渡せる窓はすっかり開け放たれていた。私はブーツを脱ぎ、ベッドに枕を四つ重ねて横になり、本を読んでいた。他のベッドの上には解体され、研かれ、組み立て直された銃が無造作に幾つも並べられ、その上にこれまで通過してきた地帯の地図が何枚も雑然と広げられていた。誰もがせっせと作業を続け、私はゆったりと休息と読書に身を任せていた。マルタン以来、まるまる一週間、ものを読んだりする時間はまったくなかった。朝になれば北に向かう予定だ。
シャルル・リッツが本を数冊届けてくれ、その上、シャンパンを六本、差し入れてくれた。一本だけ自分用に抜き取り、残りは仲間に配った。連中は味をよくするために、シャンパンを何本か混ぜ合わせ、それからグラスに注いで飲んでいた。
庭の木々から登って来る太陽を眺めるのは素晴らしい。それに司法省の壁に陽の光がチラチラさざめくように揺れるのも気に入っている。瑞々しい芝生の上には、ピカピカに研かれ、油を差した銃や、長い銃身の先端に付いているキノコ型の、どっしりしたバズーカ砲の銃頭などが、黄金色をしたワインを透かして眺められた。その情景は実に心地がよかった。
シャルル・リッツが灯りを手にして緊張感を漂わせながらも誠実なる共謀者として現れると、誰もが嬉しそうな眼差しでその姿を見上げた。
「必要なものは全部、揃っていますか、パパ」
「完璧だな」
「役立ちそうですか」
「主人に見せてやるといい、オーニー」
オーニーがシャルルに見せた。一瞬、司法省の建物に向かって実際に発射してみせるのではないかと思った。他の連中もそんな風に思ったようだ。
「一発、射って見せましょうか」
「そんなことをすると誤解を招きかねないね」シャルルが言った。
「ジョルジュ・サンク大通りに打ち込むってのはどうでしょうか。もしこの街でもう一度戦闘を交えざるを得ないときには」。オーニーは愛国心に満ち溢れたような言い方をした。
「リッツ、バンザイ」クロードが言った。「街のほかのノミやシラミどもには糞を」
「ご主人、この戦争が終わったら、微力ながらもお護りいたします」
「あなたが指揮をされたのですか」シャルルが私に尋ねた。
「それは、いわば我々自身のリハビリ計画の一部でしてね」と私は言った。「シャルル、プルーストが所有していたというコルク張りの部屋ってのはどこにあるのかな」
「カンボン通りに面したところですね」
「しょぼい野郎だな」ガイが言った。
「そのムッシュー・プルーストってえ男は何者ですか」
「作家だ」と私は答えた。「とてもすぐれた」
「で、カンボン通りで、当時、何をやりたくて住んでいたんですか」
「奴には奴なりの変なこだわりってえのが有るんだろ」クロードが説明した。「奴は自分の運転手と恋仲にあったんだ」
「悪い奴」レッドが言った。
「ヴィクトル・ユーゴーとデュマはどこに住んでいたんだろうか」オネスミが尋ねた。「ワインを回してくれないかな」
「ふたりの住所を調べなければなりませんね」シャルルが言った。
「でも、カンボン通りには住んでいなかったんじゃないかな」
「もちろん、住んだことはありません」シャルルが言った。
私は本を読んだり、会話に耳を傾けたり、同時に連中を観察したりして過ごしていた。
連中はアメリカ軍の軍服でしっかりと身を固め、俊敏な動きと高度な技術を身につけていた。顔は目の縁だけが年寄りじみた感じを漂わせていた。それもおそらく、やがて消えるだろう、と私は期待していた。しかし、シャルルの顔からは消えるようには思えなかった。シャルルはリッツのグラスに細やかな敬意を表しながら飲んでいた。連中はシャルルがグラスを手にする様子をじっと見つめ、誰もが同じように上品な動作でグラスを手にした。シャルルは口が固く、我々の一員ではなかったが、仲間として受け入れられ、もちまえの機知と困難を乗り切る才覚が称賛されていた。一方、柔な肌に包まれたジャン・ギャバンに出会ったときには、誰もがあいつは一介の役者に過ぎないと、失望した。あれやこれや思いを馳せ、また窓から漏れる光がチラチラと見慣れた連中の顔の上に戯れる様子を眺めていた。それはラベルのない偉大なるワインのごとく、私を実に幸せな気分にしてくれた。
シャルルがくれた『悪の華』は詩人のゴーチェが前書きを書いている版だ。しばらくはそれを読むとし、それからシャルルが持ってきてくれた数冊の釣りの本の一冊、マスとカワヒメマスの擬似針による釣りの本を読むことにしよう。
「今日は大変な一日でしたか」シャルルが尋ねた。
「いや。F.T.P.F.から、大変重要な大物がやって来て、必要と思った連中を全員引き抜き、その代わりに我々にはガキを何人か置いていった程度だな」
「必要と思われる者は誰でも連れて行けるものなんですかね」
「部隊の規定に合った者は誰でも。鼈甲縁のメガネをかけた、じつに野心的な奴なんだが。昨日出来上がったばかりの真新しい軍服を着ていたな」
「そいつはかつて大佐だった。袖章が一本、剥がれていましたね」
「大佐ってのは、最低の連中ですよ」オーニーが説明した。
「今日の午後にも、ここで別の大佐に出会ったな」レッドが言った。
クロードが会話を真似して言った。
「ボンジュール、ロベール」
「ボンジュール、アンドレ」
それからレッドとパパは抱き合った。誰もがみな心を動かされた。
「あの大佐殿は自分の周りをぐるっと見渡した。本人はピカピカの軍服にソミュールのパンツ、それに美しいブーツを履いていた。おそらくそれに見合ったチュニックも身に付けていただろうな。奴は俺たちの存在をしかと目にとめていた。こちらときたら、砲火を浴びた軍用トラックから、死んだアメリカ兵が着ていた軍服をちゃっかり借用して着ていたっていうわけだ。奴は軽蔑したような眼差しを向け、パパに尋ねた。君が指揮をしたのは何人くらいかね、と」
「四人、六人、八人、一二人。せいぜい、二百人だな」
「私は二千人だ」男は空をじっと見つめ、その限りない力を思い浮かべ、口をへの字に曲げ、一方の目に皺を寄せた。
二人の会話が続く。「大佐殿」パパが問う。「当地でそんなに大勢の不正規兵を抱えていて、食べさせていくのに支障を来したことはないのかな」
「自分で、予測を立てるんですな。ムッシュー・シャルル。あなたはホテルの人だ。不意の客、二千人に食事を出さなければならないことだって、少なくとも一度は、いや一日に二度は、おありでしょう」と大佐が答えた。
「問題ありませんよ。我々は強靭な愛国者に囲まれていますから」とシャルル。
「で、連中はいまなお愛国者かな」
「当然」
「祝福をさせていただきたいのですが、いかがでしょう。大佐殿」パパが言った。「我々がこの村に侵入し、この素晴らしい宿舎を占拠し、貴殿と貴殿の勇敢なる部下、二千人をお迎え出来たことはこの上なく光栄に存じます」
(続きは本誌でお楽しみください。)