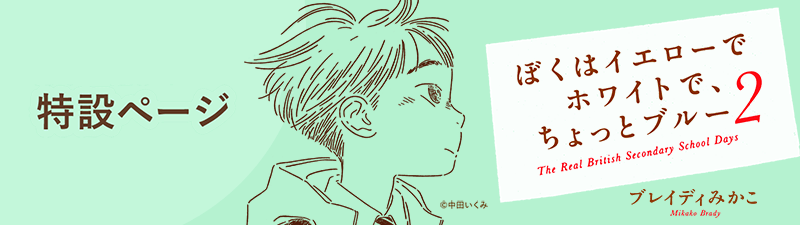1 元底辺中学校への道
「なんかまた、ずいぶん違う感じの中学校を選んだんだね」
息子が入学した中学の名前を言うと、多くの人々がこのような反応を示す。
というのも、彼が卒業した小学校と、入学した中学校とは真逆と言ってもいいぐらい違うからだ。
英国では、公立でも保護者が子どもを通わせる小・中学校を選ぶことができる。公立校は、Ofsted(英国教育水準局)という学校監査機関からの定期監査報告書や全国一斉学力検査の結果、生徒数と教員数の比率、生徒ひとりあたりの予算など詳細な情報を公開することが義務付けられていて、それを基にして作成した学校ランキングが、大手メディア(BBCや高級新聞各紙)でのサイトで公開されている。
だから保護者たちは、子どもが入学・進学する何年も前からこうしたランク表を見て将来の計画を立て、子どもが就学年齢に近づくと、ランキング上位の学校の近くに引っ越す人々も多い。人気の高い学校には応募者が殺到するので、定員を超えた場合、地方自治体が学校の校門から児童の自宅までの距離を測定し、近い順番に受け入れるというルールになっているからだ。そのため、そうした地区の住宅価格は高騰し、富者と貧者の棲み分けが進んでいることが、近年では「ソーシャル・アパルトヘイト」と呼ばれて社会問題にもなっているほどだ。
わたしたち一家は、一般的に「荒れている地域」と呼ばれており、近所の学校も常にランキングの底辺あたりを彷徨っている(ので住宅価格も横ばいの)元公営住宅地に住んでいるのだが、なぜか息子は市の学校ランキング1位の小学校に通っていた。そこは公立カトリック校だった。
英国には公立でも英国国教会やカトリック、ユダヤ教、イスラム教などの宗教校がある。もはやそんなことは忘れていたがわたしは一応カトリックの洗礼を受けており、アイルランド人の配偶者も「14歳のクリスマス以来、ミサに行ってない」と豪語するような人間ではあるが、どういうわけか彼の叔母は修道女だったり、従弟には神父もいるという敬虔なカトリック一族の出身だった。
よって彼の親族にとってはカトリック校以外に子どもを通わせるなどということはあり得ない。とはいえ、別にそんなことが家訓にあって守らなければ罰せられるわけでもないので慣習に従う必要はないのだが、わたしと配偶者もそれほど強い信条があって不熱心な信者になっているわけではなかったので、なんとなく親族からの無言の要望に押されるまま、息子をカトリック校に入学させたのだった。
ところがこのカトリック校は、わたしたちが住んでいる元公営住宅地と、それに隣接する高級住宅街の二つの教区のためにつくられた学校だった。で、教会に所属して日曜ごとにミサに通うようなコンサバな家庭は高級住宅街のほうが圧倒的に多い。従って生徒も裕福な家庭の子がほとんどであり、こうした家庭は往々にして教育熱心であるのに加え、カトリック校は一般に厳格で宿題などもガンガン出して勉強させるため、小学校ランキング1位を突っ走っているのだった。
卒業時には、この小学校の生徒たちは、ほぼ100%カトリックの中学校に入学する。これがまた市の中学ランキング1位のエリート校なのだが、息子の同級生もみんなそこに進学するし、うちもそうなるのだろうと、わたしも息子もぼんやりと思っていた。
そんなわけだったのでわたしは息子の進学先を探しているわけでもなかったのだが、彼が小学校最高学年になるとすぐに、近所の中学校から学校見学会の招待状が届いた。
そこはもともと、「ホワイト・トラッシュ(白い屑)」というまことに失礼な差別用語で表現される白人労働者階級の子どもたちが通う中学として知られていた。うちの近所でも、ほんの数年前までは、中華料理店のガラス窓にレンガを投げつけて遊んでいるガキどもや、公園の茂みの中にたむろって妙な匂いのする巻きたばこを嗜んでいたりする同校の生徒たちが問題になっていた。が、常に学校ランキングの底辺にいたその中学校が、なぜかいまランクの真ん中あたりまで浮上しているという。
いったいどういうことなんだろう。という好奇心から、見に行ってみたいなと思っていると、
「行ってもいいよ。中学の見学会に行くときは、学校を早退しても許されるし」
と息子も言うので、わたしたちはふらふらと見学会に出かけてしまったのだった。

中学校の廊下にセックス・ピストルズかよ
見学会当日、近所の中学校のホールに入ると、来年から中学生になる子どもたちとその保護者たちがすでにたくさん椅子に腰かけていた。同じように並んで座ると、脇で息子がちょっと引いているのが伝わった。
その前週、わたしたちはカトリックの中学校の見学会にも行ったが、そちらは息子の同級生がみんな来ていたので、息子もわたしの隣を離れ、友人たちと一緒に座っていた。だが、ここには彼が知っている子はひとりもいなかったからだ。
カトリック校の見学会でのプレゼンスピーチでは、壇上に立った初老の校長が、全国一斉学力検査での平均点やオックスフォード大学とケンブリッジ大学に入った卒業生の数など、いかに彼の学校が優秀かということを延々と語った。そして校長がスピーチを終えると、今度はいかにも優等生といった感じの、こういう子がオックスブリッジに行くんだろうなと思うような上流階級風の英語を話す生徒会長が出てきて、「みなさん、わが校へようこそ」と爽やかに挨拶し、学校生活がいかに有意義で素晴らしいかを朗々とスピーチした。
一方、近所の中学校のほうはというと、四十代前半という感じの若い校長が壇上に登場し、学校説明よりもジョークのオチを言うタイミングに傾注しているという感じで、けっこう本気で笑いを取りに来ていた。「え? もう終わりですか?」というぐらい簡潔なスピーチの後で、次はまた生徒会長が出て来るんだろうなと思っていると、校長は言った。
「さて、次は、わが校が誇る音楽部の演奏を聴いてください」
いきなり彼の背後の幕がサーッと上がる。
中から出てきたのは、あらゆる楽器を持ってステージ上に並んでいる夥しい数の制服姿の中学生だった。ギター、ベース、キーボード、ドラムに加え、ブラス隊、パーカッション、ウクレレ、ウッドベース、ピアニカ、なんだかよくわからない民族楽器のようなものを手にして立っている子もいる。
どっかで聞いたようなイントロが始まったなと思っていると、「アップタウン・ファンク」だった。あまりにも楽器の数が多すぎてうまいのか下手なのか判然としないのだが、勢いだけはある。ヴォーカルは男女混合の3人組で、真ん中のぽっちゃりした眼鏡の女の子が、細長い体型のブロンド少年と異様にダンスがうまい黒人の少年を従えている、という構図。ブルーノ・マーズみたいに中腰になって肩を揺らしたり、ジェームス・ブラウンみたいなステップで踊ったりしながら軽快にステージ上を移動している。
楽器の音も声も動きも多種多様過ぎて、みんなバラバラなのになぜか一丸となっていて、なんでこんなに雑多な演奏なのにサウンドがまとまっているんだろう。と、考えてしまったのだが、わりとすぐにその答えはわかった。みんな楽しそうだからである。全員がエンジョイしているから、その陽気なヴァイヴで細かいことはぶち飛び、パワフルな楽しさのうねりが生まれている。
ステージを見ている自分がついにやにやしてリズムを取っていたことに気づき、ふっと脇を見ると、妙に醒めた目つきで10歳の息子がわたしのほうを見ていた。
「上手だったよね」
演奏の後で息子に話しかけると、
「まあね」
とそっけない返事をして彼は椅子から立ち上がる。
わたしも急いで立ち上がり、案内役の女子生徒に連れられて校内を見て回った。建物からしてカトリック校とは正反対だ。カトリックの中学校は、ちょっと『ハリー・ポッター』シリーズのホグワーツ校を髣髴とさせるような古い建物で、ああいう由緒ある感じの校舎は観光客としてたまに訪れる分には風情があっていいのだろうが、天井がやけに高いし壁のひび割れやペンキの剝げ具合が目立ち、毎日過ごしていると底冷えがしそうだった。
一方、近所の中学校のほうは、英国のいたるところで見る平凡な学校だ。英国の人々はこうした実用的だが特徴のない建物のことを「キャラクターがない建築物」と表現するが、ハリポタ校舎よりずっと窓も大きくて自然光が入って明るく、壁も真っ白に塗り替えられたばかりで、暖房もよく行き渡りそうな天井の低さだ。
「明るくて、新しくていいよね。使いやすそう」
息子に話しかけると、彼は黙って頷き、楽しそうに談笑しながら同じ小学校の制服を着て歩いている少年たちの後ろを、ひとりだけ違う制服でとぼとぼと歩いていた。
英国の中学校の校舎は、数学や英語、科学、歴史といった教科ごとに教室が分かれていて、生徒たちは授業ごとに移動する。わたしたちも教科ごとの教室に案内されて、教員たちと話をしたり、展示物を見て回ったりしたが、教員たちの態度もカトリック校とはまるで正反対だった。カトリック校の教員たちは、質問があればお答えしますよ、といった風情で黙って椅子に腰かけていて、のんびり本を読んでいる人なんかもいたが、こちらはみんな教室の中に立っていて、やけに話しかけてくる。これが黙っていても生徒が集まるエリート校と、努力をしなければ生徒が集まらない学校の違いかと思った。
数学の部署を見た後で案内役の女子生徒が言った。
「次は音楽室に行きます。そこは音楽部の部室にもなっていて、いろいろな楽器が置かれています。あなたは何か楽器やってる?」
と聞かれて、息子が答えた。
「ギターを習ってます」
「ギター! いいじゃない! 私はキーボードをやってる。さっき、ホールで私たちの演奏聞いてくれた?」
肩までの長さの金髪を外巻きにした、若い頃のマリアンヌ・フェイスフルみたいな髪型の女子生徒が言う。
「え? あなたもさっきステージの上にいたの?」
わたしが尋ねると、
「はい。でもあんなにたくさんいたらわからないですよね。キーボードだけで8人いたし」
と彼女はにっこり笑った。
彼女に先導されるままわたしたちは階段を上がった。音楽室は一番上のフロアになっているらしい。女子生徒に案内されて廊下を歩いていくと、左右の壁に、見おぼえのある、というか、ひどく懐かしいサイズの正方形の物体がずらりと並んでいるのが見えてきた。
ザ・シャドウズ、ジ・アニマルズ、ザ・フー。名だたるブリティッシュ・ロックの名盤アルバムのジャケットが両側の壁にずらりと貼られていたのだ。何よりこの並べ方に信頼がおけるのはロニー・ドネガンから始まっている点だ。ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、ピンク・フロイド、デヴィッド・ボウイ、レッド・ツェッペリン、T・レックス……なぜこんなものたちが学校の廊下に。左右からこちらを見下ろしている名盤の数々を通り過ぎると、ああやっぱり、ついに見えてきた。黄色にピンクのあの毒々しい色彩。『勝手にしやがれ』のジャケットが。中学校の廊下にセックス・ピストルズかよ。
ザ・スミス、ザ・ストーン・ローゼズ、オアシス、ファットボーイ・スリムとだんだん現代に近づく並びを眺めているうちに音楽室兼音楽部室の入り口に到着した。
「ここは、学校中で私が一番好きな部屋です」と言って、女子生徒がドアを開けた。これまで見てきた教室が3つ入るぐらいの大きな部屋だった。部屋の両側に様々な楽器が所せましと並べられ、奥のほうにガラス張りになった個室のようなものが見える。
「あれは何?」
と聞くと、案内役の女子生徒が答えた。
「レコーディング・スタジオです」
「えっ? スタジオまであるの? すごい」
思わず跳ぶように中を覗きに行ってから、ふと我に返って息子のほうを振り向くと、彼は冷ややかな眼差しで戸口からじっとわたしを見ていた。

「いい子」の決断
わたしは「あの学校に行け」と息子に言ったことは一度もなかった。
しかし、熱っぽく元底辺中学校、もとい、近所の中学校のことを話す様子を見ていると、わたしがたいへん気に入ってしまったことは明らかで、それが彼の決断に影響を与えたのは間違いない、と配偶者は言う。
「音楽とかダンスとか、子どもたちがしたがることができる環境を整えて、思い切りさせる方針に切り替えたら、なぜか学業の成績まで上がってきたんだって」
「先生たちも、カトリック校と違ってフレンドリーで熱意が感じられた」
「何よりも、楽しそうでいい。だから子どもたちも学校の外で悪さをしなくなったんだろうね。学校の中で自分が楽しいと思うことをやれるから」
みたいなことを確かに言ったような気はするが、息子にあの学校をお勧めした覚えはない。なぜなら、わたしは自分の息子を知っているからである。
いい歳をして反抗的でいい加減なわたしとは違い、彼は10歳でも分別のあるしっかりとした人間だった。なにしろ、優秀で真面目なカトリックの小学校で生徒会長をしていた子どもである。基本的に、「いい子」なのだ。
だから、学校でバンド活動ができるとか、ストリートダンスのクラブがあるとかいうことよりも、彼にとっては全国一斉学力検査の平均点や卒業生の進学率などのほうがよっぽど重要かもしれないし、ギターを習っているとはいえ、彼のギターは(実はけっこううまいと言えないこともないのだが)ただ正確に弾いているという感じで、いまいちグルーヴ感がない。あの日、見学会で聴いた音楽部のファンキーな演奏とは対極にある。
まあそれでも彼はショービズ的なことにはまったく縁がないわけでもなくて、実は7歳の時に菊地凛子さんの息子役でイタリア映画に出演したことがあるのだが、その後、別に俳優や芸能人になりたがるということもなく、うちのような貧乏な家庭の子どもは巨額の借金を背負って大学に行かなくてはならないのだからそのときのために出演料は1ペンス残さず貯金しておけと言ったぐらいの、堅実派なのだった。
わたしの配偶者は一貫して自分の息子を元底辺中学校には通わせたくないと言っていた。生徒の9割以上が白人の英国人だという数字を懸念し、うちの息子は顔が東洋人なのでいじめられると決めてかかっていた。英国の中学校は11歳から16歳まで5年間通う。それはとても長い時間だし、最上級生と最下級生の年齢差も大きい。肉体的にいじめられたりしたら、うちの息子は特に体が小さいので悲劇的なことになりかねないと配偶者は言った。実際、往来でも外国人にレイシスト的な言葉を吐く中学生を見かけることがあったし、よく行っていた中華料理店の子どもが数年前に学校でいじめられて転校したこともあった。
そこにいくとカトリック校は人種の多様性がある。南米やアフリカ系、フィリピン、欧州大陸からのカトリックの移民が子どもを通わせているし、実のところ、近年、移民の生徒の割合はうなぎ上りに上昇している。いわゆる「チャヴ」と呼ばれる白人労働者階級が通う学校はレイシズムがひどくて荒れているという噂が一般的になるにつれ、白人労働者が多く居住する地区の学校に移民が子どもを通わせなくなったからだ。例えば、Mumsnetのような育児サイトの掲示板に行けば、学校選びの時期になると、ミドルクラスの英国人と移民が「あそこの学校は白人労働者階級の子どもが多いので避けるべき」みたいな情報をシェアしている書き込みを見ることができる。
こういう風潮のせいで、昨今の英国の地方の町には「多様性格差」と呼ぶしかないような状況が生まれている。人種の多様性があるのは優秀でリッチな学校、という奇妙な構図ができあがってしまっていて、元底辺中学校のようなところは見渡す限り白人英国人だらけだ。そういえば、学校見学会の帰りに、息子もぽつりと「ほとんどみんな白人の子だったね」と口にしていた。
が、地方自治体に中学校入学申請書を出す締め切り直前のことである。
息子が、突如として元底辺中学校に行きたいと言い出した。直接の原因は、仲の良いクラスメートが元底辺中学校に入学すると決めたからだった。この家庭は、母親がフルタイムの仕事を見つけたので、息子を車で学校に送り迎えできなくなり、歩いて通える中学校に入学させたいと言っていた。
「おまえが本当に行きたいなら行けばいいと思うが、俺は反対だ」
配偶者は息子にそう言った。
「どうして?」と訊く息子に彼は言った。
「まず第一に、あの学校は白人だらけだからだ。お前はそうじゃない。ひょっとするとお前の頭の中ではお前は白人かもしれないが、見た目は違う。第二に、カトリック校はふつうの学校よりも成績がいいから、わざわざ家族で改宗して子どもを入学させる人たちもいるほどだ。うちはたまたまカトリックで、ラッキーだったんだ。それなのに、その俺らのような労働者階級では滅多にお目にかかれないような特権をそんなに簡単に捨てるなんて、階級を上昇しようとするんじゃなくて、わざわざ自分から下っているようで俺は嫌だ」
息子はしばらく考え込んだものの、決意は変わらなかった。うちは母親のわたしが車を運転しないので、カトリック校に通うとなると、バスを乗り継ぎ、さらにバス停から学校までかなり歩かねばならず、雨の日も寒い冬もそれをやるより、近くの学校がいいよね、という実務的判断もあったようだった。
そんなわけで、息子は元底辺中学校に入学した。
が、これが拍子抜けするほど最初から楽しそうで、すぐに新しい友達もでき、音楽部をはじめとする複数のクラブに所属して、しょっぱなからとても忙しそうだ。わりと順応性の高い子どもなので、環境が変わったら変わったでエンジョイしてるんだろう。
「全然心配することなかったね」と言うと、「まあ、いまのところはな」と言いながら、配偶者もけっこう安心している様子だ。
そんなある朝。
慌ただしく学校に行った息子の部屋に掃除に行くと、机の上に国語のノートが開かれたままになっていた。
ゆうべ遅くまで机に向かって何かやっていたような気配だったが、肝心の宿題のノートを忘れて行ったのかな。と思ってふと見ると、先週の宿題のページだった。先生から赤ペンで添削が入っている。「ブルー」という単語はどんな感情を意味するか、という質問で、息子は間違った答えを書いてしまったのだった。
「『怒り』と書いたら、赤ペンで思い切り直されちゃった」と夕食時に息子が口にしたので、「えーっ、あんたいままでずっとそう思っていたの?」とわたしは笑い、「ブルーは『悲しみ』、または『気持ちがふさぎ込んでる』ってことだよ」と教えると、学校の先生にもそう添削されたと言っていた。
これがその宿題だったのか、と思いながら見ていると、ふと、右上の隅に、息子が落書きしているのが目に入った。青い色のペンで、ノートの端に小さく体をすぼめて息を潜めているような筆跡だった。
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー。
胸の奥で何かがことりと音をたてて倒れたような気がした。
何かこんなことを書きたくなるような経験をしたのだろうか。
わたしは息子のノートを閉じ、散らばっていた鉛筆や消しゴムをペンケースの中にいれてその上に置いた。
ふと、この落書きを書いたとき、息子はブルーの正しい意味を知っていたのだろうか、それとも知る前だったのだろうか、と思った。そう思うとそれが無性に気になった。
だけどそのことをわたしはまだ息子に聞き出せずにいる。
この本をできるだけ多くの人たちに読んでほしいと思っています。
応援していただけると嬉しいです。
(編集H&新潮社「チーム・ブレイディ」一同)