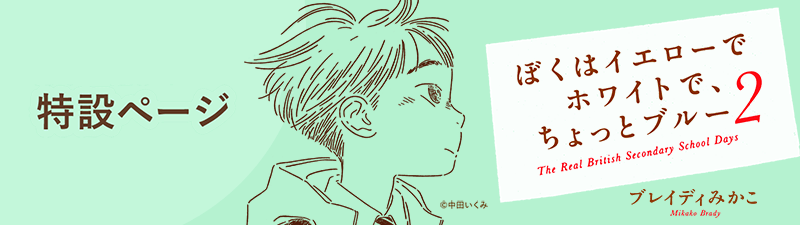1 元底辺中学校への道 6 プールサイドのあちら側とこちら側

5 誰かの靴を履いてみること
息子の中学校では、学期ごとの通知表のようなもの(プログレス・レポートと呼ぶ)をネットでダウンロードできるようにしてあり、希望者にはハードコピーも配布されている。
5段階評価でそれぞれの教科の理解の到達度が示され、授業に対する姿勢なども評価される。で、入学以来、うちの息子が輝かしい成績をおさめている教科が二つある。「演劇」と「ライフスキル教育」である。
「演劇」というのは、スクール・ミュージカル『アラジン』出演時の彼の熱意を鑑みるとむべなるかなという気もするが、「ライフスキル教育」というのは具体的には何のこと? と思った。アカデミックな教科以外の、エモーショナル・インテリジェンス(EQ、感情的知能)の分野がここに入るんだろうということは想像がつくが、コミュニケーション力とか自己コントロール力とかいうようなものを5段階で測るのは不可能なのではないだろうか。と思って尋ねてみると、息子はこう答えた。
「ちゃんと筆記試験があるよ。要するにそれ、シティズンシップ・エデュケーションのこと」
英国の公立学校教育では、キーステージ3(7年生から9年生)からシティズンシップ・エデュケーション(日本語での定訳はないのか、「政治教育」「公民教育」「市民教育」と訳され方がバラバラのよう)の導入が義務づけられている。英国政府のサイトに行くと、イングランドで行われている、中学校におけるシティズンシップ・エデュケーションのカリキュラムの要約があがっていた。
シティズンシップ・エデュケーションの目的として、「質の高いシティズンシップ・エデュケーションは、社会において充実した積極的な役割を果たす準備をするための知識とスキル、理解を生徒たちに提供することを助ける。シティズンシップ・エデュケーションは、とりわけデモクラシーと政府、法の制定と順守に対する生徒たちの強い認識と理解を育むものでなくてはならない」と書かれてあり、「政治や社会の問題を批評的に探究し、エビデンスを見きわめ、ディベートし、根拠ある主張を行うためのスキルと知識を生徒たちに授ける授業でなくてはならない」とされている。
キーステージ3では、議会制民主主義や自由の概念、政党の役割、法の本質や司法制度、市民活動、予算の重要性などを学ぶらしいのだが、こういったポリティカルな事柄をどうやって11歳の子どもたちに導入していくのだろう。
「試験って、どんな問題が出るの?」
と息子に聞いてみると、彼は答えた。
「めっちゃ簡単。期末試験の最初の問題が『エンパシーとは何か』だった。で、次が『子どもの権利を三つ挙げよ』っていうやつ。全部そんな感じで楽勝だったから、余裕で満点とれたもん」
得意そうに言っている息子の脇で、配偶者が言った。
「ええっ。いきなり『エンパシーとは何か』とか言われても俺はわからねえぞ。それ、めっちゃディープっていうか、難しくね? で、お前、何て答えを書いたんだ?」
「自分で誰かの靴を履いてみること、って書いた」
自分で誰かの靴を履いてみること、というのは英語の定型表現であり、他人の立場に立ってみるという意味だ。日本語にすれば、empathyは「共感」、「感情移入」または「自己移入」と訳されている言葉だが、確かに、誰かの靴を履いてみるというのはすこぶる的確な表現だ。
「子どもの権利を三つ書けってのは何て答えたの?」
と尋ねると、息子は言った。
「教育を受ける権利、保護される権利、声を聞いてもらう権利。まだほかにもあるよ。遊ぶ権利とか、経済的に搾取されない権利とか。国連の児童の権利に関する条約で制定されてるんだよね」
英国の子どもたちは小学生のときから子どもの権利について繰り返し教わるが、ここで初めて国連の子どもの権利条約という形でそれが制定された歴史的経緯などを学んでいるようだ。
「そういう授業、好き?」
とわたしが聞くと息子が答えた。
「うん。すごく面白い」
実はわたしが日々の執筆作業で考えているような問題を中学1年生が学んでいるんだなと思うと複雑な心境にもなるが、シティズンシップ・エデュケーションの試験で最初に出た問題がエンパシーの意味というのには、ほお、と思った。
「エンパシーって、すごくタイムリーで、いい質問だね。いま、英国に住んでいる人たちにとって、いや世界中の人たちにとって、それは切実に大切な問題になってきていると思うから」
「うん。シティズンシップ・エデュケーションの先生もそう言ってた」
と、ちょっと誇らしげに顎をあげてから息子は続けた。
「EU離脱や、テロリズムの問題や、世界中で起きているいろんな混乱を僕らが乗り越えていくには、自分とは違う立場の人々や、自分と違う意見を持つ人々の気持ちを想像してみることが大事なんだって。つまり、他人の靴を履いてみること。これからは『エンパシーの時代』、って先生がホワイトボードにでっかく書いたから、これは試験に出るなってピンと来た」
エンパシーと混同されがちな言葉にシンパシーがある。
両者の違いは子どもや英語学習中の外国人が重点的に教わるポイントだが、オックスフォード英英辞書のサイト(oxfordlearnersdictionaries.com)によれば、シンパシー(sympathy)は「1.誰かをかわいそうだと思う感情、誰かの問題を理解して気にかけていることを示すこと」「2.ある考え、理念、組織などへの支持や同意を示す行為」「3.同じような意見や関心を持っている人々の間の友情や理解」と書かれている。一方、エンパシー(empathy)は、「他人の感情や経験などを理解する能力」とシンプルに書かれている。つまり、シンパシーのほうは「感情や行為や理解」なのだが、エンパシーのほうは「能力」なのである。前者はふつうに同情したり、共感したりすることのようだが、後者はどうもそうではなさそうである。
ケンブリッジ英英辞書のサイト(dictionary.cambridge.org)に行くと、エンパシーの意味は「自分がその人の立場だったらどうだろうと想像することによって誰かの感情や経験を分かち合う能力」と書かれている。
つまり、シンパシーのほうはかわいそうな立場の人や問題を抱えた人、自分と似たような意見を持っている人々に対して人間が抱く感情のことだから、自分で努力をしなくとも自然に出て来る。だが、エンパシーは違う。自分と違う理念や信念を持つ人や、別にかわいそうだとは思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力のことだ。シンパシーは感情的状態、エンパシーは知的作業とも言えるかもしれない。
EU離脱派と残留派、移民と英国人、様々なレイヤーの移民どうし、階級の上下、貧富の差、高齢者と若年層などのありとあらゆる分断と対立が深刻化している英国で、11歳の子どもたちがエンパシーについて学んでいるというのは特筆に値する。

大雪の日の課外授業
3月になって大雪が降るという年がたまにあるが、2018年の英国はまさにそうだった。
雪が降ると英国では様々のものがストップする。電車、バスなどの交通機関が止まるほか、スノータイヤをつけて走るなどという習慣もないため、雪が積もり出すとそこらへんに車を停めて徒歩で帰宅する人などもいて、ブライトンのような坂道の多い街は、道の両側に誰のものとも知れない車がずらっと乗り捨ててあるという状況になる。
保育園、学校、大学なども休みになり、元底辺中学校からも朝いちばんで休校を知らせる携帯メールが入った。丘の斜面にあるうちの周囲などもあたり一面雪に覆われ、こりゃ餌を置いといてやらないとジャングル状態のうちの庭に集う鳥のみなさんが飢えるなと思いながら、朝から裏庭で餌置き作業に追われていると、携帯に友人から電話がかかってきた。
この友人は、底辺託児所が一昨年に潰れるまで一緒に働いていたイラン人女性であり、いまはホームレス支援団体が運営している託児所の責任者として働いている。電話に出てみれば、どうやらホームレス支援団体の事務所と倉庫を緊急開放して路上生活者の人々を受け入れているそうで、食料を買い出しに行く予定だった車が雪で立ち往生したため、事務所から徒歩で行ける距離に住んでいる人々から食料のカンパを募っているという。聞けばボランティアも不足しているようだし、学校が休みになって家でだらだらしている息子を連れて手伝いに行くことにした。
長靴で積もったばかりの白い雪をさくさく踏みしめ、ティーバッグやサンドウィッチ用の食パン、ビスケット、缶詰のベイクドビーンズ、ポテトチップス、ハムなどを詰めたバッグを息子と二つずつ下げて友人の待つ慈善団体の事務所に向かった。現地に到着すると、事務所のドアから若いボランティアの男性がちょうど出て来るところだった。彼は、わたしたちの姿を見ると「ありがとう。君たちはライフセイバーだ」と言って、息子が重そうに抱えていたバッグを受け取って運んでくれた。事務所の中にはわたしたちと同じように食料を運んできた近所の人や、ボランティアの人々がいて、すでに忙しそうに立ち働いている。
「サンクス! 助かるよ、こんなにティーバッグ持ってきてくれて。パトロール隊が紅茶作って出て行こうにもティーバッグが残りわずかになって焦っていたのよ」
わたしの友人もキッチンから顔を出して勢いよくそう言った。
事務所の中には路上生活者の人々が4人ばかり、敷物を敷いて寝転んだり、座ったりしていた。息子はおずおずとした様子で、目が合った人に「ハロー」と挨拶したりしている。
友人に言われるまま食パンにマーガリンを塗ってハムサンドウィッチを作っていると、息子がドアを開けて外に出ていくのが見えたので、わたしも急いで後を追った。
「どうしたの? 家に帰る? 母ちゃんはもう少し手伝って行くけど」
とわたしが言うと、息子が振り返った。目が心なしか潤んでいる。
「こういうことを言うのは本当に悪いと思うんだけど、でも、匂いに耐えられなくって鼻で息をするのを止めてたから、息苦しくなっちゃって……」
ガンガンに暖房を利かしていたせいもあり、内部にはアルコールと尿の匂いが混ざったような独得の臭気がこもっていたのは事実だった。
「帰りたかったら帰ってもいいよ。ただ、こんな天気の日だから、わたしと一緒に帰ってくれたほうが安心ではあるけどね」
と言うと、息子は少し考えてから答えた。
「僕も、キッチンで手伝ってもいい?」
「もちろん」と言ってわたしは息子をキッチンに連れて行った。路上生活者たちの前を横切るときに、息子の表情が少しこわばっているのがわかった。
キッチンで作っているサンドウィッチや紅茶は、事務所や倉庫にいる路上生活者の人々のためだけでなく、この雪の中でも路上に座っている人々にどこに行けばいいのか教えるために外を回っているパトロール隊が持っていくためだった。この事務所だけでなく、教会やカフェ、ナイトクラブでも、雪が降り出した昨夜から路上生活者を受け入れている。パトロール隊は塒のない人々を最寄りの緊急シェルターに案内しているのだった。
「今年はほんとうに路上生活者の数が多い。緊縮財政で、自治体は何の緊急支援もできなくなっているから、民間がなんとかするしかない」
パンにマーガリンを塗りながら友人が言った。
「緊縮って何?」と息子が聞くと、友人が説明を始めた。
「この国の住民は英国っていうコミュニティーに会費を払っている。なぜって、人間は病気になったり、仕事ができなくなったりして困るときもあるじゃない。国っていうのは、その困ったときに集めた会費を使って助け合う互助会みたいなものなの」
「その会費って税金のことだよね」
「そう。ところが、緊縮っていうのは、その会費を集めている政府が、会員たちのためにお金を使わなくなること」
「そんなことしたら困っている人たちは本当に困るでしょ」
「そう。本当に困ってしまうから、いまここでみんなでサンドウィッチを作ったりしているの。互助会が機能していないから、住民たちが善意でやるしかない」
「でも、善意っていいことだよね?」
「うん。だけどそれはいつもあるとは限らないし、人の気持ちは変わりやすくて頼りないものでしょ。だから、住民から税金を集めている互助会が、困っている人を助けるという本来の義務を果たしていかなくちゃいけない。それは善意とは関係ない確固としたシステムのはずだからね。なのに緊縮はそのシステムの動きを止める。だからこうやってみんなで集まって、ホームレスの人々のシェルターを提供したり、パトロール隊が出て行ったりしているの」
イランでは学校の先生だった友人から息子はシティズンシップ・エデュケーションの授業を受けているようだった。底辺託児所に通っていた頃から息子は友人になついていて、こんな風にたくさんのことを教わったものだった。
It takes a village.
英国の人々は子育てについてこんな言葉をよく使う。「子育てには一つの村が必要=子どもは村全体で育てるものだ」という意味だが、うちの息子を育てているのも親や学校の先生だけじゃない。こうやって周囲のいろいろな人々から彼は育てられてきたのである。

頼りないけど、そこにあるもの
しばらくすると目の覚めるような長身の美女がキッチンに入ってきた。重そうなリュックをテーブルの上にドサッとおろして、「ハーイ、お久しぶり」とわたしと息子に微笑んでいる。
イラン人の友人の長女である。彼女は二年ほど前から親元を離れてイングランド中部の大学に通っているのだが、週末に久しぶりにブライトンへ戻ってきていたらしい。だが、この雪で電車が止まり、帰れなくなってしまったので、ここで手伝うことにしたのだという。
「どうだった?」と友人が聞くと、彼女は答えた。
「スーパーの入口の軒下にまだひとり座っている人がいたから、近くのカフェに案内した。あそこのカフェ、パンとティーバッグはあるけどハムがヤバいって言ってた」
「ああ、こっちはハムは豊富にあるから、持って行ってあげたら」
「ナイトクラブのほうは、ティーバッグとコーヒーが足りないみたいだけど」
「コーヒーはあるよ。近所の人たちがたくさん持ってきてくれたから」
「じゃ、持って行くよ」
パトロール隊は緊急シェルター間の食料の移動にも一役買っているようで、友人の娘はカフェから砂糖をもらって帰って来ていた。
退屈そうにキッチンの流しの前に立っていた息子に、友人の娘が話しかけた。
「一緒に行く? ちょっと寒いし、往復1時間ぐらい歩くけど、いい運動になるよ」
「行ってくれば? ここにいてもあんまりやることもないし」
とわたしも言った。携帯があればゲームでもして遊べるのに、家に忘れてきたからできないとさっきから息子がぶうぶう言っていたからである。息子は即答で「僕も行く」と言って、友人の娘と、彼女とペアを組んでパトロールしている大学生の青年がポットに紅茶をいれるのを手伝い始めた。そして大きなリュックを渡され、いっちょ前に食品をたくさんつめてそれを背負い、大学生2人の後を追うようにして出て行った。
ローカルのラジオ局が、この慈善団体の事務所がホームレス支援のハブになっていることや、食料やブランケットなどの寄付を募っていることを告知してくれたおかげで、四輪駆動車で駆けつけてくれた人々もいて、ランチタイムが近づく頃にはキッチンの床に足の踏み場もないほど物資が置かれていた。
こういうときの英国の草の根の機動力には驚かされる。昨年ロンドンで発生したグレンフェル・タワーという高層住宅の火災でもそうだった。英国きっての富裕区の一つ、ケンジントン・アンド・チェルシーの一角に存在する低所得者向けの住宅で起きたこの火災は、70人以上の人々が命を落とす大惨事になった。あの24階建ての高層住宅で発生した火災は、建設費を節減するためにしかるべき断熱材を使用してなかったことや、スプリンクラーが設置されていなかったことが火の回りを早くし、多くの犠牲者を出す原因となったと判明し、英国の格差を象徴するような出来事だと言われた。が、あの火災でも行政より先に動き出したのは民間の人々だった。大量の食品や衣服、寝具などの物品が瞬く間に集まり、自治体や慈善団体が対応しきれないほどの多くのボランティア志願者が現地に入った。
地べたの相互扶助の精神はとても大事だ。それこそ中学校のシティズンシップ・エデュケーションでは市民活動の意義と種類、歴史などを学んだり、実地研修も行うようなので、英国のこうした助け合いの機動力は、まんざら個人の善意のみに頼っているわけではなく、教育というシステムの中にしっかりと根付いているとも言えるだろう。
キッチンのカウンターで発泡スチロールのカップにトマトスープを注いでいると、急に大きな声が響き、若い男性のボランティアが走って行った。「ファッキン」「バスタード」「ワンカー」といった卑語が断続的に響き、「2人とも落ち着いてください」とボランティアが叫んでいるのが聞こえてくる。どうやら路上生活者の間で喧嘩が勃発したようだ。
友人からスープの入ったカップを受け取っていたホームレスの青年の顔が真っ青になり、神経質そうに手をぶるぶる震わせているので、友人が慣れた調子で「大丈夫。ちょっと言い合いをしているだけ。すぐ静かになるから。大丈夫だから」と言いながら彼の背中をさすった。
「彼らがパトロールから戻ってきたら、そろそろ帰ったほうがいいと思う。小さい子どもには、ちょっときつくなってくるかも。狭いところに何人もいると、イライラしてくる人もいるからね」
と友人がわたしのほうを見て言った。
しばらくすると息子たちの一行がパトロールから戻ってきたので、わたしはコートを着てみんなに別れを告げ、息子とともに事務所の外に出た。
「どうだった? 路上にまだ座っていた人はいた?」
帰り道で息子に聞くと彼は答えた。
「ううん。もう外に座っている人はいなかった。カフェとナイトクラブには何人もいたけど。ナイトクラブに座っていた人たちのために、水筒の紅茶を注いで渡すのを手伝ったよ」
息子はそう言って、わたしの顔を見た。
「最初は、少し怖かった。正直言って、匂いのきつい人もいたし、なんかちょっと酔っぱらってるのかなって感じの、目つきがうつろな人とかもいたから」
「うん」
「でも、なんか僕、かわいがられちゃった。まだ小学生ぐらいだと思われたんだろうね、『いい子だね、感心だね』とか言って、こんなのくれた人もいた」
息子はそう言うとポケットから小さなキャンディーの包みを出した。
キャンディーがいっぺん溶けて変形し、また自然に固まったという感じの、そうとう年季の入った包みのように見えた。
「ホームレスの人から物を貰っちゃったりしてもいいのかな、ふつう逆じゃないのかなってちょっと思ったけど。でも、母ちゃん、これって……善意だよね?」
と息子が言った。
「うん」
「善意は頼りにならないかもしれないけど、でも、あるよね」
うれしそうに笑っている息子を見ていると、ふとエンパシーという言葉を思い出した。
善意はエンパシーと繫がっている気がしたからだ。一見、感情的なシンパシーのほうが関係がありそうな気がするが、同じ意見の人々や、似た境遇の人々に共感するときには善意は必要ない。
他人の靴を履いてみる努力を人間にさせるもの。そのひとふんばりをさせる原動力。それこそが善意、いや善意に近い何かではないのかな、と考えていると息子が言った。
「明日も学校休みになるかなあ」
「先生たちがいま手分けして雪かきしているらしいから、それはないかもね」
「そうかあ。……じゃあ宿題やっとかなくちゃ」
息子だけではない。
母ちゃんも今回は、これから考える大きな宿題をもらった。
この本をできるだけ多くの人たちに読んでほしいと思っています。
応援していただけると嬉しいです。
(編集H&新潮社「チーム・ブレイディ」一同)