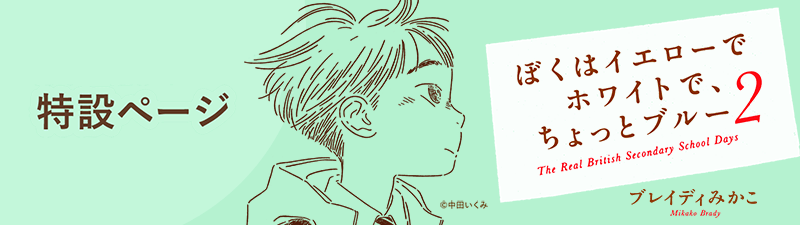8 クールなのかジャパン
わたしが毎月しこしこ書いているこの原稿のタイトルが「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」だということを知ったうちの息子が、「人の走り書きを勝手に使うな」「著作権料を支払え」とうるさいのだが、彼はふと真顔になってこう漏らした。
「でも、ほんとは『ぼくはチンキーでホワイトで、ちょっとブルー』のほうがよかったよね」
英国のストリートでいわゆる人種差別的なことを言われるとき、我々のことを「日本人」と特定してからかってくる人はまずいない。たまに、いったいどうしてわかるのかピンポイントで「日本人ですね」とか「コンニチハ」とか言ってくる人もいるのだが、だいたいそういう人は差別的言動というよりも、日本に行ったことがあるとか、アニメやマンガなどのジャパニーズ・カルチャーに興味があるとかで(日本人女性にとても興味がある、というケースも往々にしてある)、一般的な英国の人々よりも日本についてよく知っている確率が高い。
そのテの日本好きの人々は、だいたいロンドンに多く生息している(「アイ・ラヴ・ジャパニーズ・ガールズ!」とリージェント・ストリートで絶叫していたおっさんを見たこともある)。しかしブライトンのような地方の街では、一見して「日本人」と特定されることはそんなにないし、だいたい中国人と言われることが多い。たまに「韓国人」、「フィリピン人」などの変化球もあるが、日本人が白人や黒人、中東人などを見ても、「この人はデンマーク人」「この人はセネガル出身」「イラクの人だ」と見分けることができないように、英国の人たちにとっても東洋人は一つのグループとして認識されている。で、そのグループに対する差別的呼称が「チンク」とか「チンキー」であり、これは英国で暮らす日本人なら、一度や二度は言われたことがあると思う(上の階級のほうではないだろうけど)。
「チンクとかチンキーとか言うとき、だいたい先方は中国人を想定しているよね」
と息子は言う。
「シティズンシップ・エデュケーションで、先生がレイシズムについて話していたんだけど、『チンク』は中国人に対する差別用語だって言うから、僕は手をあげて発言したんだ。『それは違います。うちの母親は日本人だけどその言葉を言われています』って」
「ははははは」
わたしは力なく笑ったが、そうなのである。うちの息子はわたしが人種差別される姿を見て育っている。
「けど、最近は僕も『ファッキン・チンク』とか言われるようになったしね」
わたしの笑いのビターさに気づいたのか、息子が気を遣って言った。彼は小さい頃は色素が薄くて父親に似ていたのだが、成長するにしたがってわたし(正確にはわたしの妹)に似てきて、道端でも東洋人と確定される機会が増えてきた。
「『チンキー』だけじゃなく、『パキ』とか別の言葉についても授業で習ったの?」
と尋ねると、
「うん。そういう言葉が誰を指すのか、どうして言ってはいけないのかを先生が話した後、みんなでディスカッションした」
そういえば……。
と、わたしはあることを思い出した。それはわたしが英国に住むようになって2年目ぐらいのことだった。当時、わたしは日系新聞社のロンドンの駐在員事務所で働いていたのだが、同僚に記者アシスタントとして働いていた英国人の青年がいた。日本に住んだ経験もあり、海外旅行の経験が豊富なインテリで、ざっくばらんな人柄だったので気が合ったが、ある日、彼とわたしの意見が激しく対立したことがあった。
英国に赴任してきたばかりの日本人記者が、「パキ」というのはどういう意味なのか、それはタブーな言葉なのか、とアシスタントの青年に質問したのである。アシスタントの青年は、「パキ」というのは「パキスタン人」を短縮化した言葉だが、実際にはパキスタン人だけでなく、インドやバングラデシュなど南アジア諸国出身の人々や、外見が似ていることから中東の人々を指すこともある呼称だと答えた。ここまではいいのだが、その後で彼はこう言ったのである。
「でも、この言葉が『ニガー』みたいなタブー語かと言えばそれは違う。英国人は親密な感情を込めてこの言葉を使うこともある」
「えええええっ?」
脇で各紙社説を切り抜いてスクラップにしていたわたしは思わず叫んだ。
「それは違うよー。その言い方はあまりに乱暴」
「そんなことないよ。例えば、パキスタン人経営の雑貨屋が僕たちのフラットの前にあるんだけど、僕らは『パキ・ショップ』とそれを呼んでいる。別に差別的な気持ちじゃなくて、行きつけの、店員とも親しくなった馴染みの店、ぐらいの感覚でね」
と言いながら爽やかな笑顔を浮かべた彼を見ていると、ああ、そうだ、彼はオックスブリッジ卒のエリートな仲間たちとフラット・シェアしていたと思い出した。こういう若者たちはほんとに何の悪気もなくワイングラスを傾けながら親愛の情をこめて「パキ」とか言ってんだろうなと、その姿がありありと目に浮かぶようだった。
「けど、『パキ』ってのはもともとタブロイド紙が元植民地出身の移民を差別心を込めてネガティヴに呼んだ言葉でしょ」
「だけどそれは60年代とかの、大昔の話だよ。時代とともに言葉の用法は変わるのさ」
いやいやいや、あなたたちの階級では時代はマッハの速度で前進するのかもしれないけれども、下層の街ではいまだに60年代とたいして変わらない意味で使われていることが多いですよ、と思ったわたしは後で給湯室でこっそり日本人記者に言ったのだった。
「『パキ』とかぜったい人と喋るときに使わないほうがいいし、間違っても記事の中に書かないほうがいいと思います」
それから数年後、わたしはロンドンへの通勤生活をやめてブライトンに落ち着いたのだったが、インド人店主が経営する近所の雑貨屋の大将がティーンに刺される事件が勃発したことがあった。雑貨屋のウィンドウにはその前からスプレーで「パキ・ショップ」と何度も落書きされていた。あの落書きを見るたびに、わたしは日系新聞社のアシスタントの青年の言葉を思い出したものだった。
思えば、彼があの発言をしたのはもう20年前の話だ。ブレグジットでポリティカル・コレクトネスや分断社会の問題が世間を席巻しているいま、彼は「パキ」という言葉についてどのような見解を持っているのだろう。

意外と深いニーハオ問題
うちの息子は11歳だが、昨年9月から日本の中学校にあたるセカンダリー・スクールに通っている。で、どこの国でもそうだろうと思うが、小学校から中学校に進むと、子どもたちが急にやりたがることがある。
友人どうしで、街に行きたがるのだ。
うちの息子は体が小さくて顔も幼いため、どう見ても10歳以下にしか見えないから、「両親はどこだ」と警察に保護とかされて育児放棄と見なされても困るしと最初は渋っていたのだが、「大丈夫じゃね? あいつの友達、ガタイのでかい老け顔がけっこういるから、弟がついてきたみたいな感じで、問題にはならんと思う」と配偶者が言うので、わたしも折れた。だから、このごろでは息子は映画だビーチだと、いっちょ前に友人たちとよく出かけている。
すっかり味を覚えて週末になると友だちと外出したがるのだが、学校用の黒いスニーカーが小さくなったので、新しい靴を買うために久しぶりに母子で街に出た。
黒いパーカーを着ていっぱしのティーンぶっている息子は、店に入るたびにそこの無料Wi-Fiにスマホを繫いで何ごとかをチェックし始めるので、「あんたいい加減にしなさいよ」と叱っていると、
「やべ。母ちゃんここ出よう」
とフードを被って顔を隠すように俯いて歩き始めた。
「どうしたの?」
「同じクラスの女子たちが二階にいる。いま、そのうちの一人が買い物している写真をインスタグラムに投稿した」
「いいじゃない、別に」
「ダメだよ。母親と一緒に買い物してるところなんて見られたくない。ダサすぎる」
そう言って息子はそそくさと店の外に出ていく。
いつの間にかこんなことを言う年齢になりやがって。と思いながらわたしも後を追った。息子に画像を見せてもらうと、さすがにこの年齢では女の子たちのほうがませて見える。すっかりティーン・ガール然とした女子3人組が、唇をすぼめて目を見開き、斜め上から写すセルフィー顔で水着売り場の隅に立っていた。
そういえば、ずっとむかし、わたしが水着のバーゲンでサイズを探していたときに、勝手にとことこ歩いて行った息子が「母ちゃんがいない」と大泣きして、身長2メートルはありそうなコワモテの黒人の警備員に肩車されてわたしを探していたことがあった。わたしの姿を見つけた息子は、「母ちゃん、母ちゃん」と興奮して警備員の頭をバシバシ叩くので、「おい、キッド。いい加減にしろ」と警備員が顔をしかめて笑いながらわたしのところに連れて来てくれたことがあった。あんなに小さくてかわいかった生き物がいつの間にかフードを被って母親と他人のふりをするティーンになってしまうのだから世の中とは無情である、と思いながら通りを歩いていると、銀行のキャッシュマシーンの脇にホームレスの男性が座っていた。
「ニーハオ、ニーハオ、ニーハオ、ニーハオ」
毛布を肩から羽織ったその男性は、わたしと息子に視線を合わせてにやにやしながらしつこく何度もそう言っている。わたしは彼から目を逸らし、完全無視をきめて前を通り過ぎた。昼間っからラリってるのか濁った目つきで、ずいぶん失礼な態度だな。いくらホームレスであろうとも失礼なものは失礼なので、そこに温情を侵入させる余地などないぞ、と思っていると息子が言った。
「中国人じゃないのにね」
「まあ、そこは重要ポイントではないけどね」
わたしが答えると息子が言った。
「すごい久しぶりにあの言葉を聞いた」
「ニーハオ、ニーハオ?」
「うん。友だちと一緒に外出しているときは、言われたことないから」
お。と思った。これは、ついにあれが始まったということだろうか。よく在英日本人の、欧州人配偶者との間に子どもを持つ人々が言う、「思春期になると子どもが日本人の親から距離を取りたがる」現象。むかし、ロンドンの日系企業に勤めていたとき、現地社員の日本人女性たちがよくそういう話をしているのを耳にした。母親が日本人であることを隠したがる子どもとか、「訛ってて恥ずかしいから人前で英語をしゃべるな」と子どもに言われてしまった母親の話とか。
ついにわが家にもそのときがきたのだろうか、と身構えていると息子が言った。
「さっき起きたことについては、考え方が二つあるよね。まず一つ目は、友だちと一緒にいるときは僕は東洋人には見えないんだという考え方。実際、僕はラテン系と間違えられることもあるしね。でも、母ちゃんと一緒にいると、やっぱ親子だから、東洋人に見えるということ」
「うん」
息子がなんか理路整然と語りはじめてしまったので、ついわたしは頷く。
「そして二つ目。それは、友だちと一緒にいようが母ちゃんと一緒だろうが僕は東洋人に見えるんだという考え方。だけど、友だちといるときは男ばっかりだし、体の大きな子もいるから、失礼なことを言うと殴られたりする危険性もある。だから誰も僕に差別的なことを言わない。つまり、母ちゃんと歩いているときは、女と子どもという弱者コンビだからバカにしやすい。もし、東洋人の成人男性が2人で歩いていたとしたら、あのホームレスの人はあんなことを言ったかな」
「言わなかったんじゃないかな、きっと」
移民と英国人、男と女、大人と子ども。様々な軸に分解して語っているのか、とちょっと感心していると息子が言った。
「でも、実は三つ目の考え方もある。『ニーハオ』ってのは英語で言えば『ハロー』のことでしょ。だから、中国人には中国語で挨拶すればフレンドリーだなって思われてお金を貰えるんじゃないかというビジネス的な理由から彼は『ニーハオ』と言ったのかもしれない」
「ええっ。それは考えつかなかったな」
わたしは思わず声をあげた。
「それは違うと思うよ。そういう言い方じゃなかったもん。嫌な感じでにやにやしていたし、そんな親しみは感じられなかった」
「でも、決めつけないでいろんな考え方をしてみることが大事なんだって。シティズンシップ・エデュケーションの先生が言ってた。それがエンパシーへの第一歩だって」
「……」
「そう言えば、僕、いまでも覚えているんだけど」
と言ってわたしを見上げた息子のにやけた目が三日月形になっていた。
「むかし、やっぱり『ニーハオ』って言われたときに、母ちゃんブチ切れて『私は日本人です』って言って、腰に手を当ててぶわーっと日本語で相手にまくし立てたことがあった。みんな立ち止まって笑ってたけど、あれ、クールだった」
「そんなことあったっけ。よっぽど虫の居所が悪かったんだろうね」
「あれは笑えるからいいと思うよ、母ちゃんはあの感じ、忘れないほうがいい」
「……」
なんで11歳の子どもに説教されてるんだろうと思いながら、わたしは息子と並んで昼下がりの街をバス停に向かって歩いて行った。

W杯とミスター・ミヤギ
EU離脱の国民投票以来、英国ではNワード(注:ナショナリズムのほう)はもっとも危険なサブジェクトになった。左派はそれを頭ごなしに否定し、右派は熱狂的に称揚するという、エクストリームな分断が広がっている時期に、ワールドカップが行われたらえらいことになるかも。と懸念していたが、いざ始まってみるとそれは拍子抜けするほどいつものワールドカップだった。
ガーディアン紙のような左派紙ですら、通常の「ナショナリズムこそ諸悪の根源」みたいな報道はどこに行ったのかと思うほど、公式サイトでイングランド戦の情報を熱く更新し、「イングランド、ゴーーーール」とか書いていて、屈託がない。「これはこれ、それはそれ」の割り切りなのだろう。ブレグジットなんぞにワールドカップの楽しさを曇らされてたまるか、ということだ。英国という国のしたたかさを見た気がする。
サッカー好きの息子も初日からW杯に夢中だが、今年は様子が違う。やけに日本代表について熱心に学習しているのである。各選手の名前やこれまでのキャリア、予選での勝ち上がり方から監督交代劇まで、日本語が読めるわたし以上によく知っている。これまでのワールドカップを振り返ると、息子はいつもイングランド戦に夢中で、日本代表にこれほど入れ込んだことはなかった。いったいどうしたのだろうと思って聞いてみると、息子は言った。
「僕はイングランドに住んでいるけど、よく考えたら父ちゃんはアイルランド人だし、母ちゃんは日本人だから、イングランドの血は流れてない。だから、アイルランドと日本を応援すべきだと思うけど、今回はアイルランドは出場できなかったから、僕が応援しているのは日本」
涼しい顔で言うのだが、これはちょっとヤバい兆候なのではと不安になった。
「なんかあの子、血とか言い出してるんだよね。民族主義に傾いてんのかな」
と配偶者に相談すると彼は言った。
「おめえはちょっと左翼っぽいからすぐそういうことを気にするけど、自分がどこから来たのかってことを人間が考えるのはごく自然なことだろ。そういうことをまったく気にしないで大人になるやつのほうが俺はむしろ心配」
確かに自分の子どもの頃を思い返せば、先祖がどういう人だったのか気になって祖母を質問攻めにしていた時期があったと覚えている。一つの国の中で思春期に自分の血にロマンを感じるのはオッケーでも、国境をまたぐと民族主義者呼ばわりされるのは、さすがに息子にフェアじゃないかもなと思った。
でも、息子の通う中学校は英国人の割合が高い学校なので、日本代表なんて超マイナーなチームを応援していると孤立してしまうのでは、と心配になり聞いてみた。
「ほかにも、イングランド以外のチームを応援している移民の子とか、いるの?」
「ポーランド人とクロアチア人の女子がいるけど、2人とも全然サッカーに興味ないから、僕だけだよ」
「回りの子は何も言わない?」
「別に何も。っていうか、なんで何か言われなきゃいけないの?」
「まあ、そりゃそうだよね」
みたいな会話を交わした数日後のことであった。
息子たちの学年はレゴランドに遠足に行ったのだが、午後4時頃に息子が電話してきた。
「母ちゃん、日本やったじゃん!」
という興奮した息子の声の後ろで、「ジャパーン、ジャパーン、ヴィークトリー・トゥ・ジャーパーーン」と歌っている少年たちの声が聞こえる。日本代表のコロンビア戦が終わったところだった。ちょうど息子たちは帰りのバスに乗り込む前で、集合して並んでいた間にスマホをチェックしたら日本が勝っていたので「オーマイゴーーーッド」と息子が叫び、周囲の生徒たちも「アンビリーバボー」と大騒ぎになったということだった。
「ジャパーン、ジャパーン」という少年たちの雄叫びを聞きながら、なんと恥知らずなまでに大音量で展開されるナショナリズムなのだろう、と思ったが、よく考えてみれば息子の背後で叫んでいる少年たちは誰ひとりとして日本人じゃないのだった。どうやら、彼の友人たちにとっても、W杯の時期には、息子は「東洋人」の一人ではなく、「ジャパニーズ」になるらしい。
このようにして、めでたく自他ともに認める日本代表チームのサポーターになった息子は、毎日帰宅するとかぶりつきでW杯を見ているのだが、先日、試合のない日に二階からギターの音が聞こえてきた。さいきん、音楽部で作曲を習っているらしく、W杯観戦の合間に息子は自室で曲づくりに励んでいる。なんとなくオアシス風のギターが響いてきて、ちょっと哀愁のあるインディーロック調の、なかなかいいコード進行じゃないかと思って耳を傾けていると、息子が歌い始めた。
「グランパーズ・ボンザーイ、ウウウ、グランパーズ・ボンザーイ、ウウウー」
まだ恋愛をしたことがないから歌詞にするネタがないと言っていたので、自分が強く思うことを何でも歌にすればいいよとは答えたものの、いくら何でも「祖父の盆栽」というテーマでロックソングを書くことはないんじゃないかと思ったが、これが現時点での彼の心のさけびなのだろう。W杯で日本代表を応援しているせいで日本の祖父を思い出したのか、80年代に作られたオリジナルの『ザ・カラテ・キッド』(邦題『ベスト・キッド』)シリーズのDVDを引っ張り出してきて、1作目から全作見ているのだ。シリーズに出て来るミスター・ミヤギがわたしの父親を髣髴とさせるそうで(確かに似ている)、主人公の少年、ダニエルとミスター・ミヤギの関係に自分と祖父を投影し、妙に感傷的になっているのだった。特にミスター・ミヤギが盆栽を愛でている横顔が九州のじいちゃんのようでぐっとくるらしい。
「盆栽」は「ボンサイ」と発音するんだと何度教えても、英語ネイティブにはNサウンドの後に濁点のないSを発音するのは困難なのか「ボンザイ」になってしまうところが残念なポイントではあるのだが。
なぜだろう。思春期になると日本的なものを嫌がるという日本人と欧州人の子どもの傾向とは正反対に、うちの息子はやけに日本に意識が向いているのだ。
「あいつ、小さい頃からアンダードッグが好きっていうか、弱い者が好きじゃん。いま日本に入れ込んでいるのはそのせいじゃないかな。ドイツみたいに放っておいてもいつも勝ちそうな国(この後でこの通説は見事に覆されたが)が親の出身地だったら絶対こんなに応援してないって」
配偶者は冷静にそう分析している。
この面妖な夏のナショナリズムと盆栽ソングの行方を注意深く見守って行きたいと思う。
(続きは本書でお楽しみください。)
この本をできるだけ多くの人たちに読んでほしいと思っています。
応援していただけると嬉しいです。
(編集H&新潮社「チーム・ブレイディ」一同)