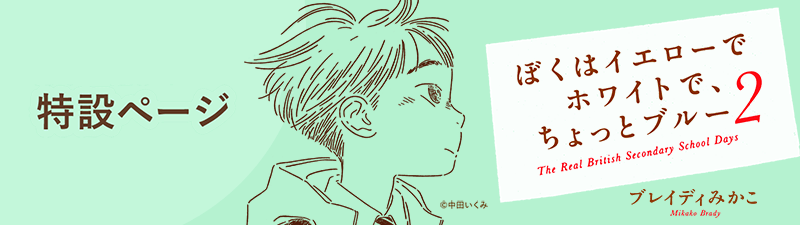6 プールサイドのあちら側とこちら側
息子が市主催の中学校対抗水泳競技会に出ることになった。
体も小さいし、特にスポーツが得意なタイプでもないので、マラソンやサッカーなどで学校代表に選ばれることはないのだが、水泳だけは別である。なにしろ、わたしが福岡の海辺の街で育った人間であり、うちの故郷界隈では泳ぐことは歩くことと大差ないというか、いつの間にかできるようになっていて当たり前だった。だから、わたしの子どもに泳げないというオプションはない。しかも、赤ん坊のころから、帰省で福岡に連れて帰るたびにわたしの親父から鍛えられ(海に投げ入れられたときにはさすがに「それだけはやめて」と怒ったが)、ガンガン泳げるようになることは産む前から自明の理であった。
そんなわけで、うちの息子は泳ぎだけは得意であり、7年生代表の一人に選ばれたと言うので、市民プールに競技会を見に行ったのだった。
市民プールの2階にあるギャラリーに上ると約250の座席はほぼ満席で、端のほうに空きを見つけて腰かけた。プールを見下ろせば、着替えを済ませた子どもたちがプールサイドに出てきて、学校別に定められた場所に集まっているところだった。息子が出て来たので手を振ると、向こうもわたしに気づいて笑って手を振り返す。
と、隣の席に座っている金髪の女性も立ち上がって声を上げた。
「ジェシー、グッド・ラック!」
シャワー室のほうからプールサイドに出て来た少女が、こちらに向かって親指を突き上げている。
脇のお母さんの逞しい腕には鎖が巻き付いた赤い薔薇のタトゥーが施されていた。顔の半分ぐらいの大きさの円形のイヤリングをして髪をひっつめにし、アディダスのジャージのボトムに白いランニング、顔には複数のピアスがきらきら光っている。
しばしぼんやりとプールサイドを見つめていると、奇妙なことに気づいた。プールサイドのこちら側にはやたらと人が密集していて、反対側はガラガラなのである。向こう側に陣を取ることになっている学校が遅れているのだろうか。プールサイドの両側の人口密度の差に気を取られていると、脇から薔薇のタトゥーのお母さんが話しかけてきた。
「おたくはどこの学校?」
息子の中学校の名を言うと、彼女は言った。
「ああ、あそこの、最近がんばっている中学か。うちの娘はW中」
それはほんの数年前まで、元底辺中学校と市の中学ランキングの最下位を争っていた学校だった。元底辺中学校がランキングの真ん中あたりまで浮上するにつれ、現底辺中学校の地位を不動のものにした学校である。「あそこの学校のサッカー・チームと試合したら、生きては帰れないという噂だよ」と息子が言っていた。
「娘さん、何年生ですか?」
と尋ねると、薔薇タトゥーのお母さんが答えた。
「うちは9年生。毎年この大会に出てるけど、何回来ても、親のほうが緊張する」
「うちの子は7年生なので、今年初めてです。……ところで、どうしてこんなにプールサイドのこちら側にばかり生徒たちがいるんですか? 向こう側はスペースがたくさん空いているから、何校か向こう側に行かせたらいいのに」
わたしが言うと、薔薇タトゥーのお母さんが答えた。
「ああ、向こう側は、ポッシュ校だから」
「ポッシュ校? つまり、私立校ってことですか?」
「そう。こっち側は公立校で、向こうは私立校のサイド」
わたしは思わずお母さんの顔を見た。
「公立校と私立校が別々のサイドってことですか? どうして混ざっちゃいけないんですか?」
「そんなことアタシに聞かれてもわからないけど」
と、隣のお母さんはもっともなことを言った。
「でも毎年、こうなっているよ。そういう決まりがあるんじゃないの」
そういう分け方をされているのなら、こちら側にわんさか人がいて、向こう側はゆったりしているのも当然だ。公立校の数は、私立校よりも多いからである。
英国は階級社会だとか、昨今ではソーシャル・アパルトヘイトなんて言葉まで登場している、というようなことを、わたしはこれまでさんざん書いてきたけれども、こうもあからさまな形で見せられるといまさらながらびっくりするな。と思った。
周囲の保護者たちを見回してみるが、プールサイドの両側の生徒数の差が激しいからどうにかすればいいのに、などと言っているのはわたしぐらいのものだった。日本人のわたしからすれば、私立校だろうが公立校だろうが学校は学校なんだから、アルファベット順にバランスよくプールサイドの両側に並べたらいいんじゃないかと思うが、どうもそれとは違う価値観というか、常識がこの場を支配しているらしい。
プールサイドのこちら側では、水着姿の中学生たちが肩をこすり合うようにして体をすぼめて立っていた。人間がすずなりになっている様子を、英語で「缶詰のイワシのような」と表現するが、まさにその絵を思い浮かべてしまうような光景だ。
他方、プールサイドの向こう側はスペースが有り余っているので、腰を回したりしながら準備体操をしている生徒や、優雅に脚を伸ばして座り、談笑している生徒たちもいた。缶詰のイワシになっているこちら側が庶民サイドなら、向こう側はバケーションを楽しむエスタブリッシュメントという感じだ。それがけっして比喩ではなく、本当に庶民とエスタブリッシュメントの子どもに分離されているのだからアイロニックな笑いの一つも浮かべたくなる。
ふと、プールサイドの向こう側に立っている少女の姿が目に入った。すらりと長身の、ビヨンセの妹のソランジュにちょっと似た黒人の少女が、じっとこちら側を見ていたような気がしたからである。
どこかで見た子だな。
と思ったが、エスタブリッシュメント・サイドにわたしと接触のある子なんているわけない。そう思い直してわたしはその大人びた容貌の少女から目を逸らした。

世にも奇妙な水泳大会
レースが始まると、わたしはさらに妙なことに気づいた。市民プールのレーンは6つしかないので、参加校すべての代表選手がいっぺんに競い合うわけにはいかない。それで学年ごとの種目別レースはどれも男女2回ずつ、計4回行われていた。例えば、7年生の男子背泳ぎが2回、女子背泳ぎが2回、という風にである。で、大会参加校は9校なので、それなら5校と4校とか、4校と5校とか、一回目と二回目で選手の数ができるだけ半々になるように分ければいいものを、常に一回目の競技が6校、二回目は3校で競い合っている。これでは、6校で競い合う一回目のレースに出る代表選手たちのほうが勝てる確率が低くなって、フェアとは言えない。
が、そのうちどうしてそうなっているのかわかった。一回目の競技にはプールサイドのこちら側から選手が6人出て行って、二回目の競技になると向こう側から選手たちが3人出てきてスタート台に立っているからだ。
つまり、競技待ちの場所がプールの両側に分かれているだけでなく、庶民側とエスタブリッシュメント側は競技も別々なのである。
「公立校と私立校は、一緒に泳がないんですね。これも毎年そうなんですか?」
と隣の薔薇タトゥーのお母さんに言うと、彼女が答えた。
「うん。これも毎年そう」
「徹底して分かれているんですね」
さらにレースを見ていると、この水泳大会は、英国社会のハードな現実をそのまま体現していることに気づいたのである。
一回目の公立校のレースでは、1位になる学校はほぼ毎回同じだった。地域の中学校ランキング1位を走っている公立カトリック校か、またはランキング2位の高級住宅街にある中学校である。まず、6人の代表選手たちがスタート台に上がると、カトリック校と裕福な地域にある公立校の選手は、見ただけでわかった。プロフェッショナルというか、本格的な競泳用の水着を着ているからだ。つまり、この中学生たちは、幼い頃からスウィミングスクールで鍛えられ、現在はスウィミングクラブで競泳選手として活動している子たちであり、素人スウィマーではありませんよ、ということなのだ。それは彼らの飛び込みのフォーム、レース運び、25メートル泳いでから折り返してくるときのターンの仕方、などを見ても明らかだった。
他方、例えば、薔薇タトゥーのお母さんの娘が通っている現底辺校の代表選手たちは、それ夏休みにビーチに行くときに着ているやつでしょ、みたいな水着を着ていて、見るからに素人臭い。飛び込みだって平気で腹打ちしていて、いかにもそこらへんの中学生という感じだ。泳ぎのフォームも不格好で、正式なターンの仕方も知らず、プールの端に手でタッチしてただ折り返す、みたいな調子だから、どうかすると1位の学校に20メートルぐらい差をつけられてゴールしており、ほぼ常に最下位である。
その点、私立校3校の代表選手が出場する二回目のレースでは、各校の力は均衡していたが、これはもう、公立校のレースとはまったくの別物と言ってもよかった。まるでオリンピック選手のような美しい飛び込み、ほんの数ストロークで25メートルが終わってしまう感じの優雅なフォーム、そしてくるっと水中で回転する折り返しのターンにいたっては、人魚と見まがうほどの華麗さである。
これは確かに、一回目に出場している公立校と、二回目に出場している私立校の選手たちを混ぜたら、実力の差があり過ぎてレースにならないだろう。大人と子ども、という言葉で同じ学年の中学生を表現するのもおかしな話だが、まったく勝負にならない。
男女の背泳ぎとメドレーリレーが終わったところで、レースはいったん中断し、それぞれの学年の1位から3位までの選手にメダルの授与が行われた。と言っても、私立校は3校で競い合っているので、メダル授与をしていると全員もらうことになってしまう。だから、ここだけは公立・私立校を一緒にし、レース中に計ったタイムで速い順番から金、銀、銅のメダルが与えられていた。3位から順に学校名と生徒名が呼び出され、メダルをもらいに選手たちが出ていく。当然のようにアナウンスされるのは私立校の名前ばかりだった。時々、公立カトリック校と裕福な地域の公立校が2位か3位に入っていることもあったが、元底辺中学校などのいわゆる「ふつうの学校」の生徒がメダルを貰うことはない。
公立校だけのレースを見ていても、競泳の順位は、公立中学校ランキングの順位とまったく同じであることがわかるように、学業で優秀な学校が、水泳でも優秀なのである。
英国の場合はプールのない公立校もけっこうあるので、学校では水泳はさわり程度しか教えておらず、どのくらい泳げるかは学校の外での訓練にかかっている。優秀な公立校の地域は住宅価格が高騰して高級住宅地になっているので、そういうところに住める親は子どもに習い事をさせる経済的余裕がある。また、カトリック教会に所属して子どもをカトリック校に入れる保護者たちも圧倒的にミドルクラスが多い。つまり、親の所得格差が、そのまま子どものスポーツ能力格差になってしまっているのだ。
むかしなら、勉強のできない子はスポーツができるとか、そういうこともあったし、労働者階級の子どもが金持ちになりたいと思ったら、スポーツ選手か芸能人になるしかない、と言われた時代もあった。だが、いまや親に資本がなければ、子どもが何かに秀でることは難しい。そのリアリティーが目の前で展開されているのを見ると、なんとも暗い気分になった。
そのうち、フリースタイル50メートルの競技が始まり、7年生男子の部でうちの息子が出て来た。民間の本格的なスウィミングスクールやクラブに通わせているわけではないが、市の水泳教室に8年間通っているので、彼は飛び込みやターンなど一応のことはできる。だが、それ以上に、九州の福岡の海で土建屋の祖父から鍛えられてきた泳ぎ手である。
なにがスウィミングクラブじゃ。乳児のころから玄界灘の荒波に投げ込まれてきたガキの意地を見せろ。と思っていると、あっさり1位になった。
元底辺中学校の生徒たちや教員が跳び上がって喜んでいる。だが、ここで1位になったからと言って、私立校のレースにはもっと凄い選手がいて、もっといいタイムを出すに決まっているので、息子がメダルを貰えるわけではなかった。
庶民とエスタブリッシュメントの間には越えられない高い壁が聳えているのである。

下層上等! 下品上等!
そんなわけで、速い選手や華麗な泳ぎっぷりはすべて私立校のレースに集中していて、公立校のレースは見劣りのするものだったのだが、9年生の男子フリースタイル50メートル競泳でその様相が一変した。
公立校のレースで、いきなり派手な柄パンみたいなだぼだぼの海水パンツをはいた選手がスタート台に現れたときのことである。真っ黒なゴーグルをかけた姿がグラサンをかけてビーチをうろつく兄ちゃんみたいで、競泳大会には場違いな感じで浮いていたのだけれども、この少年がめちゃくちゃ速いのだった。優美なフォームで泳ぐわけではなかったが、弾丸のように泳ぐというか、とにかくエネルギッシュで圧倒的な速さを見せつけ、2位の選手が折り返したのとほぼ同時にすでに50メートルを泳ぎ切ろうとしていた。
「ゴー! ゴー! ジャーック!」
薔薇タトゥーのお母さんが立ち上がって声援を贈っていた。場内を見渡せば、ギャラリーのあちらこちらで彼女のように立ち上がり、大声で叫んでいるおばさんやおじさんたちがいる。弾丸少年がゴールすると、薔薇タトゥーのお母さんは「ぎゃあああああっ」ともうほとんど乱心したような声をあげて両手を挙げて跳び上がった。
「あの子、うちの学校の子なんだよ。うちのヒーローなんだ」
薔薇タトゥーのお母さんは興奮して言った。
「すっごい速いですね。私立校の選手よりいいタイムが出てそう」
「当たり前だろ。あの子は小学生のときにスカウトされて、才能があるから無料でコーチに訓練受けてる。コーチと一緒に全国を回っていろんな大会に出てるんだから」
脇のお母さんはまるで自分の子どものことのように誇らしげに話した。
専属コーチがついてちゃんとした競泳大会に出ているのなら、あんなふざけたヤシの木の柄の海パンじゃなくて、きちんとした競泳用水着を持っているはずだ。ということは、彼はわざとあんな恰好をしているのだろうか。地元の中学校対抗の水泳大会なんて、はなから舐めきっているのかな、と思っていると、再びレースは中断し、メダル授与の時間になった。
平泳ぎ50メートルから授与が始まり、フリースタイル50メートルの結果発表になると、なんと7年生男子の部でうちの息子が3位に入っていた。元底辺中学校からは初のメダルである。プールサイドのこちら側の元底辺中学校の陣地からわっと歓声が上がり、息子はちょっと恥ずかしそうにおずおずと出て行って、メダルを受け取った。他の公立校の選手や教員もさかんに拍手を贈っている。
やがて9年生男子フリースタイル50メートルのメダル授与式が始まった。ピタッとしたサイクリングパンツみたいな競泳用トランクスをはいた私立校の選手が、銅メダル、銀メダルの順番で名前を呼ばれてメダルを取りに行き、「当然だろ」みたいな涼しい顔つきでプールサイドの反対側に戻って行く。次に1位の選手の学校名と名前がアナウンスされると、脇の薔薇タトゥーのお母さんやら、あちらこちらの座席に散らばっている現底辺中学校関係者らしき人々やら、プールサイドにいる同校の生徒、教員やらが、「わーっ」と怒濤のような声を上げた。くだんの柄パン選手が、現底辺中学校の陣地からメダルを受け取りに出て来た。公立校初の金メダルである。柄パン選手はメダルを受け取ると、プールサイドのこちら側に向かって両腕をあげて大袈裟に力こぶをつくって見せ、両手を唇にあてて派手なしぐさで何度も投げキッスを飛ばした。
もうギャラリーで見ている同校のお母さんたちは大騒ぎだ。親指と人差し指を口の中に突っ込んでぴいーーーっと口笛を吹いている人や、「ジャ―――――ック!」と黄色い声を上げている人もいる。
淡々と品よく行われていたメダル授与式が、突然ジャスティン・ビーバーのコンサートみたいになった瞬間だった。なんてサービス精神にあふれた少年だろう。このサービス精神は、現底辺中学校関係者だけでなく、明らかにプールサイドのこちら側にいる生徒たちにも向けられていた。愛校心、というよりも、愛階級心というか。英国の労働者階級にはこういうところがある。下層上等! 下品上等! と言っているかのようだ。
この不遜さの根源にあるものは、自分たちの階級に対する彼らのプライドなのだろう。ジャックという柄パン少年にしても、然るべき大会でメダルを貰うときにはこんな投げキッスなんてしないはずだ。公立校の子は私立校の子には滅多に勝てないという事実、公立校の生徒は狭い場所に押し込まれて缶詰のイワシになっているファクト。それを、彼は思い切り笑い飛ばしてやろうとしているように見えた。プールサイドのこちら側のティーンたちも、みんな割れんばかりの拍手を彼に贈っている。
庶民とエスタブリッシュメント。
99%と1%、という言葉が浮かんだ。正確には、このプールサイドの場合は6校と3校だが。
そんなことを考えながら場内を見ていると、ふと、プールサイドの向こう側から、またあのソランジュみたいな少女がこちらを見ていたような気がした。
大会が終わり、市民プールの玄関の前で息子が出て来るのを待っていた。次々と着替えを済ませた生徒たちが出てきて、友人や保護者と合流し、談笑しながら去っていく。
そのうち息子が出て来たので「よくやったね」と話しかけていると、あのソランジュみたいな黒人の少女が名門私立校の制服を着て出て来たのが見えた。上品なミドルクラス風の金髪の中年女性が「リアーナ!」と手を上げて呼び、少女はにっこり笑って金髪の女性に歩み寄り、肩を抱かれて一緒に駐車場のほうに歩いて行った。
リアーナという名前が頭の中でいつまでも残響していた。
懐かしい名だったからだ。むかし底辺託児所で預かっていた、白人の母親と黒人の父親を持つ女の子の名前。父親はDVで刑務所に服役中で、シングルマザーの母親が育児放棄の疑いを持たれソーシャルワーカーが介入していた家庭だった。福祉課にリアーナを取り上げられまいと必死で踏ん張っていた母親は、さっきの女性より年齢的にずっと若かったし、髪もブルネットで、頰に夫から暴行を受けたときの傷跡があった。わたしが民間の保育園に転職してからあの母子に会ったことはないが、底辺託児所のリアーナも、ちょうどあのくらいの年恰好になっているはずだ。それに、リアーナ、などというポップスターの名前を、私立の名門女子校に子どもを通わせるような階級の親が自分の娘につけるだろうか。
いろんなことが頭の中をぐるぐる回っていた。「母ちゃん」と腕を突つかれて息子のほうを見ると、誇らしげに制服の上から銅メダルをさげている。
「明日、学校に持って来いって校長先生が」
「なんで?」
「しばらく校長室に飾るんだって。なんか、すごく嬉しかったみたい」
メダルをさげた胸を突き出さんばかりにして歩き出す息子の後をわたしも追いかけた。
と、急に駐車場のゲートが開き、わたしたちは立ち止まった。走り出て来た車の運転席にはさきほどの金髪の女性、助手席にはリアーナと呼ばれていた少女が、優美な鳥のように長い首をかしげて座っているのが見えた。
ぽつぽつと降り出した冷たい雨の中を、その白いアウディはゆっくりと通り過ぎ、スピードを上げながら大通りのほうに消えて行った。
この本をできるだけ多くの人たちに読んでほしいと思っています。
応援していただけると嬉しいです。
(編集H&新潮社「チーム・ブレイディ」一同)