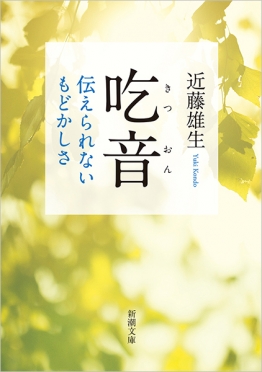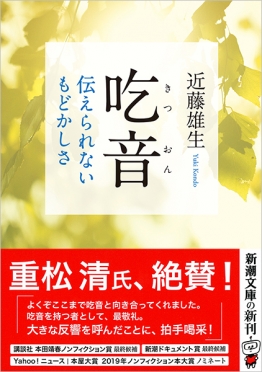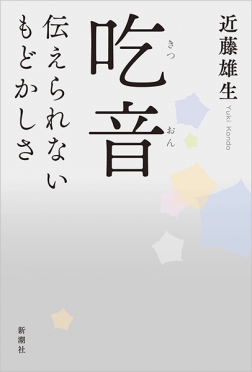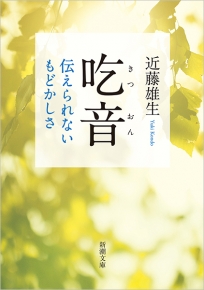
吃音―伝えられないもどかしさ―
605円(税込)
発売日:2021/04/26
- 文庫
- 電子書籍あり
死にたいほどの苦しさも、言葉にならない。100人に一人を孤独にさせる「吃音」とは何か。
店で注文ができない。電話に出るのが怖い。どもって奇異な視線を向けられたらという不安感から逃れられない……話したい言葉がはっきりあるのに、その通りに声が出ない「吃音」。理解されにくいことが当事者を孤独にし、時に自殺に追い込むほど苦しめる。自らも悩んだ著者が、当事者をはじめ家族や専門家など、多数の関係者に取材を続け、問題に正面から向き合った魂のノンフィクション。
一〇〇万人が持つ問題
『バリバラ』番組収録
高橋啓太の三五年
訓練開始
治すのか 受け入れるのか
羽佐田竜二の方法
叶わなかった殉職
変化の兆し
歯科医師の意志
電話番を外してほしい
人生を変えた軽微な事故
吃音者同士のつながり
初めてのスピーチ
吃音だけのせいではない
吃音者に対しての職場のあり方
断念した夢の先
ひどくちらかった部屋
みんなに追いつきたい
唯一の動く姿と声
訓練の果て
吃音がよくなったとしても
神様みたいな存在
「一杯珈琲」
吃音とはいったい何か
小さな文字で埋めつくされた連絡帳
なんとかしてあげたいという思い
五年後の表情の変化
文庫版あとがき
書誌情報
| 読み仮名 | キツオンツタエラレナイモドカシサ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | Getty Images/カバーPhoto、新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮45から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 272ページ |
| ISBN | 978-4-10-102761-6 |
| C-CODE | 0195 |
| 整理番号 | こ-71-1 |
| 定価 | 605円 |
| 電子書籍 価格 | 605円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2021/04/26 |
書評
理解されない苦しさ、を理解するために。
言葉がつっかえる、いわゆる「どもる」吃音の人は、詰まり方や軽重の度合いはさまざまでも、日本中におよそ百万人いるとされる――僕も、その一人である。
決して症例が少ないわけではないのに、吃音が起きるメカニズムは不明。治療法も確立されていない。なにより〈本人にとっては深刻でも、他人からは問題がわかりにくい場合がある〉。苦手な言葉でも場面や体調などによってうまく話せるときがあるから、ややこしい。さらに〈うまく話せなくなりそうな場面で沈黙すれば、他の人から見たらそもそも何が問題なのかほとんどわからないということにもなりうる〉……。
著者の近藤雄生さん自身、本書の中でも詳細に記しているとおり、かつて吃音に苦しんできた。ところが二十代も残り半年になった頃、2005年の終わりに突然症状が軽減して、〈吃音は、私の中からその姿を消していった〉。そうなのだ。そういうことがあるのだ、吃音には。僕も一番症状がひどかった十代後半の頃に比べると、五十代後半のいまはずいぶん楽に話せるようになった。しかし、近藤さんはこうも言う。〈もしかすると、何かをきっかけにすべてが元に戻ってしまう可能性もあるだろう〉。自分を引き合いに出しすぎて申し訳ないが、僕も体調の悪いときや、その場に嫌いな奴がいるところでは、ひどいことになってしまう。
なんともやっかいな吃音に、近藤さんはじっくりと腰を据えて向き合った。取材に約五年、本書の出発点でもある吃音矯正所についての短編ルポルタージュに取り組んだのは2002年というから、じつに十七年もの歳月の元手がかかっている。掛け値なしの労作なのだ。
その取材で、近藤さんはほんとうに多くの人に会っている。吃音に悩み苦しむ当事者はもとより、家族や周囲の人たち、研究者や医療関係者、吃音はコントロールできるはずだと語る言語聴覚士、吃音を受け容れようという自助グループ、かつて吃音を苦に自殺を図った男性、苦しみを誰にも語らずに/語れずに命を絶ってしまった青年の遺族……。
重い取材である。つらい旅でもあっただろう。吃音を持つ人の就労支援をおこなうNPO法人を起ち上げた男性は、吃音を理由に職場を去らざるを得なかった彼自身の過去を語りながら、「なんで涙が出てくるんだろう」と照れ笑いを浮かべる。僕も泣いた。彼の涙よりも、むしろ照れ笑いのほうに胸を衝かれた。彼の話だけではない。頁をめくるごとに、つらかった記憶や悔しかった記憶、言葉がうまく出ないもどかしさに地団駄を踏んだ記憶がよみがえって、何度も泣いた。いい歳をして子どものように――子どもの頃の自分のために、涙をぽろぽろ流した。
だからこそ、うれしかった。にこにこ笑ううれしさではなく、万感の思いを込めて、無言で、近藤さんに最敬礼したくなった。吃音のある人も、周囲の人も、一色に塗りつぶせるものではない。十人十色。誰もに〈その人だけの物語〉がある。しかし、その物語を語るには、彼や彼女の言葉は詰まりすぎる。〈吃音は、言葉だけでなく、その人自身の姿もまた、内に閉じ込めてしまう〉――それをゆっくりと、丁寧に、寄り添うようにして引き出してくれたのが、近藤さんではないか。最敬礼とはそういう意味である。
だが、急いで言っておく。本書は断じて「こんな可哀相な人たちの、こんな悲しい物語」ではない。本書の縦軸となって描かれる一人の父親――高橋さんという男性の、少年時代からいまに至るまでの歩みが、それを教えてくれるはずである。何度もけつまずきながら(つまりは、どもりながら)高橋さんは歩きつづける。その背中からたちのぼるのは、吃音の物語にとどまらない、人が人とつながりながら生きていくことの普遍の尊さなのだ。
〈人が生きていく上で、他者とのコミュニケーションは欠かせない。/吃音の何よりもの苦しさは、その一端が絶たれることだ。言葉によって相手に理解を求めるのが難しい。さらに、その状況や問題を理解してもらうのも容易ではない。二重の意味で理解されにくいという現実を、吃音を持つ人たちはあらゆる場面で突きつけられる〉
理解されない苦しさを理解されない――その苦しさは、いまの社会では(悔しいけれど)吃音を持つ人だけのものではないだろう。本書は、吃音をめぐるノンフィクションであると同時に、他者とつながること、他者を理解することについて問いかける一冊として、広く、深く、開かれている。
(しげまつ・きよし 作家)
波 2019年2月号より
単行本刊行時掲載
「吃音」をもっと知るために~重松清が近藤雄生に聞く~(「考える人」掲載)
著者プロフィール
近藤雄生
コンドウ・ユウキ
1976(昭和51)年東京都生れ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。ノンフィクションライター。大谷大学/京都芸術大学/放送大学非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。2003(平成15)年、自身の吃音をきっかけの一つとして、妻とともに日本を発つ。オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、5年以上にわたって、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国。以来、京都市を拠点に執筆する。著書に『遊牧夫婦』『旅に出よう』『まだ見ぬあの地へ』『吃音』『オオカミと野生のイヌ』(共著)などがある。