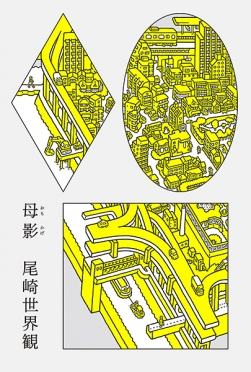母影
605円(税込)
発売日:2023/07/28
- 文庫
- 電子書籍あり
芥川賞候補作! カーテン越しに少女が見た、世界の歪。芸人・又吉直樹氏の解説収録。
小学校で独りぼっちの「私」の居場所は、母が勤めるマッサージ店だった。「ここ、あるんでしょ?」「ありますよ」電気を消し、隣のベッドで客の探し物を手伝う母。カーテン越しに揺れる影は、いつも苦し気だ。母は、ご飯を作る手で、帰り道につなぐ手で、私の体を洗う手で、何か変なことをしている――。少女の純然たる目で母の秘密と世界の歪(いびつ)を鋭く見つめる、鮮烈な中編。芥川賞候補作品。
書誌情報
| 読み仮名 | オモカゲ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 寄藤文平+垣内晴/カバー装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 128ページ |
| ISBN | 978-4-10-104452-1 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | お-112-2 |
| 定価 | 605円 |
| 電子書籍 価格 | 605円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2023/07/28 |
書評
此の世をもうひとつの眼で見るための子供
私が子供(小学校低学年)の頃、周囲の大人は近視のことを近眼《きんがん》と云っていた。私の母親はこれを、ちかめ、と発音していた。子供の私はこのことに対して違和感を抱かなかったが、ちかめ、という言い方には未開・土俗の響きがあることは薄々感じており、自分自身は、ちかめ、という言葉を使わなかった。
母親はその、ちかめ、であった。そのため遺伝の法則により中学に進む頃より私も、ちかめ、になった。その頃より私は意識して近視という言葉を使うようになった。
そういう自分だから、近視眼的、という言葉を聞くと、なめとんのか、と思う。近視と近眼を混ぜるなボケ。言うなら近眼的、か、近視的か、どっちかにせぇ、と思うのである。
といってでも人がその言葉を使うときに言いたいこと、というのはこれは理解できる。つまり全体を見ずに部分だけを見て判断することを批判してこんな言い方をするのであるが仰る通りで全体を把握しないで部分だけを見ているといろんなことを間違う。だから、全体を見て、正確な見取り図を描かなければあかぬ。
そしてこれをするためには現実の世界に生きて経験を積み、見聞きした物事、思ったこと感じたことを正確に表す言葉を習得する必要がある。これができるようになった者を大人と云い、これが未だできていない者を子供と云う。
というのは年齢には関係がなくて、六十になっても子供のままで、部分と感覚の世界のみに生きる人もあれば十三かそれくらいで全体を識って精確な見取り図を描く者もある。
なので持続可能な社会を建設してより良く生きていくためには私たちは大人の視点、視座を身につける必要があると思うのであるが、しかーし。
尾崎世界観氏の『母影』を読んでそうでもないのかも知れぬ、と思うようになった。というのは、この小説は子供の視点で描かれているため、世界は部分的にしか把握できておらず、しかもその捉え方は極めて感覚的で、大人がするように見聞きしたことを全体の中に位置づけることはない。
ところがこの小説を読むと、その全体というものが果たして、本当の意味で、全体、なのか。というか、それ以前に大人の視力は平均的であるだけで、もしかして物事が歪んで見えているのではないか、という気がしてくる。
その歪みとはなにかというと例えば、大人が此の世の出来事を見るときには必ず善悪というフィルターがかかる。
この小説で言うと、母親が、「変なこと」をしている、ということは道徳的に非難されることで、自動的に悪として位置づけられるが、語り手の子供からすれば、それは単に、「変なこと」に過ぎず、悪ではない。
その、部分的で感覚的な見方は、靴や乗車券、と言った物、日没や雨や風といった自然現象、人物にも及ぶ。
ただし、これだけが「変」と認識され、他の事と区別されるのは、周囲の自分に対する反応が変化する、というのは例えば学校で差別迫害される、母親の様子が変わる、といったことを同時か、または予見的に察知するからである。
同時というのは、そのことと周囲の反応が同時に起こって、変、と思うことで、予見的というのは、そのことによって、周囲の反応がある前から、これって変なことかも知らん、と思っていたら思った通りの反応が周囲からあって、やはり変だった、と思うようなことである。
作者はこうしたことを丹念にひとつびとつ描いて、小説を読むとき誰もが手にしているはずの見取り図を敢えて用いない。それは、純粋無垢な子供と不純で汚れた大人というありきたりな図を描くのではなく、作者が一般的な見取り図の歪みに馴染めない感覚を有して、それとはまた別の見取り図を拵えたい、世界を見るとき、このように見たい、と願っているからであると私には思える。
したがってここで描かれるのは当然、無垢な子供ではなく、作者が巧んで拵えた、此の世をもうひとつの眼で見るための子供である。
ここで作者は、意識せる狂人、というが如くに、意識せる近視、意識せる遠視に
影であった母が言葉として実体化して子と重なり、それから以降、母影となる過程と結末、エンディングの残響が遠く響く、この女の子供の将来をもまた作者は見て居るようにも思える。
(まちだ・こう 作家)
波 2021年2月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ
「芥川賞候補!!」はもう味のしないガムになった
――『母影』は2019年11月頃から書き始め、2020年12月号の「新潮」に掲載。芥川賞候補になり、2021年1月に単行本が刊行されました。今読み返してみて、いかがでしょうか。
自分が書いたという気がしないです。また、一回しかできない書き方だとも感じました。隙だらけなのがわざとでも実力不足からでもあり、普段文庫化の際はかなり直すものの、これは手を入れられなかったです。崩れかけのジェンガのようで、少しも触れない。逆に言えば、当時そういうところまで書き上げることができていてよかったです。
――本作の執筆の前後で変化を感じますか。
『母影』で変化したのではなく、コロナ禍という「変化」があったからこそ書けた作品だと感じています。あの日々だけが別物で、あれほど小説に向き合える時間は今後ないかもしれません。そんなおかしな時期、等しく全員にあったイレギュラーな瞬間を、小説として形に残せたのは自分にとって大きいことでした。だから『母影』は、自分の名刺のような存在になりました。
――芥川賞候補作としても話題になり、多くの方に読まれました。かけられた言葉で印象に残っているものはありますか。
「何でわざわざこんな話を」と言われることもあって、悔しい気持ちは大きかったですね。音楽活動の方でも、人が歌わないような感情をずっと形にしてきたのですが、音楽は音に反応し、伝えたいと思ったものをそのまま出せば成立します。小説は、“良いと思ったもの”同士の間に途方もない距離があって、そこを言葉で埋めなくてはならない。その筋力がまだなかったために苦労しました。それでも自分自身が「何でこんな」と思う物語に救われてきたので、それを『母影』でできたことは自信になりました。
――小学校低学年の女の子が主人公です。自分から離れた存在を書いたことで、何か手応えはありましたか。
小学生の女の子を大人の男が書いているという、そのズレを、意外とみんな気にするということがわかりました。自分にとって、創作は基本的に何かになりきるもので、音楽でも自分の話を正面からは歌いません。「これ以上やると過剰に反応される」という題材は、だからこそやりがいもあります。ただ、何を書いても結局は自分のことになるもの。その上で、どこまで離れられるかだと思っています。思えば、子供の頃から「これ以上遠くにいったらはぐれるかな」とか、かくれんぼで「見つけてもらえないかもしれないな」とか、いつもぎりぎりを探りたい感覚がありました。
――子供は尾崎さんにとってどんな存在でしょうか。
怖いです。彼らは素直に感情を出してくるので、一番傷つけられる可能性が高い。自分も子供の頃、大人に対して色んな感情を持っていたので、そう思うんでしょうね。大人は知識も言葉もあり、また、自分の感覚で何となくわかってしまうけれど、子供は言葉がそこまでないから、「内側」は宇宙。その分書きがいがあるし、ちょっと悪く書きたくもなります。
――『母影』では、そんな子供と母親をつなぐ存在として、「手」が象徴的な役割を果たしています。
コロナ禍ということもあったかもしれません。手洗いに消毒、みんな「手」を意識していましたよね。手がすべてを握っていて、逆にここさえ綺麗にしておけば大丈夫というイメージは、書きながらずっとありました。舞台にしたマッサージ店も、手に結びつきます。
――雑誌「スピン」で連載中の「すべる愛」の舞台もグレーゾーンな性風俗、メンズエステで、「手」の接触がありますね。
『母影』は親と子という近い存在でしたが、「すべる愛」では、知らない人と体が接触する異様さを書きたいと思いました。いま世間でも、体を奪われることに以前より敏感になっていると感じます。それは、男女問わず自分が体を他者に「貸す、預ける」という意識があるからじゃないかと思うんです。性行為も労働も妊娠出産も、その時間は誰かに渡していて、体の全部が自分のものになっていない。それを成り立たせるには気持ちかお金か、それぞれあるのかもしれないけれど、「肉体として奪われた」と感じた時に人は怒るのだと思いました。
――コロナ禍に書いた『母影』が、少しずつ日常を取り戻し始めた今年文庫化することと、今後についてお聞かせください。
単行本より小さく、身構えずに物語が入ってくる文庫で、主人公とどう向き合って頂けるかが気になります。寄藤文平さん(文平銀座)デザインの新カバー、又吉直樹さんの解説もすばらしいです。そして、「芥川賞候補になりました」という連絡があった日のことは忘れられませんが、もうすっかり味のしないガムになりました(笑)。コロナ禍のような時間はきっともうないので、自力で小説を書き上げて、『母影』に続く名刺を増やしたいと思っています。
(おざき・せかいかん ミュージシャン/作家)
波 2023年8月号より

存在感の濃い極太の偽物でいたい
――デビュー作の『祐介』は、売れないロックバンドのボーカルが主人公でしたが、『母影』は小学校低学年ぐらいの少女の視点で描かれています。なぜこのような設定にしたのでしょうか。
普段からコンサートの前などに整体マッサージをよく利用していて、あるお店で、女の子が学校の宿題をしている場面に遭遇したんです。あれこれ妄想するのが好きなので、もし隣のベッドで怪しいマッサージが始まったらどうなるんだろう……と思って、冒頭の十数枚を書いてみました。それが2019年11月頃。「新潮」の編集者に連絡してみたら反応が良かったので、これでいけるんじゃないかと思っていた矢先に、新型コロナで音楽活動がストップしてしまいました。2020年はバンド結成10周年で過去最大のツアーが組まれていたので、本当に悔しい思いをしました。時間はあるので、曲をつくることもできたのですが、この悔しさを音楽で晴らそうとすると、つくる曲自体がコロナに感染するような気がして、ひたすら小説を書いていました。
――執筆にあたって、どのようなことを心がけましたか。
まだ言葉になっていないもの、確定していないものを、ちゃんと自分の感覚で書こうと思いました。子どもは言葉を知らないので、目の前で何が起こっているのか、なんとなくわかっていても大人のように言い表すことはできませんよね。少女の母親はマッサージ店のカーテンの向こう側で何かをしていて、お客さんが変な声を出している。明らかに普通ではないけど、それを何と表現すればいいのかわからない。音楽の場合は、歌詞をメロディに乗せるので、音階や声のニュアンスで意味が届いてしまう。その感覚で小説を書くと、今度は言葉が足りなくて読み手にうまく伝わらない。「帯に短し襷に長し」といった感じで、小説は難しいですね。でも、そこを苦労して乗り越えないと文芸誌には掲載してもらえない。今回は、「新潮」に載せてもらうという目標があったことが大きかったですね。
――純文学の雑誌に載せることを意識したのはいつからでしょうか。
2016年に『祐介』を刊行したあとです。文学作品として批評されることも皆無だったので、悔しい思いをすることすらなくて、クリープハイプのファンが小説を買ってくれただけという感じで、とても後悔しました。これではCDを違った形態で出したようなもので、所詮はこんなものなのか、という気持ちだけが残りました。音楽に関しては、けなされても何を書かれてもまったく気にならないのですが、文章に関してはすごく腹が立ちますね。それは自分が、まだちゃんと小説を書けていないからだと思うんです。できないことをやるというのはとても大事なことで、ずっと音楽だけをやっていると、裸の王様みたいな恥ずかしい存在になってしまいそうで。だから自分にとって救いなんですよ。小説を書くということが。
――小説を読むことで救われた経験はありますか。
高校卒業後に加藤製本という会社に就職して、「見本」という部署に配属されて、時々、投げ込みチラシを入れる作業を担当していました。当時は彼女ができたばかりで毎日のように夜中まで遊んでいて、作業中に居眠りしてよく怒られていました。でも本に囲まれた仕事が好きで、印刷ズレなどで不良品になった本をたくさんもらえました。町田康さんの『くっすん大黒』や『屈辱ポンチ』を読んで、どんどん破滅に向かっていく主人公に救われていましたね。当時の自分もヤバかったんです。親にはバンドを続けていることを隠して就職して、メンバーには就職したことを内緒にしていて。自分がおかしいんじゃないかと悩んだときに、もっと変なことを小説にする作家がいるから、安心していいんだと思えました。
――その頃から、いつか小説を書くと決めていたのでしょうか。
自分が書けるなんて思いもしなかったですね。結局、加藤製本は1年ほどで辞め、バンド活動に専念しましたが、まったく売れないのでお金がない。だから近所の図書館で自転車カゴいっぱいに本を借りて読んでいました。2012年にメジャーデビューをして、2014年に「音楽と人」という雑誌で町田康さんと対談をさせて頂いたときに、「小説は書かないんですか」という質問に「絶対書きませんよ」と即答したんです。当時は本当にそう思っていましたが、結果的に嘘をつくことになり、後悔しています。でも思い返してみれば、心のどこかで書きたいと思っていたのかもしれません。
――それから6年ほどで、芥川賞にノミネートされることになりましたね。
とにかく嬉しかったです。小説が本当に好きで、真剣に向き合ってきたので、これからも書き続けていいという「許し」を戴いたような気がしました。いろいろと批評されて、もっと悔しい思いもするでしょうけれど、そんな程度のことと引き換えに候補になれるのならば、しっかり受け入れます。スーパーマリオがスターを取って無敵になっているような気分ですね。このまま選考会がずっと延期になって、1年ぐらいこの状態が続いたらいいのにと思っているぐらいです。
――2018年冬季号「文藝」の高橋源一郎さんとの対談で、ご自身を「偽物の小説家」とおっしゃっていましたが、もはや本物なのでは?
いや、それはないです。偽物が、しっかり濃くなってきている感じです。いちばんダメなのは薄い偽物だと思うので、むちゃくちゃ極太の偽物でいたい。あくまでミュージシャンが本業ですが、これからも全力で、本気で、偽物の本物を目指していきたいです。
(おざき・せかいかん ミュージシャン)
波 2021年2月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
尾崎世界観
オザキ・セカイカン
1984(昭和59)年、東京都生れ。2001(平成13)年結成のロックバンド「クリープハイプ」のヴォーカル・ギター。2012年、アルバム『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』でメジャーデビュー。2016年、初小説『祐介』を上梓し話題となり、2020(令和2)年には「母影(おもかげ)」で芥川賞候補となる。エッセイに『苦汁100%』『苦汁200%』『泣きたくなるほど嬉しい日々に』、直木賞作家の千早茜との共作小説に『犬も食わない』、対談集に『身のある話と、歯に詰まるワタシ』、歌詞集に『私語と』などがある。