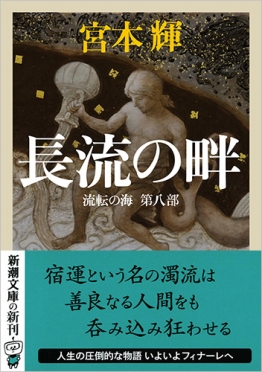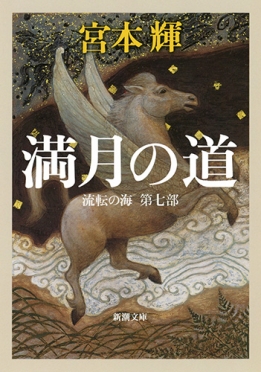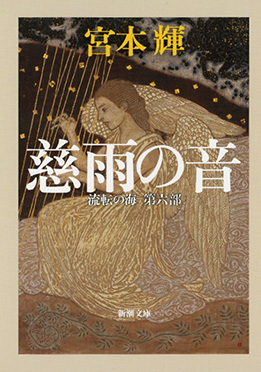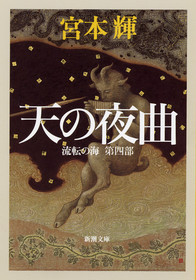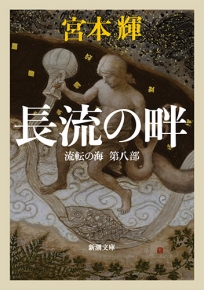
長流の畔―流転の海 第八部―
825円(税込)
発売日:2018/09/28
- 文庫
- 電子書籍あり
熊吾の小さな狂いは、房江を大きく狂わせた。松坂一家の明日は深い闇へと繋がっていた。
昭和38年、松坂熊吾は会社の金を横領され金策に奔走していた。大阪中古車センターのオープンにこぎ着けるのだが、別れたはずの女との関係を復活させてしまう。それは房江の知るところとなり、彼女は烈しく憤り、深く傷つく。伸仁は熊吾と距離を置き、老犬ムクは車にはねられて死ぬ。房江はある決意を胸に秘め城崎へと向かった……。宿運の軸は茫洋たる暗闇へと大きく急速に傾斜していく。
書誌情報
| 読み仮名 | チョウリュウノホトリルテンノウミダイハチブ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 榎俊幸/カバー装画、新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 480ページ |
| ISBN | 978-4-10-130757-2 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | み-12-57 |
| ジャンル | 文学賞受賞作家 |
| 定価 | 825円 |
| 電子書籍 価格 | 825円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/03/15 |
書評
老若男女の織り成す壮大な人間模様 宮本輝「流転の海」全九冊について
今年の一月中旬から二月末にかけて、コロナ禍の東京に居ながら、私は長い旅をしていた。それで、退屈なはずの日常が楽しくて豊かな日々に変貌した。
実は宮本輝の「流転の海」シリーズ全九冊を一気に読んでいたのだ。すでに単行本が刊行された時に読んだものもあるのだが、全編を続けて読むことで、この大河小説がいかに魅力にあふれたものか、まざまざと実感した。これは偉業だ。驚嘆すべき仕事だ。
物語は1947年に始まり、1968年に終わる。敗戦後の焼け跡から、高度経済成長へ。宮本の父親をモデルにしたという松坂熊吾を中心に、千数百人を超える老若男女が登場し、日本の戦後史が描かれていく。
小説の視点は徹底して低い。絶えず、地べたのにおいが漂い、河川の流れる音が聞こえ、雑踏の声が響く。庶民たちが織り成す人間模様が次から次に展開される。私たちは、ある時には登場人物の突然の死に無常を思い、別の場面では裏切りに人間存在の本性を考える。男女の情愛に人生の深みを感じ、絆の強さに接して宿命の重さに驚く。
舞台は大阪を中心に四国の南宇和(愛媛)、富山、金沢、兵庫県の尼崎市、城崎温泉などに移っていく。しかし、前面に出てこない土地もある。「東京」だ。これは「東京」抜きの戦後史なのである。「東京」はいつも遠くから距離を置いて眺める存在でしかない。はっきり言って、この小説に登場する人々は目の前の生活に必死で、そんなものにかかわりあっていられないのだ。
流行歌もあまり出てこない。芸能やスポーツの話題は数えるほどだ。そういう安易な方法で時代が表現されることはない。逆に世界の出来事はスターリンの死去からベトナム戦争や文化大革命、ケネディ暗殺、大学闘争まで、登場人物たちが自分の見方で話題にする。
主人公の熊吾はダンスホールの経営、中華料理店、プロパンガスの販売など、さまざまな仕事に手を染める。ただ、中心になって打ち込むのは中古車の販売だ。中古車部品の販売やモータープールの運営も含めて、商売の実態が生々しく描かれる。景気の浮き沈みに、人々はため息をつき、喜びに沸く。経済成長は自動車の普及とともにある。自動車を選んだのは熊吾ならではの読みだろう。自動車とは戦後日本社会の急所の一つなのだ。時代を表すのに、中古車は卓抜な鏡だと気づかされる。
熊吾はバイタリティーにあふれ、エネルギッシュで全てのことに対して情が深い。そして特筆すべきことは、彼が市井の思想家でもあることだ。彼は思索し、あらゆる生活の場面で哲学を語る。
いくつもの心に刺さる言葉が彼から発せられる。人間にとって大切なことは何か。日本人とはどういう民族か。戦後社会というものをどう考えるのか。戦争は人間のどういう性質をあらわにするか。自尊心よりも大切なものを持つとはどういうことか。ダメな教師とはどういうものか。私たちはしばしば立ち止まり、思いをはせることになる。
そんなに人の世が見えている熊吾なのに何度も失敗する。脇が甘いし、誘惑に弱いし、自分の健康管理もできない。熊吾の妻である房江は苦労を重ねながら自身の生き方を見いだす。自殺未遂を経て、自立する女性として生まれ変わっていく。熊吾が五十歳になって初めてできた息子の伸仁は今度新しく文庫になる第九部『野の春』では大学生になって、文学とテニスとアルバイトと恋愛に明け暮れる。
そう、この第九部でははっきりと時代が移り変わっているのを感じさせるのだ。ずっと読んできた読者は精神病院に入れられて死んでいく熊吾に何を思うのだろうか。味わいは苦くて複雑だが、主人公がやがて宇宙に還っていくような解放感を感じるのも確かだろう。
登場人物たちの中から、自分の贔屓をつくるのも楽しい。私は断然、南宇和の鍛冶屋の男性と、茶道を追求する在日コリアンの男性に惹かれた。二人とも個性的な苦労人だ。南宇和の鍛冶屋は戦場でギリギリの体験をしてきたし、在日コリアンの男性は貧しく、日本語の読み書きも不自由だ。だが、二人とも人間としての芯がしっかりとしていて、それが表情にもしぐさにも表れている。この二人が小説に姿を現すと、私は何か、なごんだような気持ちになる。彼らが第九部でも登場するので心が弾んだ。
一月から二月というのは、私の苦手な季節だ。寒さはどこまで続くのかとどんよりした空を見ていてつらいし、春はなかなかやってこないし、そのうち花粉症に悩まされる。毎年、とても長く感じる。ところが、今年はあっという間に過ぎていった。小説に読み浸る喜びで、時間の流れが速くなったのだった。
(しげさと・てつや 聖徳大学教授・文芸評論家)
波 2021年4月号より
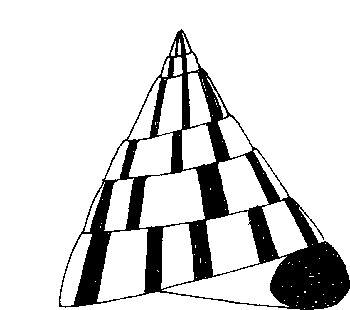
「死と失敗と挫折」を乗り越えて行く人間の姿
『流転の海』第八部『長流の畔』までを完成するのに宮本輝は三十五年の歳月をかけた。『流転の海』は何もかもが廃墟と化した敗戦後の日本を舞台に、関西の庶民の生活が再現され、庶民の視点で歴史が語られる作品である。
宮本輝は1947年に神戸市で生まれた。愛媛県生れの父熊市は大阪に出て自動車部品を中国に輸出する仕事についた。母雪恵は茶屋の仲居をしている時、熊市と出会い結婚した。父は性的に放縦で、暴力をひめた、反道徳的な、恐るべき男である。母はすべてを受け容れてくれるタイプの女である。
小説のなかの熊吾は熊市、房江は母雪恵がモデルであり、二人の息子伸仁のモデルは輝自身である。そしてこの小説は作家一家の戦後史であり現代史となっている。
1952年、熊吾は大阪の中之島で事業を再開した。三階建てのビルで中華料理店、雀荘、テントパッチ工業の三つの商売をはじめた。その事業が中華料理店の食中毒事件、共同経営者の杉野信哉の脳溢血、うつ病の症状をともなった妻の更年期障害と不幸が続出して破綻する。心機一転を図って大阪を離れ、富山に移り新しい事業を開始しようとするがうまくいかない。そして数々の経験を積んできた熊吾は、1964年の東京オリンピック景気にわく街をあわただしく駆け回っていた。彼は中古車を販売する大阪中古車センターと松坂板金塗装の店を経営していたが、社員に運転資金を横領され事業の危機に見舞われていた。
熊吾は新聞で南ベトナムの僧侶が焼身自殺したのを見て、自分のなかで何かが狂いはじめたことを自覚した。彼は戦場で指揮官の命令である満州の集落を焼いた。彼は生きている農民はいないと信じて焼いたが、銃剣で喉を刺された老人はまだ生きていることを知った。自分の「狂い」にはこうした無意識化の「何か」が影響しているのではないか。
俺が犯した失敗は、まだ若い博美の体に再び手を出したことだったと熊吾は思っていた。もう六十六歳になる俺が博美の体に執着し、厄介なヤクザ者と別れさせるために七十万円もの金を使った。そして博美のことを妻に知られてしまった。
「俺は、男の機能も糖尿病とともに萎えたとばかり思っていたが、博美の体は別格で、いつも若いころと同じくらいに漲らせてくれる」。熊吾のなかの男の業は消えていなかった。
高校生の伸仁は、若い女に狂い借金のために駆け回る父の生き方に反撥する。また母が自殺未遂をしたことで自分を捨てたと抗議する。
城崎の満月を見に行くのを楽しみに生きてきた房江は、夫のあとをつけて、夫が若い女の家に行き、「お父ちゃん、おかえり」と言って迎えられているのを見てショックを受けた。そこで房江の堪忍袋の緒が切れた。房江は夫と愛人がこもる部屋に乗りこんだ。慌てて阻止しようとする夫を突き飛ばし、ここで女と野垂れ死にすればいいと言い置いて帰ってきた。
その後、房江は夫と女を罵倒した自分が、激しく嫉妬しているのを感じた。嫉妬はやがて寂しさを伴った悲しみへ、さらにあきらめへと変ってゆく。夫へのあきらめばかりではない。自分の人生へのあきらめだった。夫は去り、息子は自立した。私は一人だ。房江の孤独を救える人はいない。
この孤独のなかで、房江は睡眠薬自殺を図る。何かの意思が働いたのか、房江の自殺は未遂に終わる。
「累々たる死と失敗と挫折」を経験して人は老いてゆく。その「死と失敗と挫折」を繰り返しつつそれを乗り越えて行く人間の逞しさを読み取るのが、小説を読む楽しさではなかろうか。
まちがいなく著者の集大成となるはずのこの小説の完成まであと一息である。
(かわにし・まさあき 文芸評論家)
波 2016年7月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ

執筆35年の大河長篇で描く、人間の幸福と命。
戦後の時代を背景に、松坂熊吾の波瀾万丈の人生が描かれる大河小説『流転の海』。
いよいよ迫る完結に向けて、第八部『長流の畔』が刊行されるにあたり、宮本作品の愛読者で、モデルで作家の押切もえさんとの記念対談をお届けします。
書き始めたのは三十五年前
押切 『流転の海』シリーズは、戦後の日本を背景に先生ご自身のお父様をモデルにされて、この第八部に至るまでもう三十五年も書き続けられているのですね。
宮本 そう、三十四歳で書き始めました。
押切 最初に読んだ時は、主人公熊吾の破天荒で情に厚く豪快な人柄に惹かれ、逞しく生き抜く姿に勇気をもらいながらも、妻の房江への態度があまりに横暴で、読んでいて胸苦しい部分もありました。
宮本 まあ、でも明治の男としては普通だったんです。口より先に手が出るとか、あんな横暴なことは今は通用せえへんやろなと思いますけど。
押切 確かに今だとすぐに離婚だ、別居だとなると思いますが、巻を追って読むうちにお互いの立場を尊重できる愛の深さが伝わってきました。こういう関係が新鮮でしたし、改めて考えさせられます。
宮本 第一部の冒頭で熊吾は五十歳ですが、その時僕は三十四歳ですから五十歳の男の生理的なことや体力の感覚などが実感としてわからなかったんですよ。僕が女のことわからないのと一緒でね。
押切 えー、先生の作品を読んでいると、女性を十分おわかりになっているような気がしますが(笑)。
宮本 いやいや、女は謎です(笑)。僕の母親になる房江が三十六歳で、熊吾が五十歳の時に子が出来ますが、まだ三十四歳ですから勘で書くしかなかった。けれど小説が進むと熊吾が僕より先に年取って、年齢差が開いてきます。それで計算してみると、どうもこの話は当初の予定の五部ではとても終わらない。けれどやっぱり自分が五十歳に近づかないと熊吾のことは書けないと思ったので、第一部を書き終えてから第二部『地の星』へ進むまで間をあけたんです。
押切 どれくらいでしょうか。
宮本 せめて四十代になるまではと思い、再び書き始めたのが四十三歳でした。
押切 ああ、十年近くかかったのですね。
宮本 「私は今年八十二歳です。『流転の海』を最後まで読めるのでしょうか」というようなお手紙をたくさんいただきました。それでも待つ以外なかったんです。
押切 物語では多くの不運があったりして、死が数多く登場します。先生ご自身が死を近しく感じていらっしゃるのが伝わってきます。
宮本 僕は体が弱くて、子どもの時に、二十歳まで生きられないだろうと言われました。だから絶えず僕はみんなより早く死ぬんだという意識がありました。風邪でも引くと自分をすごく大事にしてね、「もう学校行ってもええぞ」と言われても、「いや、もう一日寝てる」とかね。
押切 小さい時から死を意識されてた。
宮本 芥川賞をもらった三十歳の時に血を吐きまして。結核なんだけれど、せっかく芥川賞もらったんだから、とにかくもう一作だと『幻の光』を書き終えて入院した。それで療養して三十四歳の時に、結核の薬を飲まなくていい状態になれたんです。よし、これからはどんどん仕事しようと、その勢いで『流転の海』に取りかかったんです。ところが三十五年たってもまだ書き終えていない(笑)。
押切 この第八部『長流の畔』で熊吾の年齢と並ばれましたね。お父様をより深くわかるようになられましたか?
宮本 余計わからなくなったんです。僕が二十二歳の時に父は亡くなりましたが、今から四十七年前の六十九歳と今の六十九歳は、ものすごく違うと思います。
押切 そうですね、今の先生と作中の熊吾は重ならないように見えます(笑)。
宮本 それでも、父の死んだ年齢を超えた時、親孝行ができたな、と思いました。親より早く死ぬのは親不孝ですからね。父より長く生きられたから今度は母を抜かなきゃいけない。母は七十九歳で亡くなりましたので、あと十年。
押切 もっと長生きして下さい。この第八部では房江が熊吾の浮気によって辛い目に遭い、気持ちが「驚き、嫉妬、悲しみ、諦め」と変化して……。絶望のどん底までいっても、最後まで自分が大好きなお酒はやめないというところが、ものすごく人間らしくて好きになります。
宮本 本当にお酒が好きだったんです。
押切 房江はぎりぎりまで苦しんでも、その後生まれ変わったように強くなりますね。働くことでまた「本当の顔を見せる」というような表現がありましたけど、そんな逞しさにとても共感しました。
宮本 母は自殺未遂の後、ものすごく強い人になりました。その後はもう、熊吾のことなんか知るか、みたいな(笑)。
押切 格好いい! でも房江さんが未遂に終わった後で、伸仁が「お母ちゃんは、ぼくを捨てたんや」と言う場面にすごくジーンと来て、涙が出ました。
宮本 うん、それは長いことありました。死のうと思って断崖絶壁の上まで行った、あるいは踏切の前に立った、という人は多い。けれど、おふくろは飛び込んだんです。運がよくて助かったけれど、一度死んだんです。ということは、この人は俺を置いて死のうとしたんだというのが、僕の中でずっとわだかまりでした。
押切 その心情は、お母様の前では出さないようにされていたんですか?
宮本 いえ、「おまえは私を憎々しそうに見る」とおふくろは晩年も言ってました。そんなつもりないんですけど、どこかにあったんやろね。僕もまあ未熟でしたから。今も未熟ですけど。
押切 とてもそうは思えません(笑)。
宮本 若い頃はそう受けとってしまうんですね。もうすぐ八十歳という時に死んだんですが、幼い時から苦労し通しできて、当時の八十歳といったら長寿ですから、「ああ、よかったなあ」と思いました。その予兆を第九部で書かないと、ずっと読んできてくれた読者に対して申し訳ない。みんな不幸せになって死んでいくなんて、なめとんのかと言われます(笑)。
押切 すごく混沌とした人間関係で、波瀾万丈なことが次々に起きて、不運もあるけど、それぞれに希望や幸せが残ってて、全巻に生の喜びが強く感じられます。
宮本 そうですか、それならよかった。
宮本作品との出会い
押切 私は先生の作品では『錦繍』を一番最初に読みました。今回の房江さんの印象と重なるので思い出していたんですが、愛し合いながらも別れた男女、とりわけ女性の揺れ動く心情が往復書簡の形式で丁寧に描かれていて感動しました。中でも「宇宙の不思議なからくり」という言葉が強く自分に入ってきたんです。私自身、十年前に首を骨折しまして……。
宮本 えー?
押切 その時は少し死を感じたというか(笑)、自分は何故生かされているんだろうとか、そんなことをずっと考えていた私にとって、教科書みたいな本なんです。
宮本 教科書ですか(笑)。
押切 人生とは何かということを、先生の小説で教えていただいたんです。
宮本 あの出来事があったから現在がある、というのは、不思議なことですけどありますね。
押切 熊吾も今回ラスト近くでそんなふうに強烈に思う訳ですが、先生はずっとそう強く感じて生きてこられたのですね。
宮本 そう、渦中にはわからないものですが、そういう人生を生きてきました。
歌うな、酔うな
宮本 押切さんも最近、小説書かれましたね。
押切 先生に仰られると緊張してしまいます。文章を書く時に心がけるべきことを教えていただけないでしょうか?
宮本 デビュー作となった『泥の河』を何度も書き直している時に、何がダメなのかずっと考えて、俺は描写じゃなくて説明をしていたんだ、とわかったんです。ただし、描写と説明を混ぜてはいけないと頭ではわかっても、どの文章が必要でどれが不要かわからない。編集者でもわからないと思う。難しいなあ、これがわかったらもうサナギが蝶に変わります。
押切 ああ、変わりたい(笑)。自分で独りよがりになってしまっている文章を書いてしまうことがままあります。
宮本 それは歌ってるからです。「どうだ、うまいだろう」と歌っている文章で描写すると鼻持ちならない。自分で自分の文章に酔うみたいなものですね。書き出しに多い。
押切 うわー(笑)。あるかもしれません。
宮本 『泥の河』の書き出しに苦しんでいた時に、森敦の『月山』を読んだんです。『月山』の冒頭の数頁は素晴らしい名文です。一見何でもないけれど、歌ってないし酔ってない。文章だけで読ませる小説です。これを読んだことで『泥の河』が出来ました。とにかく押切さんは今、いい小説を読むことです。小説に限らずいい文章を読む。俳句でもいい。
押切 早速読んでみます。祖母が山形の出で、月山は見慣れた景色ですが、文章で味わってみます。もう一つ、小説を書くにあたって大切にされていることは何ですか。
宮本 受け取り方はそれぞれですが、書き手側に明白に伝えたいメッセージがない限りは、一行も書き出せないですね。最近、そういうものを小説に込めない、求めないという人が多くなっているけれど、結局、人間にとって一番大事なことは、幸福とは、命とは何か、ということだと思います。
押切 はい。
宮本 蟻一匹だって、ものすごく大きな知恵を小さな体の中に内包している。そういうものを作り出してる命とは何なんだ。そう考えると次は、死とは、生とは何か、という方向へ行かざるを得ない。長い歴史に耐えてきた作品というのは、『オデュッセイア』でも『ユリシーズ』や『失われた時を求めて』や『戦争と平和』にしても、最後はそこへ行き着きます。それを書かないと古典として残っていかない。そういうものは、やはり小説そのものが面白い。僕は行き詰ったら必ず『赤毛のアン』を読みます。
押切 あ、第七部の『満月の道』に伸仁の愛読書として出てましたね。
宮本 人間の幸福とは何かということが、今は子どもじみた尻の青い者が口にする言葉として取られているけれど、実はそう言う人が最もわかってないと思います。自分が小説家として読者に伝えられるのは、それだけです。それがないと、どんなに上手に書いても、人の心を打たない。「上手な小説だな」で終わりですよ。
機関車の点検中
押切 いよいよ最後の第九部を書き始めるにあたってのお気持ちを教えて下さい。
宮本 次は「野の春」と決まりました。題も名前も書いて、「第一章 一」と書いてあるのに、そこから全然進まない。ビビってるんです。
押切 今回の「あとがき」に「臆病風に吹かれて」いると書かれていましたね。
宮本 そう、今ビュービュー臆病風(笑)。もうこれ書き出したら、あとはないぞ、嫌だなあという感じですね。
押切 そういう時、何かリフレッシュ法はありますか?
宮本 ないない。もう書くのが嫌だという時は、とにかく小説を書くんです。
押切 書けなくても、向き合う?
宮本 「えいやぁ」と書き始めるんです。機関車を最初にゴトンと動かすには、ものすごく大きな力が必要ですけど、動き出すと少しずつ速くなっていくでしょう? 動かしたから動き出すんです。だから書きたくない、もう嫌だという時は、書くんです。一行でも、二行でもとにかく書く。そうしたら自然にエンジンが入るんです。別に小説でなく、仕事でも何でも、それをしたくない時は、それをするんです。それが最良のコツで、それ以外に方法はない。
押切 わかりました。では「野の春」は、今、機関車の点検中ですね。
宮本 車輪をトンカチで叩いているところ。よし行くぞと決めたら大丈夫でしょう。
押切 「新潮」での連載開始を楽しみにさせていただきます。今日はありがとうございました。
2016年5月19日新潮社クラブにて
(おしきり・もえ モデル、作家)
(みやもと・てる 作家)
波 2016年7月号より
単行本刊行時掲載
関連コンテンツ
著者プロフィール
宮本輝
ミヤモト・テル
1947(昭和22)年、兵庫県神戸市生れ。追手門学院大学文学部卒業。広告代理店勤務等を経て、1977年「泥の河」で太宰治賞を、翌年「螢川」で芥川賞を受賞。その後、結核のため2年ほどの療養生活を送るが、回復後、旺盛な執筆活動をすすめる。『道頓堀川』『錦繍』『青が散る』『流転の海』『優駿』(吉川英治文学賞)『約束の冬』(芸術選奨文部科学大臣賞)『にぎやかな天地』『骸骨ビルの庭』(司馬遼太郎賞)『水のかたち』『田園発 港行き自転車』等著書多数。2010 (平成22)年、紫綬褒章受章。2018年、37年の時を経て「流転の海」シリーズ全九部(毎日芸術賞)を完結させた。