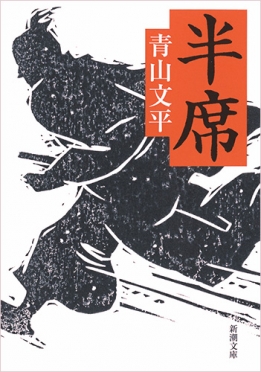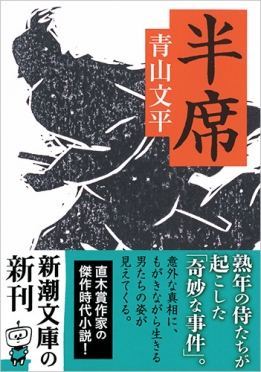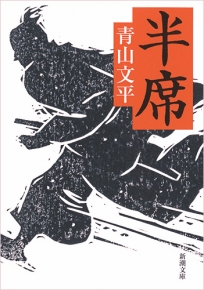
半席
693円(税込)
発売日:2018/09/28
- 文庫
- 電子書籍あり
分別ある熟年武士たちが、なぜ「奇妙な事件」を起こしたのか。意外な動機が心にささる!
御家人から旗本に出世すべく、仕事に励む若き徒目付の片岡直人。だが上役から振られたのは、不可解な事件にひそむ「真の動機」を探り当てる御用だった。職務に精勤してきた老侍が、なぜ刃傷沙汰を起こしたのか。歴とした家筋の侍が堪えきれなかった思いとは。人生を支えていた名前とは。意外な真相が浮上するとき、人知れずもがきながら生きる男たちの姿が照らし出される。珠玉の武家小説。
真桑瓜
六代目中村庄蔵
蓼を喰う
見抜く者
役替え
書誌情報
| 読み仮名 | ハンセキ |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮文庫 |
| 装幀 | 原田維夫/カバー装画、新潮社装幀室/デザイン |
| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |
| 判型 | 新潮文庫 |
| 頁数 | 320ページ |
| ISBN | 978-4-10-120093-4 |
| C-CODE | 0193 |
| 整理番号 | あ-84-3 |
| ジャンル | 歴史・時代小説、歴史・時代小説 |
| 定価 | 693円 |
| 電子書籍 価格 | 605円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/03/15 |
書評
老いの味わい
新潮文庫の中からお気に入りがあれば、三冊ご推薦をとのご依頼です。で、膨大な蔵書目録の頁をめくっておりましたが案外、忽ちにその三冊が決まりました。
先ずは、私、やっと三十路のとば口で読み、そのルポルタージュの見事さに圧倒された一冊。『人の砂漠』。沢木耕太郎の初期作品です。八編のルポから成り、その中でも終章の「鏡の調書」に圧倒されました。
主人公は八十三歳、滝本キヨと名乗る老婆で詐欺師。ふらり流れ着いた岡山の田舎町で銀座に土地をもつ億万長者を演じ、寸借詐欺をくり返し、町内の人達にも六百万円ほどの損害を与えて指名手配に。通報で逮捕されるが、取り調べに際して、このばあちゃんは凜として応じ、臆するところがない。まだ二十代の若きジャーナリスト、沢木耕太郎はこの老詐欺師に興味をもち、彼女の犯行をさらえるうちに意外な事実を次々と洗い出す。六百万円を騙し取りながらこの老婆が自分の贅沢の為に使ったのは八万八千円のみ。日々の生活費のほか残りは町内の人達への贈り物に費やされたという被害金額。案外、この老詐欺師が町内の人達を励ましていたのでは、と思い当たった著者は、そこに老詐欺師の「意地」を感じ取るのです。
それにしても人間を見つめ、人間を報告する著者の筆力に、同じ世代に属しながら圧倒されました。
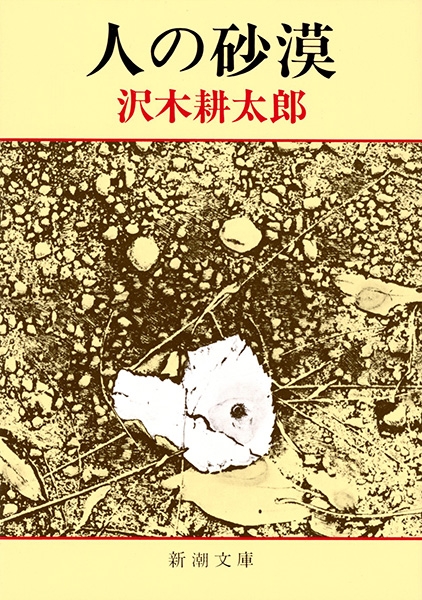
そして次なる一冊が『半席』。青山文平の武家小説。私、六十路半ばに読みまして、まあ、身につまされること此の上なし。
戦国の世から二百年ほどが過ぎた江戸の世。サムライが刀剣で名を揚げる時代は去り、役所の役名で威勢を競う文官の世。
徒目付の片岡直人は上役から奇妙な水死事件の「真の動機」を探り当てるように命じられる。台所頭役の矢野作左衛門が木置き場の筏の上で釣りをしていて、足を滑らせて冬の水に沈み水死した。その死の腑に落ちない奇妙さを探る内に若き片岡直人は老いの無残、老いの手強さという真相に辿り着く。その真相とは、八十九歳になっても家督を譲らぬ作左衛門にあった。ただひたすらに役目を譲って貰えると待ち続けた七十二歳の養子の信二郎だが、凍て水の木場で家宝の銘刀「埋忠明寿」をたなご釣りの一尺(三十センチほど)竿と交換していたことを知り逆上する。老いて、何ひとつ譲らぬ作左衛門に怒りを向けると作左衛門は唐突に「飯が旨いのだ」という。老いと共にゆっくり枯れてゆく筈の欲望が少しも老いてゆかない。欲望が若いまま、八十九になっても子や孫に何ひとつ譲りたくないという。そして作左衛門はたなご竿を筏から投げ捨てる。信二郎がその場を離れると吝嗇にも作左衛門は竿を拾おうと凍て水に手を伸ばし、落ちて沈んだ。
この作左衛門の「飯が旨いのだ」が実に身につまされるひと言。「飯が旨い」「仕事には張り」を感じて「遊びは楽しい」。何ひとつ子や孫に譲りたくない作左衛門の長寿を呪う信二郎。著者・青山文平は若い世代にのしかかる枯れない老人の「無残」を描いて実に巧みです。全く新しいタイプの書き手で身につまされる武家小説です。
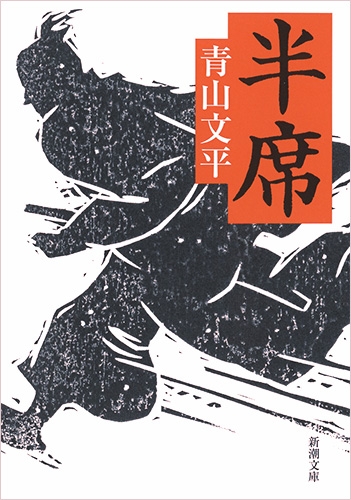
そして最後の三冊目、『白川静さんに学ぶ 漢字は怖い』。表題の白川静さんとは、九十六年の生涯を漢字の字源を求めて亀の甲羅、獣の肩甲骨に刻まれた甲骨文字を渉猟。ついに三千二百年の時を貫いて漢字の生まれた源流に辿り着いた博士です。その学績は驚嘆すべきもので、著者、小山鉄郎は「一途」な白川文字学を伝えてくれます。
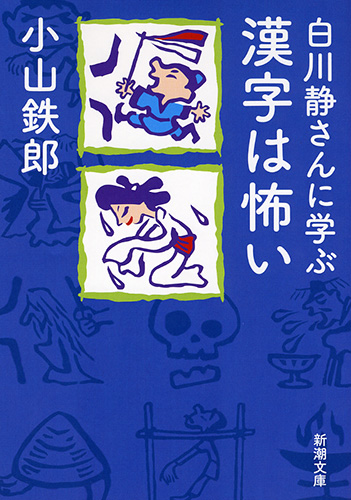
例えば「而」という部首。このひと文字で髪を垂らした巫祝、祈祷師の姿だそうです。その髪を垂らした人は何を祈るか。これは雨を乞う専門の神官で、故に雨と組み合わせて「需」、もとめる、まつの意味を持つひと文字。「さんずい」を横におけば「濡」れるし、「にんべん」をおけば「儒」となり孔子の説いた儒教となり世間を潤す道徳の教えとなるわけです。
この博士の面目は中国にとらわれることなく、人類史に立って漢字を解く「一途」にあります。白川博士を知る入門書には最適の一冊です。
三人の著者は団塊と呼ばれた世代に生まれ、1970年代に青春を通過した人達。奇妙な共通点で「老い」に憧れて、青春を足早に去った若者達です。その三人がそれぞれに老いの「意地」「無残」「一途」を描いているわけで、味わい深き樹液のような作品です。
是非、御賞味を。
(たけだ・てつや 歌手/俳優)
波 2021年6月号より
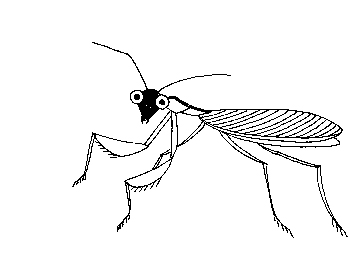
江戸の事件にのぞく、平成ニッポン
直木賞受賞後第一作。あざやかな着想、あざやかな筆さばき。六十歳をこえてデビューした人が、ためこんだ元手で一挙に花を咲かせたぐあいだ。
時は十九世紀はじめ、いみじくも「文化」を年号とした頃あい。世界有数の大都市江戸は人口百万をこえていたのではあるまいか。そこにあって、いるかいないかの下級武士が主人公だ。職のない小普請組がワンサといる。片岡直人がやっとありついたのが
「自分は無理でも、いずれは生まれてくるのであろう自分の子には、要らぬ雑事に煩わされることなく、御勤めだけに集中させてやりたい」
愛すべき、優等生の青年である。となれば、ひたすら御勤めをきちんと果たすこと。それを心に決めているのに、肝心の上司がこっそりと「頼まれ御用」を言ってくる。へたに応じて表の御用に支障をきたすと、出世の糸口がフイになりかねない。にもかかわらず一度請けたのが二度となり、三度、四度ときて、全六話が裏の御用の顛末。
どれもいたってヘンテコな事件なのだ。当年八十九歳という高齢ながら、カクシャクとして表台所頭を務めていた老人が、木場へたなご釣りに出かけ、何を思ったか、やにわに筏の上を走り出し、水にとび込んで水死した。
お次の事件は、老人サロンの仲のいい両名、ともに八十七歳。会も押し詰まった頃、やにわに一方が脇差抜いて斬りかかった。
三つめ。ほんの涙金で一季奉公を二十年以上もリチギに勤め上げた四十八歳の男が、不意に姿を消したとおもうと、フラリと主家にあらわれ、何でもないやりとりのくだりに主人の背中を突きとばした。踏み石に頭を打ちつけ、主人は絶命。主殺しには鋸挽のすさまじい刑罰が待っている。
表だっては、すべて決着のついていることなのだ。証人もいれば当人の自白もあって、裁きのとおりに進行する。ところが粋狂な組頭がそっと御用を誘いかける。なぜ事件が起きたのだろう。どうして斬りかかったり、突きとばしたりしたのか、当人から訊き出してくれまいか。
上司の組頭は、初出のときは内藤康平といった。このたび内藤雅之と改めてある。意味深い改名である。康平は「公平」を連想させる。たしかにそんなお役目をになっているが、もっと人間味あふれた大きな人物であって、いわば体制内の雅かな平常心の男。直人こと青っぽい直情型の青年を、よく見ている。加えてもうひとり狂言まわしがいて、こちらは沢田源内といったり、島崎貞之といったり、名前も商売もくるくるかわる。体制外の雅かな平常心の役まわり。
「劇」は不可解な事件の解明だが、これに寄りそい、さらにもう一つある。円熟した大江戸という歴史のドラマ。頼まれ御用の舞台となる神田多町の居酒屋七五屋からして、フクイクと文化が匂ってくる。主人喜助が釣り上げた魚。その料理法。「洗いってのが、ありがてえなあ。刺身は野締めでも喰えるが、洗いは活締めじゃなきゃあ喉を通るもんじゃねえ」
そんなセリフに、青年は反発する。武士が喰い物を云々するのはいかがなものか。そんなときの雅之の返答。「けどな、旨いもんを喰やあ、人間知らずに笑顔になる」
ミヤビ男は、武士は食わねど高楊子の貧国の哲学を歯牙にもかけない。自分の言葉どおり、旨いもんとなると、とてもいい笑顔になる。およそ徒目付らしくない。
物語のドラマは、ささいなことなのだ。ほとんど誰の目にもとまらない。本人だけに見えていたこと、気にかけていたこと、ちょっとした思いこみ、こころはなれなかったこと。そんなさなかのほんの一瞬だ。その人の視点に世界がうつったとたんに事件が起きる。もはや元へはもどらない。
語られているのは江戸・文化年間の町と人だが、そっくりそのまま平成ニッポンの町と人にあてはまる。そのあやうさと幸せ。新鮮で警抜で、意味深い。優れた時代小説の得意ワザであって、かくもあざやかに「現代」をとらえることができるのだ。
(いけうち・おさむ ドイツ文学者・エッセイスト)
波 2016年6月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ

“フルスペックの人間”を描きたい
直木賞受賞後第一作『半席』の刊行にあたり、青山さんに自問自答の形でエッセイをお書きいただきました。
――書く時代が絞られていますね。十八世紀後半から十九世紀前半。なぜですか。
これまでは、そこが、武家にとってキーワードがない時代だから、とお答えしてきました。キーワードがないということは、一人ひとりの武士にしてみれば、動くべきお手本がないということですね。いわゆる叩き台がない。で、それぞれが自分の頭と身体で考え、自分で行動しなければならない。その、それぞれの解に、
――「これまでは」ということは、いまは違うと。
いえ、理由は一つではないということです。その時代に焦点を当てる別の理由もある。今回はその二番目の理由を語らせていただこうと思って、それはつまり、成熟、です。江戸時代のなかで、いちばん成熟したのが十八世紀後半から十九世紀前半なんですね。この時代は表面的な動きが目立たなくて、“時代劇”的には地味なのでしょうが、それは世の中が成熟している
――成熟、を描きたい、ということですか。
やはり小説の書き手ですから、結局は
――なんで、成熟していてほしいのでしょう。
たとえば、多くの人が食えない時代を想定してみてください。人々がなによりも希求するのは、食えるようになる、ということですね。当然、その時代の人間を描くと、食えるようになるための営みを書くことになる。しかし、実際に食えるようになってみると、そこはゴールではなく、むしろ、そこから食えるようになった後の人間としての問題が始まるわけでしょう。
――たしかに。
別の例えを言えば、江戸初期の東北には、“戦乱が一度あるくらいなら、七年飢饉が続いたほうがまだいい”という言い伝えが残っているそうです。武家以外の人々にしてみれば、戦国時代の戦乱には辟易していたのでしょう。そういう実社会の厭戦気分が、徳川の時代を招き寄せたという見方さえあると聞きますが、これにしても、では戦のなくなった時代がユートピアかと言えば、そんなことはありえない。つまり、ひとつひとつ問題が解決されるに連れ、それまでは封印されていた問題が浮かび出てくるわけです。
――つまりは、時代が成熟するに連れ、人間は見知らぬ問題に向き合わなければならないということでしょうか。
そういうことなんじゃないですかね。思うに、人間には人間たらしめている成分があって、ひとつひとつ問題が解決されて、時代が成熟するに連れて、未知の成分が抽出されてくるのだと思います。
あおやま・ぶんぺい 1948年神奈川県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。2011年、『白樫の樹の下で』で第一八回松本清張賞を受賞し、作家デビュー。2015年、『鬼はもとより』で第一七回大藪春彦賞受賞。2016年、『つまをめとらば』で第一五四回直木賞受賞。他の著書に『伊賀の残光』『春山入り』『かけおちる』等がある。
〈好評既刊!〉
『伊賀の残光』
還暦過ぎの伊賀衆・山岡晋平。ある日、伊賀同心の友が殺される。大金を得たばかりという友の死の謎を究明せんと動きだすが――。『流水浮木―最後の太刀―』改題。〈新潮文庫〉
『春山入り』
果し合いの姿のまま、なぜか独りで切腹した侍の謎を追う「約定」の他、武家としての生き方に縛られながらも、己れの居場所を掴もうともがき続ける武士の姿を描く粒揃いの短編集。『約定』改題。〈新潮文庫〉
(あおやま・ぶんぺい 作家)
波 2016年5月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
青山文平
アオヤマ・ブンペイ
1948(昭和23)年、神奈川県生れ。早稲田大学政治経済学部卒業。経済関係の出版社に18年勤務したのち、フリーライターとなる。2011(平成23)年、『白樫の樹の下で』で松本清張賞を受賞しデビュー。2015年、『鬼はもとより』で大藪春彦賞、2016年、『つまをめとらば』で直木賞を受賞。2022(令和4)年、『底惚れ』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞を受賞した。江戸中期の成熟した時代にあってなお、懸命にもがき生きる人々を描く作家として、熱烈なファンが多い。著書に『かけおちる』『伊賀の残光』『春山入り』『励み場』『半席』『跳ぶ男』『遠縁の女』『やっと訪れた春に』『江戸染まぬ』『本売る日々』『泳ぐ者』などがある。